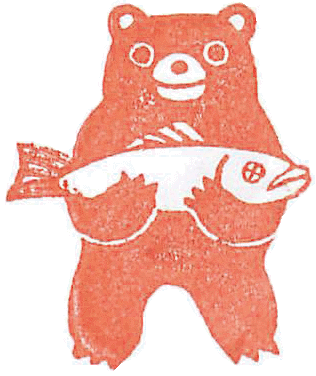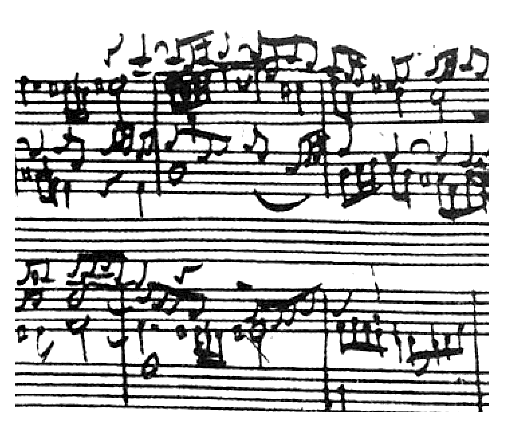解説:池田光穂
最初にヘーゲルのお話をしましょう。現実としての 薔薇は理性のシンボルである、と彼は言ったそうです。ヘーゲルは同時に、その理性を狡知というか、ずる賢いものだとしていると聞きます(歴史哲学における「理性の狡知(List der Vernunft)」)。しかし私は薔薇と 聞くと、私はどちらかと言うと中世的なゴシックが好きなので、ウンベルト・エーコの『薔薇の名前』のほうを先に思い出してしまうのです。そこで語られる薔 薇は、むしろ知性や知恵、さらにはエソテリックな神秘のようなものです。そこに立ち現われてきたときに、理性の刀のようにスパッスパッと事物を切っていく 便利なツールというよりも、むしろ表れたときに解釈を求められる神秘のようなもの、あるいは謎かけ、ないしは解釈が求められるようなもの、そういうものと して立ち表われてくるのではないか、と思います。そのような知恵を、古代ギリシャの人たちは——これはアリストテレスから来ていますが——「プロネーシ ス」(実践知)と呼んできました。アリストテレスによる と、人間にはさまざまな知性のレパートリーがあってそれを分類しています。
今日は「場所で変わる対話の不思議?」というお話を しましょう。次の写真は「実践知と現場 力」という授業風景です。水を半分入れたペットボトルを頭に載 せています。この日はジャワの舞踏家の佐久間新(さくま・しん)さんという方を講師にお招きしました。看護学の実習室で一時間半の授業の間、ずっとペットボトルを乗せてました。私もこれで完全にはまりまして、その後会議をするときなども頭にペットボトルを載せています。ペットボトルを載せるとそれを固定し なければならないので、頭を自由に動かして自由な会話ができないので硬直した話し方になります。顎が上に上がるのではなく下のほうを向く話し方になりま す。

■世界的に有名になったサクマ新さん指導による「ペットボトル授 業」です!
つまり、それだけで一つの教訓になりますね。頭に ペットボトルを載せるだけで人は話し方が変わる。話し方が変わると、話す私の人格が変わったようにも見 える。頭にペットボトルを載せていれば、変わった人だと思われますが、そのペットボトルが見えなかったら、「この人は今日はいつもと違う」と思われる。あ るいは初めて出会った人は、私がいつもペットボトルを載せたような姿勢で話していれば、「なんておとなしい人でしょう」という印象を持つかもしれません。 今日はそのような教訓のお話をさせていただきます。
レジュメにふざけたようなアイコンが記してあります(このページの最後をみてください!)。熊が鮭を抱いているアイコンです。私は最近、中央アメリカ のグァテマラのマヤ系の先住民運動のことを研究しています。ある一つの国民国家内で差別されて いる先住民の人たちの文化の復興、それから国政や政治へのか かわり、あるいはどのようなかたちで先住民のアイデンティティをとりもどすのか、という研究をしています。それでアイヌの人たちとも仲良くなり、北海道に 遊びに行ったときにお土産に鮭の燻製をいただきました。そのアイヌの人たちがつくっている鮭の燻製のシールが気に入ってしまいまして、このように使ってい るわけです。授業の資料などにも使っているのですが、これは私にとっては非常に重要です。大学の資料はほとんど文字だけですが、「そんなものは俺たちの本 物の大学の授業ではない。大学の授業は本当はもっと楽しいものだし、それを表現する資料というのも楽しいものだ」という思いをこめています。もし子供でし たらレジュメのアイコンから興味を持ってくれて大人と子どもの対話が始まります。名は体を表わすではありませんが、「我々がおこなう大学の授業が変わっていくので あれば(授業をおこなう)我々を含めた皆さん自身も変わらないと意味がありません」というのがここでの趣旨です。
私たちのコミュニケーションデザイン・センターは、十数 名の常勤職員と二十名弱の特認の教員から成る組織です。今は大阪大学の豊中キャンパスにあります が、発足当時は千里万博公園にある万博記念機構の施設に間借りをしていました。そのときに、シンボルカラーをオレンジということにして、教室のフロアもオ レンジに統一、「オレンジ・ショップ」と言われる教室にしました。そ こで車座になったり椅子に座ったりして授業をします。会議室の机も丸テーブルで、教授 会もそこでやりました。このアイデアを出したのは、大阪大学前総長の鷲田清一先生でした。鷲田先生は、「人間は異なった空間に配置されるだけで、その環境 におかれた人間の間のコミュニケーションの質が変わる」と仰られ、全国の大学でも珍しい、あるいは先進的な取り組み——全学の研究科の大学院生たちに共通 教育としてコミュニケーションデザイン科目を受けさせるという学則に改正——をしました。つまり教養部のような授業を大学院全体の共通教育科目としてつ くったわけです。
このプロジェクトは、ある意味で非常に先進的でし た。強ばらずにリラックスして楽しく授業をする。そして授業は教員が学生に対してレクチャーをすること よりも、学生同士が対話をすることを重視する。教師は学生の対話のなかに一緒に入る。私たちのチームは臨床コミュニケーション・チームと言って、教員のユ ニットをつくってタスクフォースのような感じで授業をしています。そのチームのなかでグループ討論し全体にフィードバックする。それをホワイトボードに書 かせて〈見える化〉する。たんに書かせて終わりということではなくて、三〜五分くらいの簡単なプレゼンテーションをさせる。さらに、「ポスター セッション のようなかたちで集まってください」と言って、ホワイトボードの前でプレゼンテーションを 聞く学生との間でやりとりをするという授業です。
そこでのポイントは、非常に楽しいということ、それ から体を動かすことです。椅子の上に一時間半も座っているといかに集中力のある学生でも眠たくなって しまいます。この授業では、隣の人と会話をしたり、プレゼンテーションをしたり、立ったり座ったりします。僕などはごろっと横になったりしています。そう いうことが当たり前になってくると、まったく気にならなくなってきます。人間は集中力がなくなってだらっと人の話を聞くときと、興味を持って聞くときと まったく違う理解があります。そして、そういうものをつねにフィードバックするようにしています。「君はどういう感じで授業を聞いたか」と後でチェックす る。「そのときどういう感じがしたか」などを学生自身にリフレキシブルに、反省的に想像させて、理解することと体を動かすことの関係はどういうものであっ たのか、理解させます。あるいはテーマのなかにそういうものを挙げる。

■自家製即興手話によるコミュニケーションの伝達活動
二枚目の左端の写真。男性二人が膝をついて向かい合 い、女性二人がそれを見ています。これは、あるタスクを与えて、「言葉を喋らずにこのメッセージを伝 えなさい」というものです。伝えたものをホワイトボードに書き、その後本当にそのメッセージが伝わったかどうか、あるいはそのときにメッセージを発する人 とメッセージを受ける人がどういうつもりでジェスチャーをしたのか、ということを解説させます。そのようにして、「言葉が通じないときに、人間はどのよう なコミュニケーションの工夫をするのか」を授業で学ぶわけです。こういうことは、基本的にやった者勝ちみたいなところがありますから、みんながこのような 授業をやるようになると、私達もレパートリーがなくなってしまいますので、対話型の授業が進んでいくとそのレベルを上げていく、あるいはプロブレム・ベー スド・ラーニングと呼ばれるように、授業の課題を学生自身につくらせるなどの工夫をします。
授業では、ヒューマン・コミュニケーションに関する テーマが多いです。私は、ホラを吹くと か、科学者がウソをつく、あるいは食品の偽造などのテーマが好 きなのですが、そのようなテーマでみんなが思っていることを議論するという授業をしています。
このように場所ややり方を変えると一時間半はあっと いう間です。いかに議論を上手にできるようになるか。ディベートよりも対話の相手からどれだけ有意義 なことを引き出せるか、に焦点を置いています。これも教育の成果には、歩留まりみたいなものがありまして、最初はやはり知らない者同士ということもありま すし、授業の最初の回から高い水準を求めてはいけません。アイスブレイクという技 法がありますが、これと同じで授業が進めば進むほど、開始後に彼らが議論 に集中できるまでの時間がどんどん短くなってきます。報告する人とグループを仕切る司会者——ファシリテーターと呼んでいます——はローテーションで変え ていきます。授業の一セメスターが終わるときには、全員が最低一回は経験することになります。最初はやはり慣れていないので、仕切るのが上手な人が出てき て司会をするわけですが、だんだん苦手な人も参入し、みんなができるようになります。効率良く見知らぬ人たちと楽しく議論できるようになります。
もちろん、実際にその人に完全に身についてくるかど うかの潜在力はわかりませんが、みんながそういうことに物怖じしなくなり、この教室はこのような環境 なのだということに馴染むと、自然にできるようになる。これはマジックというよりも、「ここの空間はそのようなことをしても大丈夫なんだ」という認識を当 事者たちに引き起こすこと。私の専門である文化人類学の儀礼やお祭りのような気持ちをもってもらうことです。お祭りでは、褌をはいたり、裸になったり、妙 なコスチュームやメイクアップをして、普通であれば格好悪いと思うことをみんなでやる。そのなかに自然に、祭りそのもの中に没入していくわけです。それと 同じように、「この授業はこのような場なのだ」と認識すると、私たちもそうです し、学生のほうもその状況にすぐに馴染んでいきます。そして仲間どうしの対 話がどんどん進んで行きます。対話が進むと、自分たちは「議論が上手になった」と自覚するようになるのです。
ですが、先ほど申しましたように、この過程は少しず つ上手になっていくものです。教師は、その直前のセメスターでの学生の心証が調子良いと、次のセメス ターでなかなか学生がのってこないとキレたりイライラすることもあるのですが、そのような心理的態度は長い間やっているとブレーキになります。最後に、学 生たちに、我々の手のうちを明かします。「僕たちの仕事は、じつは君たち学生をおだてることにあったんだ」と。しかし「おだてられたけれども、最後に獲得 した皆さんの討議の力は皆さん自身がつけたものだし、このやり方は非常に普遍性を持っているから、他の授業や社会の現場でも使うことができる」と伝えま す。皆さんにとってみれば卒業みたいなものだが、気に入ればまた来てもいい。そういう経験知を持つ人がいることで、次に新しく来る学生たちにより効率よく 会話型の授業ができる。君たち自身がTA(ティーチング・アシスタント)になり、そして教員になるのだ。それから社会に出たり、大学院に進みさらに専門知 識を発揮するようになったりするときに、皆さん自身がこの技法を使ってその場を盛り上げることができる——そういうメッセージを述べて授業をクローズする ことにしています。
ここで見られるものは、やはり「成長」ということで す。成長するのは学生たちだけではなく教員もそうです。それが、大阪大学コミュニケーションデザイ ン・センターの当初から——まだわずか数年くらいですが——かかわった私自身のつたない経験から見えたことです。その都度その都度一喜一憂し、複 数の教員 が同時に授業に参加しますので、おびただしい数の教員同士のオフの反省会を重ねてきた結果です。このようなノウハウをみなさんの大学の授業のなかで応用で きるの であれば、パテントフリーですので皆さんも是非お試しになってください。また、我々のノウハウとみなさんの大学が持ってらっしゃるノウハウを交換できれ ば、大学 の授業はどんどん変わっていくのではないかと思います。かなり楽観的な話になりましたが、それが私の結論であります。
最後に、「会議は踊る」という言葉がありますが、そ れを私なりにパラフレーズしますと「授 業は踊るものである」そして冒頭のヘーゲルに戻ると「ここが教 室だ、ここで対話型の授業をしよう!」ということです。
■現場力とはなにか?
「現場力(げんばりょく)」を学生たちにどう伝えるのかという問いから出発します。そ こでは現場力から現場が再定義できるのではないかと思います。では現場とは何か。それは 最初から抽象化されたものではなく、そこで持っているような性格や特性を抽象化すると「現場」という用語になるのではないかと思います。現場は具体的な場 所です。そのように考えると、「あなたの現場とは何ですか」と問われると、一つは大学の教員として、教育者としての私の現場は教室です。文化人類学者の研 究者としては、グァテマラやメキシコの南のチアパス州——現在のメソアメリカと呼ばれ るところです——がフィールドワークの現場です。
その現場で発揮される私の力が「現場力」ではないか と思います。つまり、教室で立ち現れるある種感動的な経験であり、フィールドワークの経験を通して体 験するような何かではないかと思います。そこから再び現場を定義してみます。私たちの教育現場での臨 床コミュニケーションを、「時間と空間が制限されてい るなかで、ある種の目的を持った対人コミュニケーション」と定義しています。これは私にとっての「現場」とパラフレーズすることができます。時空間が制限 されたなかである種の目的を引き出さなければならない。誰が対照か。人間です。人間と人間の出逢い、相互作用。このような要素で成り立っているものが「現 場」であると私は理解しています。
そのなかで「現場力」を伝えるということは、五感を 働かせてその現場に臨んだときに、限られたなかで何が見えてくるのか、ということです。当初に立てた 目的みたいなものが達成されたかどうか、をセッションの終わりで評価することができること。そのなかで働きかけるものは人間と人間との関係。それを支える もののなかには、機械やもの、歴史的文脈、あるいは政治的な圧力であるとか、非常に抽象的で空気のような人間が持つ環境の力 みたいなものがあります。そういうものの相互作用を見出すこと。まさに環境のなかに生きる人間、世界内存在のようなもののあり方ではないか、と思います。 そしてまた、失敗から学ぶこともとても重要です!
■人間関係に悩む日本の生徒たち、その伝統を学生や院生そし て教員も引き摺っているのではないでしょうか?
私は教員のキャラではないようで、学生とガヤガヤ やっているので、学生が遠慮しているようには見えないし、そのようにさせないように授業をしています。 ただ、「友達地獄」や「KY」という観点からコメントさせて頂くと、日本の大学生活は、大学教育の 環境が悪いとは思いますが、一種のサブカルチャー化、あ るいはナショナル・カルチャー化していると思います。我々の人間関係は、ルース・ベネディクトの主張ではないですが、集団主義が最優先されるところがあり ます。KY、みんなと合わせない奴はおかしんじゃないか、というプレッシャーが非常に強いですよね。
私は、これを解消するには、トータル・インスティ チューション(全制的施設:刑務所や 修道院などがモデルになるような生活のすべてが管理される施設)と しての大学の考え方をやめればいいと思う。学生が大学だけにいるのではなく、キャンパスの外に頻繁に出ること。「授業以外は大学に寄りつくな」「サーク ル? そんなものをキャンパスだけでやるな。やってもいいけど、やるんだったら社会人と一緒にスポーツやれ」というように。年齢の幅も限られている集団の なかで、「単位をとらねばならない」「試験のときになんとかしなくてはならない」「あの先生うざい」などと価値観を共有しなければならなくなっている。 「友達をつくるのなら自分たちと違う奴を探せ」と言えるように、大学がそういう異質化や差異化を尊ぶような環境を自然につくり出せればいいと思います。逆 のアンチ・ナショナル・カルチャーみたいなものを生産する場所であるべきだと思います。大学に来たからには、世の人とは違う考え方を模索してみよ、と。で も現実は自分たちに足かせをはめるプレッシャーに困っているような感じがします。
私たち教員は学生たちの気持ちにはなかなかなれませ んが、学生たちには、「大学? そんもんどうでもええやないか。友達地獄で苦しんでるくらいだった ら、社会は広いぞ、外に出ろ」というアドバイスをしたくなりますね。
■質問に対する応え方
非常にテクニカルな話をしましょう。今の学生たちが上手にプレゼンテーションで きない、言語化できないのは事実です。私たちはよくリアクション・ペー パーなど、フィードバックのペーパーを書かせます。「今日やったことについて、気づいたことを書きなさい」と言うと、ぶわーっと書いてきます。試験世代な ので、ほとんどハビトゥス化していますから、書くことは書くんです。それを集め、その場でおもしろそうなものを読みあげて返していく。教師がその意見につ いて考えたことや感じたことを応答しながらパラフレーズして、「君の考えはこれでいいかな」と返していくんです。そうすると、自分が取り上げられたという 感動もあるし、自分の言葉が教師に正しく伝わっているかどうかを大変気にしてますから、やはり返答があるんです。こういうことをくり返しているうちに質疑 のフィードバックに慣れていく。書くのに慣れるということがあるとすれば、今度はその時間と手続きを圧縮して、思ったことを直接言えるようにすること。そ のためには、ひたすら書きやすい、聞きやすい、話しやすい教室の環境をつくっていく。それは空間の変化であり、授業の構成の仕方であり、知識の与え 方で す。それは、勉強のやり方全般に言えることです。
質問したときに、良い先生ほどその質問に対して真摯 に答えようとしますが、私の場合は、「え、それってどういう意味?」とか、「あなたがその質問に今 持っている答えはどんな答え?」と問い返すことで、教師である自分が考えていることをすぐには応えてあげない。「どう考えてるの?」「どういうふうに見て るの?」「言葉の定義が僕と違うから、もう一度定義して」というかたちで質問や問題をずらしていくことで、違ったふうに考えることを促す。論文書いたりす るのも自分で問題をつくることですし、書いたものの最初の読者は本人なわけだから、書くことのなかで自分の知識や考えをブラッシュアップしていくわけです よね。今度は、それを他者との対話のなかでやれればいい。そのためにはよく考えないとなりません。考えて構成することと書いたものでロジックを構成するこ との違いについて、心を砕く必要があると思います。基本的には、コミュニケーションのモードチェンジを頻繁にやっていくことがコミュニケーションの総体だ と思います。私のつたない経験からもそのようなことが言えるのではないか、と思います。
■学生のリアクションに応えるために
リアクション・ペーパーをとって次の週が連休などで 休みだったら二週間後となると、間があきすぎますね。かなり破格ですが、授業が半分終わった時点で一 〇分くらい時間をとって書かせる。それで五分くらいでぱっとおもしろそうなのをピックアップする。最初は、いきなり名指しすると、それこそ「友達地獄」 じゃないけれどスケープゴートにされるので、「こんな意見があった。おもしろいな」というかたちで全体に投げ返してあげる。人間はみんなそうですが、同じ 教室で受けている質問は、「自分だったらこう答えるかもしれない」というように半分くらい我が事のように聞くので、そのことに対するリアクションは非常に 心に残るし、単純に満足度がぐっと上がります。単純にいちばん最後にやるアンケートを非常に短いものにするだけでいい。つまり、それに対してリアクション してあげることが大切なんです。
教室の雰囲気は一回では変わりませんが、それを習慣
化していくと、このタイミングでこのようなことを書けばいい、というように学生自身もペースがつかめま
す。そして、知識の提供とか、文献を読ますなどの部分のアウトソースは適切な教科書を使う。そのためには授業そのもののトータルデザインを変える必要があ
ると思いますが、座学でもコミュニケーション教育の利点は使えると思います。
■授業を評価するとはどういうことか?
あるの授業評価アンケートは、「声は大きかったですか」「授業はわかりやすかったで すか」「視聴覚機材は適切に使ってましたか」「服装はちゃんとしてま したか」など多項目を10点満点で評価するという非常に詳細なものです。ある私立大学で非常勤講師をやっていた頃、その大学で企画された授業評価の例題 チャートのようなアンケートがあり、私に下された学生の評価に対して弁明を求めると いうものでした。私はそのときに「服装が乱れていた」ポイントが高かっ たので、自己弁明してこういう大学の教育とは関係のない愚かな項目をによってそんなものはクソだ、そんなことするから駄目になるんだ、という反論は一応さ せてもらいました。そしてその中で私への評価が高い部分を示して「その例題チャートの中でこの部分は突出しているだろ。これが私の授業の特質なんだ」とい う弁明をしました。このような手はありますよね。
また、そのような既存の労務管理であるとか、「あな たは評判が良いけれどちゃんと教育しているのか」という問いに対する反論としては、授業評価について のメソドロジーを脱構築するのではどうでしょうか。例えば「質的にインタビューをとったらどうですか」など。それは実際に私たちのセンターではやったこと があります。あとはフォローアップです。たとえば授業を受けてから一年後にやる。そのときにユニークなデータが出たら、「教育の効は、授業が終わった時点 で満足したらOKなのか」という世間の偏見やアンケートの前提に対する一つのアンチテーゼになるわけです。
これは一人の教員だけでできることではないので、心 を同じくした同士が集まってそのようなワーキンググループをつくって、かなりしつこく具体的な改善対 策をやらないとだめですが。そういうかたちでレジスタンスというわけではないですが、「教育の評価とは何だろう」と問うていく。たんにアンケートをとれば 良い授業かどうかわかるという考え方に対するアンチテーゼ。「撒いた種にはいろいろな刈り取り方がある」というかたちで、教育効果のエビデンスの枠組みを ずらしていくというのはどうでしょう。大学はそれができる場所だと思います。あるいは、理想的にはそのような場であるべきだと私は信じています。
■大学では現場力を学ぼう!
大学では多くの人たちにとって「現場力」という言葉すら知らなかったということが未だ 多いと思います。教育や科学技術の水準は高まっているので、大学で 学ばないとならないことがたくさんある。ですから、「現場力なんて後でいい」「社会に出たら現場じゃん」という風潮が強い。「そんなことでいいのか」とい うことです。学問や知恵とは、まさに現場で役に立ち、危険を防げるもの、あるいは人間のためになる、環境のためになるものであるはずなのに、今そういうも のによって我々は苦しめられているわけじゃないですか。人災と自然災害のハイブリット災害によって苦しめられている。ですから、「現場力」ということを キーワードにして、今までのやり方、考え方とは違うものを導きたいという気持ちが大学のなかにあるので、気持ちとしては最優先事項なんです。
けれども、今の制度のなかでは、それが難しいのかも しれません。つまり、明日、明後日に授業が始まったときには、ひょっとしたら現場力みたいなものの大 切さが後回しにされる状況かもしれません。週末は「現場力が大事だ」、月曜になったら「本を読まないといけない」というような二重性のなかに、国公立を問 わず大学全体が置かれているではないかと思います。問題は、はたしてそれでいいのか?ということですね。
日本の大学生は、図書館を利用するのがとてもへたくそです。それは、日本の大学教授の多くが——欧米への長期の海外留学経験者を除いて——理系はおろか、人文社会 系の先生も、自分たちの学問を形成する途上で十分な恩恵を被ったことがないからです。だから、学生にも図書館をフルに利用するようなさまざまなノウハウを伝授する機会が少ないのです。最近 はインターネットの接続ができたり、図書館にノートパソコンを持ち込んで研究できる機会も多くなりました。しかし、紙に印刷された本を読む行為は、ネット 上における情報収集行為とは、どうも根本的に異なる経験のようです。このことが明らかにされ る以前に、図書館機能の過度の電子化がすすめられ、書物の収集や整理が蔑ろにされることは、図書館にとって致命的なことです。電子化は、紙の本のメディア としての機能を促進し、また、知の断片化や脱臨床化がなされるような利用のされ方——卑近な例ですが、インターネットでググってコピペしたものを引用の典 拠表示なしにレポートを書くこと(剽窃=ひょうせ つ、と言います)——としてのみ電子化することを大変危惧してます。そのためには、学生は図書館にどんどん押し寄せて、本のことを図書館員にじゃ んじゃん聞き、図書館はそれに応じれるくらいの実力をもたなければなりません。その点では、日本の大学図書館は、いまだ開発途上国並みです——なお、名誉 のために開発途上国にも少ないながらすごい力量と驚くべき包容力をもった司書さんがいるユニークな図書館がいっぱいあります!
リンク
文献
その他の情報
クレジット:「シンポジウム「知の現場力とはなに か」(講演と座談会の記録:共著)『臨床知と徴 候知』後藤正英・吉岡剛彦編、Pp.296-339、作品社、2012年3月(→「研究業績リスト:池田光穂」)