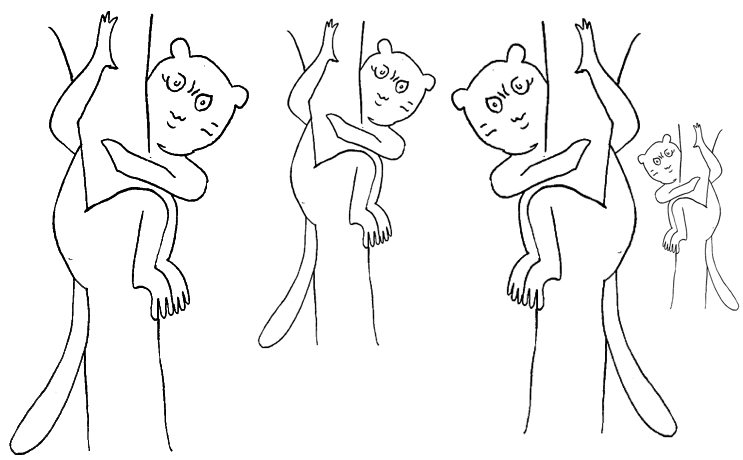
トランスクリティーク
Transcritique; Kant and Marx
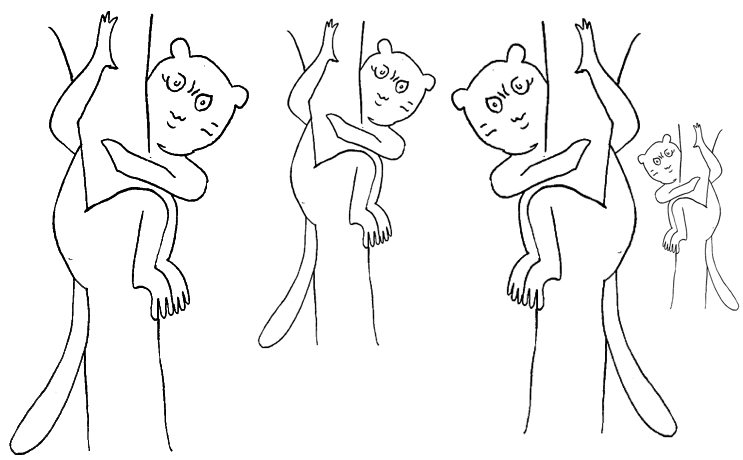
☆ 『トランスクリティーク:カントとマルクス』は柄谷行人の著作、岩波現代文庫(2010年)のほか、英語版(2003)をふくめ、さまざまな版がある。書 肆の岩波書店の紹介文→「カントによってマルクスを読み,マルクスによってカントを読む.社会主義の倫理的根源を明らかにし,来るべき社会への実践を構想 する本書は,絶えざる「移動」による視差の獲得とそこからなされる批評作業(トランスクリティーク)の見事な実践であり,各界に大きな衝撃を与えた.2003年英語版に基づき改訂.」
【序文】
| カントからマルクスを読む |
マルクスからカントをよむ |
| 批判の意味をとりもどす |
批判の意味をとりもどす |
| カント的批判 |
マルクス的批判 |
| 倫理学 |
政治経済学 |
| 主体的・倫理的契機 |
唯物論 |
| 道徳的実践的=「自由」の問題 |
資本の欲動と限界を明らかにする |
| (自他の)人間性を手段でなく目的として扱え |
|
| アソシエーションをめざす |
共産主義を志向 |
| 自由の国や目的の国はコミュニズムである |
コミュニズム |
| 『純粋理性批判』 |
『資本論』 |
| 人間理性の限界を明らかにすることを通して実践的な可能性を拓く |
柄谷は冷戦終焉(1989年)以降、未来について考えるようになる。 |
| 形而上学批判をヒュームとともに歩む(カントとヒューム共通点)=形而上学は独断論 |
ヒュームとは異なり合理性や目的論を志向する=コミュニズムという形而上学もまた独断論?(p.8) |
| ヒューム批判を通して形而上学を「取り戻す」 |
柄谷はコミュニズムという形而上学[=科学]を「取り戻したい」 |
| 純粋理性批判は超越論的主体を前提とする |
マルクスはコミュニズムを構成的理念とは考えなかった。彼は統整的理念としてそれを考えた。 |
| 『判断力批判』よりも『純粋理性批判』を(16) |
マルクスは、ヘーゲルを受けて、宗教的批判の最後は人間(=絶対知)が人間にとって最高の存在者とする(→精神現象学)。 |
| カント的な至上命令 |
マルクスにとってコミュニズムは定言命法(=至上命令)的な道徳的問題である(8) |
| カント的な意味での批判 |
マルクス的な意味での批判 |
| 超越論的(=しかし、カントには他者がいる) |
☆マルクス主義が人々のこころを捉えていた時代には、「デコンストラクション」や「知の考古学」は「効力」をもっていた。だが、しかし、……。懐疑論的相対 主義、複数の言語ゲーム(公共的合意の概念)、美学的な現状肯定、経験論的歴史主義、カルスタなどサブカルチャー重視は、(冷戦の終焉以降/共産主義の終 焉以降)支配思想すなわちヘゲモニックな階級が利用する思想になった(柄谷 2004:8)
【イントロダクション】
| ・カントの超越論的態度とはなにか?——経験に先行する形式を明るみにだす(14) ・もし我々の主観的視点が光学的欺瞞なら、他者の視点(ひいては客観的視点)もそのようなことであることをまぬかれない。(15) ・反省のメタファーは、鏡に映されるもので表現されよう(15) |
・純粋理性批判 |
| ・人は判断力批判にゆだねるが、ここは純粋理性批判だ(16) ・霊視者の夢(16) ・第一部はカントの読み直し、第2部はマルクス ・資本論と視差(17) |
・判断力批判 |
| ・マルクスは(エンゲルスと異なり)宗教批判にずっとこだわっていた(19) ・国家と資本批判の提要は、国家と資本が「宗教」的意味を負っているからだ(19) ・資本主義は「力」であり、宗教的なものだ ・商品は、よくよく考えると、形而上学的な小理屈や神学的偏屈さにみちたものだ(19) |
・ヘーゲル法哲学批判序説 ・G.W.F.ヘーゲル『法の哲学』1821 ・「資本主義の生産」 |
| ・グルントリッセから資本論の移行における懐疑論(サミュエル・ベイリーのリカード労働価値説の批判)(20) ・商品の価値は、他の商品との関係にしかない、つまり労働価値説は幻想だ(というベイリーの批判)(20) ・ベイリーの批判は、デカルトに対するヒュームの批判に似ている。 ・カントは、自己は仮象であるが、超越論的統覚Xがある——このXを何らかの実体にしてしまうのが「形而上学」 ・われわれは、Xを経験的実体としてとらえようとする欲動からは逃れられない。 ・自己はたんなる仮象ではなく、調節論的な仮象だ(カント)(21) ・マルクスは、ベイリーが商品と商品の関係しか見ておらず、そこに貨幣が媒介することが抜け落ちていると批判(21) ・ものではなく、ものが置かれる関係の場を、考えよ(21) |
|
| ・では、マルクスにとって、なぜ貨幣か?——それは一般的等価形態におかれることだ。 ・商品は「相対的価値形態」をもち、貨幣は「等価形態」をもつ(22) ・守銭奴を考える:守銭奴は物=使用価値への欲望ではなく、等価形態にある物への欲動である(22) ・守銭奴は、資本の蓄積欲動をもつ。それは、交換可能性の権利を蓄積しようとする(→守銭奴は交換という権利を行使しない) ・価値形態論におけるマルクスの「重要な移動」のひとつは、使用価値あるいは、流通過程の重視である(23) |
|
| ・マルクスは、使用価値と交換価値の区分を廃棄する。商品には交換価値などない。 |
|
| ・資本論は、恐慌がもたらした、強い視差 ・資本の自己実現(ヘーゲルに同一化する)のように資本主義を描写した(24) ・一切の秘密が価値形態論にある。 ・交換のあやうさは、決済のかたちであらわれる(24) ・恐慌はマルクスにとって強い視差だった ・資本は世界を組織しながらも、同時に自らの限界をこえない——これが「資本論」の世界(25) ・資本とは増殖する貨幣であり、G—W—G' すなわち(貨幣)—(商品)—(貨幣)'の運動の過程にある(25) |
「生
産様式(mode of production)」 とはマルクス主義経済 学の中心的概念の一つで
あり、人間の財貨の生産の様相(モード)のことである。資本主義は、古典派経済学ならびにマルクス主義では、G—W—G'
すなわち(貨幣)—(商品)—(貨幣)' 、資本=貨幣を増殖するプロセスのことである。 |
| ・恐慌は資本主義が永続的に発展するプロセスのひとつだ(28) ・貨幣や信用の世界とは、経済的なものよりも、宗教的なものの世界である(28) ・マルクスは、価値形態を考察したあとで、商品交換の発生を歴史的に考察する(28-29) ・商品交換は、共同体どうしではじまる(29) ・共同体の外で商品になった瞬間に、共同体のなかでも商品になる(化ける)(29)——資本論第1巻第2章 ・1)共同体の中の交換は、互酬である ・2)共同体と共同体の関係のなかには、強奪がある ・3)共同体間のあいだに商品交換もある(30) |
・交換(「資本論」) |
| ・ネーションとステートの間は異種的な結婚だ(B・アンダーソン)(30) ・柄谷はこれをうけて、国家と資本のあいだも、異質な結婚と主張(30)→それを実現させたのがブルジョア革命(31) |
・ベネディクト・アンダーソン『想像の共同体』論 |
| ・エンゲルスの古典的革命概念の放棄(33) |
|
| ・アソシエーションの可能性(34) ・ゴータ綱領批判(35) |
|
| ・商品とは相対的価値形態におかれる(物、サービス、労働力) ・貨幣は等価形態におかれるもの(37) ・マルクスは、階級関係や、文化、言説の多様性に敏感だった(ブリュメール18日) |
・ルイ・ボナパルトのブリュメール18日 |
| ・相対的価値形態(商品)と等価形態(貨幣)の非対称的な関係はつづいたままである(38) ・価値形態において場が主体を規定する(39) |
|
| ・資本にとって、消費は剰余価値が最終的に実現される場である。消費は、消費者の意思に従属させられる。(40) ・売りと買いは、分離させられている。生産と消費は分離している。 ・労働者は消費者であるのに、消費者から労働者を切り離し、資本制では、あたかも、企業と消費者が経済主体であるかのように見せられている(40) |
|
| ・労働者が資本に対抗しうる点:1)働くな(アントニオ・ネグリ)、2)資本制の商品は買うな(マハトマ・ガンジー) |
|
| ・ポランニーは、資本制を社会のがんであるかのように捉えた(43) |
|
| ・流通過程に関与することは、合法的であり、非暴力だ(アソシエーションの正当化?)(43-44) ・トランスポジショナルなモーメントが、そこにはある(44) |
☆
| 序文 イントロダクション ――トランスクリティークとは何か |
(承前) |
| 第一部 カント |
|
| 第一章 カント的転回 1 コペルニクス的転回 2 文芸批評と超越論的批判 3 視差と物自体(69-) |
・コペルニクス的転回は単に、天動説→地動説ということではない(48-)——カントにとっては「物自体」 ・カント「感性的直感能力は、受容性にほかならない」(48) ・ハイデガーを例外として、他の哲学者は「物自体」を拒否した(ハイデガー「カントと形而上学の問題」)(49) ・コペルニクスは終生(少なくとも表面的には)プロレマイオスの宇宙論にしたがい、天文学者だけが地動説を理解するように書いた(トーマス・クーン「コペルニクス革命」) ・太陽が地球を回るようにした際の、回転運動のズレが、その逆とした時に、解消するように説明しただけで、後者のように実際にそうなっていると主張したのではない(51-51) ・フロイトの評価(54-) ・カントの超越論的の代わりに「トランスクリティーク」を使う(56)——カントの思想の要衝は主観性の哲学ではなく、物自体の哲学である。(→「超越論的哲学」) ・カント以前と以後で、科学認識、道徳、芸術は大きく変化する(57) ・ヘーゲルは、哲学を芸術の上におくが、それはすでに哲学が美学化されているからだ(57) ・柄谷によると、純粋→実践→判断力と展開するのではなく、判断力の議論が最初からあり、それが純粋の議論の出発点になるという(57-58)(63)(66)→趣味判断における普遍的理性(80) ・趣味判断は要請するのではなく、要求する(60) ・カントの共通感覚(61) ・視霊者の夢(72-73)のなかに、他者の視点の議論がある ・反省は、他人の視点で自分をみることだ(73) ・カントの超越論は、他者からみることと自己のあいだの視差による(76)——それは光学的欺瞞 ・カントのアンチノミーに視差はあらわれる(→「純粋理性のアンチノミー」「アンチノミーまたは二律背反」)(76) ・同一性の自己がある(デカルト)は純粋理性の誤謬推理だとカントはいう(77) ・同一性の自己がある(テーゼ)、同一性の自己などない(アンチテーゼ)→その弁証論的解決「超越論的主観X」(77) ・カントの宗教は、超越論的仮象、統整的理念として存在する(79) |
| 第二章 総合的判断の問題 1 数学の基礎 2 言語論的転回 3 超越論的統覚 |
・メノンにおける数学的教育(101) ・ソクラテスのやり方は法廷の形式(102) ・カントの綜合判断(103) ・ウィトゲンシュタインとソクラテス対話(104) ・超越論的統覚(110-) |
| 第三章 Transcritique 1 主体と場所 2 超越論的と横断的 3 単独性と社会性 4 自然と自由 |
・方法序説によるシナ人やカニバル(118) ・(デカルト)真理は共同体の文法や慣習にもとづく差異である(118)→この部分では、デカルトは独我論ではない。 ・レヴィ=ストロース「私の未開人」(121) ・デカルトのゴギトは人類学的コギトだ——ジェイムズ・クリフォード(122)(→「方法序説 第四部」) ・デカルトを擁護する(125) ・デカルトには、私は疑うと私は思うが、両義的に提示される(126) ・フッサールの超越論的現象学(128)(→「超越論的哲学」) ・フッサールは、カントの超越論という言葉をつかいながら、さらに遡行して、デカルトまでたどりつく(デカルト的省察)(133) ・デカルトはフッサールがそう考えたような思想家ではない(134) ・デカルトに疑問を強いているのは、時間空間的な差異であり、自分が属している共同体にとって異なるものだ(135)(→異文化) ・カントは共同体あるいは国家なるものを私的なものとしてみている(179) ・個別性/普遍性に関するルカーチのヘーゲル的なカント批判(151) ・社会性とは他者との関係だ(155) ・固有名(164) ・超越論的態度は倫理的(165)(175) ・スピノザと決定論に関するコメンタリー(169) ・カントにおける自由の意味は、事後性にある(171) ・自己、主体、自由を証明する(173) ・カントにおいて倫理的な対象は、死者や未来の人を含むことができるのか?——実践倫理的な意味での定言命令のリストに収載されるか(185-187-188) ・カントにとって「物自体」は他者(187)——対象が我々の認識を形づくるのではなく、我々の認識が対象を形成する(ノート) ・カントは倫理的な対象は、死者や未来の人を含むことができると考えていたようだ(187-188) ・カントの道徳論は、根本的に経済的(190) |
| 第二部 マルクス |
Pp.198- |
| 第一章 移動と批判 1 移動 2 代表機構 3 恐慌としての視差 4 微細な差異 5 マルクスとアナーキストたち |
・マルクスは体系化を拒否する(198) ・マルクスの思考は超越論的だ(199) ・コペルニクス的転回(202) ・カントの批判はトランスクリティーク(202) ・マルクスは、エンゲルスが史的唯物論に移行していたのに、手間取ったのは、ヘーゲル宗教論にとりかかって=固執していたから(208) ・ブリュメール18日と、ヘーゲル歴史哲学の皮肉な関係 ・マルクスは普通選挙における代表には懐疑的(220) ・真理を表象において見出す近代思想をハイデガーは批判(221) ・資本は増殖する貨幣:G-W-G'そのもの(228) ・金融資本は自己増殖:G-G' ・資本はヘーゲルの精神に類似する(232) ・法哲学における歴史の終焉(234) ・エピクロスとデモクリトスのあいだの差異=視差(238) ・資本論の独自性は価値形態論にあり(241) ・マルクスのアソシエーション志向(245) ・プルードンの思考は流通過程にたいする闘争だが、産業資本の(野放図な)成長を知るマルクスには、それが耐えられない(262) ・マルクスのいうプロレタリア独裁(274) |
| 第二章 総合の危機 1 事前と事後 2 価値形態 3 資本の欲動 4 貨幣の神学・形而上学 5 信用と危機 |
・資本論を、経済学のみならず、マルクスの哲学や革命論として読むべし(280) ・資本の蓄積運動は、G-W-G'そのもの(281) ・アダム・スミス:商品とは使用価値と交換価値である。——アダム・スミスは商品交換と交換一般を区別しない(311) ・資本論における価値形態論(292) ・あるものが商品であるか、貨幣であるかは、それが置かれた位置による(295) ・お金(兌換される金銀)のみが価値として、モノとの相対的な意味をもちはじめる(貨幣形態が消えて、価値形態そのものになる)(298-299) ・この価値形態論こそコペルニクス的転回だ(302-303) ・リカードは独断論、ベイリーは経験論(懐疑論)(303) ・商品交換は、共同体がおわるところで始まる(307) ・シェイクスピア(323) |
| 第三章 価値形態と剰余価値 1 価値と剰余価値 2 言語学的アプローチ 3 商人資本と産業資本 4 剰余価値と利潤 5 資本主義の世界性 |
・資本増殖の「欲動」(342) ・産業資本の資本の増殖はG-(Pm+A)-G' なのに、マルクスは商品資本の流通(資本の増殖)について G-W-G'について焦点化して考えた(なぜか?)(354) ・G-WとW-G'が[つまり売りと買いが]それぞれの別のところで起こる(=時間的脱臼でもある)ことが加速するとと、売りと買いの間の本質的統一が強力に自己主張をする、それが恐慌だ(資本論1巻1編3章2節a)(354) ・ヴァレリーの芸術論(356-358)「芸術についての考察」(第5巻) ・「循環を媒介するもの」 |
| 第四章 トランスクリティカルな対抗運動 1 国家と資本とネーション 2 可能なるコミュニズム |
・近代世界システム論・批判(404) ・近代絶対主義王権国家への着目(406) ・カール・シュミット:主権者は不可視であるが、例外状況のにおいて決断者としての主権者が露出する(シュミット「政治神学」) ・資本のメタモルフォシスを価値形態における場所変換にみる(440) |
| 岩波現代文庫版あとがき |
★トランスクリティークの定義は上でこのように書かれています:「絶えざる「移動」による視差(パララックス)の獲得とそこからなされる批評作業」だと。
| ■編集部からのメッセージ 本書は柄谷行人氏の主著として,海外でも広く知られています.しかし本書に初めて出会われた方の中には本書の書名について,イメージを持ちにくいという 方がおられることでしょう.とりあえずトランスクリティークとは「移動と視差(parallax)による批評」とご理解いただければ幸いです.それでは,本書では何を批評しよ うとしているのでしょうか. 「序文」には本書の位置づけが以下のように書かれています. 「本書は二つの部分,カントとマルクスに関する考察からなっている.この二つは分離されているように見えるけれども,実際は分離できないものであって, 相互作用的に存在する.私がトランスクリティークと呼ぶものは,倫理性と政治経済学の領域の間,カント的批判とマルクス的批判の間の transcoding,つまり,カントからマルクスを読み,マルクスからカントを読む企てである.私がなそうとしたのは,カントとマルクスに関する共通 する「批判(批評)」の意味を取り戻すことである.いうまでもなく,「批判」とは相手を非難することではなく,吟味であり,むしろ自己吟味である」. そして本書の問題意識として「イントロダクション」では,「視差」の重要性が記されています.マルクスを衝き動かしたものは自分の視点だけで他人の視点 だけで見ることではなく,「それらの差異(視差)から露呈してくる「現実」に直面することである」.そして著者は述べています.「重要なのは,マルクスの 批判がつねに「移動」とその結果としての「強い視差」から生まれていることだ.カントが見いだした「強い視差」は,カントの主観主義を批判し客観性を強調 したヘーゲルにおいて消されてしまった.同様に,マルクスが見いだした「強い視差」は,エンゲルスやマルクス主義者によって消されてしまった.その結果, 強固な体系を築いたカント,あるいはマルクスというイメージが確立されたのである.しかし,注意深く読めば,このようなイメージがまったく違うということ がわかる」. 以上の課題意識に基づいて,本書が書かれていること.何よりもカント⇔マルクスという水脈をいかに見いだしていくかという著者の立場が哲学史の再検討に とどまらず,カントによってマルクスを読み,マルクスによってカントを読む――社会主義の倫理的根源を明らかにし,来るべき社会に向けての実践を構想する という課題そのものであることが理解されるのではないかと想います.その意味で本書の第四章は飾り物ではなく,資本,国家,ネーションという三つの基礎的 な交換様式をふまえ,さらにそれを超える交換様式(アソーシエーション)という思想の提示として,現代世界論が示されているという必然性も理解されるもの と思われます. 「岩波現代文庫版あとがき」で柄谷氏は,本書においてヘーゲル批判という問題意識がどれほど強いものであったかを次のように述べています. 「私の考えでは,資本・ネーション・国家を相互連関的体系においてとらえたのは,『法の哲学』におけるヘーゲルである.それはまた,フランス革命で唱えら れた自由・平等・友愛を統合するものでもある.ヘーゲルは,感性的段階として,市民社会あるいは市場経済の中に「自由」を見出す.つぎに,悟性的段階とし て,そのような市場経済がもたらす富の不平等や諸矛盾を是正して「平等」を実現するものとして,国家=官僚を見出す.最後に理性的段階として,「友愛」を ネーションに見出す.ヘーゲルはどの契機をも斥けることなく,資本=ネーション=国家を,三位一体的な体系として弁証法的に把握したのである. ヘーゲルはイギリスをモデルにして近代国家を考えていた.ゆえに,そこにいたる革命は今後においても各地にあるだろう.しかし,この三位一体的な体制が できあがったのちには,本質的な変化はありえない.ゆえに,そこで歴史は終わる,というのがヘーゲルの考えである.もちろん,ヘーゲル以後にも歴史はあっ た.しかし,本質的な変化は存在しないというほかない.『法の哲学』は今なお有効なのである.ここでもし歴史は終わっていないというのであれば,あれこれ の出来事があるというだけではなく,資本=ネーション=ステートを越えることが可能であるということを示さなければならない. 私が本書で試みたのは,そのようなヘーゲルの批判である.もちろん,私は正面からヘーゲルを扱わなかった.そうするかわりに,カントとマルクスを論じた のである.カントをマルクスから読むとは,カントをヘーゲルに乗り越えられた人ではなく,ヘーゲルが乗り越えられない人として読むことだ.マルクスをカン トから読むとは,カントがもっていたがヘーゲルによって否定されたしまった諸課題の実現を,マルクスの中に読むことだ. しかし,私がヘーゲルのことをあらためて意識したのは,『トランスクリティーク』を日本で出版したあとまもなく起こった事件,すなわち,二〇〇一年の 9/11事件,そして,イラク戦争においてである.この時期,アメリカのネオ・コンは,ヨーロッパが支持した国連を,カント主義的夢想として嘲笑した.彼 らは,フクヤマとは違ったタイプのヘーゲル主義者だった.ヘーゲルは,カントのいう国家連合には,それに対する違反を軍事的に制裁する実力をもった国家が ないから,非現実的だと述べた人である.このとき,私はあらためてカントについて,特に『永遠平和』の問題について考えるようになったのである. 『トランスクリティーク』において,私は国家がたんなる上部構造ではなく,自律性をもった主体(エージェント)だということを書いている.それは,国家 が先ず他の国家に対して存在することから来ている.したがって,他の国家がある以上,国家をその内部からだけでは揚棄することはできない.ゆえに,一国だ けの革命はありえない.ゆえに,マルクスもバクーニンも,社会主義革命は「世界同時革命」としてしかありえないと考えていた.しかし,本書を書いたとき, 私はこの問題をさほど深刻に考えていなかった.各国における対抗運動がどこかでつながるだろうと考えていたのである.二〇〇一年以後の事態が示したのは, 何もしないなら,各国の対抗運動は資本と国家によって必ず分断されてしまうだろう,ということだ. ところで,一国だけでは成り立たないのは,社会主義革命だけではない.ルソー的な市民革命もそうである.たとえば,フランス革命はたちまち,諸外国から の干渉と侵入に出会った.そのことが内部に恐怖政治をもたらし,他方で,革命防衛戦争から(ナポレオンによる)征服戦争に発展していったのである.カント はその過程で『永遠平和のために』(一七九五年)を発表したが,そのずっと前に,ルソー的な市民革命がそのような妨害に出会うこと,ゆえに,それを防ぐた めに諸国家連合が必要だということを考えていた.つまり,「永遠平和」のための構想は,たんなる平和論ではなく,いわば「世界同時革命」論として構想され たのである.だからこそ,ヘーゲルはカントに反対し,ナポレオン戦争を通してヨーロッパ各地に生まれた,資本=ネーション=国家こそ,最終的な社会形態で あると考えたのである. 私は本書において,交換様式から社会構成体の歴史を見る視点,さらに,資本=ネーション=ステートを越える視点を提起した.しかし,それはまだ萌芽的な ものでしかないことを,私は認める.以後の私の仕事は,それをもっと詳細に,全人類史において解明することであった.そのために,一〇年ほどの時間が必要 であった.それは『世界史の構造』(岩波書店,2010年)という本である.『トランスクリティーク』の続編として読んでいただけると幸いである.」 以上に示されているように,本書は極めて豊かな構想力に裏付けられた書物です.ただじっくりと読み進めていただければ,本書は,岩波新書『世界共和国へ』の広大な理論的後背地を明らかにした仕事としてご理解いただけるのではないかと思います. 本書は2001年,批評空間社から刊行され,03年MITプレスからかなりの加筆がなされた上で英語版が刊行され,その後改訂された上で04年3月に小社から『定本 柄谷行人集』の第三巻として刊行されました.現代文庫では『定本 柄谷行人集』を底本としています. 本書のご一読をぜひお勧めするものです.そして岩波新書『世界共和国へ』,そして本年に刊行予定の『世界史の構造』にもぜひご注目いただきたいと思います. |
序文 イントロダクション――トランスクリティークとは何か 第一部 カント 第一章 カント的転回 1 コペルニクス的転回 2 文芸批評と超越論的批判 3 視差と物自体 第二章 総合的判断の問題 1 数学の基礎 2 言語論的転回 3 超越論的統覚 第三章 Transcritique 1 主体と場所 2 超越論的と横断的 3 単独性と社会性 4 自然と自由 第二部 マルクス 第一章 移動と批判 1 移動 2 代表機構 3 恐慌としての視差 4 微細な差異 5 マルクスとアナーキストたち 第二章 総合の危機 1 事前と事後 2 価値形態 3 資本の欲動 4 貨幣の神学・形而上学 5 信用と危機 第三章 価値形態と剰余価値 1 価値と剰余価値 2 言語学的アプローチ 3 商人資本と産業資本 4 剰余価値と利潤 5 資本主義の世界性 第四章 トランスクリティカルな対抗運動 1 国家と資本とネーション 2 可能なるコミュニズム 岩波現代文庫版あとがき |
| https://www.iwanami.co.jp/book/b255864.html |
|
| Kojin
Karatani's Transcritique introduces a startlingly new dimension to
Immanuel Kant's transcendental critique by using Kant to read Karl Marx
and Marx to read Kant. In a direct challenge to standard academic
approaches to both thinkers, Karatani's transcritical readings discover
the ethical roots of socialism in Kant's Critique of Pure Reason and a
Kantian critique of money in Marx's Capital. Karatani reads Kant as a philosopher who sought to wrest metaphysics from the discredited realm of theoretical dogma in order to restore it to its proper place in the sphere of ethics and praxis. With this as his own critical model, he then presents a reading of Marx that attempts to liberate Marxism from longstanding Marxist and socialist presuppositions in order to locate a solid theoretical basis for a positive activism capable of gradually superseding the trinity of Capital-Nation-State. |
柄
谷行人の著書『トランスクリティーク』は、カール・マルクスをカントで読み、カントをマルクスで読むという手法により、イマニュエル・カントの『超越論的
批判』に驚くほど新しい次元を導入している。両思想家に対する従来の学術的アプローチに真っ向から異議を唱えるこの著書では、カントの『純粋理性批判』に
おける社会主義の倫理的ルーツと、マルクスの『資本論』におけるカント的な貨幣批判が発見されている。 柄谷はカントを、信頼を失った理論的教義の領域から形而上学を奪い取り、倫理と実践の領域に本来あるべき場所に戻そうとした哲学者として読んでいる。これ を自身の批判モデルとして、彼は次に、資本論、国民国家、マルクス主義の三位一体を徐々に凌駕する積極的な行動主義の確固たる理論的基盤を確立するため に、マルクス主義を長年のマルクス主義的・社会主義的前提から解放しようとするマルクスの解釈を提示している。 |
| An
immensely ambitious theoretical edifice in which new relations between
Kant and Marx are established, as well as a new kind of synthesis
between Marxism and anarchism. The book is timely from both practical
and theoretical perspectives, and stands up well against a tradition of
Marx exegesis that runs from Rosdolsky and Korsch to Althusser and Tony
Smith. Fredric Jameson, William A. Lane Professor of Comparative Literature, Duke University, author of Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism |
カ
ントとマルクスの新たな関係が確立され、マルクス主義とアナーキズムの新たな統合が図られた、非常に野心的な理論的構築物である。この本は、実践的にも理
論的にも時宜を得たものであり、ロズドルスキーやコルシュからアルチュセールやトニー・スミスに至るマルクス解釈の伝統に十分対抗できる。 フレドリック・ジェイムスン、デューク大学比較文学ウィリアム・A・レーン教授、著書『ポストモダニズム、あるいは後期資本主義の文化論』 |
| https://mitpress.mit.edu/9780262612074/transcritique/ |
|
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆