Cross-boundary Studies of Rethinking of
Global Studies from the
Indigenous people's points of views
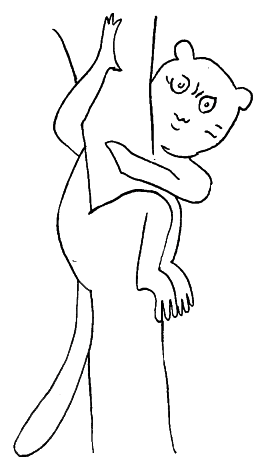

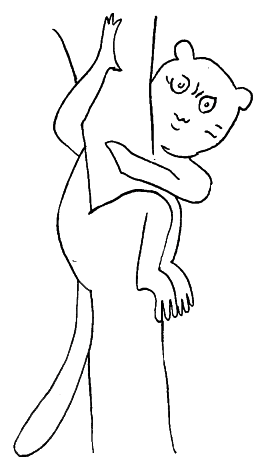
Cross-boundary Studies of Rethinking of
Global Studies from the
Indigenous people's points of views
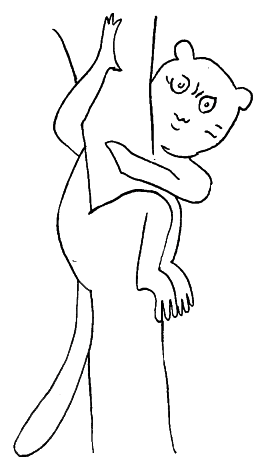

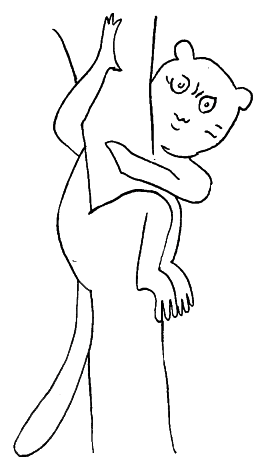
| こ
のページは、日本学術振興会が時限付き(平成28年〜平成
30年:2016-2018年度)で公募テーマを設けた、科学研究費委員会特設分野研究部会グローバル・スタディーズ小委員会が運営マネジメントした「グ
ローバル・スタディーズ」の枠組みについて的確に考え、批判し、そして、その改善にむけて提言するために、設けられたものである(→「グローバル・スタ
ディーズの諸相」)。 |
★当時の審査員のメンバーは下記のとおりである。こ の人たちが合議により、この分野の設置を決定し、「グローバル・スタディーズ」の科目をきめられた可能性がある。
◎グローバル・スタディーズとはなにか?
グローバル・スタディーズは、地球研究のことではない。グローバル・ イシュー(地球規模の課題)に取り組むための、基礎研究と応用研究のアンサンブルのことである。 グローバルな現象が、グローバル・イシューになるためには、世界の諸要素の連結と相互依存(=お互いの影響関係)がみられるため、それらを、過去から現在 までつづく関係の連鎖として把握し、現今のイシュー(課題)のあり方の構造を解釈規定し、そして、その構造が未来においてどのように変化しうるのかと分析 する。
すなわち、グローバル・イシュー(地球規模の課題)とよばれる地球レベルでの喫緊の課題、すな わち温暖化や人新世などの地球環境問題から、移民や難民などの人文社会的問題まで、多岐にわたる分野の問題を解決するためには、もはや、個別のディシプリ ン(学問分野)に個々の研究者は留まっていてはならない。そのために、グローバル・イシューの課題を設定すれば、分野をこえた研究者集団を組織し、学際的 な共同研究・共同調査を基調として、それらの問題に多角的に取り組まなけばならないというものである。
◎グローバル・スタディーズはどのような問題意識から出発しているか。
繰り返しになるが、グローバル・イシュー(地球規模の課題)とよばれる地球レベルでの喫緊の課題、すな わち温暖化や人新世などの地球環境問題から、移民や難民などの人文社会的問題まで、多岐にわたる分野の問題を解決するためには、もはや、個別のディシプリ ン(学問分野)に個々の研究者は留まっていてはならない。そのために、グローバル・イシューの課題を設定すれば、分野をこえた研究者集団を組織し、学際的 な共同研究・共同調査を基調として、それらの問題に多角的に取り組まなけばならないというものである。
◎グローバル・スタディーズは、世界の開発問題から起源するという点で、SDGsの誕生と軌を一にしている。
国連開発計画(United Nations Development Programme , UNDP )は、1965年に出発した地球レベルでの経済開発計画である。UNDPはさらに、その前には、the Expanded Programme of Technical Assistance (EPTA) と、個々の基金を統合する形で登場したのである。国連は10年単位で、さまざまな国際計画を立案し、宣言してきたが、UNDPは、1990年になり、 Human Development Report 1990, by the UNDP. (In 1990, the UN Development Programme launched the first Human Development Report.)すなわち『人間開発報告』をまとめて、世界の途上地域において、さまざまな課題達成を報告しているが、それらを統合する人間開発計画がさ らに必要であると勧告した。そのため、1990年からの10年間を、 Millennium Development Goals (MDGs)すなわち「ミレニアム開発目標」を達成するための期間であることを正式にアナウンスした。そして、2000年にミレニアム宣言をまとめ、8つ のゴールと21のターゲットを策定した。それから15年後に、The Post-2015 Development Agenda を策定することになり、それが、2016年から2030年までの、持続可能な開発目標(UN Sustainable Development Goals, SDGs)に繋がるのである(→「国連の持続可能な開発目標とグローバル・ イシューズ」)。当然、SDGsの通称であり「グローバル・ゴールズ」は、本研究領域である、グローバル・スタディーズと陰に陽に関わっているこ とは明らかである。
◎グローバル・スタディーズに欠けている視点の存在
グローバル・イシュー(地球規模の課題)を考える際に、もはや解決済みのもの、あるいは、今後は確実に消滅し、未来のイシューの解決にそれ ほど寄与しないものを切り捨てる可能性がある。現実に、私たちが関わり研究している、民族や文化の多様性は、グローバル化のなかで均質化するか、あるいは 多様化するにしても、他者の存在を脅かすような原理主義的かつ分離主義的なものは飼い慣らされるか、排除される。先住民の存在はグローバル・スタディーズ の中で等閑視される可能性をもつ。
◎2008年グローバル・スタディーズ・コンソーシアムの開催
| Global studies (GS)
or global affairs (GA) is the interdisciplinary study of global
macro-processes. Predominant subjects are global politics, economics,
and law, as well as ecology, geography, culture, anthropology and
ethnography. It distinguishes itself from the related discipline of
international relations by its comparatively lesser focus on the nation
state as a fundamental analytical unit, instead focusing on the broader
issues relating to cultural and economic globalization, global power
structures, as well of the effect of humans on the global environment.
Prominent topics include migration, climate change, global governance
and globalization. |
グローバル・スタディーズ(GS)またはグローバル・アフェアーズ
(GA)とは、グローバルなマクロプロセスに関する学際的な研究である。主な対象は、グローバルな政治、経済、法律、そして生態学、地理学、文化、人類
学、民族学などである。その代わりに、文化や経済のグローバル化、グローバルな権力構造、人間が地球環境に及ぼす影響など、より広範な問題に焦点を当てま
す。主なテーマは、移民、気候変動、グローバル・ガバナンス、グローバリゼーションなどである。 |
| Six defining characteristics of
global studies were identified by scholars at the first annual meeting
of the Global Studies Consortium in Tokyo in 2008:[2] - Transnationality; which highlights the focus on global processes; rather than the connections between individual states studied in international relations; - Interdisciplinary: global studies scholarship can involve politics, economics, history, geography, anthropology, sociology, religion, technology, philosophy, health as well as the study of the environment, gender, and race; - Contemporary and historical examples range from the transnational activity of the Greek and Roman Empires to modern European colonialism; - Postcolonial and Critical-theoretical in its approach: global studies often emphasizes a postcolonial perspective, and attempts to analyze global phenomena through a critical-theoretical, multicultural lens. This includes criticising perspectives of eurocentrism and orientalism in traditional conceptual frameworks. |
2008年に東京で開催されたグローバル・スタディーズ・コンソーシア
ムの第1回年次総会で、研究者たちはグローバル・スタディーズを定義する6つの特徴を明らかにした。 - トランスナショナル性:国際関係で研究される個々の国家間のつ ながりではなく、世界的なプロセスに焦点を当てることを強調する。 - 学際性:グローバル・スタディーズの研究には、政治、経済、歴 史、地理、人類学、社会学、宗教、技術、哲学、健康、さらに環境、ジェンダー、人種などの研究が含まれる。 - 現代および歴史的な例としては、ギリシャ・ローマ帝国の国境を 越えた活動から、近代ヨーロッパの植民地主義に至るまで、さまざまなものがある(→「人新世」)。 - ポストコロニアル、批判理論的アプローチ:グローバル・スタ ディーズは、しばしばポストコロニアルな視点を強調し、批判理論的、多文化的なレンズを通してグローバルな現象を分析しようとする。これには、従来の概念 的枠組みにおけるヨーロッパ中心主義やオリエンタリズムの観点を批判することも含まれる。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Global_studies |
https://www.deepl.com/ja/translator |
◎【批判的観点:01】人新世とプランテーション新世:Anthropocene and Plantationocene
もし、人新世(Plantationocene.html)という概念が、グローバル・スタディーズに影響をうけつつ登場したとすれば、 「プ ランテーション新世(Plantationocene)」は、それに似ていながら、その概念の政治的中立性というカモフラージュを払拭し、地球全体の人類 の苦境を表現する対抗的な概念で あることがわかるだろう。
人新世とは「人為的な気候変動に限らず、地球の地質や生態系に人類が大き な影響を及ぼし始めた時期から始まる地質学的なエポックの提案である。2022年2月現在、国際層序委員会(ICS)も国際地質科学連合(IUGS)も、 この用語を地質学的時間の区分として公式に承認しているわけではない。しかしながら、この地質時代区分は、第二次世界大戦後に社会経済や地球システムのト レンドが飛躍的に増加した「大加速」の 開始時期や「原子時代(the Atomic Age)」と重なる。人新世の開始時期については、12,000〜15,000年前の農業革命の始まりから1960年代まで、様々なものが提唱されてい る。しかし、1950年代の原爆実験による放射性核種の降下量のピークを、人新世の始まりとする説が有力で、1945年の最初の原爆の爆発、あるいは 1963年の部分的核実験禁止条約が制定された頃とされている」出典「」)。
他方、プランテーション新世(Plantationocene)は、「人新世」に代わる用語として「人新世の起源 を近世のアメリカ大陸
における植民地主義の始まりとし、プランテーションの歴史に注目することで、その背後にある暴力的な歴史を浮き彫りにした」かたちで提示された。プラン
テーション新世(Plantationocene)とは「スペインとポルトガルの植
民者が、1,500年代までに、大西洋諸島で100年前に開発したプランテーションのモデルをアメリカ大陸に輸入し始めたことからはじまる(→「生態学的
帝国主義」)。これらのプランテーションのモ
デ
ルは、移住による強制労働(奴隷制)、集約的な土地利用、グローバル化した商業、絶え間ない人種的暴力に基づくもので、これらすべてが世界中の人間および
人類以外の生物の生活を一変させた。現在および過去のプランテーションは、植民地主義、資本主義、人種差別の歴史と、気温上昇、海水面の上昇、有害物質、
土地の処 分などに対して他の人間よりもリスクが大きい環境問題を切り離すことができないという」点で重要なのである(出典)。
◎【批判的観点:02】今日、世界レベルで指摘されることをなんでも突っ込めばグローバル・スタディーズになるのではないか?という批判
今日、世界レベルで指摘されることをなんでも突っ込めばグローバル・スタディーズになるのではないか?という批判。これは、上掲の解説にあ るように、「トランスナショナル性」や「学際性」というものを謳いすぎると、玉石混交、呉越同舟のなんでもありの路線につながってしまうのではないという 批判が可能である。そのために、焦点がぼけて、また論争のためのフォーカスが保てず、いわゆる「ノーマルサイエンス(通常科学[化])」という枠組みの なかでの、「パズル解き」すら生じない、学問領域と しては、不活性な結果におわってしまうのではないか、という危惧が考えられる。
◎【批判的観点:03】グローバルなコンテクストの中で動く主体(エージェンシー)=先住民の観点からみると
グローバルなコンテクストの中で動く主体(エージェンシー)例えば、先住民という観点からみると、(a)グ ローバル化現象にまつわる視点が西洋近代の中心地からの眼差しにより構成され、(b)近代の普遍化がグローバル化と同一視されていることを、批判できないだろ うか? もし(c)グローバル化が「世界の連結」現象であるならば、連結されている 末端は先住民を含む周辺民族である。だが現在のグローバル・スタ ディー ズは周辺からの声を研究に反映しているであろうか。(d)先 住民はグローバル化現象における「土地との絆を保ち」「伝統的生業形態のもとで」「現地の文化の担い 手」として固定的な機能を果たす代名詞になっていないだろうか(→「先住民のステレオタイプ批判」)。もちろんそうではない。(e)周辺からの声や眼差しに応えようとする研究こそが求められている(→「作業ファイル: 先住民の視点からグ ローバル・スタディーズを再考する」)。
以上の、5つの審問を、わたくしたちの研究に対する審問とする。
(a)グローバル化現象にまつわる視点が西洋近代の中心地からの眼差しにより構成されていないか?
(b)近代の普遍化がグローバル化と同一視されてはいないか?
(c)グローバル化が「世界の連結」現象であるならば、連結されてい る末端は先住民を含む周辺民族である。だが現在のグローバル・スタ ディー ズは周辺からの声を研究に反映しているであろうか?
(d)先住民はグローバル化現象における「土地との絆を保ち」「伝統 的生業形態のもとで」「現地の文化の担い 手」として固定的な機能を果たす代名詞になっていないだろうか?
(e) 周辺からの声や眼差しに応えようとする研究になっているだろうか?
クレジット
このページは、池田光穂(研究代表)「先住民の視
点からグローバル・スタディーズを再構築する領域横断研究(KAKEN)」(課題番号:18KT0005)による助成を得たものである。(総合資
料)10桁パスワード(pdf): shiryo_shu180903s.pdf(科研研究会の内部資料ですので未公開です)

■本研究に至る過程(ここからのリンクは、10桁パスワード(pdf)等)※現在この10桁パスワードを失念したために、ファイルが開くことが できない状態です。そのため関連するページにリンクしています。
書式
リンク(先住民)
リンク(グローバルスタディーズ関係)
文献
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
Do not paste, but
[Re]Think our message for all undergraduate
students!!!