音楽人類学・民族音楽学
Anthropology of music experience, ethno-musicology
Frances
Densmore (1867-1957) recording Blackfoot chief Mountain Chief for
the Bureau
of American Ethnology in 1916// Conjunto musical religional,
Dolores Copan, Honduras, ca. 1985
音楽人類学・民族音楽学
Anthropology of music experience, ethno-musicology
Frances
Densmore (1867-1957) recording Blackfoot chief Mountain Chief for
the Bureau
of American Ethnology in 1916// Conjunto musical religional,
Dolores Copan, Honduras, ca. 1985
音 楽人類学(あるいは音楽経験の人類学)あるいは民 族音楽学(Ethnomusicology) とは、音楽(music)を奏 で、聴き、音楽について語り、身体を動かし、また音的記憶の中にいきる人々の文化的あるいは社会的経験の諸相から音楽を考察する学 問(=経験ならびに理論科学)である(→「音楽美学批判」 「音楽理論」「民族学」 「文化人類学」)。
音
楽人類学あるいは民族音楽学(EM)は、最近まで「エキゾチック」「原始的・未開的」「異
質」とみなされてきた伝統的な社会や文化の音楽表現を研究する学問であった。しかし、今はそうではない!!!(そんなことを言う人がいれば、その人は「い
まや愚
かになった」のである)。しかしながら、20
世紀末、相互に関連する4つの現象(グローバリゼーション、古い社会単位の崩壊、ローカルなジャ
ンルのハイブリッド化、ワールドミュージックの出現)に
よって、もはや現代とは似ても似つかない世界のために100年以上前に構想されたこの学問の役割と方向性が問われている(EMという用語はヤープ・クンス
ト(Jaap Kunst,
1891-1960)により1950年代に造られた)。この時点で、われわれのEMの科学的管理の棚卸しを行い、利用可能なモデルの理論、イデオロギー的
前提、観点を批判的に検討することが不可欠になった。そして、それは「音楽」概念の見直しでもある。
さ
て、音楽とは何だろう?音楽とは、形式、和声、旋律、リズム、またはその他の表現的な内容の何らかの
組み合わせを作り出すための音の配置である。音楽の定義は 文化によって異なるが、音楽はすべての人間社会の側面であり、文化的普遍である(→「音楽」「音楽理論」)。
民 族音楽学(エスノミュージコロジー ethnomusicology)とは、なぜ、そして、どのようにして、人間が「音楽的(musical)」なのかを探求する学問である。この定義では、 民族音楽学は、社会科学、人文学、生物科学のように、すべての生物学的、社会的、文化的、さらには美学的多様性の中に人間の本性を理解しようとしている諸 科学の中に位置づけられる。(この場合の)「音楽的」とは、音楽的才能や能力において定義されるべきものではなく、むしろ、創作し、演奏し、認識できるよ うに組織化し、物理的にも感情的にも反応し、そして人間が組織化したサウンドの意味を解釈する人間の能力のことをいう(Timothy Rice 2014:1)。民族音楽学を学術用語としてはじめて定義したのは、ヤープ・クンスト(Jaap Kunst, 1891-1960)である。
 "Ethnomusicology
is the study of music from the cultural and social aspects of the
people who make it. It encompasses distinct theoretical and methodical
approaches that emphasize cultural, social, material, cognitive,
biological, and other dimensions or contexts of musical behavior, in
addition to the sound component.
Folklorists, who began preserving and studying folklore music in Europe
and the US in the 19th century, are considered the precursors of the
field prior to the Second World War. The term ethnomusicology is said
to have been first coined by Jaap Kunst from the Greek words ἔθνος
(ethnos, "nation") and μουσική (mousike, "music"), It is often defined
as the anthropology or ethnography of music, or as musical
anthropology.[Seeger, Anthony. 1983. Why Suyá Sing. London:
Oxford
University Press. Pp. xiii-xvii.] During its early development
from
comparative musicology in the 1950s, ethnomusicology was primarily
oriented toward non-Western music, but for several decades it has
included the study of all and any musics of the world (including
Western art music and popular music) from anthropological, sociological
and intercultural perspectives. Bruno Nettl once characterized
ethnomusicology as a product of Western thinking, proclaiming that "ethnomusicology as western culture knows it
is actually a western phenomenon";[Nettl, Bruno (1983).
The
Study of Ethnomusicology. Urbana, Ill.: University of Illinois Press.
p. 25.] in 1992, Jeff Todd Titon described it as the study of "people
making music".[Titon, Jeff Todd (1992). Worlds of Music
(2nd ed.). New
York: Schirmer. pp. xxi.]"- Ethnomusicology.
by Wiki
"Ethnomusicology
is the study of music from the cultural and social aspects of the
people who make it. It encompasses distinct theoretical and methodical
approaches that emphasize cultural, social, material, cognitive,
biological, and other dimensions or contexts of musical behavior, in
addition to the sound component.
Folklorists, who began preserving and studying folklore music in Europe
and the US in the 19th century, are considered the precursors of the
field prior to the Second World War. The term ethnomusicology is said
to have been first coined by Jaap Kunst from the Greek words ἔθνος
(ethnos, "nation") and μουσική (mousike, "music"), It is often defined
as the anthropology or ethnography of music, or as musical
anthropology.[Seeger, Anthony. 1983. Why Suyá Sing. London:
Oxford
University Press. Pp. xiii-xvii.] During its early development
from
comparative musicology in the 1950s, ethnomusicology was primarily
oriented toward non-Western music, but for several decades it has
included the study of all and any musics of the world (including
Western art music and popular music) from anthropological, sociological
and intercultural perspectives. Bruno Nettl once characterized
ethnomusicology as a product of Western thinking, proclaiming that "ethnomusicology as western culture knows it
is actually a western phenomenon";[Nettl, Bruno (1983).
The
Study of Ethnomusicology. Urbana, Ill.: University of Illinois Press.
p. 25.] in 1992, Jeff Todd Titon described it as the study of "people
making music".[Titon, Jeff Todd (1992). Worlds of Music
(2nd ed.). New
York: Schirmer. pp. xxi.]"- Ethnomusicology.
by Wiki
「民 族音楽学は、音楽を作る人々の文化的・社会的側面 から音楽を研究する学問である。音の要素に加え、音楽的行動の文化的、社会的、物質的、認知的、生物学 的、その他の次元や文脈を強調する明確な理論的、方法的アプローチを包含している。音楽民族誌の中では、音楽演奏に参加する行為(ミュージッ キング)を直接的かつ個別的に研究することである。19世紀に欧米で民俗音楽の保存と研究を始めた民俗学者たちが、第二次世界大戦前では、 この分野の先駆者とされている。民族音楽学という言葉は、ギリシャ 語のἔθνος(ethnos、「国民/民族」)とμουσική(mousike、「音楽」)からヤープ・クンスト(Jaap Kunst, 1891-1960)によって作られたと言われており、しばしば 音楽の人類学または民族学、あるいは音楽人類学と定義されている[1]。 1950年代に比較音楽学から発展した当初は、民族音楽学は主に非西洋音楽を対象としていたが、数十年前から人類学、社会学、異文化間の視点から世界のあ らゆる音楽(西洋芸術音楽、ポピュラー音楽を含む)を研究対象とするようになった [1]。ブルーノ・ネトル(Bruno Nettl, 1930-2020)はかつて民族音楽学を西洋的思考の産物として特徴づけ「西洋文化が知っている民族音楽学は実は西洋の現象である」と宣言した [2]。1992年にジェフ・トッド・ティトンはそれを「音楽を作る人々」の研究であると表現した[3]」。
目 次(数字は登場順の自動番号によるもので、意味の階層性にはそれほど関係していない)
****| List of ethnomusicologists. Choreomusicology Ethnochoreology Society for Ethnomusicology Fumio Koizumi Prize for Ethnomusicology List of musicologists List of musicology topics Musicology Prehistoric music Smithsonian Folkways Sociomusicology World music International Council for Traditional Music Society for Ethnomusicology |
民族音楽学者の一覧。 舞踏音楽学 民族舞踏学 民族音楽学会 民族音楽学小泉文夫賞 音楽学者の一覧 音楽学トピックの一覧 音楽学 先史時代の音楽 スミソニアン・フォークウェイズ 社会音楽学 ワールドミュージック 国際伝統音楽評議会 民族音楽学会 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnomusicology |
| Music Music is found in wide-ranging settings and format, including chants, musicals, live performances, recorded performances, and spiritual rituals. In prehistoric times, music was used to communicate, to tell the stories of people and express important elements of cultures. Music articulates the human experience, focusing on what people want to remember about their history and what they desire for the future. It has been used to heal, to demonstrate power, and to archive the experiences of people. Present-day music is an extension and an evolution of the music that has come before. It is a medium that represents the depths of time, culture, and history. Prehistoric musical instruments, called music artifacts in anthropology, include woodwinds and percussion instruments of ancient nomadic tribes. These instruments began as rudimentary music artifacts and evolved into more sophisticated technological equipment invented and formed for the exclusive purpose of creating music. Sorce: https://openstax.org/books/introduction-anthropology/pages/16-2-anthropology-of-music |
1. 音楽(→「音楽」) 音楽は、聖歌、ミュージカル、生演奏、録音された演奏、スピリチュアルな儀式など、さま ざまな場面や形式で見られる。先史時代には、音楽はコミュニケー ションを図り、人々の物語を伝え、文化の重要な要素を表現するために使われていた。音楽は人間の経験を明確にし、人々が自分たちの歴史について覚えておき たいことや、未来に望むことに焦点を当てる。音楽は、癒しや力を示し、人々の経験を記録するために使われてきた。現在の音楽は、これまでの音楽の延長であ り、進化である。それは、時間、文化、歴史の深みを表現するメディアである。人類学で音楽工芸品と呼ばれる先史時代の楽器には、古代の遊牧民族の木管楽器 や打楽器が含まれる。これらの楽器は、初歩的な音楽工芸品として始まり、音楽を創造することだけを目的として発明され、形成された、より洗練された技術装 置へと進化した。 |
| Ethnomusicology Someone who studies music from a global perspective, as a social practice, and through ethnographic field work is called an ethnomusicologist. The Society for Ethnomusicology defines ethnomusicology as “the study of music in its social and cultural contexts” (n.d.). Ethnomusicology is complex, requiring the work of many scientific disciplines. It requires study of many geographic areas, with a focus on the social practice of music and the human experience. Ethnomusicology is interdisciplinary, with a close relation to cultural anthropology. It is sometimes described as a historical research approach to understanding the cultures of people through their music. One well-known ethnomusicologist was Frances Densmore, who focused on the study of Native American music and culture. |
2. 民族音楽学 音楽をグローバルな視点から、社会的実践として、民族誌的フィールドワークを通して研究する人を民族音楽学者と呼ぶ。民族音楽学会は、民族音楽学を「社会 的・文化的文脈における音楽の研究」(n.d.)と定義している。民族音楽学は複雑な学問であり、多くの科学的学問分野の研究を必要とする。音楽の社会的 実践と人間の経験に焦点を当てながら、多くの地域を研究する必要があります。民族音楽学は学際的であり、文化人類学とも密接な関係がある。音楽を通して人 々の文化を理解する歴史的研究アプローチと表現されることもある。有名な民族音楽学者としては、ネイティブ・アメリカンの音楽と文化の研究に力を注いだフ ランシス・デンズモアがいる。 |
| Musical Instruments in Prehistory The field of ethnomusicology focuses on all aspects of music, including its genre, its message, the artist(s) who created it, and the instruments they used to do so. Have you ever considered why a particular musical instrument was created? Who made it? Why did they make it? What did they want it to do? How was it used? How did they dream up the design? Emily Brown (2005), formerly of the US National Park Service, studied the development of musical instruments in Ancestral Puebloan sites. Her study yielded insights into the types of instruments created. These included percussion and woodwind flutes that were used to create music culturally centric to the Puebloan people. Her study also yielded great insight into the structural hierarchy of those entrusted to manufacture music-making instruments. Not too dissimilar to today’s trade apprenticeships and master programs found in construction, Ancestral Puebloan people established a system of passing down the construction techniques central to creating musical instruments, ensuring that the knowledge would be carried on by future generations. Brown’s study connected music instruments to politics, music, social status, and social experiences. The Structure and Function of Music in Different Societies Music is grounded in the human experience. It is a theatrical expression of its creator’s thoughts and perceptions. The structure of music has evolved along with the experiences of the humans who created it. Examples of this can be found in the early 1800s hymns of Choctaw tribes. These hymns provide an artistic expression of traumatic experiences, referring to a time when the Choctaw people were removed from their homelands and relocated to reservation lands by the US government. They speak of both individual and collective experiences as these peoples made the arduous journey to their new locations. The songs speak about broken promises, the journey, and the fate of their people. |
3. 先史時代の楽器 民族音楽学の分野では、音楽のジャンル、メッセージ、それを創り出したアーティスト、そのために使われた楽器など、音楽のあらゆる側面に焦点を当ててい る。ある楽器がなぜ作られたのか、考えたことはあるだろうか?誰が作ったのか?なぜ彼らはそれを作ったのか?何をさせたかったのか?どのように使われたの か?彼らはどうやってそのデザインを思いついたのだろう?元米国国立公園局のエミリー・ブラウン(2005年)は、プエブロ族の遺跡における楽器の発達に ついて研究した。彼女の研究は、作られた楽器の種類についての洞察をもたらした。これらの楽器には、プエブロ族にとって文化的に中心的な音楽を創造するた めに使用された打楽器や木管フルートが含まれていた。彼女の研究はまた、音楽を作る楽器の製造を任された人々の構造的なヒエラルキーについても大きな洞察 をもたらした。今日の建設業に見られる徒弟制度やマスター・プログラムとはあまり似ていないが、先祖代々のプエブロの人々は、楽器を作るための中心的な建 設技術を伝承するシステムを確立し、その知識が後世に受け継がれるようにしていたのである。ブラウンの研究は、楽器を政治、音楽、社会的地位、社会的経験 と結びつけている。 さまざまな社会における音楽の構造と機能 音楽は人間の経験に根ざしている。それは、創作者の思考と知覚の演劇的表現である。音楽の構造は、それを生み出した人間の経験とともに進化してきた。その 例は、1800年代初頭のチョクトー族の賛美歌に見ることができる。これらの賛美歌は、チョクトー族がアメリカ政府によって故郷を追われ、保留地に移住さ せられた時代に言及し、トラウマ的な経験を芸術的に表現したものである。讃美歌は、これらの民族が新しい土地への困難な旅路を歩んだ際の、個人的および集 団的な経験について語っている。歌は、破られた約束、旅、そして彼らの人々の運命について語っている。 |
| For enslaved people, music was a
mechanism of emotional escape from difficult situations as well as a
means of communicating with those speaking different languages during
the Middle Passage, the journey from Africa to locations of forced
labor. One of the most iconic spirituals, or songs for survival, is “Go
Down Moses.” Harriet Tubman, the legendary Underground Railroad
conductor, said that she used this spiritual as a way to signal to
those who were enslaved in the area who she wanted to help escape to
freedom (Bradford [1886] 1995). The song ostensibly speaks about the
experience of the Israelites enslaved by the Egyptians in ancient
times. For enslaved Black people in America, the song spoke directly to
their own longing for freedom. The chorus of “Go Down Moses” is as
follows: Go down, Moses, Way down in Egypt’s land. Tell ol’ Pharaoh, Let my people go. Thus saith the Lord, bold Moses said, Let my people go, If not, I’ll smite your firstborn dead, Let my people go. Listen to this song on the Library of Congress website. Numerous populations have utilized music as a means of resistance. During the civil rights movement of the 20th century, Black artists such as Nina Simone, Aretha Franklin, and Sam Cooke used their music as a way to challenge structural inequity. Aretha Franklin, a Black singer, songwriter, and pianist, wrote and performed music anchored in the Black church that came to represent Black American culture. She achieved national and international fame for her rich voice and heartfelt performances, and she was able to use her artistic talents to bring a message of both hope and resistance to her audience. Her songs spoke to both where people were and where they wanted to be. Sam Cooke was an American singer who was given the nickname “King of Soul” by his fans and those in the music industry. Like many, he started out singing in church, but eventually his music and passion evolved to secular music. He is credited with having significant influence on the civil rights movement, and his music often explored themes of oppression and fighting for a cause. The music of his first band, Soul Stirrers, focused on stirring the listener’s soul to engage in the movement for racial equality. Suit jacket, hat, and guitar in a glass display case. Figure 16.13 Sam Cooke’s performance outfit and instruments are on display in the Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland, Ohio. The music of Sam Cooke had considerable influence on the Civil Rights movement. (credit: “Sam Cooke’s Outfit” by Steven Miller/flickr, CC BY 2.0) Sorce: https://openstax.org/books/introduction-anthropology/pages/16-2-anthropology-of-music Perhaps no artist in recent times is better known for using music as a catalyst for social change than Bob Dylan. Dylan was a 1960s-era musical artist who spoke to many cultures and generations about injustice and the need for inclusion and change. His 1964 song “The Times They Are a-Changin’” urged politicians and voters to support the civil rights movement. He was also well known for his opposition to the Vietnam War. His music may have very well changed the course of history, given his influence on his fans’ thoughts, perspectives, and attitudes toward inclusion (Ray 2017). |
奴隷にされた人々にとって、音楽は困難な状況からの感情的な逃避のメカ
ニズムであり、アフリカから強制労働を強いられる場所への旅である「中道」の間、異なる言語を話す人々とコミュニケーションをとる手段でもあった。最も象
徴的なスピリチュアル・ソング(生き残るための歌)のひとつが、"Go Down Moses "である。伝説的な地下鉄道(Underground
Railroad)の車掌であったハリエット・タブマンは、このスピリチュアル・ソングを、自由への脱出を手助けしてほしい地域の奴隷に合図を送る方法と
して使ったと語っている(Bradford [1886]
1995)。この歌は表向きには、古代にエジプト人に奴隷にされたイスラエルの民の経験について語っている。アメリカで奴隷となった黒人たちにとって、こ
の歌は自由への憧れを直接的に物語っている。Go Down Moses」のコーラスは以下の通り: 降りて行け、モーゼス、 エジプトの地に降りて ファラオに言え、 我が民を解放せよ。 主はこう仰せられる、 わたしの民を行かせなさい、 そうでなければ、私はあなたの初子を打ち殺す、 私の民を行かせよ。 米国議会図書館のウェブサイトでこ の歌を聴いてみよう。 数多くの民族が、抵抗の手段として音楽を利用してきた。20世紀の公民権運動では、ニーナ・シモン、アレサ・フランクリン、サム・クックといった黒人アー ティストが、構造的な不平等に挑戦する手段として音楽を利用した。黒人シンガー、ソングライター、ピアニストであるアレサ・フランクリンは、黒人教会に根 ざした音楽を作曲し、演奏した。彼女はその豊かな歌声と心のこもったパフォーマンスで、国内外での名声を獲得し、その芸術的才能を駆使して、聴衆に希望と 抵抗の両方のメッセージを届けることができた。彼女の歌は、人々が今いる場所と、彼らが望む場所の両方に語りかけた。 サム・クックは、ファンや音楽業界の人々から "キング・オブ・ソウル "というニックネームを与えられたアメリカの歌手だ。多くの人と同じように、彼も最初は教会で歌っていたが、やがて彼の音楽と情熱は世俗音楽へと発展して いった。彼は公民権運動に大きな影響を与えたとされ、彼の音楽はしばしば抑圧や大義のために戦うというテーマを探求した。彼の最初のバンド、ソウル・ス ターラーズの音楽は、リスナーの魂をかき立てて人種平等運動に参加させることに重点を置いていた。 ガラスの展示ケースに収められたスーツの上着、帽子、ギター。 図16.13 サム・クックの演奏衣装と楽器は、オハイオ州クリーブランドのロックの殿堂に展示されている。サム・クックの音楽は公民権運動に多大な影響を与えた。 (credit: "Sam Cooke's Outfit" by Steven Miller/flickr, CC BY 2.0) 近年、ボブ・ディランほど音楽を社会変革の触媒として使ったことで知られるアーティストはいないだろう。ディランは1960年代に活躍した音楽アーティス トで、多くの文化や世代に不公正と包摂と変革の必要性を訴えた。彼の1964年の曲「The Times They Are a-Changin'」は、政治家や有権者に公民権運動を支持するよう促した。彼はまた、ベトナム戦争に反対したことでもよく知られている。彼の音楽は、 彼のファンの考え、視点、インクルージョンに対する態度に影響を与えたことを考えると、歴史の流れを変えたかもしれない(Ray 2017)。 |
| Personal History: Zora Neale Hurston was a Black American anthropologist, author, and filmmaker. She was born in Notasulga, Alabama, to a sharecropper turned carpenter and a former schoolteacher. All of her grandparents were born enslaved. Hurston moved to Eatonville, Florida, an all-Black town, in 1892, at the age of two. She often referenced Eatonville as her home, as she had no recollection of her time in Alabama. She lived in Eatonville until 1904, when her mother passed. At the time, Eatonville was a well-established Black community with a booming economy. According to multiple accounts, Hurston was never indoctrinated into feeling racial inferiority. While she was a resident, her father was elected mayor of the town. All the shop owners and government officials were also Black American elites. In adulthood, Huston often used Eatonville as the setting of her stories. Huston left Eatonville due to a poor relationship with her stepmother. She enrolled in classes at Morgan College in Maryland, lying about her age of 26 to be eligible for a free high school education. She graduated in 1918 and attended Howard University, a historically Black university in Washington, DC, before transferring to Barnard College at Columbia University. At Barnard, Hurston studied under Franz Boas as an undergraduate and graduate student. She also worked with other foundational anthropologists, including Ruth Benedict and Margaret Mead. Area of Anthropology: In addition to her time in academia, Hurston was a central figure in the Harlem Renaissance as a literary artist, working closely with Langston Hughes, among other writers. She was a pivotal literary artist whose work directly reflected the trials, tribulations, and successes of Black American communities and subsocieties that were often overlooked or exoticized (Jones 2009). Hurston was a cultural anthropologist who was passionate about southern American and Caribbean cultural practices. She spent significant time in these geographical areas, immersing herself in the diverse cultures of Black people in the American South and the Caribbean. Accomplishments in the Field: One of Hurston’s most notable anthropological works is Mules and Men (1935), based on ethnographic research she conducted in lumber camps in north Florida. One focus of this work was the power dynamics between the White men who were in charge and the Black women laborers, some of whom the men took as concubines. In addition to this work, Hurston studied Black American song traditions and their relationship to the music of enslavement and to the musical traditions of pre–Middle Passage Africans. Importance of Her Work: Hurston not only studied human society and culture as an anthropologist but was also an active participant in the arts. She was a central figure in the Harlem Renaissance, which was a flowering of Black culture centered in the Harlem neighborhood of New York City. Her most popular novel is Their Eyes Were Watching God (1937; Carby 2008). Her specific anthropological and ethnographic research focus areas were Black American and Caribbean folklore. She also worked for the Federal Writer’s Project, part of the Works Progress Administration, as a writer and folklorist. Hurston is now an iconic figure for the Association of Black Anthropologists and several Black anthropological studies journals. |
4.【コラム】 個人の歴史 ゾラ・ニール・ハーストンはアメリカの黒人人類学者、作家、映画監督。 アラバマ州ノタスルガで、小作人から大工になった男と元教師の間に生まれた。祖父母 は全員奴隷として生まれた。ハーストンは1892年、2歳のときに黒人だけの町であるフロリダ州イートンヴィルに移り住んだ。アラバマにいた頃の記憶がな いため、彼女はしばしばイートンヴィルを故郷としていた。母親が亡くなる1904年までイートンヴィルに住んでいた。当時、イートンヴィルは経済が発展 し、黒人のコミュニティとして確立していた。複数の証言によれば、ハーストンは人種的劣等感を教え込まれることはなかった。彼女が住んでいた頃、父親が町 長に選ばれた。店の主人や政府の役人も皆、アメリカ黒人のエリートだった。大人になってからも、ヒューストンはしばしばイートンヴィルを物語の舞台にし た。 継母との関係が悪化したため、ヒューストンはイートンヴィルを離れた。メリーランド州のモーガン・カレッジに入学し、26歳という年齢を偽って無料で高校 教育を受ける資格を得た。1918年に卒業した彼女は、ワシントンDCにある歴史的に黒人の多いハワード大学に入学し、その後コロンビア大学のバーナー ド・カレッジに編入した。バーナード大学では、学部生および大学院生としてフランツ・ボースに師事。また、ルース・ベネディクトやマーガレット・ミード ら、人類学の基礎を築いた研究者たちとも共同研究を行った。 人類学の分野 学術活動に加え、文学者としてもハーレム・ルネッサンスの中心人物であり、ラングストン・ヒューズらと緊密に仕事をした。彼女は極めて重要な文学者であ り、その作品には、しばしば見過ごされたり異国視されたりする黒人アメリカ人コミュニティや部分社会の試練、苦難、成功が直接反映されている(Jones 2009)。 ハーストンは文化人類学者であり、アメリカ南部やカリブ海諸国の文化的慣習に情熱を注いでいた。彼女はこれらの地域で多くの時間を過ごし、アメリカ南部と カリブ海地域の黒人の多様な文化に没頭した。 フィールドでの業績 ハーストンの最も注目すべき人類学的著作のひとつに、フロリダ北部の木材キャンプで行った民族誌的調査に基づく『Mules and Men』(1935年)がある。この著作の焦点のひとつは、責任者である白人男性と黒人女性労働者(そのうちの何人かは男性が妾として連れて行った)との 間のパワー・ダイナミクスであった。この仕事に加え、ハーストンは黒人アメリカ人の歌の伝統と、奴隷化の音楽との関係、そして中世以前のアフリカ人の音楽 の伝統との関係を研究した。 彼女の仕事の重要性:ハーストンは人類学者として人間の社会と文化を研究しただけでなく、芸術にも積極的に参加した。ニューヨークのハーレム地区を中心に 黒人文化が花開いたハーレム・ルネッサンスの中心人物である。彼女の最も有名な小説は『彼らの目は神を見ていた』(1937年、Carby 2008年)である。彼女の人類学的・民俗学的研究の重点分野は、ブラック・アメリカンとカリブ海の民俗学であった。彼女はまた、作家および民俗学者とし て、労働進歩局(Works Progress Administration)の一部である連邦作家プロジェクト(Federal Writer's Project)のために働いた。ハーストンは現在、黒人人類学者協会(Association of Black Anthropologists)や複数の黒人人類学研究雑誌の象徴的存在となっている。 |
| 5. Methoology of Musicing 5.1 The Importance of Sociocultural Context in Understanding Music Ethnomusicologist Patricia Campbell (2011) proposes that children’s perspectives on musical interests are derived from their family, community, and environment. How did you learn about music you liked? What did your parents listen to, and what do you listen to? While you may have learned about and grown to like other music as you aged, your appreciation for music is founded in the sociocultural environment that you were raised in. Imagine growing up in a family that only listened to Bansuri bamboo flute music. Would you even know, for example, what rap music is? 5.2 Music as a Basis for Subculture and Community The affiliation of music with identity became a common topic of inquiry in ethnomusicology in the 1980s, perhaps prompted by the music subcultures of the 1970s that arose among groups of people who did not identify with mainstream norms, values, or ideals. Among the music subcultures that emerged during that time was the punk subculture (Moran 2010). Though it was often seen as no more than youthful rebellion, the punk subculture formed its own community, values, and ideals founded in a do-it-yourself, or DIY, ethos. This can be found in the lyrics, music, and performances of punk groups such as the Ramones and the Clash, as well as more recent pop-influenced groups such as Green Day and Blink-182. The lyrics tell stories of needing to break from common ideals and values in order to think and do for oneself. 5.3 Cultural Appropriation Cultural practices important to communities are often integrated into the fabric of each person’s identity. Cultural appropriation is defined as the improper or disrespectful use of a meaningful element of a culture or identity outside of its intended cultural context by someone who is not a part of that culture or identity (Young 2008). The act of cultural appropriation by dominant cultures threatens to erase remaining parts of a culture that may already be jeopardized. Cultural appropriation is tied to social inequity in that it involves a socially dominant group using the culture of a marginalized group for exploitative or capitalist gain. The cultural significance of the appropriated elements is lost. While the act of cultural appropriation is centuries old, there has been a renewed call from marginalized communities in recent years to understand how and why this practice is harmful. Wesley Morris (2019) wrote an article for the New York Times’ 1619 Project regarding the mass appropriation of Black music. Morris noted instances of appropriation by artists such as Steely Dan, Eminem, and Amy Winehouse, all White American or British music superstars. Musical appropriation is the use of one genre’s musical contributions in other music that is not of the same genre, style, or culture. The power of Black music to articulate the history, struggles, and marginalization of Black people has appealed to other social groups as well, many of them drawn to the ability of this music to communicate its message with clarity and boldness. Morris also discusses how, more recently, the appropriation of Black lyrics, songs, and musical presentation styles has become a method of addressing the need for integration and integrated culture. This can be seen in Black artist Lil Nas X’s 2019 remix of his hit song “Old Town Road,” for which he teamed up with White country musician Billy Ray Cyrus to perform a duet. The song itself is a blending of cultures, musical and racial, and offers a social contribution to evolving efforts at inclusion. |
5.
音楽を人類学的に研究するための観点 5.1 音楽を理解する上での社会文化的コンテクストの重要性 民族音楽学者のパトリシア・キャンベル(Patricia Campbell, 2011)は、子どもの音楽に対する興味は、家族、コミュニティ、環境から得られると提唱している。好きな音楽はどうやって知ったのか?両親は何を聴いて いたのか、そしてあなたは何を聴いているのか。年齢を重ねるにつれて他の音楽を知り、好きになったかもしれませんが、音楽に対する評価は、あなたが育った 社会文化的環境の中で築かれたものです。バンスリの竹笛しか聴かない家庭で育ったことを想像してみてほしい。例えば、ラップ・ミュージックが何であるか、 あなたは知っているだろうか? 5.2 サブカルチャーとコミュニティの基盤としての音楽 音楽とアイデンティティの結びつきは、1980年代に民族音楽学でよく取り上げられるようになった。おそらく、1970年代に主流派の規範や価値観、理想 に同調しない人々のグループから生まれた音楽サブカルチャーがきっかけだったのだろう。その時期に生まれた音楽サブカルチャーの中に、パンク・サブカル チャーがあった(Moran 2010)。若者の反抗に過ぎないと見なされることも多かったが、パンク・サブカルチャーは、DIY(ドゥ・イット・ユアセルフ)の精神に基づいた独自の コミュニティ、価値観、理想を形成した。これは、ラモーンズやクラッシュといったパンク・グループや、グリーン・デイやブリンク182といった最近のポッ プに影響を受けたグループの歌詞、音楽、パフォーマンスに見られる。歌詞には、自分で考え、自分で行動するためには、一般的な理想や価値観から脱却する必 要があるというストーリーが綴られている。 5.3 文化的流用 地域社会にとって重要な文化的慣習は、多くの場合、各人のアイデンティティの基盤に組み込まれている。文化的流用とは、ある文化やアイデンティティの意味 ある要素を、その文化やアイデンティティの一部ではない者が、意図された文化的文脈の外で不適切に、あるいは無礼に使用することと定義される(Young 2008)。支配的な文化による文化的流用という行為は、すでに危うくなっている文化の残存部分を消し去る恐れがある。文化的流用は、社会的に支配的な集 団が搾取的または資本主義的な利益のために社会的に疎外された集団の文化を利用するという点で、社会的不平等と結びついている。転用された要素の文化的意 義は失われる。文化的流用という行為は何世紀も前から行われているが、近年、周縁化されたコミュニティからは、この行為がどのように、そしてなぜ有害なの かを理解しようとする声が再び高まっている。 ウェスリー・モリス(2019)は、ニューヨーク・タイムズ紙の「1619プロジェクト」に黒人音楽の大量流用に関する記事を寄稿した。モリスは、ス ティーリー・ダン、エミネム、エイミー・ワインハウスといったアーティストによる流用の例を指摘した。音楽の流用とは、あるジャンルの音楽的貢献を、同じ ジャンル、スタイル、文化ではない他の音楽に利用することである。黒人の歴史、闘争、疎外を明確に表現するブラック・ミュージックの力は、他の社会集団に もアピールしており、彼らの多くは、明確かつ大胆にメッセージを伝えるこの音楽の能力に惹かれている。モリスはまた、最近では黒人の歌詞、歌、音楽表現ス タイルの流用が、統合と統合文化の必要性を訴える手法となっていることについても論じている。これは、黒人アーティスト、リル・ナスXが2019年に発表 したヒット曲「Old Town Road」のリミックスで、白人のカントリー・ミュージシャン、ビリー・レイ・サイラスとデュエットしたことに見られる。この曲自体は、音楽的、人種的な 文化の融合であり、インクルージョンの取り組みを進化させる社会的貢献を提供している。 |
◎
研究者たち
 Jaap Kunst (12
August 1891 in Groningen – 7 December 1960 in Amsterdam) Jaap Kunst (12
August 1891 in Groningen – 7 December 1960 in Amsterdam)Jaap Kunst (12 August 1891 in Groningen – 7 December 1960 in Amsterdam) was a Dutch musicologist. He is credited with coining the term "ethnomusicology" as a more accurate name for the field then known as comparative musicology. Kunst studied the folk music of the Netherlands and of Indonesia. His published work totals more than 70 texts.[1] Early life Kunst was born in 1891 in Groningen. Both of his parents were musicians, and his father was a music-school teacher. He began to study the violin at only 5 years old, and continued to play the instrument throughout his life.[2][3] Kunst was drawn toward folk music as a result of vacations to the island of Terschelling.[3] Kunst decided to pursue a career in law. While studying law, Kunst published the results of his first musical research.[4] Kunst earned a degree in law from the University of Groningen in 1917. and pursued a career in banking and law for the next two years.[2] However, he soon tired of this work.[4] Work in Indonesia In 1919, Kunst set out on a tour of the Dutch East Indies with a recently-formed musical trio. This group performed 95 times throughout Indonesia.[2] Kunst heard a gamelan ensemble for the first time at the Paku Alaman palace in Yogyakarta. Impressed, he decided to remain in Java to study Indonesian music, while the other members of his trio departed.[2] Taking a job as an official in the colonial government, Kunst remained in Java for fifteen years.[4] He married Kathy van Wely in 1921; she became a partner in Kunst's work.[2][4] Kunst was the first person to record gamelan music on wax cylinders. He amassed an archive of photographs, recordings, and instruments of Indonesian music.[2][4] He ceded much of his collection to the Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (now the National Museum of Indonesia).[2] Later activities In 1934, Kunst returned to the Netherlands, and he became the curator of Amsterdam's Colonial Museum (now the Royal Tropical Institute) in 1936.[2] Later, he became a lecturer at the University of Amsterdam.[4] Kunst first used the term "ethno-musicology" in his 1950 publication Musicologica. He stated: The name of our science is, in fact, not quite characteristic; it does not 'compare' any more than any other science. A better name, therefore, is that appearing on the title page of this book: ethno-musicology.[5] Ethnomusicology (with no hyphen) quickly replaced comparative musicology as the name of the field. This usage was influenced by the formation of the Society for Ethnomusicology in 1955. In 1956, Kunst released a bestselling album of folk songs, on Folkways Records, entitled Living Folksongs and Dance-Tunes from the Netherlands.[6] Kunst died in 1960 of throat cancer.[4] Ideas Kunst believed musical study must take into account the cultural context of its creation. In his view, musicology was incomplete without ethnographic elements. Contrary to mainstream European scholarship at the time, Kunst believed that music from other continents was no less sophisticated than the music of Europe, and he often argued this point against others.[4] Legacy Since 1965, the Society for Ethnomusicology has offered an annual prize named after Kunst. Until 2018, the prize honored the most significant ethnomusicological article of the previous year by a society member. From 2019 onward, only researchers in their first 10 years of scholarship are eligible for the prize.[7] Writings with C. Kunst-van Wely. De Toonkunst van Bali. (Weltevreden, 1924; part 2 in Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde, LXV, Batavia, 1925) with R. Goris. Hindoe-Javaansche muziekinstrumenten. (Batavia, 1927; 2nd ed., revised, Hindu-Javanese Musical Instruments, 1968) A Study on Papuan Music (Weltevreden, 1931) Musicologisch onderzoek 1931 (Batavia, 1931) Over zeldzame fluiten en veelstemmige muziek in het Ngada- en Nagehgebied, West-Flores (Batavia, 1931) De toonkunst van Java (The Hague, 1934; English translation, Music in Java, 1949; 3rd ed., expanded, 1973) Een en ander over den Javaanschen gamelan (Amsterdam, 1940; 4th ed. 1945) Music in Flores: A Study of the Vocal and Instrumental Music Among the Tribes Living in Flores (Leiden, 1942) Music in Nias (Leiden, 1942) Around von Hornbostel's Theory of the Cycle of Blown Fifths (Amsterdam, 1948) The Cultural Background of Indonesian Music (Amsterdam, 1949) Begdja, het gamelanjongetje (Amsterdam, 1950) De inheemsche muziek in Westelijk Nieuw-Guinea (Amsterdam, 1950) Metre, Rhythm, and Multi-part Music (Leiden, 1950) Musicologica: A Study of the Nature of Ethnomusicology, Its Problems, Methods, and Representative Personalities (Amsterdam, 1950; 2nd ed., expanded, retitled Ethnomusicology, 1955; 3rd ed. 1959) Kultur-historische Beziehungen zwischen dem Balkan und Indonesien (Amsterdam, 1953, English translation, 1954) Sociologische bindingen in de muziek (The Hague, 1953)  Jaap Kunst, early ethnomusicologist and creator of the term 'ethno-musicology', plays the Indonesian triton, beside other traditional Indonesian instruments. |
 6. ヤープ・クンスト, Jaap
Kunst 6. ヤープ・クンスト, Jaap
Kunstヤープ・クンスト(Jaap Kunst、1891年8月12日フローニンゲン市 - 1960年12月7日アムステルダム市)は、オランダの音楽学者である。当時比較音楽学と呼ばれていた分野をより正確な名称として「民族音楽学」という言 葉を作り出したのは彼であると言われている。オランダとインドネシアの民族音楽を研究した。1] 生い立ち 1891年、フローニンゲンに生まれる。両親は音楽家で、父親は音楽学校の教師であった。わずか5歳でヴァイオリンを習い始め、生涯を通じて楽器を弾き続 けた[2][3]。クンストはテルシェリング島での休暇をきっかけに民族音楽に惹かれ、法律の道に進むことを決意する[3]。 1917年にフローニンゲン大学で法律の学位を取得し、その後2年間は銀行と法律の仕事に従事した[2]。 しかし、彼はすぐにこの仕事に飽きた。 4] インドネシアでの仕事 1919年、クンストは結成されたばかりの音楽トリオとともに、オランダ領東インドへの巡業に出発した。ジョグジャカルタのパク・アラマン宮殿で初めてガ ムラン・アンサンブルを聴き、感銘を受けたクンストはインドネシアに残ることを決意する。1921年にキャシー・ヴァン・ウェリーと結婚し、クンストの仕 事のパートナーとなる[2][4]。 クンストは、ガムラン音楽をワックスシリンダー(蝋管)に録音した最初の人物である。彼はインドネシア音楽の写真、録音、楽器のアーカイブを蓄積した [2][4]。 彼はコレクションの多くをKoninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen(現在のインドネシア国立博物館)に譲り渡すことになった[2]。 その後の活動 1934年、クンストはオランダに戻り、1936年にアムステルダムの植民地博物館(現在の王立熱帯研究所)の学芸員となった[2]。 その後、アムステルダム大学の講師となった[4]。ク ンストは1950年に出版した『ムクロジカ』で初めて「民族音楽学」という言葉を使った。彼は次のように述べている:我々の科学の名前は、実際には、全く 特徴的ではない、それは他のどの科学よりも「比較」しない。したがって、より良い名前は、この本のタイトルページに表示されているものである:民族音楽学[5] 民族音楽学(ハイフンなし)はすぐにフィールドの名前として比較音楽学に取って代わられた。1956年、クンストはフォークウェイズ・レコードから『オラ ンダの生きた民謡と舞曲』という民謡のベストセラー・アルバムを発表した[6]。クンストは1960年に咽頭癌で死去した[4]。 理念 クンストは、音楽研究は、その創作の文化的背景を考慮しなければならないと考えていた。音楽学は民俗学的な要素を抜きにしては成り立たないと考えたのであ る。当時のヨーロッパの主流の学問とは異なり、クンストは他の大陸の音楽もヨーロッパの音楽に劣らず洗練されていると考えており、この点についてしばしば 他者と論争を繰り広げた[4]。 遺産と顕彰 1965年以来、民族音楽学会はクンストの名を冠した賞を毎年授与している。2018年までは、学会員による前年の最も重要な民族音楽学的論文を表彰する ものであったが、2019年以降は、研究歴10年以上の研究者のみが対象となる[7]。2019年以降は、研究歴10年目の研究者のみが受賞対象となる [7]。 著作 C. Kunst-van Wely と共著。バリの音楽芸術。(Weltevreden、1924年、第2部は『Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde』誌、LXV、バタビア、1925年) R. Goris と共著。ヒンドゥー・ジャワの楽器。(バタビア、1927年、改訂第2版、Hindu-Javanese Musical Instruments、1968年) A Study on Papuan Music(ウェルテヴェーデン、1931年) Musicologisch onderzoek 1931(バタビア、1931年) 西フローレス、ンガダおよびナゲ地域における珍しい笛と多声音楽について(バタビア、1931年) ジャワの音楽芸術(ハーグ、1934年、英語訳、Music in Java、1949年、第3版、増補、1973年) ジャワのガムランについて(アムステルダム、1940年、第4版、1945年) フローレスの音楽:フローレスに住む部族のボーカルおよび器楽の研究(ライデン、1942年) ニアスの音楽(ライデン、1942年) フォン・ホルンボステルの吹奏五度循環理論について(アムステルダム、1948年) インドネシア音楽の文化的背景(アムステルダム、1949年) ベグジャ、ガムランの少年(アムステルダム、1950年) 西ニューギニアの土着音楽(アムステルダム、1950年) 『拍子、リズム、および多声音楽』(ライデン、1950年) 『音楽学:民族音楽学の性質、その問題、方法、および代表的な人物に関する研究』(アムステルダム、1950年、第2版、増補、改題『民族音楽学』、1955年、第3版、1959年) 『バルカンとインドネシアの文化歴史的関係』(アムステルダム、1953年、英語訳、1954年) 『音楽における社会学的結びつき』(ハーグ、1953年)  ヤープ・クンストは、初期の民族音楽学者であり「民族音楽学」という用語の創始者である。彼はインドネシアのトリトンをはじめ、他の伝統的なインドネシア楽器を演奏する。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Jaap_Kunst |
|
| Bruno Nettl (14
March 1930 – 15
January 2020) Bruno Nettl (14 March 1930 – 15 January 2020) was an ethnomusicologist who was central in defining ethnomusicology as a discipline.[1][2] His research focused on folk and traditional music, specifically Native American music the music of Iran and numerous topics surrounding ethnomusicology as a discipline.[3] |
7.
ブルーノ・ネトル(Bruno Nettl、1930年3月14日
- 2020年1月15日) ブルーノ・ネトル(Bruno Nettl、1930年3月14日 - 2020年1月15日)は、民族音楽学(ethnomusicology)を学問として定義する上で中心となった民族音楽学者[1][2]。 民族音楽や伝統音楽、特にアメリカ先住民の音楽、イランの音楽、学問としての民族音楽学に関する多くのトピックに焦点を当てて研究していた[3]。 |
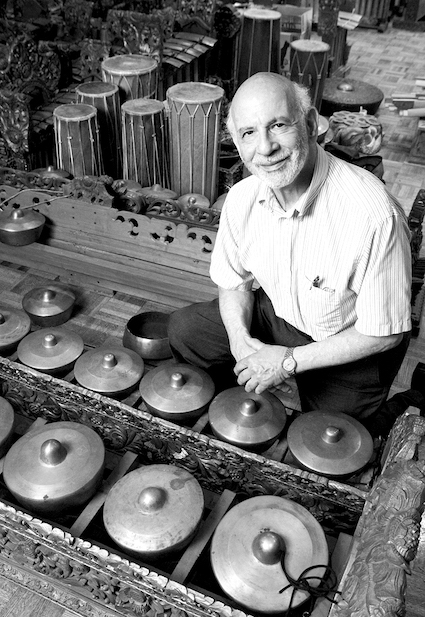 Bruno
Nettl (1930-2020) was born in Prague, Czechoslovakia in 1930, and
he was the son of
Paul and Gertrude (Hutter) Nettl, who both had musical backgrounds.[4]
In 1939, Nettl and his family, which was of Jewish heritage, moved to
the US to escape the Holocaust, which caused several deaths within his
family.[5][6] He studied at Indiana University with George Herzog[7]
and the University of Michigan and taught from 1964 at the University
of Illinois, where he eventually was named Professor Emeritus of Music
and Anthropology. Nettl met his wife, Wanda Maria White, while he was a
student at Indiana University and the couple married in 1952.[8] Bruno
and Wanda had two children, Rebecca and Gloria.[9] The Nettl’s were a
connected family, as his daughters continued living in Champaign even
in their adult lives, and Bruno was said to be a devoted father and
husband who cherished every moment with his family.[10] He continued to
teach part-time until his death. Nettl introduced and expanded the
ethnomusicology department at the University of Illinois, making it
among the national leaders in ethnomusicology.[11] Nettl was known to
have pride in the accomplishments of his students, many of whom went on
to teach at leading national universities.[12] Active principally in
the field of ethnomusicology, he did field research with Native
American peoples (1960s and 1980s, see Blackfoot music), in Iran (1966,
1968–69, 1972, 1974), and in South India (1981–82). He served as
president of the Society for Ethnomusicology and as editor of its
journal, Ethnomusicology. Nettl held honorary doctorates from the
University of Illinois, Carleton College, Kenyon College, and the
University of Chicago. He was a recipient of the Fumio Koizumi Prize
for ethnomusicology, and was a fellow of the American Academy of Arts
and Sciences. Nettl was named the 2014 Charles Homer Haskins Prize
Lecturer by the American Council of Learned Societies. In the course of
his long career as a scholar and as a professor, he was the teacher of
many of the most visible ethnomusicologists active today in the
international scene, including Philip Bohlman, Christopher Waterman,
Marcello Sorce Keller, and Victoria Lindsay Levine. The Sousa Archives
and Center for American Music holds the Bruno Nettl Papers, 1966–1988,
which consists of administrative and personal correspondence while
Nettl was a professor and head of the Musicology Division for the
University of Illinois School of Music.[13][14][15] Bruno
Nettl (1930-2020) was born in Prague, Czechoslovakia in 1930, and
he was the son of
Paul and Gertrude (Hutter) Nettl, who both had musical backgrounds.[4]
In 1939, Nettl and his family, which was of Jewish heritage, moved to
the US to escape the Holocaust, which caused several deaths within his
family.[5][6] He studied at Indiana University with George Herzog[7]
and the University of Michigan and taught from 1964 at the University
of Illinois, where he eventually was named Professor Emeritus of Music
and Anthropology. Nettl met his wife, Wanda Maria White, while he was a
student at Indiana University and the couple married in 1952.[8] Bruno
and Wanda had two children, Rebecca and Gloria.[9] The Nettl’s were a
connected family, as his daughters continued living in Champaign even
in their adult lives, and Bruno was said to be a devoted father and
husband who cherished every moment with his family.[10] He continued to
teach part-time until his death. Nettl introduced and expanded the
ethnomusicology department at the University of Illinois, making it
among the national leaders in ethnomusicology.[11] Nettl was known to
have pride in the accomplishments of his students, many of whom went on
to teach at leading national universities.[12] Active principally in
the field of ethnomusicology, he did field research with Native
American peoples (1960s and 1980s, see Blackfoot music), in Iran (1966,
1968–69, 1972, 1974), and in South India (1981–82). He served as
president of the Society for Ethnomusicology and as editor of its
journal, Ethnomusicology. Nettl held honorary doctorates from the
University of Illinois, Carleton College, Kenyon College, and the
University of Chicago. He was a recipient of the Fumio Koizumi Prize
for ethnomusicology, and was a fellow of the American Academy of Arts
and Sciences. Nettl was named the 2014 Charles Homer Haskins Prize
Lecturer by the American Council of Learned Societies. In the course of
his long career as a scholar and as a professor, he was the teacher of
many of the most visible ethnomusicologists active today in the
international scene, including Philip Bohlman, Christopher Waterman,
Marcello Sorce Keller, and Victoria Lindsay Levine. The Sousa Archives
and Center for American Music holds the Bruno Nettl Papers, 1966–1988,
which consists of administrative and personal correspondence while
Nettl was a professor and head of the Musicology Division for the
University of Illinois School of Music.[13][14][15] |
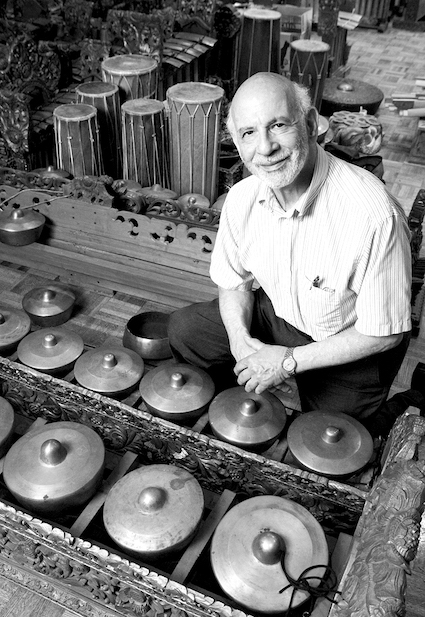 ブ
ルーノ・ネトルは、1930年、チェコスロバキアのプラハに生まれ、ポール・ネトルとガートルード(ハッター)・ネトルの息子で、ともに音楽家であった。
1939年、ユダヤ人の血を引く家族とともに、家族内で数人の死者を出したホロコーストから逃れるためにアメリカに渡った[5][6]。
インディアナ大学でジョージ・ヘルツォーク[7]、ミシガン大学で学び、1964年からイリノイ大学で教え、ついには音楽と人類学の名誉教授に就任した。
ネトルはインディアナ大学在学中に妻のワンダ・マリア・ホワイトと出会い、1952年に結婚した[8]
。ブルーノとワンダの間にはレベッカとグロリアという2人の子供がいた[9]
。ネトル一家は、娘たちが成人してもシャンペーンに住み、またブルーノは家族との時間を大切にする父親、夫だったといわれ、つながりを持つことができた
[10]
。ネットルはイリノイ大学の民族音楽学部門を導入・拡大し、民族音楽学で全米をリードする存在となった[11]。ネットルは教え子たちの成果に誇りを持っ
ており、多くの教え子が国立大学の一流校で教えるようになったことでも知られている[12]。
[主に民族音楽学の分野で活躍し、アメリカ先住民(1960年代と1980年代、ブラックフット音楽を参照)、イラン(1966、1968-69、
1972、1974)、南インド(1981-82)で現地調査を行った。)
民族音楽学会の会長、同学会誌『民族音楽学』の編集長を務めた。イリノイ大学、カールトンカレッジ、ケニオンカレッジ、シカゴ大学から名誉博士号を授与さ
れた。民族音楽学で小泉文夫賞を受賞し、アメリカ芸術科学アカデミーのフェローでもある。ネトルは、米国学協会協議会から2014年チャールズ・ホー
マー・ハスキンズ賞の講師に指名された。学者として、また教授としての長いキャリアの中で、フィリップ・ボールマン、クリストファー・ウォーターマン、マ
ルチェロ・ソース・ケラー、ヴィクトリア・リンゼイ・レヴィンなど、現在国際的に活躍する多くの著名な民族音楽学者の師となった。Sousa
Archives and Center for American Musicが所蔵するBruno Nettl Papers,
1966-1988は、Nettlがイリノイ大学音楽学部教授および音楽学部長であったときの事務的および個人的な書簡から構成されている[13]
[14][15]。 ブ
ルーノ・ネトルは、1930年、チェコスロバキアのプラハに生まれ、ポール・ネトルとガートルード(ハッター)・ネトルの息子で、ともに音楽家であった。
1939年、ユダヤ人の血を引く家族とともに、家族内で数人の死者を出したホロコーストから逃れるためにアメリカに渡った[5][6]。
インディアナ大学でジョージ・ヘルツォーク[7]、ミシガン大学で学び、1964年からイリノイ大学で教え、ついには音楽と人類学の名誉教授に就任した。
ネトルはインディアナ大学在学中に妻のワンダ・マリア・ホワイトと出会い、1952年に結婚した[8]
。ブルーノとワンダの間にはレベッカとグロリアという2人の子供がいた[9]
。ネトル一家は、娘たちが成人してもシャンペーンに住み、またブルーノは家族との時間を大切にする父親、夫だったといわれ、つながりを持つことができた
[10]
。ネットルはイリノイ大学の民族音楽学部門を導入・拡大し、民族音楽学で全米をリードする存在となった[11]。ネットルは教え子たちの成果に誇りを持っ
ており、多くの教え子が国立大学の一流校で教えるようになったことでも知られている[12]。
[主に民族音楽学の分野で活躍し、アメリカ先住民(1960年代と1980年代、ブラックフット音楽を参照)、イラン(1966、1968-69、
1972、1974)、南インド(1981-82)で現地調査を行った。)
民族音楽学会の会長、同学会誌『民族音楽学』の編集長を務めた。イリノイ大学、カールトンカレッジ、ケニオンカレッジ、シカゴ大学から名誉博士号を授与さ
れた。民族音楽学で小泉文夫賞を受賞し、アメリカ芸術科学アカデミーのフェローでもある。ネトルは、米国学協会協議会から2014年チャールズ・ホー
マー・ハスキンズ賞の講師に指名された。学者として、また教授としての長いキャリアの中で、フィリップ・ボールマン、クリストファー・ウォーターマン、マ
ルチェロ・ソース・ケラー、ヴィクトリア・リンゼイ・レヴィンなど、現在国際的に活躍する多くの著名な民族音楽学者の師となった。Sousa
Archives and Center for American Musicが所蔵するBruno Nettl Papers,
1966-1988は、Nettlがイリノイ大学音楽学部教授および音楽学部長であったときの事務的および個人的な書簡から構成されている[13]
[14][15]。 |
| The Study of Ethnomusicology,
initially published in 1983, provides comprehensive discourse of
ethnomusicology and is widely considered some of Nettl’s best work.[16]
The book’s first edition included 29 chapters discussing the ins and
outs of ethnomusicology, which Nettl expanded to 31 chapters in 2005,
and 33 chapters in 2015.[17] The work includes an array of riveting
discussions surrounding ethnomusicology, including defining the
practice, the topic of universals, fieldwork, and the effects of music
on different cultures and demographics.[18] Nettl discusses fieldwork throughout his book, as seen in Chapter 10, “Come Back and See Me Next Tuesday: Essentials of Fieldwork,” and Chapter 11, “You Will Never Understand This Music: Insiders and Outsiders.”[19] Chapter 10 provides an insight into Nettl’s fieldwork, as the chapter opens by detailing Nettl’s interactions with a Native American called Joe.[20] Nettl had to do a series of favors for Joe before earning the right to interview him, demonstrating the importance of earning one’s trust while conducting fieldwork.[21] Next, Nettl used this anecdote as a base to dive deeper into fieldwork, stating how every ethnomusicologist has a unique approach to fieldwork, fieldwork can be a private matter for some ethnomusicologists, and understanding cultural dynamics and building relationships plays a tremendous role in the success of one’s fieldwork.[22] He also explained how three kinds of data should be gathered in fieldwork: texts, structures, and “the imponderabilia of everyday life."[23] This chapter also extensively investigated the history of fieldwork in ethnomusicology.[24] In this section, Nettl showed how fieldwork and research have become more unified, how ethnomusicologists became more willing to immerse themselves into a field, and how the increased accessibility of travel evolved fieldwork.[25] The chapter concluded by detailing the best ways to identify an informant within the field and how to best extract information from him or her.[26] Meanwhile, Chapter 11 concentrates on a somewhat controversial ethnomusicological topic: insiders and outsiders.[27] The chapter begins by explaining how natives to a culture tend not to appreciate foreign, especially Western, ethnomusicologists entering their domain and making claims about their music and cultures.[28] Nettl also elaborated on how some ethnomusicologists struggle to ingratiate themselves into a field and how some view music systems as “untranslatable.”[29] Nettl then articulated three common problems with outsider ethnomusicologists:[30] • They are only focused on comparing foreign traditions to their own. • They want to use their own approaches to non-Western music. • They generalize categories of music too easily. The chapter then transitioned to examining insiders.[31] Nettl stated that colonialism could lead to confusion when determining whom an insider is and debated whether insiders should help ethnomusicologists without compensation.[32] The chapter concluded by outlining the best way to conduct fieldwork.[33] Fieldwork is most effective when insiders and outsiders have mutual respect and understanding.[34] It is also essential for outsiders to enter a field with an open mind and engage in their research as a “participant.”[35] |
1983年に出版された『The Study of
Ethnomusicology』は、民族音楽学の包括的な言説を提供し、ネトルの最高傑作と広く考えられている[16]。この本の初版は、民族音楽学の
内実を論じる29章を含み、2005年に31章、2015年に33章に拡張された。 [17]
この作品には、実践の定義、普遍性の話題、フィールドワーク、異なる文化や人口動態に対する音楽の効果など、民族音楽学をめぐる興味深い議論が数多く含ま
れている[18]。 ネットルは、第10章「Come Back and See Me Next Tuesday」や第11章「You Will Never Understand This Music: Insiders and Outsiders」に見られるように、本書を通じてフィールドワークを論じている[19]。第10章では、冒頭でジョーというネイティブ・アメリカンと の交流が描かれており、ネットルのフィールドワークへの洞察を与えている[20]。 次に、ネットルはこの逸話をもとに、フィールドワークについて深く掘り下げ、民族音楽学者にはそれぞれフィールドワークに対するユニークなアプローチがあ ること、フィールドワークは民族音楽学者によってはプライベートな問題であること、文化の力学を理解し人間関係を構築することがフィールドワークの成功に 多大な役割を果たすことを述べている[21] 。 また、フィールドワークでは、テキスト、構造物、「日常生活の不可思議なもの」という3種類のデータを収集すべきことを説明した[23]。本章では、民族 音楽学におけるフィールドワークの歴史も広く調査した[24]。 [この章では、フィールドワークと研究がどのように一体化していったのか、民族音楽学者がどのようにフィールドに没頭することを望むようになったのか、旅 行へのアクセス性の向上がどのようにフィールドワークを進化させていったのかが示されている[25]。 この章の最後では、フィールド内でインフォーマントを特定する最善の方法と、彼または彼女から情報を引き出す最善の方法が詳述されている[26]。 一方、第11章では、やや議論の多い民族音楽学のトピックであるインサイダーとアウトサイダーに焦点を当てている[27]。この章では、まず、ある文化の 出身者が、外国、特に西洋の民族音楽学者が自分たちの領域に入り、自分たちの音楽と文化について主張することを認めない傾向にあることを説明している [28]。 [また、ネットルは、ある民族音楽学者がいかにそのフィールドに恩を着せるのに苦労しているか、そして、いかに音楽システムを「翻訳不可能なもの」として 見ているかについても詳しく説明している[29]。そして、ネットルはアウトサイダーの民族音楽学者に共通する三つの問題を明示している[30]。 外国の伝統と自国の伝統とを比較することだけに集中している。 非西洋音楽に対して独自のアプローチを使いたがる。 音楽のカテゴリーを安易に一般化しすぎる。 そして、インサイダー(=民族音楽学者たち自身へ)の考察に移行した[31]。ネトルは、インサイダーが誰であるかを決定する際に植民地主義が混乱を招く 可能性があると述べ、インサイダーは報酬なしで民族音楽学者を助けるべきかどうかを議論した[32]。本章は、フィールドワークを行う最善の方法について 概説して締めくくられている。インサイダーとアウトサイダーが相互に尊敬と理解を持つとき、フィールドワークは最も有効である[34]。またアウトサイ ダーにとってオープンマインドを持って現場に入り、「参加者」として調査に従事することが重要である[35]。 |
| Nettl’s contributions to
ethnomusicology have been cited in publications throughout the field
and he has undoubtedly influenced the work of other scholars. For
example, Nettl’s work is mentioned extensively in Stephen Amico’s “‘We
Are All Musicologists Now’; or, the End of Ethnomusicology,” a piece
that criticized several aspects of ethnomusicology.[36] Amico first
used Nettl’s “Contemplating Ethnomusicology: What Have We Learned” to
point out that the world’s music has become an “unholy mix” and that
the consensus did not find this alarming.[37] Amico also cited this
piece to make the point that ethnomusicological research is losing its
authenticity.[38] Finally, Amico disagreed with a point from Nettl’s
Elephant: On the History of Ethnomusicology, which was that
ethnomusicologists had yet to figure out their profession’s goals and
central questions.[39] Another scholar who benefitted from Nettl’s
contributions was Anna Schultz. In her essay “Still an
Ethnomusicologist (for Now),” she cited Nettl’s Elephant numerous times
to make the point that musicology and musicologists were imperative in
shaping what we now know as ethnomusicology.[40] Additionally,
Australian ethnomusicologist Clint Bracknell heavily utilized the 1983
and 2005 publications of The Study of Ethnomusicology to make numerous
claims about the emergence of non-Western voices in ethnomusicology in
his work, “‘Say You’re a Nyungarmusicologist’: Indigenous Research and
Endangered Song.”[41] |
ネットルの民族音楽学への貢献は、この分野のあらゆる出版物に引用され
ており、彼が他の学者の研究に影響を与えたことは間違いないでしょう。例えば、スティーブン・アミコの「『We Are All
Musicologists Now』; or, the End of
Ethnomusicology」は、民族音楽学のいくつかの側面を批判した作品であり、ネットルの研究は広く言及されている[36]。アミコはまずネッ
トルの「民族音楽学について考えてみよう。また、アミコはこの作品を引用して、民族音楽学的研究がその真正性を失いつつあるという指摘をしている
[38]。最後に、アミコはネットルの『象』からの指摘に反対している。また、ネットルの貢献から恩恵を受けた研究者として、アンナ・シュルツがいる。
シュルツは、「(今のところは)まだ民族音楽学者」というエッセイの中で、音楽学と音楽学者が現在の民族音楽学というものを形成する上で不可欠な存在であ
ることを主張し、ネトルのエレファントを何度も引用している[40]。
[さらに、オーストラリアの民族音楽学者クリント・ブラックネルは、1983年と2005年に出版された『民族音楽学研究』を大いに利用し、「『ニョンガ
ル音楽学者』と言え」という著作で、民族音楽学における非西洋人の声の出現について多くの主張を行っている。先住民の研究と絶滅の危機に瀕した歌」
[41]。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Nettl |
https://www.deepl.com/ja/translator |
| Steven Feld (born August 20,
1949) Steven Feld (born August 20, 1949) is an American ethnomusicologist, anthropologist, and linguist, who worked for many years with the Kaluli (Bosavi) people of Papua New Guinea. He earned a MacArthur Fellowship in 1991. Early life Feld was born in Philadelphia, Pennsylvania, on August 20, 1949. He graduated with a BA cum laude at Hofstra University in anthropology in 1971. He first went to the Bosavi territory in 1976, accompanied by anthropologist Edward L. Schieffelin, whose recordings of the Bosavi inspired him to pursue this work.[1] His work there fulfilled his dissertation (later published as Sound and Sentiment) for his PhD from Indiana University in 1979 (in anthropology/linguistics/ethnomusicology). Career Feld later returned several times in the 1980s and 1990s to Papua New Guinea to research Bosavi song, rainforest ecology, and cultural poetics. He has also made briefer research visits to various locations in Europe. He has taught at Columbia University, New York University, University of California at Santa Cruz, University of Texas at Austin, and University of Pennsylvania. He is currently (since 2003) a professor of anthropology and music at the University of New Mexico. Since 2001, he has also held a visiting appointment at the Grieg Academy, University of Bergen, Norway, as a professor of world music. In 2002, he founded the VoxLox label, "documentary sound art advocates for human rights and acoustic ecology." His most recent book Jazz Cosmopolitanism in Accra (2012) is based on five years of research and collaboration in Accra, Ghana. He is also a musician, and he has been active in the New Mexican music scene since the 1970s.[2] Some of Feld's recordings are sampled on the track, "Kaluli Groove" on the 2007 album Global Drum Project by Mickey Hart, Zakir Hussain, Sikiru Adepoju, and Giovanni Hidalgo. Academic work Schizophonic mimesis Schizophonic mimesis is a term coined by Steven Feld that describes the separation of a sound from its source, and the recontextualizing of that sound into a separate sonic context. The term in and of itself describes how sound recordings, split from their source through the chain of audio production, circulation, and consumption, stimulate and license renegotiations of identity in an ethnomusicological perspective. The term is composed of two parts: schizophonia and mimesis. Firstly, schizophonia, a term coined by Canadian composer R. Murray Schafer, refers to the split between an original sound and the reproduction/transmission of this sound, be it in a recording, a song, etc. For example, any sound recording, radio, and telephone is a machine of schizophonia, in that they all separate the sound from its original source; in the case of radio, the source of a New York radio show is from New York, but a listener in Los Angeles hears the noises from Los Angeles. Secondly, mimesis describes an imitation or representation of that separated sound into another context. For example, mimesis has occurred if one places a recording of a baby's gurgle into a song. Notable examples In 1969, ethnomusicologist Hugo Zemp recorded a Solomon Island woman named Afunakwa singing a popular Solomon Islands lullaby called "Rorogwela". Then, in 1992, on Deep Forest's album Boheme, a song called "Sweet Lullaby" samples Zemp's field recording of Rorogwela. Furthermore, in 1996, Norwegian saxophonist Jan Garbarek sampled the melody of "Rorogwela" in his song "Pygmy Lullaby" on his album Visual World. The field recording is an example of schizophonia, and the placing of this field recording into "Sweet Lullaby" is an instance of schizophonic mimesis. The sampling of the melody in "Pygmy Lullaby" demonstrates further schizophonic mimesis.[3] In 1966, ethnomusicologist Simha Arom recorded a particular style of music from the Ba-Benzélé Pygmies called Hindewhu, which consists of making music with a single-pitch flute and the human voice. Soon after, Herbie Hancock adapted the Hindewhu style by using a beer bottle instead of a flute in his 1973 remake of "Watermelon Man". Then, Madonna's song "Sanctuary" from the 1994 album Bedtime Stories sampled Hancock's adaptation of Hindewhu. Again, the field recording is an example of schizophonia, and the use of the Hindewhu style in Hancock's adaptation and "Sanctuary" are examples of schizophonic mimesis. Works Jazz Cosmopolitanism in Accra: Five Musical Years in Ghana. Duke University Press, 2012 Sound and Sentiment: Birds, Weeping, Poetics, and Song in Kaluli expression. University of Pennsylvania Press, 1982, 2nd ed. 1990; based on dissertation (with Charles Keil) Music Grooves. University of Chicago Press, 1994 (with Keith Basso, as eds.) Senses of Place. School of American Research Press, 1996 (with Bambi B. Schieffelin and others) Bosavi-English-Tok Pisin Dictionary. Australian National University, Pacific Linguistics C-153, 1998 (with Dick Blau, Charles Keil, and Angeliki V. Keil) Bright Balkan Morning: Romani Lives and the Power of Greek Music in Macedonia. Wesleyan University Press, 2002 Website ISBN 978-0-8195-6488-7 (with Virginia Ryan) Exposures: A White Woman in West Africa Voxlox Publication, 2006 (with Nicola Scaldaferri) When the trees resound - Collaborative Media Research on an Italian Festival, Nota, Udine, 2019 Recordings Music of the Kaluli. Institute of Papua New Guinea Studies, 1981 The Kaluli of Papua Nugini: Weeping and Song. Bärenreiter Musicaphon, 1985 Voices of the Rainforest. Rykodisc, 1991 Rainforest Soundwalks: Ambiences of Bosavi, Papua New Guinea. Earth Ear, 2001 Bosavi: Rainforest Music from Papua New Guinea. Smithsonian Folkways, 2001 Bells and Winter Festivals of Greek Macedonia. Smithsonian Folkways, 2002 For VoxLox The Time of Bells Vol. 1 & 2, 2004; Vol. 3 (with Nii Noi Nortey), 2005; Vol. 4, 2006 Suikinkutsu: A Japanese Underground Water Zither, 2006 The Castaways Project (with Virginia Ryan) 2006 Topographies of The Dark:2007 https://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Feld |
スティーブン・フェルド(1949年8月20日生まれ) スティーブン・フェルド(1949年8月20日生まれ)は、アメリカの民族音楽学者、人類学者、言語学者であり、パプアニューギニアのカルリ(ボサビ)族 と長年にわたる共同研究を行ってきた。1991年にマッカーサー・フェローシップを受賞。 生い立ち 1949年8月20日、ペンシルベニア州フィラデルフィア生まれ。1971年、ホフストラ大学人類学部を優秀な成績で卒業。1976年、人類学者エドワー ド・L・シーフェリン(Edward L. Schieffelin)の案内でボサヴィ(Bosavi)族の領土を訪れ、彼の録音したボサヴィ族に触発され、この仕事を志すようになった[1]。 1979年にインディアナ大学で博士号を取得するための学位論文(後に『Sound and Sentiment』として出版)は、ここでの研究が完成した。 経歴 フェルドはその後、1980年代から1990年代にかけて何度かパプアニューギニアに戻り、ボサビの歌、熱帯雨林の生態学、文化詩学を研究した。また、 ヨーロッパ各地を短期間訪れたこともある。 コロンビア大学、ニューヨーク大学、カリフォルニア大学サンタクルーズ校、テキサス大学オースティン校、ペンシルバニア大学で教鞭をとる。現在(2003 年~)、ニューメキシコ大学人類学・音楽学部教授。2001年からは、ノルウェーのベルゲン大学グリーグ・アカデミーの客員教授も務めている。 2002年、"人権と音響エコロジーのためのドキュメンタリー・サウンド・アートの提唱者 "であるVoxLoxレーベルを設立。近著『Jazz Cosmopolitanism in Accra』(2012年)は、ガーナのアクラにおける5年間のリサーチとコラボレーションに基づいている。 彼はミュージシャンでもあり、1970年代からニューメキシコの音楽シーンで活躍している[2]。 ミッキー・ハート、ザキール・フセイン、シキル・アデポジュ、ジョヴァンニ・イダルゴによる2007年のアルバム『Global Drum Project』のトラック「Kaluli Groove」では、フェルドの録音の一部がサンプリングされている。 アカデミックな仕事 シゾフォニック・ミメーシス スキゾフォニック・ミメシス(Schizophonic mimesis)とは、スティーブン・フェルド(Steven Feld)による造語で、音源から音を分離し、その音を別の音の文脈に再文脈化することを表す。この用語自体は、オーディオの生産、流通、消費の連鎖を通 して、音源から切り離された録音が、民族音楽学的観点から、アイデンティティの再交渉をどのように刺激し、許可するかを説明している。 この用語は、シゾフォニアとミメーシスという2つの部分から構成されている。まず、シゾフォニアとは、カナダの作曲家R.マレー・シェーファーによる造語 で、録音や歌など、原音とその再生/伝達との分裂を指す。例えば、録音、ラジオ、電話はすべて、音を元の音源から分離するという点で、分裂症の機械であ る。ラジオの場合、ニューヨークのラジオ番組の音源はニューヨークのものだが、ロサンゼルスのリスナーにはロサンゼルスの雑音が聞こえる。次に、ミメーシ スとは、分離された音を別の文脈で模倣したり表現したりすることである。例えば、赤ちゃんのうなり声を録音したものを歌の中に入れると、ミメーシスが起こ る。 注目すべき事例 1969年、民族音楽学者のヒューゴ・ゼンプは、アフナクワというソロモン諸島の女性が「ロログウェラ」というソロモン諸島でポピュラーな子守唄を歌って いるのを録音した。そして1992年、ディープ・フォレストのアルバム『Boheme』に収録された「Sweet Lullaby」という曲は、ゼンプが現地で録音した「Rorogwela」をサンプリングしている。さらに1996年には、ノルウェーのサックス奏者、 ヤン・ガルバレクがアルバム『Visual World』に収録した「Pygmy Lullaby」で「Rorogwela」のメロディーをサンプリングしている。フィールド・レコーディングはシゾフォニアの一例であり、このフィール ド・レコーディングを「Sweet Lullaby」に挿入することはシゾフォニック・ミメーシスの一例である。ピグミーの子守唄」でのメロディのサンプリングは、さらなるシゾフォニック・ ミメーシスを示している[3]。 1966年、民族音楽学者のシムハ・アロムは、バ・ベンゼレ・ピグミーのヒンデウーと呼ばれる特殊なスタイルの音楽を録音した。その直後、ハービー・ハン コックが1973年に「Watermelon Man」をリメイクした際、フルートの代わりにビール瓶を使ってヒンデウ・スタイルをアレンジした。そして、1994年のアルバム『Bedtime Stories』に収録されたマドンナの曲「Sanctuary」は、ハンコックがヒンデウーをアレンジしたものをサンプリングしたものだ。繰り返しにな るが、フィールド・レコーディングはシゾフォニアの例であり、ハンコックの翻案と「Sanctuary」におけるヒンデウーのスタイルの使用はシゾフォ ニック・ミメーシスの例である。 作品 ジャズ アクラにおけるコスモポリタニズム:ガーナでの5年間の音楽生活。デューク大学出版、2012年 音と感情:Kaluli表現における鳥、嘆き、詩学、歌。ペンシルベニア大学出版、1982年第2版、1990年、論文に基づく (チャールズ・キールとの共著)音楽グルーヴ。シカゴ大学出版、1994年 (キース・バッソとの共編著)『Senses of Place』School of American Research Press, 1996 (バンビ・B・シェフェリン他との共著)『Bosavi-English-Tok Pisin Dictionary』オーストラリア国立大学、パシフィック・ランゲージ学C-153、1998年 (ディック・ブラウ、チャールズ・キール、アンジェリカ・V・キールとの共著)『ブライト・バルカン・モーニング:マケドニアにおけるロマの生活とギリシャ音楽の力』ウェスリアン大学出版、2002年 ウェブサイト ISBN 978-0-8195-6488-7 (ヴァージニア・ライアンとの共著)『エクスポージャーズ:西アフリカの白人女性』ヴォクソロックス出版、2006年 (ニコラ・スカルダフェリとの共著)『When the trees resound - Collaborative Media Research on an Italian Festival』(「木々が響き渡るとき - イタリアの祭りを題材とした共同メディア研究」)Nota、ウディネ、2019年 録音 Kaluli族の音楽。パプアニューギニア研究所、1981年 パプアニューギニアのKaluli族:嘆きと歌。ベーレンライター・ムジカフォン、1985年 熱帯雨林の声。ライコディスク、1991年 Rainforest Soundwalks: Ambiences of Bosavi, Papua New Guinea. Earth Ear, 2001 Bosavi: Rainforest Music from Papua New Guinea. Smithsonian Folkways, 2001 Bells and Winter Festivals of Greek Macedonia. Smithsonian Folkways, 2002 For VoxLox 2004年;第3巻(ニー・ノイ・ノーテーとの共作)、2005年;第4巻、2006年 水琴窟:日本の地下水琴、2006年 ザ・キャスタウェイズ・プロジェクト(ヴァージニア・ライアンとの共作)2006年 トポグラフィー・オブ・ザ・ダーク:2007年 |
John Blacking (1928-1990)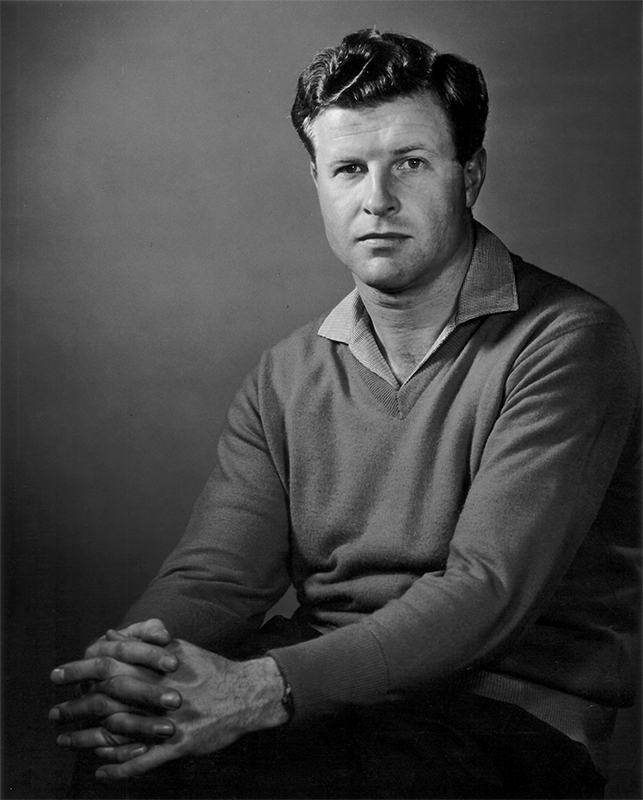 John Blacking was another
ethnomusicologist who sought to create an
ethnomusicological parallel to linguistic models of analysis. In his
work on Venda music, he writes, "The problem of musical description is
not unlike that in linguistic analysis: a particular grammar should
account for the processes by which all existing and all possible
sentences in the language are generated."[72] Blacking sought more than
sonic description. He wanted to create a musical analytical grammar,
which he coined the Cultural Analysis of Music, that could incorporate
both sonic description and how cultural and social factors influence
structures within music. Blacking desired a unified method of musical
analysis that "...can not only be applied to all music, but can explain
both the form, the social and emotional content, and the effects of
music, as systems of relationships between an infinite number of
variables."[72] Like Nattiez, Blacking saw a universal grammar as a
necessary for giving ethnomusicology a distinct identity. He felt that
ethnomusicology was just a "meeting ground" for anthropology of music
and the study of music in different cultures, and lacked a
distinguishing characteristic in scholarship. He urged others in the
field to become more aware and inclusive of the non-musical processes
that occur in the making of music, as well as the cultural foundation
for certain properties of the music in any given culture, in the vein
of Alan Merriam's work. John Blacking was another
ethnomusicologist who sought to create an
ethnomusicological parallel to linguistic models of analysis. In his
work on Venda music, he writes, "The problem of musical description is
not unlike that in linguistic analysis: a particular grammar should
account for the processes by which all existing and all possible
sentences in the language are generated."[72] Blacking sought more than
sonic description. He wanted to create a musical analytical grammar,
which he coined the Cultural Analysis of Music, that could incorporate
both sonic description and how cultural and social factors influence
structures within music. Blacking desired a unified method of musical
analysis that "...can not only be applied to all music, but can explain
both the form, the social and emotional content, and the effects of
music, as systems of relationships between an infinite number of
variables."[72] Like Nattiez, Blacking saw a universal grammar as a
necessary for giving ethnomusicology a distinct identity. He felt that
ethnomusicology was just a "meeting ground" for anthropology of music
and the study of music in different cultures, and lacked a
distinguishing characteristic in scholarship. He urged others in the
field to become more aware and inclusive of the non-musical processes
that occur in the making of music, as well as the cultural foundation
for certain properties of the music in any given culture, in the vein
of Alan Merriam's work.Some musical languages have been identified as more suited to linguistically focused analysis than others. Indian music, for example, has been linked more directly to language than music of other traditions.[67] Critics of musical semiotics and linguistic-based analytical systems, such as Steven Feld, argue that music only bears significant similarity to language in certain cultures and that linguistic analysis may frequently ignore cultural context.[73] |
ジョ
ン・ブラッキング (1928-1990)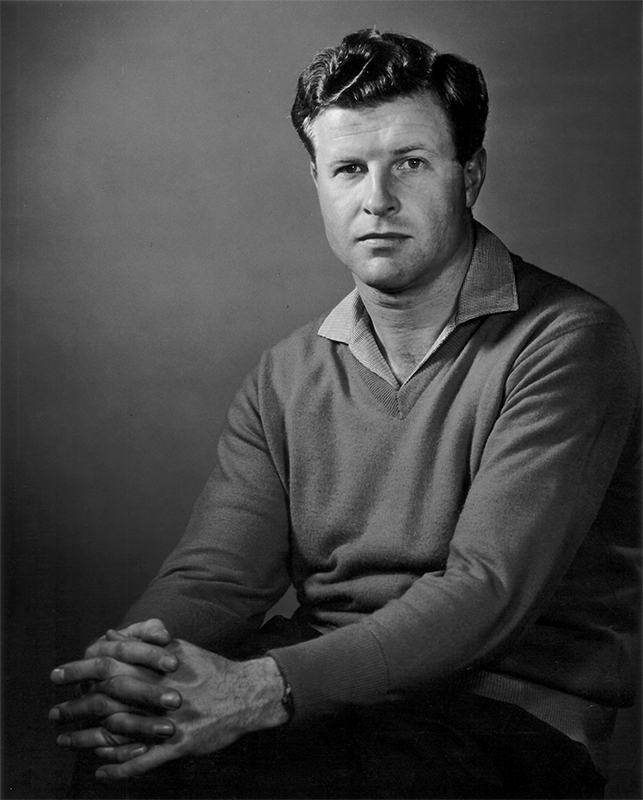 ジョ
ン・ブラッキングは言語学的な分析モデルに民族音楽学的な並列を作り出そうとしたもう一人の民族音楽学者であった。ヴェンダ音楽に関する著作の中
で、
彼は「音楽記述の問題は言語分析におけるそれと似ていない。特定の文法は、言語におけるすべての既存およびすべての可能な文が生成される過程を説明しなけ
ればならない」と書いている[72]。彼は、音の記述と文化的、社会的要因がどのように音楽の中の構造に影響を与えるかの両方を取り入れることができる、
音楽の文化分析と呼ばれる音楽分析文法を作りたかったのである。ブラッキングは「...すべての音楽に適用できるだけでなく、音楽の形式、社会的・感情的
内容、効果の両方を、無限の変数の間の関係のシステムとして説明できる」音楽分析の統一的方法を望んでいた[72]。ナティエスのように、ブラッキングは
民族音楽学に独特のアイデンティティを与えるために普遍的文法を必要だと考えていた。彼は民族音楽学が音楽の人類学と異なる文化における音楽の研究の「出
会いの場」に過ぎず、学問的に際立った特徴を欠いていると感じていた。彼は、アラン・メリアムの仕事のように、音楽が作られる際に生じる非音楽的なプロセ
スや、ある文化における音楽の特性の文化的基盤について、この分野の人々がもっと認識し、包括的になるよう促したのである。 ジョ
ン・ブラッキングは言語学的な分析モデルに民族音楽学的な並列を作り出そうとしたもう一人の民族音楽学者であった。ヴェンダ音楽に関する著作の中
で、
彼は「音楽記述の問題は言語分析におけるそれと似ていない。特定の文法は、言語におけるすべての既存およびすべての可能な文が生成される過程を説明しなけ
ればならない」と書いている[72]。彼は、音の記述と文化的、社会的要因がどのように音楽の中の構造に影響を与えるかの両方を取り入れることができる、
音楽の文化分析と呼ばれる音楽分析文法を作りたかったのである。ブラッキングは「...すべての音楽に適用できるだけでなく、音楽の形式、社会的・感情的
内容、効果の両方を、無限の変数の間の関係のシステムとして説明できる」音楽分析の統一的方法を望んでいた[72]。ナティエスのように、ブラッキングは
民族音楽学に独特のアイデンティティを与えるために普遍的文法を必要だと考えていた。彼は民族音楽学が音楽の人類学と異なる文化における音楽の研究の「出
会いの場」に過ぎず、学問的に際立った特徴を欠いていると感じていた。彼は、アラン・メリアムの仕事のように、音楽が作られる際に生じる非音楽的なプロセ
スや、ある文化における音楽の特性の文化的基盤について、この分野の人々がもっと認識し、包括的になるよう促したのである。音楽言語の中には、言語学的な分析に適しているものとそうでないものがあることが確認されている。例えばインド音楽は他の伝統の音楽よりも直接的に言語と 結びついている[67]。スティーブン・フェルドなどの音楽記号論や言語ベースの分析システムの批判者は、音楽は特定の文化においてのみ言語と大きな類似 性を持ち、言語分析はしばしば文化的文脈を無視する可能性があると主張している[73]。 |
 Alan Parkhurst
Merriam Alan Parkhurst
MerriamAlan Merriam, American anthropologist and ethnomusicologist Alan Parkhurst Merriam (1 November 1923 – 14 March 1980) was an American ethnomusicologist known for his studies of music in Native America and Africa.[1] In his book The Anthropology of Music (1964), he outlined and develops a theory and method for studying music from an anthropological perspective with anthropological methods. Although he taught at Northwestern University and University of Wisconsin, the majority of his academic career was spent at Indiana University where he was named a professor in 1962 and then chairman of the anthropology department from 1966 to 1969, which became a leading center of ethnomusicology research under his guidance.[2] He was a co-founder of the Society for Ethnomusicology in 1952 and held the elected post of president of that society from 1963 to 1965. He edited the Newsletter of the Society for Ethnomusicology from 1952 to 1957, and he edited the journal Ethnomusicology from 1957 to 1958.[2] Merriam's initial work was based on fieldwork carried out in his native Montana and central Africa. He undertook extensive field research among the Flathead Indians of Montana in 1950 (for his PhD) and again in 1958.[2] In Africa, he studied with the Songye and Bashi people of Zaïre (now the Democratic Republic of Congo) and Burundi in the 1950s and again in 1973.[2] Later, Merriam proposed a tripartite model for the study of ethnomusicology, centering on the study of "music in culture." This model suggested that music should be studied on three analytic levels: conceptualization about music; behavior in relation to music; and analysis of music's sounds.[3] In later works, Merriam amended his original concept of "music in culture" to "music as culture."[citation needed] Merriam died in the LOT Polish Airlines Flight 007 crash on March 14, 1980.[4][5] Early life and education Born to a highly musical household in Missoula, Montana, Merriam began studying piano and clarinet at a young age. His father was the Chairman of the English department at Montana State University, and his mother was a highly skilled cellist. During his younger years, Merriam performed in numerous school bands and local dance orchestras. Merriam studied music at Montana State University ('47) and began graduate work in anthropology at Northwestern University ('48) where he became acquainted with the anthropologist Melville J. Herskovits, who "stimulated his interest in the study of music as a cultural phenomenon." Merriam went on to complete a doctorate in anthropology, his dissertation titled "Songs of the Afro-Bahian Cults: An Ethnomusicological Analysis." This dissertation was significant to the field of Ethnomusicology, because it was the first instance of the word "ethnomusicology" being used as an adverb, marking a shift away from the adverbial usage of the phrase "comparative musicology."[6] Merriam as an Ethnomusicologist Due to its nature as a field at the intersection of several disciplines, ethnomusicology takes on many forms and is viewed through many lenses, highly dependent on the goals and background of the ethnomusicologist.[7] With training as an anthropologist, Merriam was a member of the anthropology school of ethnomusicology. Along with the musicology school, these two factions of ethnomusicology make up a large population in the world of ethnomusicology and they are often at odds.[8] His heavy association with the anthropology school of ethnomusicology had resulted in his views on the various issues plaguing ethnomusicology to considered representative of the attitudes and views of the anthropology school.[9] Issues that Merriam has weighed on in heavily in his opinion pieces are the way the field had been and should be defined and the directions it was taking during his lifetime. On defining ethnomusicology, Merriam draws on his background as an anthropologist to surmise that as a field ethnomusicology should aim to study "music in culture." Merriam emphasizes that "In other words I believe that music can be studied not only from the standpoint of musicians and humanists, but from that of social scientists as well, and that, further, it is at the moment from the field of cultural anthropology that our primary stimulation is coming for the study of music as a universal aspect of man's activities." to further his argument that ethnomusicology must continue its transition into the study of broader issues by removing focus from the study of musical objects.[10] He continued his efforts to arrive at a more accurate definition of ethnomusicology by later suggesting that music was the study of "music as culture." The distinction between these two approaches to define ethnomusicology lie in how culture is treated relative to the study of music. The approach of studying "music in culture" assumes that culture is a complex quality inherent to any society and music exists as a component of that quality. Treating "music as culture" conceives culture not as an object with comments but as a fluid construct and that methods of understanding it can be applied to understanding music.[11] Merriam's idea of how ethnomusicology should be defined drew from his idea of what an ethnomusicologist should accomplish. Merriam had, like all ethnomusicologists, completed fieldwork in his area of interest, but he was characterized by his peers in ethnomusicology as being more scientific and focusing on drawing conclusion from data. In his own writings, he emphasizes the application of data gathered in the field to solving relevant musical problems and how such application is motivated by the approach and goal of the researcher. Further, he claims the indispensable link between the data gathered in the field and the conclusions drawn from it by proposing his opinion on "armchair ethnomusicologists": "The day of the "armchair ethnomusicologist" who sits in the laboratory and analyzes the music that others have recorded…is fast passing in our discipline. I do not deny the contribution of such a specialist in the past, nor in the future, but his role is becoming progressively smaller, and rightly so, for method and theory are inseparable in the gathering of data, and the descriptive phase of our study in which we treat simply structural facts is giving way before the broader interpretations."[12] Merriam is characterized by a drive to solve relevant problems using data gathered in the field hands-on. An individual that stood as a foil to him was his fellow ethnomusicologist, Mantle Hood. A member of the musicology school of ethnomusicology, Hood was known for initiating an important ethnomusicology graduate program at UCLA. This graduate program was centered on bimusicality or "international musicianship," the practice in graduate ethnomusicology where students should make the effort to become proficient in musical traditions outside of their own. His program emphasized learning to listen and hear without prejudice or ethnocentricity, rhythmic and tonal fluency outside of the Western tradition, and performance experience in non-Western vocal and instrumental performance with the last being what his program is most known for.[13] These two ethnomusicologists in practice emphasized different things in what they believed ethnomusicology should accomplish. Hood was more interested in creating a graduate student body that could accomplish the egalitarian purpose of ethnomusicology in spreading world musics and preserving them. In contrast, Merriam's priorities lay in proposing a theoretical framework (as he does in The Anthropology of Music) for studying musical data and using that analysis for application towards solving musical problems. Merriam's contribution to ethnomusicology was felt past his death but especially in the works of Tim Rice of UCLA in the 1980s as he himself was trying to propose a more composed and exact model for conducting work in ethnomusicology. He deconstructed Merriam's method as stated in The Anthropology of Music and described it as consisting of three analytical levels. This simplified model was used by Rice as a foil to the method he was proposing, consistently referencing how his model furthered things accomplished by the Merriam model.[14] The Anthropology of Music The purpose of this book is to create a better understanding of the anthropological aspects of music, defining ethnomusicology as not the study of the music of non-western cultures, but instead as the study of the relationship which music bears to society. Merriam claims the goals of ethnomusicology cannot be realized by considering music to be an object separate from the humans which make it, and therefore argues for the sake of an anthropology of music. Studying just the music as an object, Merriam argues, is counterintuitive to the goals of ethnomusicology, excluding a very important aspect of ethnomusicology, which is music's intrinsic ties to the ways humans act. Articulating this relationship, Merriam states, "Music sound cannot be produced except by people for other people, and although we can separate the two aspects conceptually, one is not really complete without the other. Human behavior produces music, but the process is one of continuity; the behavior itself is shaped to produce music sound, and thus the study of one flows into the other". Ethnomusicology, Merriam posits, "has most often been made in terms of what [musicology] encompasses," being that the realms of musicology and ethnomusicology are exclusive to one another, and ethnomusicology has simply been relayed as being what musicology is not. Moving towards a clearer definition of ethnomusicology, Merriam writes that ethnomusicology "makes its unique contribution in welding together aspects of the social sciences and aspects of the humanities in such a way that each complements the other and leads to a fuller understanding of both. Neither should be considered as an end in itself; the two must be joined into a wider understanding." This definition of ethnomusicology comes in response to a number of other important ethnomusicology authors, such as Jaap Kunst, who defined ethnomusicology via the types of music studied in the field, "The study-object of ethnomusicology, or, as it originally was called: comparative musicology, is the traditional music and musical instruments of all cultural strata of mankind, from the so-called primitive peoples to the civilized nations. Our science, therefore, investigates all tribal and folk music and every kind of non-Western art music."[15] Merriam's own definition of ethnomusicology concerns a more general idea set with which the field of ethnomusicology is concerned with. In his own words, he defines it simply as "the study of music in culture" (cite Merriam's 1960 work here). This definition embodies the purpose of the entirety of The Anthropology of Music, being that ethnomusicology is not weighed further in favor of the ethnological or musicological, but instead an inseparable amalgamation of the two. Another aspect of ethnomusicology which Merriam sought to make clear in The Anthropology of Music is the overarching goal of the field of ethnomusicology. Merriam claims, "There is no denial of the basic aim, which is to understand music; but neither is there an acceptance of a point of view which has long taken ascendancy in ethnomusicology, that the ultimate aim of our discipline is the understanding of music sound alone." This harkens back to the difficulties in ethnomusicology's past priorities, which were simply the understanding of sound as an object in and of itself, and almost no emphasis was placed on the relationship music had with the cultures it existed in. Merriam divides his stated goals of ethnomusicology into three different approaches, the first being the appreciation of the music of other cultures. Many ethnomusicologists, Merriam asserts, are under the impression that the music of many non-western cultures are either abused or neglected, and that they are worthy of appreciation in western society the same way western music is appreciated. Merriam's second listed goal of ethnomusicology is the preservation of the music of these cultures, a transformative phenomenon Merriam describes as "a constant factor in human experience." The third perceived goal concerns a more general fascination with the use of music as a form of communication among humans, and the study of music in the various ways people use it to communicate will enable a better understanding of human communication in general. Merriam's own take on this perception is stated as "The problem of understanding has not always been well understood…the study of music as a means of communication, then, is far more complex than it might appear, for we do not know what precisely music communicates, or how it communicates it."[3] Select bibliography Primary works Merriam, Alan P. (1964). The Anthropology of Music. Northwestern Univ. Press. Merriam, Alan P. (1967). Ethnomusicology of the Flathead Indians. Viking Fund publications in anthropology, no.44. Chicago: Aldine. Merriam, Alan P. (1974). An African world: the Basongye village of Lupupa Ngye. Indiana Univ. Press. Secondary works Wendt, Carolyn Card, ed. (1981). Discourse in Ethnomusicology II: A Tribute to Alan Merriam. Bloomington, Indiana: Ethnomusicology Publications Group. OCLC 7926583. Nettl, Bruno (2001). "Merriam, Alan P.". The New Grove Dictionary of Music and Musicians. London: MacMillan. https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_P._Merriam |
 アラン・パークハースト・メリアム アラン・パークハースト・メリアムAlan Merriam, American anthropologist and ethnomusicologist アラン・パークハースト・メリアム(Alan Parkhurst Merriam、1923年11月1日 - 1980年3月14日)は、ネイティブアメリカンとアフリカの音楽研究で知られるアメリカの民族音楽学者である[1]。著書『音楽の人類学』(The Anthropology of Music、1964年)では、人類学の視点から人類学的手法で音楽を研究するための理論と方法を概説し、発展させた。ノースウェスタン大学とウィスコン シン大学で教鞭をとったが、学問的キャリアの大半はインディアナ大学で過ごした。1962年に教授に就任し、1966年から1969年まで人類学部の学長 を務め、彼の指導のもと民族音楽学研究の主要拠点となった[2]。1952年に民族音楽学会(Society for Ethnomusicology)を共同設立し、1963年から1965年まで同学会の会長に選出された。1952年から1957年まで民族音楽学会の ニュースレターを編集し、1957年から1958年まで雑誌『Ethnomusicology』を編集した[2]。 メリアムの最初の仕事は、彼の故郷であるモンタナと中央アフリカで行われたフィールドワークに基づいていた。アフリカでは、1950年代にザイール(現在 のコンゴ民主共和国)とブルンジのソンイェ族とバシ族を調査し、1973年にも再び調査を行った[2]。後にメリアムが提唱した民族音楽学の研究モデル は、"文化の中の音楽 "の研究を中心とした三部構成であった。このモデルは、音楽は3つの分析レベル、すなわち音楽に関する概念化、音楽に関連した行動、音楽の音の分析で研究 されるべきであると示唆した[3]。後の著作において、メリアムは「文化の中の音楽」という当初の概念を「文化としての音楽」に修正した[要出典]。 メリアムは1980年3月14日のLOTポーランド航空007便墜落事故で死亡した[4][5]。 生い立ちと教育 モンタナ州ミズーラの音楽一家に生まれたメリアムは、幼い頃からピアノとクラリネットを習い始めた。父親はモンタナ州立大学の英語学部長で、母親は熟練し たチェリストだった。若い頃、メリアムは数々のスクール・バンドや地元のダンス・オーケストラで演奏した。 モンタナ州立大学で音楽を学び(47年)、ノースウェスタン大学で人類学の大学院に進んだ(48年)。そこで人類学者メルヴィル・J・ハースコヴィッツと 知り合い、「文化現象としての音楽研究への興味を刺激された」。学位論文のタイトルは『Songs of the Afro-Bahian Cults: 民族音楽学的分析 "である。この学位論文は民族音楽学の分野にとって重要なものであった。というのも、「民族音楽学」という言葉が副詞として使われた最初の例であり、「比 較音楽学」という言葉の副詞的用法からの転換を示すものだったからである[6]。 民族音楽学者としてのメリアム 民族音楽学は複数の学問分野が交差する分野であるため、様々な形をとり、様々なレンズを通して見られるが、それは民族音楽学者の目標や背景によって大きく 左右される[7]。音楽学学派と並んで、民族音楽学のこの2つの派閥は民族音楽学の世界で大きな人口を占めており、しばしば対立している。[8] 民族音楽学の人類学学派との関係が深かったため、民族音楽学を悩ませている様々な問題に対する彼の見解は、人類学学派の態度や見解を代表するものと見なさ れるようになった。 [9]メリアムが意見書の中で重きを置いている問題は、彼が存命中、この分野がどのように定義されてきたか、またどのように定義されるべきか、そしてその 方向性である。 民族音楽学の定義について、メリアム氏は人類学者としての経歴を生かし、民族音楽学は "文化の中の音楽 "を研究する分野であるべきだと推測している。メリアム氏は次のように強調する。 「言い換えれば、音楽は音楽家や人文科学者の立場からだけでなく、社会科学者の立場からも研究することができる。 彼は後に、音楽は "文化としての音楽 "の研究であると示唆し、民族音楽学のより正確な定義に到達するための努力を続けた。民族音楽学を定義するためのこれら2つのアプローチの違いは、音楽研 究に対して文化をどのように扱うかにある。文化における音楽」を研究するというアプローチは、文化はあらゆる社会に内在する複雑な性質であり、音楽はその 性質を構成する要素として存在するという前提に立っている。文化としての音楽」を扱うことで、文化はコメントを持つ対象としてではなく、流動的な構成要素 として考えられ、それを理解する方法は音楽を理解することにも応用できるのである[11]。メリアムの民族音楽学がどのように定義されるべきかという考え は、民族音楽学者が何を達成すべきかという彼の考えから導き出されたものである。メリアムも他の民族音楽学者と同様、自分の関心領域でフィールドワークを こなしていたが、民族音楽学の仲間からは、より科学的でデータから結論を導き出すことに重点を置いていると評されていた。彼自身の著作では、フィールドで 収集したデータを関連する音楽的問題の解決に応用すること、そしてその応用が研究者のアプローチと目標によっていかに動機づけられるかを強調している。さ らに、「アームチェア・エスノミュージコロジスト(腕利きの民族音楽学者)」についての見解を提示することで、フィールドで収集したデータとそこから導き 出される結論との間に不可欠な結びつきを主張している: 「研究室に座って、他人が録音した音楽を分析する "アームチェア民族音楽学者 "の時代は、私たちの学問分野では急速に過ぎ去りつつある。私は、過去においても将来においても、そのような専門家の貢献を否定するつもりはないが、その 役割は次第に小さくなりつつあり、それは当然のことである。 メリアムの特徴は、現場で実際に収集したデータを使って、関連する問題を解決しようとする意欲にある。彼と瓜二つだったのが、同じ民族音楽学者のマント ル・フッドである。民族音楽学の音楽学派の一員であったフッドは、UCLAで重要な民族音楽学の大学院プログラムを開始したことで知られている。この大学 院プログラムは、バイ・ミュージカリティ、つまり「国際的な音楽性」を中心に据えたもので、大学院の民族音楽学では、学生は自国以外の音楽的伝統に習熟す る努力をしなければならない。彼のプログラムでは、偏見や民族中心主義にとらわれることなく聴くこと、西洋の伝統以外のリズムや調性の流暢さを学ぶこと、 そして西洋以外の声楽や器楽の演奏経験を積むことが重視され、特に最後の経験が彼のプログラムで最もよく知られている。フッドは、世界の音楽を広め、保存 するという民族音楽学の平等主義的な目的を達成できるような大学院生集団を作ることに、より関心を持っていた。対照的に、メリアムが優先したのは、音楽 データを研究するための理論的枠組みを提案し(『音楽の人類学』(The Anthropology of Music)で行っているように)、その分析を音楽的問題の解決に役立てることであった。 メリアムの民族音楽学への貢献は、彼の死後も感じられたが、特に1980年代にUCLAのティム・ライス(Tim Rice)が、民族音楽学での研究をより構成的かつ正確に行うためのモデルを提案しようとしていた。彼は『The Anthropology of Music(音楽の人類学)』で述べられているメリアムの方法を解体し、それを3つの分析レベルからなるものとして説明した。この単純化されたモデルは、 ライスによって、彼が提案していた方法に対する箔付けとして使われ、一貫して自分のモデルがメリアムモデルによって達成されたことをさらに前進させること に言及していた[14]。 音楽の人類学 本書の目的は、音楽の人類学的側面をよりよく理解することであり、民族音楽学を非西洋文化の音楽を研究するものではなく、音楽が社会にもたらす関係を研究 するものと定義している。メリアム氏は、音楽をそれを作る人間から切り離された対象として考えることでは、民族音楽学の目標は達成できないと主張し、音楽 の人類学の必要性を主張している。音楽をただ対象として研究することは、民族音楽学の目標とは直感的に逆行するものであり、民族音楽学の非常に重要な側面 である、音楽と人間の行為との本質的な結びつきを排除するものである、とメリアム氏は主張する。メリアム氏は、この関係を次のように述べている、 「音楽という音は、人が人のために作るものであり、この2つの側面を概念的に分けることはできても、一方が他方なしには成立しない。人間の行動は音楽を生 み出すが、そのプロセスは連続性のあるものであり、行動そのものが音楽音を生み出すように形作られ、したがって一方の研究は他方に流れ込む」と述べてい る。 音楽学と民族音楽学の領域は互いに排他的であり、民族音楽学は単に音楽学にはないものとして伝えられてきた。メリアム氏は、民族音楽学の明確な定義に向け て、民族音楽学は「社会科学の側面と人文科学の側面を、それぞれが他方を補完し、両者をより深く理解するように結びつけることで、独自の貢献をしている」 と書いている。どちらもそれ自体が目的であってはならない。 この民族音楽学の定義は、この分野で研究される音楽の種類によって民族音楽学を定義したヤープ・クンスト(Jaap Kunst)のような、他の多くの重要な民族音楽学の著者に呼応するものである、 「民族音楽学の研究対象は、元来は比較音楽学と呼ばれていたように、いわゆる原始民族から文明国に至るまで、人類のあらゆる文化層の伝統的な音楽と楽器で ある。したがって私たちの科学は、すべての部族音楽と民族音楽、そしてあらゆる種類の非西洋芸術音楽を調査する」[15]。 メリアム自身の民族音楽学の定義は、民族音楽学という分野が関わる、より一般的な考え方に関するものである。彼自身の言葉では、「文化における音楽の研 究」と定義している(メリアムの1960年の著作を引用)。この定義は、『音楽の人類学』全体の目的を体現するものであり、民族音楽学は民族学的か音楽学 的かの二者択一ではなく、両者の不可分の融合であるということである。 メリアムが『音楽の人類学』で明らかにしようとした民族音楽学のもう一つの側面は、民族音楽学という分野の包括的な目標である。音楽を理解するという基本 的な目的は否定しないが、私たちの学問の究極的な目的は音楽の音だけを理解することであるという、民族音楽学で長い間優勢を占めてきた見解を受け入れるこ ともない」とメリアムは主張している。これは、民族音楽学の過去の優先順位が、単に音をそれ自体として理解することであり、音楽が存在する文化との関係に ほとんど重きを置いていなかったことの難しさを思い起こさせる。メリアム氏は、民族音楽学の目標を3つの異なるアプローチに分けている。多くの民族音楽学 者は、多くの非西洋文化の音楽が虐待されているか、軽視されているかのどちらかであるという印象を持っており、西洋音楽が評価されるのと同じように、西洋 社会でも評価される価値があるとメリアム氏は主張する。メリアムが民族音楽学の第二の目標として挙げているのは、これらの文化の音楽を保存することであ る。第三の目標は、人間同士のコミュニケーションの一形態としての音楽の使用に関する、より一般的な魅力に関するもので、人々がコミュニケーションのため に音楽を使用する様々な方法を研究することで、人間のコミュニケーション全般をよりよく理解することができるようになる。この認識に関するメリアム自身の 見解は、「理解の問題は、常によく理解されてきたわけではない......コミュニケーションの手段としての音楽の研究は、見かけよりもはるかに複雑であ る。 参考文献 主要著作 Merriam, Alan P. (1964). The Anthropology of Music. Northwestern Univ. Press. Merriam, Alan P. (1967). Ethnomusicology of the Flathead Indians. Viking Fund publications in anthropology, no.44. Chicago: Aldine. Merriam, Alan P. (1974). An African world: the Basongye village of Lupupa Ngye. Indiana Univ. Press. 二次的著作 Wendt, Carolyn Card, ed. (1981). Discourse in Ethnomusicology II: A Tribute to Alan Merriam. Bloomington, Indiana: Ethnomusicology Publications Group. OCLC 7926583. Nettl, Bruno (2001). 「Merriam, Alan P.」. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. London: MacMillan. |
| PART ONE: ETHNOMUSICOLOGY CHAPTER 1. The Study of Ethnomusicology 3 CHAPTER 2. Toward a Theory for Ethnomusicology 17 CHAPTER 3. Method and Technique 37 PART TWO: CONCEPTS AND BEHAVIOR CHAPTER 4. Concepts 63 CHAPTER 5. Synesthesia and Intersense Modalities 85 CHAPTER 6. Physical and Verbal Behavior 103 CHAPTER 7. Social Behavior: The Musician 123 CHAPTER 8. Learning 145 CHAPTER 9. The Process of Composition 165 PART THREE: PROBLEMS AND RESULTS CHAPTER 10. The Study of Song Texts 187 CHAPTER 11. Uses and Functions 209 CHAPTER 12. Music as Symbolic Behavior 229 CHAPTER 13. Aesthetics and the Interrelationship of the Arts 259 CHAPTER 14. Music and Culture History 277 CHAPTER 15. Music and Cultural Dynamics 303R eferences Cited 321 Index 345 |
音楽人類学 / アラン・P・メリアム著 ; 藤井知昭,
鈴木道子訳, 音楽之友社 , 1980年 第1部 民族音楽学 第1章 民族音楽学の研究 3 第2章. 民族音楽学の理論に向けて 17 第3章. 方法と技法 37 第2部 概念と行動 第4章 概念 第5章 共感覚と相互感覚モダリティ 85 第6章 身体行動と言語行動 103 第7章 社会的行動: 音楽家 123 第8章 学習 学習 145 第9章 作曲の過程 165 第3部 問題と結果 第10章. 歌曲テキストの研究 187 第11章. 用途と機能 209 第12章. 象徴的行動としての音楽 229 第13章. 美学と芸術の相互関係 259 第14章. 音楽と文化史 277 第15章. 音楽と文化力学 303章 引用文献 321 索引 345 【追記】 アラン・メリアム「音楽人類学」の第12章の議論が、情動や感覚の人類学の研究課題に交錯するのではないかと、現在検討中。 第13章「諸芸術間の相互関係と美学」も重要性です。西洋美学の審美性の6つの要素が、他の民族の美的観念に対して独自の性格づけをもっていることを指摘 して、西洋美学の審美性の概念を批判していることです。つまり、1)心理的距離をたもてること、2)操作することを目的としている、3)音として把握する 音楽に情緒的性格を与えようとすること、4)美を芸術作品やその他の創作過程に与えようとすること、5)審美的なものを創造しなくてはならないという目的 意志がある、6)美的なものに哲学を与えること、です。これをメリアムは、彼のフィールドのパソンギュ人やフラットヘッドの音楽経験と対峙させています。 これは彼のフィールドワーカーとしての面目躍如といったところです。すばらし |
 Anthony Seeger Anthony SeegerFrom hymns and spirituals, to songs of protest, and the national anthem; music has always played a powerful role in American life.--Anthony Seeger, PhD Anthony Seeger is a Curator and Director Emeritus of Smithsonian Folkways Recordings. Additionally, he is a Distinguished Professor of Ethnomusicology Emeritus at the University of California, Los Angeles. Born into a musical family, he is also an anthropologist, ethnomusicologist, audiovisual archivist, record producer, and amateur musician. Professor Seeger received his BA in Social Relations from Harvard University and his MA and PhD in Anthropology from the University of Chicago. Professor Seeger lived in Brazil for nearly 10 years and spent much of that time as a member of the Graduate Program in Social Anthropology in the Department of Anthropology at the National Museum in Rio de Janeiro. His anthropological research focused on the music and culture of the Kĩsêdjê people (formerly known as the Suyá) of Mato Grosso, Brazil. He also helped establish the Musicology/Ethnomusicology/Music Education MA program at the Brazilian Conservatory of Music. Professor Seeger later returned to the US to serve as director of the Archives of Traditional Music at Indiana University Bloomington, where he also taught. He then moved to the Smithsonian Institution to assume the direction of the recently acquired Folkways Records and to become the first curator of the Smithsonian’s Folkways archival collection. He established the Smithsonian Folkways Recordings record label, where he was the executive producer for more than 250 CDs as well as a collaborator on DVDs and radio series. He was also the faculty director of the UCLA Ethnomusicology Archive. Professor Seeger has been active in several professional organizations. He served as president of the Society for Ethnomusicology, president and secretary general of the International Council for Traditional Music, chair of the Research Archives Section of the International Association of Sound and Audiovisual Archives, and vice president of the Brazilian Association for Ethnomusicology. Professor Seeger was elected as a member of the American Academy of Arts and Sciences, and he received a Guggenheim research fellowship, among other grants. He was awarded the Tai Chi Traditional Music Prize for lifetime achievement from the Central Conservatory of Music in Beijing and also received the Lifetime Contribution Award from the Brazilian Studies Association. Professor Seeger has published three books, four coedited volumes, and more than 120 articles and book chapters on the music and culture of Indigenous Brazilians, Indigenous rights issues, ethnomusicology, audiovisual archiving, American music, intellectual property, and other subjects. Among Professor Seeger’s books are Nature and Society in Central Brazil: The Suya Indians of Mato Grosso and Why Suyá Sing: A Musical Anthropology of an Amazonian People. With Dr. Shubha Chaudhuri, he coedited Archives for the Future: Global Perspectives on Audiovisual Archives in the 21st Century. Additionally, he produced and presented a 1988 series of six 30-minute radio shows for the BBC on American traditional music. Professor Seeger now lectures in the US and abroad. https://www.wondrium.com/anthony-seeger |
 アンソニー・シーガー(Anthony Seeger) アンソニー・シーガー(Anthony Seeger)賛美歌やスピリチュアルな歌から、抗議の歌、国歌まで、音楽は常にアメリカ人の生活の中で力強い役割を果たしてきた。——アンソニー・シガー. アンソニー・シーガーはスミソニアン・フォークウェイズ・レコーディン グスのキュレーター兼名誉ディレクター。また、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の特別名誉教授(民族音楽学)でもある。音楽一家に生まれ、人類学者、民 族音楽学者、オーディオビジュアル・アーキビスト、レコード・プロデューサー、アマチュア・ミュージシャンでもある。ハーバード大学で社会関係学の学士号 を、シカゴ大学で人類学の修士号と博士号を取得。 シーガー教授はブラジルに10年近く滞在し、その大半をリオデジャネイロ国立博物館人類学部の社会人類学大学院プログラムのメンバーとして過ごした。彼の 人類学的研究は、ブラジルのマトグロッソ州に住むKĩsêdjê族(以前はSuyá族として知られていた)の音楽と文化に焦点を当てたものであった。ま た、ブラジル音楽院の音楽学/民族音楽学/音楽教育学修士プログラムの設立にも貢献した。 その後、シーガー教授はアメリカに戻り、インディアナ大学ブルーミントン校の伝統音楽アーカイブのディレクターを務め、そこで教鞭も執った。その後、スミ ソニアン博物館に移り、最近買収したフォークウェイズ・レコードの指揮を執り、スミソニアンのフォークウェイズ・アーカイヴ・コレクションの初代キュレー ターとなった。スミソニアン・フォークウェイズ・レコーディングス・レコード・レーベルを設立し、250枚以上のCDのエグゼクティブ・プロデューサーを 務めたほか、DVDやラジオシリーズの共同制作者でもあった。また、UCLA民族音楽学アーカイブのファカルティ・ディレクターも務めた。 シーガー教授は、いくつかの専門団体で活躍している。民族音楽学会会長、国際伝統音楽協議会会長兼事務局長、国際音響視聴覚アーカイブズ協会研究アーカイ ブズ部会長、ブラジル民族音楽学会副会長などを歴任。シーガー教授はアメリカ芸術科学アカデミーの会員に選出され、グッゲンハイム研究奨学金などを受賞。 また、北京の中央音楽院から生涯功労賞として太極伝統音楽賞を授与されたほか、ブラジル研究協会からも生涯貢献賞を受賞している。 シーガー教授は、ブラジル先住民の音楽と文化、先住民の権利問題、民族音楽学、視聴覚アーカイブ、アメリカ音楽、知的所有権などに関して、3冊の著書、4 冊の共編著、120本以上の論文や本の章を出版している。シーガー教授の著書に『Nature and Society in Central Brazil』がある: The Suya Indians of Mato Grosso』、『Why Suyá Sing: A Musical Anthropology of an Amazonian People』などがある。シュバ・チャウドゥリ博士との共編著に『Archives for the Future』: 21世紀における視聴覚アーカイブのグローバルな展望』を共同編集。また、1988年にはBBCでアメリカの伝統音楽に関する30分のラジオ番組6シリー ズを制作・放送した。シーガー教授は現在、米国内外で講演活動を行っている。 |
 Tim Rice Tim RiceTim Rice recently retired after thirty years as a professor of ethnomusicology at UCLA. He specializes in the traditional music of the Balkans, especially from the Slavic-speaking nations of Bulgaria and Macedonia. In that field he is the author of May it Fill Your Soul: Experiencing Bulgarian Music (Chicago, 1994) and Music in Bulgaria: Experiencing Music, Expressing Culture (Oxford, 2004) as well as numerous articles in major journals. In terms of research themes, he has written on musical cognition, politics and music, meaning and music, mass media, music teaching and learning, and theory and method in ethnomusicology, including a book entitled Ethnomusicology: A Very Short Introduction (Oxford, 2014). He was founding co-editor of the ten-volume Garland Encyclopedia of World Music and co-edited Volume 8, Europe. Tim has served the field of ethnomusicology in a variety of ways, including editing the journal Ethnomusicology (1981-1984), acting as President of the Society for Ethnomusicology (2003-2005), and serving on the Executive Board of the International Council for Traditional Music (2007-2013). At UCLA, Rice served as chair of the Department of Ethnomusicology, associate dean of the School of the Arts and Architecture, and inaugural director of the UCLA Herb Alpert School of Music. In 2016, Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Bulgaria) awarded him the degree Doctor Honoris Causa for his contributions to Bulgarian music studies. His home department at UCLA recently sponsored a day-long symposium “Ethnomusicology in Theory and Practice” on May 19, 2017 in honor of Tim’s career. tim.rice@centerforworldmusic.org https://centerforworldmusic.org/about-us/meet-team/tim-rice/ +++++++++++++++++ Timothy Rice publishes 'Ethnomusicology: A Very Short Introduction' Christina Mattson | June 17, 2014 Timothy Rice, professor of ethnomusicology and director of the department of music at the UCLA Herb Alpert School of Music, has published a new book, “Ethnomusicology: A Very Short Introduction.” Rice's book concisely defines and explores this growing field. Though ethnomusicology focuses on music created by different cultures, mostly by declared musicians, the field recognizes a central belief that all people are musical and that this experience of music is central to the human experience. Rice explains the methods of ethnomusicological research, which usually involve living within a community and participating in, observing and recording that community’s musical events. Rice also ties the data from these observations to other social sciences when he discusses patterns in musical traditions and the ways they reflect cultural practices. Rice has previously written about the research themes of musical cognition, politics and music, meaning and music, mass media, music teaching and learning and theory and method in ethnomusicology. He specializes in the traditional music of the Balkans, especially from the Slavic-speaking nations of Bulgaria and Macedonia; his writings in that field include the books “May it Fill Your Soul: Experiencing Bulgarian Music” and “Music in Bulgaria: Experiencing Music, Expressing Culture” in that field, as well as numerous articles in major journals. Gateways to Understanding Music, Second Edition, explores music in all the categories that constitute contemporary musical experience: European classical, popular, jazz, and world music. Covering the oldest forms of human music making to the newest, this chronology presents music from a global rather than a Eurocentric perspective. Each of 60 "gateways" addresses a particular genre, style, or period of music. Every gateway opens with a guided listening example that unlocks a world of music through careful study of its structural elements. How did the piece come to be composed or performed? How did it respond to the social and cultural issues at the time, and what does that music mean today? Students learn to listen to, explain, understand, and ultimately value all the music they encounter in their world. New to this edition is a broader selection of musical examples that reflect the values of diversity, equity, and inclusion advocated by North American universities. Eight gateways have been replaced. A timeline of gateways helps students see the book’s historical narrative at a glance. Features Values orientation - Diverse, equitable, and inclusive approach to music history. All genres of music - Presents all music as worthy of study, including classical, world, popular, and jazz. Global scope within a historical narrative - Begins with small-scale forager societies up to the present, with a shifting focus from global to European to American influences. Recurring themes - Aesthetics, emotion, social life, links to culture, politics, economics, and technology. Modular framework - 60 gateways - each with a listening example - allow flexibility to organize chronologically or by the seven themes. Consistent structure - With the same step-by-step format, students learn through repeated practice how to listen and how to think about music. Anthology of scores - For those courses that use the textbook in a music history sequence. Gateways to Understanding Music continues to employ a website to host the audio examples and instructor’s resources. https://www.routledge.com/Gateways-to-Understanding-Music/Rice-Wilson/p/book/9781032216294 Modeling ethnomusicology Ethnomusicology is an academic discipline with a very broad mandate: to understand why and how human beings are musical through the study of music in all its geographical and historical diversity. Ethnomusicological scholarship, however, has been remiss in articulating such goals, methods, and theories. A renowned figure in the field, Timothy Rice is one of the few scholars to regularly address this problem. In this volume, he offers a compilation of essays drawn from across his career that finds implicit and yet largely unrecognized patterns unifying ethnomusicology over its recent history. Modeling Ethnomusicology summarizes thirty years of thinking about the field of ethnomusicology as Rice frames and reframes the content of eight of his most important essays from their original context in relation to the environment of today's ethnomusicology. Rice proposes a variety of models meant to guide students and researchers in their study of ethnomusicology. Some of these models pull together disparate strands of the field, while others propose heuristic models that generate questions for researchers as they plan and conduct their research. A new introduction to these essays reviews the history of his writing about ethnomusicology and proposes an innovative model for theorizing in ethnomusicology by ethnomusicologists. This book will be an enduring, essential text in undergraduate and graduate ethnomusicology classrooms, as well as a must-buy for established scholars in the field. Table of Contents Introduction Chapter 1: Toward the Remodeling of Ethnomusicology Chapter 2: Toward a Mediation of Field Methods and Field Experience in Ethnomusicology Chapter 3: Reflections on Music and Meaning: Metaphor, Signification and Control in the Bulgarian Case Chapter 4: Time, Place, and Metaphor in Musical Experience and Ethnography Chapter 5: Reflections on Music and Identity in Ethnomusicology Chapter 6: Ethnomusicological Theory Chapter 7: The Individual in Musical Ethnography Chapter 8: Ethnomusicology in Time of Trouble Bibliography Index Ethnomusicology : a very short introduction / Timothy Rice, Oxford University Press , 2014 . - (Very short introductions, 376) Ethnomusicologists believe that all humans, not just those we call musicians, are musical, and that musicality is one of the essential touchstones of the human experience. This insight raises big questions about the nature of music and the nature of humankind, and ethnomusicologists argue that to properly address these questions, we must study music in all its geographical and historical diversity. In this Very Short Introduction, one of the foremost ethnomusicologists, Timothy Rice, offers a compact and illuminating account of this growing discipline, showing how modern researchers go about studying music from around the world, looking for insights into both music and humanity. The reader discovers that ethnomusicologists today not only examine traditional forms of music-such as Japanese gagaku, Bulgarian folk music, Javanese gamelan, or Native American drumming and singing-but also explore more contemporary musical forms, from rap and reggae to Tex-Mex, Serbian turbofolk, and even the piped-in music at the Mall of America. To investigate these diverse musical forms, Rice shows, ethnomusicologists typically live in a community, participate in and observe and record musical events, interview the musicians, their patrons, and the audience, and learn to sing, play, and dance. It's important to establish rapport with musicians and community members, and obtain the permission of those they will work with closely over the course of many months and years. We see how the researcher analyzes the data to understand how a particular musical tradition works, what is distinctive about it, and how it bears the personal, social, and cultural meanings attributed to it. Rice also discusses how researchers may apply theories from anthropology and other social sciences, to shed further light on the nature of music as a human behavior and cultural practice. About the Series: Oxford's Very Short Introductions series offers concise and original introductions to a wide range of subjects--from Islam to Sociology, Politics to Classics, Literary Theory to History, and Archaeology to the Bible. Not simply a textbook of definitions, each volume in this series provides trenchant and provocative--yet always balanced and complete--discussions of the central issues in a given discipline or field. Every Very Short Introduction gives a readable evolution of the subject in question, demonstrating how the subject has developed and how it has influenced society. Eventually, the series will encompass every major academic discipline, offering all students an accessible and abundant reference library. Whatever the area of study that one deems important or appealing, whatever the topic that fascinates the general reader, the Very Short Introductions series has a handy and affordable guide that will likely prove indispensable. List of illustrations Chapter 1: Defining ethnomusicology Chapter 2: A bit of history Chapter 3: Conducting research Chapter 4: The nature of music Chapter 5: Music and culture Chapter 6: Individual musicians Chapter 7: Writing music history Chapter 8: Ethnomusicology in the modern world Chapter 9: Ethnomusicologists at work References Further reading Suggestions for listening |
 ティ
ム・ライス(Tim Rice) ティ
ム・ライス(Tim Rice)ティ ム・ライスは、UCLAの民族音楽学教授を30年間務めた後、最近退職した。専門はバルカン半島、特にスラブ語圏のブルガリアとマケドニアの伝統音楽。こ の分野では、『May it Fill Your Soul: Experiencing Bulgarian Music』(シカゴ、1994年)、『Music in Bulgaria: Experiencing Music, Expressing Culture』(オックスフォード、2004年)のほか、主要雑誌に多数の論文を執筆。研究テーマとしては、音楽認知、政治と音楽、意味と音楽、マスメ ディア、音楽教育と学習、民族音楽学の理論と方法などについて執筆しており、『Ethnomusicology: A Very Short Introduction』(オックスフォード、2014年)など。全10巻からなる『Garland Encyclopedia of World Music』の創刊共同編集者であり、第8巻『Europe』の共同編集者でもある。 雑誌『Ethnomusicology』の編集(1981-1984年)、民族音楽学会会長(2003-2005年)、国際伝統音楽評議会理事(2007 -2013年)など、さまざまな形で民族音楽学の分野に貢献してきた。UCLAでは、民族音楽学部長、芸術建築学部副学部長、UCLAハーブ・アルパート 音楽院初代院長を歴任。 2016年、ブルガリアのソフィア大学 "St. Kliment Ohridski "から、ブルガリア音楽研究への貢献に対して名誉博士号を授与された。UCLAの彼の出身学部では、2017年5月19日にティムのキャリアを記念して1 日シンポジウム「Ethnomusicology in Theory and Practice」を開催した。 tim.rice@centerforworldmusic.org https://centerforworldmusic.org/about-us/meet-team/tim-rice/ +++++++++++++ ティモシー・ライス、『民族音楽学』を出版: とても短い入門書 クリスティーナ・マットソン|2014年6月17日 ティモシー・ライス(UCLAハーブ・アルパート音楽学部民族音楽学教授・音楽学部ディレクター)が、新著 "Ethnomusicology: を出版した。 ライス氏の著書は、この成長分野を簡潔に定義し、探求している。民族音楽学は、異なる文化、主に宣言された音楽家たちによって創られた音楽に焦点を当てて いるが、この分野は、すべての人が音楽的であり、この音楽体験が人間の経験の中心であるという中心的な信念を認めている。 ライス氏は、民族音楽学的研究の方法について説明する。通常、コミュニティ内に住み、そのコミュニティの音楽イベントに参加し、観察し、記録する。ライス はまた、音楽の伝統のパターンと、それが文化的慣習を反映する方法について論じるとき、これらの観察から得られたデータを他の社会科学と結びつける。 ライス氏はこれまでに、音楽的認知、政治と音楽、意味と音楽、マスメディア、音楽教育と学習、民族音楽学における理論と方法といった研究テーマについて執 筆してきた。専門はバルカン半島、特にスラブ語圏のブルガリアとマケドニアの伝統音楽で、この分野での著作に『May it Fill Your Soul: Experiencing Bulgarian Music』、『Music in Bulgaria: Experiencing Music, Expressing Culture』などがあり、主要ジャーナルにも多数の論文が掲載されている。 音楽を理解するための入り口、第2版では、現代の音楽体験を構成するす べてのカテゴリーにおける音楽を探求している: ヨーロッパのクラシック音楽、ポピュラー音楽、ジャズ、ワールド・ミュージックなど、現代の音楽体験を構成するすべてのカテゴリーにおける音楽を探求して いる。人類最古の音楽から最新の音楽までを網羅したこの年表は、ヨーロッパ中心ではなく、グローバルな視点から音楽を紹介している。60の「ゲートウェ イ」はそれぞれ、音楽の特定のジャンル、スタイル、時代を取り上げている。各ゲートウェイの冒頭には、音楽の構造的要素を注意深く研究することで音楽の世 界を解き明かす、ガイド付きリスニング例が掲載されている。その曲がどのように作曲され、演奏されるようになったのか。当時の社会的・文化的問題にどのよ うに対応し、その音楽が今日どのような意味を持つのか。生徒たちは、自分たちの世界で出会うすべての音楽を聴き、説明し、理解し、最終的に価値を見出すこ とを学ぶ。 この改訂版では、北米の大学が提唱する多様性、公平性、包摂の価値観を反映した、より幅広い音楽例を取り上げています。8つのゲートウェイが入れ替わりま した。ゲートウェイの年表により、本書の歴史的な物語が一目でわかる。 特徴 価値観重視 - 多様性、公平性、包括性を重視した音楽史へのアプローチ。 あらゆるジャンルの音楽 - クラシック、ワールドミュージック、ポピュラー、ジャズなど、あらゆる音楽を研究対象としています。 歴史的な物語における世界的な範囲 - 小規模な採集社会から始まり、現在に至るまで、世界的な影響からヨーロッパ、アメリカへと焦点を移している。 繰り返されるテーマ - 美学、感情、社会生活、文化、政治、経済、テクノロジーとの関連。 モジュール式フレームワーク - 60のゲートウェイ(各ゲートウェイにはリスニングの例が掲載)により、時系列または7つのテーマ別に柔軟に構成することができる。 一貫した構成 - 同じステップ・バイ・ステップのフォーマットで、生徒は繰り返し練習することにより、音楽の聴き方、音楽についての考え方を学ぶことができる。 楽譜のアンソロジー - 音楽史の授業でこのテキストを使用するコースのために。 Gateways to Understanding Musicは、引き続きウェブサイトを採用し、オーディオ例と講師用リソースをホストしています。 『民族音楽学をモデリングする』 民族音楽学は、地理的・歴史的に多様な音楽の研究を通して、人間がなぜ、そしてどのように音楽的なのかを理解するという、非常に広い使命を持った学問分野 である。しかし、民族音楽学の研究は、そのような目標や方法、理論を明確にすることに欠けていた。この分野で著名なティモシー・ライスは、この問題に定期 的に取り組んでいる数少ない学者の一人である。本書では、ライスがそのキャリアの中で培ってきたエッセイの中から、近年の民族音楽学を統合する暗黙の、し かしほとんど認識されていないパターンを見出すための集大成を提供する。エスノミュージコロジーのモデル化』は、ライスがエスノミュージコロジーのフィー ルドについて30年間考えてきたことをまとめたもので、ライスの最も重要な8つのエッセイの内容を、今日のエスノミュージコロジーを取り巻く環境との関連 において、当初の文脈から枠組みを変え、再構築している。ライスは、学生や研究者が民族音楽学を研究する際の指針となるよう、さまざまなモデルを提唱して いる。これらのモデルの中には、この分野の異分野をまとめるものもあれば、研究者が研究を計画し、実施する際に疑問を生み出す発見的モデルを提案するもの もある。これらのエッセイに新たに付された序論では、民族音楽学に関する著作の歴史を振り返り、民族音楽学者による民族音楽学の理論化のための革新的なモ デルを提案している。本書は、学部および大学院の民族音楽学の授業において、不朽の必須テキストとなるだろう。 目次 はじめに 第1章 民族音楽学の再構築に向けて 第2章 民族音楽学におけるフィールド・メソッドとフィールド経験の媒介に向けて 第3章 音楽と意味についての考察: ブルガリアの事例における隠喩、意味づけ、統制 第4章 音楽体験と民族誌における時間、場所、隠喩 第5章 民族音楽学における音楽とアイデンティティについての考察 第6章 民族音楽学理論 第7章 音楽民族誌における個人 第8章 困難の時代における民族音楽学 参考文献 索引 Ethnomusicology : a very short introduction / Timothy Rice, Oxford University Press , 2014 . - (Very short introductions, 376) 民族音楽学者は、音楽家と呼ばれる人たちだけでなく、すべての人間は音楽的であり、音楽性は人間経験の本質的な試金石のひとつであると信じている。この洞 察は、音楽の本質と人類の本質について大きな問いを投げかけるものであり、民族音楽学者は、これらの問いに適切に取り組むためには、地理的、歴史的に多様 な音楽を研究しなければならないと主張する。この「超短編入門」では、民族音楽学者の第一人者であるティモシー・ライスが、この成長著しい学問分野をコン パクトかつ明快に解説している。読者は、今日の民族音楽学者が、日本の雅楽、ブルガリアの民族音楽、ジャワのガムラン、ネイティブ・アメリカンの太鼓や歌 といった伝統的な音楽形態を研究するだけでなく、ラップやレゲエからテックス・メックス、セルビアのターボフォーク、さらにはモール・オブ・アメリカのパ イプイン・ミュージックまで、より現代的な音楽形態も探求していることを知る。ライス氏によれば、こうした多様な音楽形態を調査するために、民族音楽学者 は通常、そのコミュニティに住み、音楽イベントに参加し、観察し、録音し、ミュージシャンやその後援者、聴衆にインタビューし、歌い、演奏し、踊ることを 学ぶ。音楽家やコミュニティの人々と信頼関係を築き、何カ月も何年もかけて密接に協力することになる人々の許可を得ることが重要なのだ。特定の音楽的伝統 がどのように機能し、何が特徴的で、個人的、社会的、文化的な意味をどのように背負っているのかを理解するために、研究者がどのようにデータを分析するの かがわかる。ライス氏はまた、人間の行動や文化的実践としての音楽の本質にさらに光を当てるために、研究者が人類学やその他の社会科学の理論をどのように 適用するかについても論じている。シリーズについて オックスフォード大学のVery Short Introductionsシリーズは、イスラム教から社会学、政治学から古典学、文学理論から歴史学、考古学から聖書まで、幅広いテーマについて簡潔で 独創的な入門書を提供している。このシリーズの各巻は、単なる定義の教科書ではなく、与えられた学問分野や分野の中心的な問題について、辛辣で挑発的な、 しかし常にバランスの取れた完全な論考を提供している。また、Very Short Introductionの各巻は、そのテーマがどのように発展し、社会にどのような影響を及ぼしてきたかを示しながら、当該テーマの読み応えのある展開 を示している。最終的には、このシリーズはすべての主要な学問分野を網羅し、すべての学生にアクセスしやすく豊富な参考文献を提供する予定である。どの学 問分野が重要で魅力的であろうと、一般読者を魅了するトピックであろうと、Very Short Introductionsシリーズにはハンディで手頃なガイドがあり、おそらく不可欠なものとなるだろう。 図版リスト 第1章 民族音楽学の定義 第2章:歴史について 第3章 調査の実施 第4章 音楽の本質 第5章 音楽と文化 第6章 個々の音楽家 第7章:音楽史を書く 第8章 現代世界における民族音楽学 第9章 仕事における民族音楽学者 参考文献 参考文献 リスニングのすすめ |
| Ethnomusicology "Ethnomusicology is the study of music from the cultural and social aspects of the people who make it. It encompasses distinct theoretical and methodical approaches that emphasize cultural, social, material, cognitive, biological, and other dimensions or contexts of musical behavior, in addition to the sound component. Folklorists, who began preserving and studying folklore music in Europe and the US in the 19th century, are considered the precursors of the field prior to the Second World War. The term ethnomusicology is said to have been first coined by Jaap Kunst from the Greek words ἔθνος (ethnos, "nation") and μουσική (mousike, "music"), It is often defined as the anthropology or ethnography of music, or as musical anthropology.[Seeger, Anthony. 1983. Why Suyá Sing. London: Oxford University Press. Pp. xiii-xvii.] During its early development from comparative musicology in the 1950s, ethnomusicology was primarily oriented toward non-Western music, but for several decades it has included the study of all and any musics of the world (including Western art music and popular music) from anthropological, sociological and intercultural perspectives. Bruno Nettl once characterized ethnomusicology as a product of Western thinking, proclaiming that "ethnomusicology as western culture knows it is actually a western phenomenon";[Nettl, Bruno (1983). The Study of Ethnomusicology. Urbana, Ill.: University of Illinois Press. p. 25.] in 1992, Jeff Todd Titon described it as the study of "people making music".[Titon, Jeff Todd (1992). Worlds of Music (2nd ed.). New York: Schirmer. pp. xxi.]"- Ethnomusicology.  Frances Densmore at the Smithsonian Institution in 1916 where she was recording Blackfoot chief Mountain Chief for the Bureau of American Ethnology. In this picture, Mountain Chief is listening to a recording. |
8. 民族音楽学(概要) 民族音楽学は、音楽を作る人々の文化的・社会的側面から音楽を研究する 学問である。音の要素に加え、音楽的行動の文化的、社会的、物質的、認知的、生物学的、その他の次元や文脈を強調する明確な理論的、方法的アプローチを包 含している。音楽民族誌の中では、音楽演奏に参加する行為として知られるミュージッキングを直接個人的に研究することである。 19世紀に欧米で民俗音楽の保存と研究を始めたフォークロリストが、第二次世界大戦前のこの分野の先駆者とされている。民族音楽学という言葉は、ギリシャ 語のἔθνος(ethnos、「国民」)とμουσική(mousike、「音楽」)からヤープ・クンストによって作られたと言われており、しばしば 音楽の人類学または民族学、あるいは音楽人類学と定義されている[1]。 1950年代に比較音楽学から発展した当初は、民族音楽学は主に非西洋音楽を対象としていたが、数十年前から人類学、社会学、異文化間の視点から世界のあ らゆる音楽(西洋芸術音楽、ポピュラー音楽を含む)を研究対象とするようになった [1]。ブルーノ・ネトルはかつて民族音楽学を西洋的思考の産物として特徴づけ、「西洋文化が知っている民族音楽学は実は西洋の現象である」と宣言した [2]。1992年にジェフ・トッド・ティトンはそれを「音楽を作る人々」の研究であると表現した[3]。  フランシス・デンスモア(Frances Densmore)は1916年、スミソニアン協会でアメリカ民族学局のためにブラックフット族の首長マウンテン・チーフの記録を取っていた。この写真では、マウンテン・チーフが録音に耳を傾けている。 |
| Definition Stated broadly, ethnomusicology may be described as a holistic investigation of music in its cultural contexts.[4] Combining aspects of folklore, psychology, cultural anthropology, linguistics, comparative musicology, music theory, and history,[5] ethnomusicology has adopted perspectives from a multitude of disciplines.[6] This disciplinary variety has given rise to many definitions of the field, and attitudes and foci of ethnomusicologists have evolved since initial studies in the area of comparative musicology in the early 1900s. When the field first came into existence, it was largely limited to the study of non-Western music—in contrast to the study of Western art music, which had been the focus of conventional musicology. In fact, the field was referred to early in its existence as "comparative musicology," defining Western musical traditions as the standard to which all other musics were compared, though this term fell out of use in the 1950s as critics for the practices associated with it became more vocal about ethnomusicology's distinction from musicology.[7] Over time, the definition broadened to include study of all the musics of the world according to certain approaches.[8][9] While there is not a single, authoritative definition for ethnomusicology, a number of constants appear in the definitions employed by leading scholars in the field. It is agreed upon that ethnomusicologists look at music from beyond a purely sonic and historical perspective, and look instead at music within culture, music as culture, and music as a reflection of culture.[7][9] In addition, many ethnomusicological studies share common methodological approaches encapsulated in ethnographic fieldwork, often conducting primary fieldwork among those who make the music, learning languages and the music itself, and taking on the role of a participant observer in learning to perform in a musical tradition, a practice Mantle Hood termed "bi-musicality".[10] Musical fieldworkers often also collect recordings and contextual information about the music of interest.[7] Thus, ethnomusicological studies do not rely on printed or manuscript sources as the primary source of epistemic authority. Ethnomusicologists developed a qualitative practice-based research method; DIY/DIA enthonograpy which stands for do it yourself + do it again. |
9. 定義 民俗学、心理学、文化人類学、言語学、比較音楽学、音楽理論、歴史学などの側面を組み合わせ、多くの学問分野からの視点を取り入れている[6] 。この分野が誕生した当初は、従来の音楽学の中心であった西洋の芸術音楽の研究とは対照的に、非西洋音楽の研究に大きく限定されていた。実際、この分野は 設立当初は「比較音楽学」と呼ばれ、西洋音楽の伝統を他のすべての音楽と比較する基準として定義していたが、この言葉は1950年代に民族音楽学と音楽学 との区別について批判が強まり、使われなくなった[7]。 時とともに、定義は特定のアプローチによる世界のすべての音楽の研究を含むよう広げられた[8][9]。 民族音楽学に対する単一の権威ある定義は存在しないが、この分野の主要な学者によって採用されている定義には多くの不変的なものがある。さらに、多くの民 族音楽学的研究は、民族誌的フィールドワークに包含される共通の方法論的アプローチを共有しており、しばしば音楽を作る人々の間で主要なフィールドワーク を行い、言語と音楽自体を学び、音楽の伝統で演奏することを学ぶ参加観察者の役割を担っており、マントル フード氏はこれを「バイミュージカリティ」と呼んでいる[9]。 [このように、民族音楽学的研究は、認識的権威の主要な源として印刷物や写本に依存することはない。民族音楽学者は質的な実践に基づく研究方法として、 DIY/DIA enthonograpy(自分でやる+もう一度やる)を開発した。 |
| History While the traditional subject of musicology has been the history and literature of Western art music, ethnomusicology was developed as the study of all music as a human social and cultural phenomenon. Oskar Kolberg is regarded as one of the earliest European ethnomusicologists as he first began collecting Polish folk songs in 1839 (Nettl 2010, 33). Comparative musicology, the primary precursor to ethnomusicology, emerged in the late 19th century and early 20th century. The International Musical Society in Berlin in 1899 acted as one of the first centers for ethnomusicology.[11] Comparative musicology and early ethnomusicology tended to focus on non-Western music, but in more recent years, the field has expanded to embrace the study of Western music from an ethnographic standpoint. |
10. 歴史 音楽学の伝統的な対象が西洋の芸術音楽の歴史と文学であるのに対し、民族音楽学は人間の社会的・文化的現象としての音楽全般を研究するものとして発展して きた。1839年にポーランドの民謡を収集し始めたオスカー・コルベルグは、ヨーロッパで最も早い時期に誕生した民族音楽学者の一人とみなされている (Nettl 2010, 33)。民族音楽学の前身である比較音楽学は、19世紀後半から20世紀前半に登場した。比較音楽学や初期の民族音楽学は非西洋の音楽に焦点を当てる傾向 があったが、近年では民族誌的な立場から西洋音楽を研究する分野にも広がっている[11]。 |
| Theories and methods Ethnomusicologists often apply theories and methods from cultural anthropology, cultural studies and sociology as well as other disciplines in the social sciences and humanities.[12] Though some ethnomusicologists primarily conduct historical studies, the majority are involved in long-term participant observation. Therefore, ethnomusicological work can be characterized as featuring a substantial, intensive ethnographic component. Anthropological and Musicological Approaches Two approaches to ethnomusicological studies are common: the anthropological and the musicological. Ethnomusicologists using the anthropological approach generally study music to learn about people and culture. Those who practice the musicological approach study people and cultures to learn about music. Charles Seeger differentiated between the two approaches, describing the anthropology of music as studying the way that music is a "part of culture and social life", while musical anthropology "studies social life as a performance," examining the way "music is part of the very construction and interpretation of social and conceptual relationships and processes."[13] Charles Seeger and Mantle Hood were two ethnomusicologists that adopted the musicological approach. Hood started one of the first American university programs dedicated to ethnomusicology, often stressing that his students must learn how to play the music they studied. Further, prompted by a college student's personal letter, he recommended that potential students of ethnomusicology undertake substantial musical training in the field, a competency that he described as "bi-musicality."[10] This, he explained, is a measure intended to combat ethnocentrism and transcend problematic Western analytical conventions. Seeger also sought to transcend comparative practices by focusing on the music and how it impacted those in contact with it. Similar to Hood, Seeger valued the performance component of ethnomusicology. Ethnomusicologists following the anthropological approach include scholars such as Steven Feld and Alan Merriam. The anthropological ethnomusicologists stress the importance of field work and using participant observation. This can include a variety of distinct fieldwork practices, including personal exposure to a performance tradition or musical technique, participation in a native ensemble, or inclusion in a myriad of social customs. Similarly, Alan Merriam defined ethnomusicology as "music as culture," and stated four goals of ethnomusicology: to help protect and explain non-Western music, to save "folk" music before it disappears in the modern world, to study music as a means of communication to further world understanding, and to provide an avenue for wider exploration and reflection for those who are interested in primitive studies.[14] This approach emphasizes the cultural impact of music and how music can be used to further understand humanity. The two approaches to ethnomusicology bring unique perspectives to the field, providing knowledge both about the effects culture has on music, and about the impact music has on culture. |
11. 理論と方法 民族音楽学者は、文化人類学、文化研究、社会学、および社会科学や人文科学の他の分野の理論や方法を適用することが多い[12]。したがって、民族音楽学 の研究は、実質的かつ集中的な民族誌的要素を特徴とするものであるといえる[12]。 人類学的アプローチと音楽学的アプローチ 民族音楽学研究には、人類学的アプローチと音楽学的アプローチの2つが一般的である。人類学的アプローチを使う民族音楽学者は、一般に、人々や文化につい て学ぶために音楽を研究する。音楽学的アプローチを実践する人は、音楽を学ぶために人々や文化を研究する。チャールズ・シーガーは2つのアプローチを区別 し、音楽人類学は音楽が「文化や社会生活の一部」であることを研究すると説明し、音楽人類学は「社会生活をパフォーマンスとして研究し」、「音楽が社会 的・概念的関係やプロセスのまさに構築と解釈の一部」であることを検証している[13]。 チャールズ・シーガーとマントル・フッドは、音楽学的アプローチを採用した2人の民族音楽学者であった。フッドは、民族音楽学に特化したアメリカ初の大学 プログラムの1つを開始し、しばしば学生が研究した音楽の演奏方法を学ばなければならないことを強調した。さらに、ある大学生の私信に促されて、民族音楽 学を学ぶ学生に、その分野で実質的な音楽訓練を行うことを勧め、その能力を「バイ・ミュージック性」と表現した[10]。これは、民族中心主義と戦い、問 題のある西洋の分析的慣習を超えるための措置だと彼は説明している。シーガーはまた、音楽とそれがそれに接する人々にどのような影響を与えたかに注目する ことで、比較の慣習を超越しようとした。フッドと同様、シーガーも民族音楽学の演奏という要素を重視した。 人類学的アプローチをとる民族音楽学者には、Steven FeldやAlan Merriamといった学者がいる。人類学的な民族音楽学者は、フィールドワークの重要性を強調し、参加型観察を用いている。これは、演奏の伝統や音楽技 術に個人的に触れること、ネイティブ・アンサンブルへの参加、無数の社会的慣習への参加など、さまざまな異なるフィールドワークの実践を含むことができ る。同様に、アラン・メリアムは民族音楽学を「文化としての音楽」と定義し、民族音楽学の目標として、非西洋音楽の保護と説明を助けること、現代社会で消 滅する前に「民族」音楽を救うこと、世界理解を深めるためのコミュニケーション手段としての音楽を研究すること、原始学に関心を持つ人々に幅広い探究と考 察の道を提供すること、の4つを挙げている[14]。 このアプローチは、音楽の文化的影響と人類への理解を深めるための音楽利用を強調したものである。 民族音楽学の2つのアプローチは、文化が音楽に与える影響と、音楽が文化に与える影響の両方について知識を提供し、この分野にユニークな視点をもたらして いる。 |
| Analysis Problems of analysis The great diversity of musics found across the world has necessitated an interdisciplinary approach to ethnomusicological study. Analytical and research methods have changed over time, as ethnomusicology has continued solidifying its disciplinary identity, and as scholars have become increasingly aware of issues involved in cultural study (see Theoretical Issues and Debates). Among these issues are the treatment of Western music in relation to music from "other," non-Western cultures[15] and the cultural implications embedded in analytical methodologies.[16] Kofi Agawu (see 2000s) noted that scholarship on African music seems to emphasize difference further by continually developing new systems of analysis; he proposes the use of Western notation to instead highlight similarity and bring African music into mainstream Western music scholarship.[17] In seeking to analyze such a wide scope of musical genres, repertories, and styles, some scholars have favored an all-encompassing "objective" approach, while others argue for "native" or "subjective" methodologies tailored to the musical subject. Those in favor of "objective" analytical methods hold that certain perceptual or cognitive universals or laws exist in music, making it possible to construct an analytical framework or set of categories applicable across cultures. Proponents of "native" analysis argue that all analytical approaches inherently incorporate value judgments and that, to understand music it is crucial to construct an analysis within cultural context. This debate is well exemplified by a series of articles between Mieczyslaw Kolinski and Marcia Herndon in the mid-1970s; these authors differed strongly on the style, nature, implementation, and advantages of analytical and synthetic models including their own.[16][18][19][20] Herndon, backing "native categories" and inductive thinking, distinguishes between analysis and synthesis as two different methods for examining music. By her definition, analysis seeks to break down parts of a known whole according to a definite plan, whereas synthesis starts with small elements and combines them into one entity by tailoring the process to the musical material. Herndon also debated on the subjectivity and objectivity necessary for a proper analysis of a musical system.[16] Kolinski, among those scholars critiqued by Herndon's push for a synthetic approach, defended the benefits of analysis, arguing in response for the acknowledgment of musical facts and laws.[20] Analytical methodologies As a result of the above debate and ongoing ones like it, ethnomusicology has yet to establish any standard method or methods of analysis. This is not to say that scholars have not attempted to establish universal or "objective" analytical systems. Bruno Nettl acknowledges the lack of a singular comparative model for ethnomusicological study, but describes methods by Mieczyslaw Kolinski, Béla Bartók, and Erich von Hornbostel as notable attempts to provide such a model.[21] Perhaps the first of these objective systems was the development of the cent as a definitive unit of pitch by phonetician and mathematician Alexander J. Ellis (1885). Ellis made notable contributions to the foundations of comparative musicology and ultimately ethnomusicology with the creation of the cents system; in fact, the ethnomusicologist Hornbostel “declared Ellis the ‘true founder of comparative scientific musicology.’”[22] Prior to this invention, pitches were described by using measurements of frequency, or vibrations per second. However, this method was not reliable, “since the same interval has a different reading each time it occurs across the whole pitch spectrum.”[23] On the other hand, the cents system allowed any interval to have a fixed numerical representation, regardless of its specific pitch level.[24] Ellis used his system, which divided the octave into 1200 cents (100 cents in each Western semitone), as a means of analyzing and comparing scale systems of different musics. He had recognized that global pitch and scale systems were not naturally occurring in the world, but rather “artifices” created by humans and their “organized preferences,” and they differed in various locations.[25] In his article in the Journal of the Society of Arts and Sciences, he mentions different countries such as India, Japan, and China, and notes how the pitch systems varied “not only [in] the absolute pitch of each note, but also necessarily the intervals between them.”[26] From his experiences with interviewing native musicians and observing the variations in scales across the locations, he concludes that “there is no practical way of arriving at the real pitch of a musical scale, when it cannot be heard as played by a native musician” and even then, “we only obtain that particular musician’s tuning of the scale.”[27] Ellis's study is also an early example of comparative musicological fieldwork (see Fieldwork). Alan Lomax's method of cantometrics employed analysis of songs to model human behavior in different cultures. He posited that there is some correlation between musical traits or approaches and the traits of the music's native culture.[28] Cantometrics involved qualitative scoring based on several characteristics of a song, comparatively seeking commonalities between cultures and geographic regions. Mieczyslaw Kolinski measured the exact distance between the initial and final tones in melodic patterns. Kolinski refuted the early scholarly opposition of European and non-European musics, choosing instead to focus on much-neglected similarities between them, what he saw as markers of "basic similarities in the psycho-physical constitution of mankind."[15] Kolinski also employed his method to test, and disprove, Erich von Hornbostel's hypothesis that European music generally had ascending melodic lines, while non-European music featured descending melodic lines. Adopting a more anthropological analytical approach, Steven Feld conducted descriptive ethnographic studies regarding "sound as a cultural system."[29] Specifically, his studies of Kaluli people of Papua New Guinea use sociomusical methods to draw conclusions about its culture. |
12. 分析 解析の問題点 世界には多様な音楽が存在するため、民族音楽学は学際的に研究される必要がある。民族音楽学が学問的なアイデンティティを確立し、文化研究に関わる問題意 識が高まるにつれ、分析・研究の方法も変化してきた(「理論的課題と論争」参照)。これらの問題の中には、「他の」非西洋文化からの音楽との関係における 西洋音楽の扱い[15]や分析的方法論に埋め込まれた文化的意味合いがある[16]。Kofi Agawu(2000年代参照)は、アフリカ音楽に関する研究は継続的に新しい分析システムを開発することによってさらに違いを強調していると思われると 指摘し、代わりに類似性を強調しアフリカ音楽を西洋音楽の主流の研究対象とするために西洋音楽の表記法を使うことを提案する[17]。 このように幅広い音楽のジャンル、レパートリー、スタイルを分析しようとする場合、包括的な「客観的」アプローチを支持する学者もいれば、音楽の主題に合 わせた「固有」または「主観的」な方法論を主張する学者もいる。客観的」な分析方法を支持する人々は、音楽にはある種の知覚的、認知的な普遍性や法則性が 存在し、文化圏を超えて適用できる分析枠組みやカテゴリーを構築することが可能であると考える。一方、「ネイティブ」な分析手法の支持者は、すべての分析 手法は本質的に価値判断を含んでおり、音楽を理解するためには、文化的な文脈の中で分析を構築することが重要であると主張する。この議論は1970年代半 ばのMieczyslaw KolinskiとMarcia Herndonの一連の論文によく示されており、これらの著者は彼ら自身を含む分析モデルと合成モデルのスタイル、性質、実装、利点について強く異なって いた[16][18][19][20] Herndonは「固有カテゴリー」と帰納的思考に基づき、音楽を調べるための2つの異なる方法として分析と合成を区別している。彼女の定義によれば、分 析が明確な計画に従って既知の全体の一部を分解しようとするのに対し、合成は小さな要素から始まり、そのプロセスを音楽の素材に合わせることによって1つ の実体に結合させるものである。また、ハーンドンは音楽システムの適切な分析に必要な主観性と客観性について議論した[16]。コリンスキーはハーンドン の合成的アプローチの推進に批判された学者の中で、音楽の事実と法則を認めることを主張し、分析の利点を擁護している[20]。 13. 分析の方法論 以上のような議論の結果、民族音楽学はいまだ標準的な分析方法を確立していない。しかし、普遍的な、あるいは「客観的」な分析システムを確立しようという 試みがなされていないわけではない。ブルーノ・ネトルは民族音楽学的研究のための唯一の比較モデルがないことを認めているが、ミエチスワフ・コリンスキ、 ベーラ・バルトーク、エーリヒ・フォン・ホルンボステルによる方法をそのようなモデルを提供しようとする注目すべき試みとして記述している[21]。 これらの客観的システムの最初のものは、おそらく音声学者であり数学者であるアレクサンダー・J・エリスによる音程の決定的な単位としてのセントの開発 (1885年)であっただろう。実際、民族音楽学者のホーンボステルは「エリスを『比較科学的音楽学の真の創始者』と宣言している」[22]。この発明以 前は、音程は周波数、または1秒あたりの振動の測定値を用いて記述されていた。エリスは、オクターブを1200セント(半音ごとに100セント)に分割す るこのシステムを、異なる音楽の音階システムを分析・比較する手段として使った。彼は、世界の音律や音階は自然界に存在するものではなく、人間とその「組 織化された好み」によって作られた「人工物」であり、それらは各地で異なることを認識していた[25]が、インド、日本、中国といった異なる国々について 言及し、「それぞれの音の絶対音高だけでなく、それらの間の間隔も必ず異なる」と述べている[26]。 「また、エリスの研究は、比較音楽学のフィールドワークの初期の例でもある(「フィールドワーク」参照)。 アラン・ローマックスのカントメトリックスという手法は、異なる文化圏における人間の行動をモデル化するために楽曲を分析するものでした。彼は、音楽の特 徴やアプローチと音楽の母国文化の特徴の間に何らかの相関関係があると仮定した[28]。カントメトリックスは、曲のいくつかの特徴に基づいて定性的な採 点を行い、文化や地域間の共通性を比較的に探った。 ミエチスワフ・コリンスキーは、メロディパターンの初音と終音の間の正確な距離を測定した。また、エーリッヒ・フォン・ホルンボステルの「ヨーロッパの音 楽は一般的に上行の旋律線を持ち、非ヨーロッパの音楽は下降の旋律線を持つ」という仮説を検証し、反証するためにこの方法を使用した[15]。 より人類学的な分析アプローチを採用したスティーブン・フェルドは「文化システムとしての音」に関する記述的な民族学的研究を行った[29]。特にパプア ニューギニアのカルリ族に関する研究では、社会音楽的手法を用いてその文化に関する結論を導き出している。 |
| Fieldwork Bruno Nettl, Emeritus Professor of Musicology at Illinois University,[30] defines fieldwork as "direct inspection [of music, culture, etc] at the source", and states that "It is in the importance of fieldwork that anthropology and ethnomusicology are closest: It is a 'hallmark' of both fields, something like a union card". However, he mentions that ethnomusicological fieldwork differs from anthropological fieldwork because the former requires more “practical” information about “recording, filming, video-taping, [and] special problems of text-gathering.”[31] The experience of an ethnomusicologist in the field is his/her data; experience, texts (e.g. tales, myths, proverbs), structures (e.g. social organization), and "imponderabilia of everyday life" all contribute to an ethnomusicologist's study.[32] He also notes how ethnomusicological fieldwork “principally involves interaction with other humans” and is primarily about “day-to-day personal relationships,” and this shows the more “personal” side of the discipline.[33] The importance of fieldwork in the field of ethnomusicology has required the development of effective methods to pursue fieldwork. History of Fieldwork In the 19th century until the mid-20th century, European scholars (folklorists, ethnographers, and some early ethnomusicologists) who were motivated to preserve disappearing music cultures (from both in and outside of Europe), collected transcriptions or audio recordings on wax cylinders.[34] Many such recordings were then stored at the Berliner Phonogramm-Archiv at the Berlin school of comparative musicology, which was founded by Carl Stumpf, his student Erich M. von Hornbostel, and medical doctor Otto Abraham. Stumpf and Hornbostel studied and preserved these recordings in the Berlin Archiv, setting the foundation for contemporary ethnomusicology. But, the "armchair analysis" methods of Stumpf and Horbostel required very little participation in fieldwork themselves, instead using the fieldwork of other scholars. This differentiates Stumpf and Hornbostel from their present-day contemporaries, who now use their fieldwork experience as a main component in their research.[35] Ethnomusicology's transition from "armchair analysis" to fieldwork reflected ethnomusicologists trying to distance themselves from the field of comparative musicology in the period following World War II.[citation needed] Fieldwork emphasized face-to-face interaction to gather the most accurate impression and meaning of music from the creators of the music, in contrast with "armchair analysis" that disconnected the ethnomusicologist from the individual or group of performers.[35] Stumpf and Hornbostel were not the only scholars to use "armchair" analysis. Other scholars analyzed recordings and transcriptions that they did not make. For instance, in his work Hungarian Folk Music, Béla Bartók analyzes various traits of Hungarian folk songs. While drawing from recordings made by himself, Bartók also relies on transcriptions by other musicians; among them are Vikar Béla [Béla Vikar; Vikar Béla], Zoltán Kodály, and Lászo Lajtha. These transcriptions came in recorded and printed format, and form the majority of Bartók's source material.[36] In 1935, the journal American Anthropologist published an article titled "Plains Ghost Dance and Great Basin Music," authored by George Herzog. Herzog was an assistant to Hornbostel and Stumpf. Herzog draws from material "available to [him]" and "in the literature," including transcriptions by James Mooney for the Bureau of American Ethnology; Natalie Curtis, and Alice C. Fletcher. Herzog analyzes structure and melodic contour of Ghost Dance songs. He notes that Ghost Dance music's "paired patterns" occur in many Native American tribes' music, and they may have migrated from tribe to tribe.[37] Writing later in the 1950s, Jaap Kunst wrote about fieldwork for the purpose of recording and transcribing sound. Kunst lists various "phonogram-archives," collections of recorded sound. They include the archives founded by Stumpf.[38] Among other developments, the 1950s and 1960s saw the expansion of fieldwork, as opposed to "armchair" analysis. In 1950, David McAllester conducted a study of Navajo music, particularly the music of the Enemy Way ceremony. The work was published as Enemy Way Music: A Study of Social and Esthetic Values As Seen in Navaho Music. In it, McAllester details the procedures of the Enemy Way ceremony, as well as the music itself.[39] Aside from Enemy Way music, McAllester sought Navajo cultural values based on analysis of attitudes toward music. To his interviewees, McAllester gave a questionnaire, which includes these items: - Some people beat a drum when they sing; what other things are used like that? - What did people say when you learned how to sing? - Are there different ways of making the voice sound when we sing? - Are there songs that sound especially pretty? - What kind of melody do you like better: (illustrate with a chant-like melody and a more varied one). - Are there songs for men only? [for women only? for children only?][40] The ethnomusicologist Alan Merriam reviewed McAllester's work, calling it "strange to speak of a work published in 1954 as 'pioneering,' but this is precisely the case."[41] He described McAllester's work as "[relating] music to culture and culture to music in terms of the value system of the Navaho [sic]." As of 1956, the time that Merriam published his review, the idea of such work "occurred to ethnomusicologists with surprising infrequency."[41] In his work The Anthropology of Music, published in 1964, Merriam wrote that "ethnomusicology has suffered from the amateur field collector whose knowledge of its aims has been severely restricted. Such collectors operate under the assumption that the important point is simply to gather music sound, and that this sound–often taken without discrimination and without thought, for example, to problems of sampling–can then simply be turned over to the laboratory worker to do something about it."[42] In the same work, Merriam states that "what the ethnomusicologist does in the field is determined by his own formulation of method, taken in its broadest sense." Fieldwork can have multiple areas of inquiry, and Merriam lists six of these: 1. Musical material culture: classification of instruments, cultural perception of musical instruments. 2. Song texts. 3. Categories of music: "envisaged by [...] the people themselves as various separable types of songs." 4. The musician: "the training of musicians and the means of becoming a musician"; perceptions of musicians." 5. The uses and functions of music in relation to other aspects of culture. 6. Music as a creative cultural activity: "what are the sources from which music is drawn?"[43] Bruno Nettl describes early 20th-century fieldwork as extraction of music, which is analyzed elsewhere. Between 1920 and 1960, however, fieldworkers wished to map entire musical systems, and resided longer in the field. After the 1950s, some not only observed, but also participated in musical cultures.[44] Mantle Hood wrote about this practice as well. Hood had learned from musicians in Indonesia about the intervals of sléndro scales, as well as how to play the rebab. He was interested in the characteristics of Indonesian music, as well as "social and economic valuations" of music.[45] By the 1980s, participant-observer methodology became the norm, at least in the North American tradition of ethnomusicology.[44] Aside from this history of fieldwork, Nettl writes about informants: the people whom fieldworkers research and interview. Informants do not contain the entirety of a musical culture, and need not represent the ideal of the culture. According to Nettl, there is a bell-shaped curve of musical ability. In a community, the majority are "simply good" at their music. They are of greatest interest. However, it is also worth seeing who a community recommends as informants. People may direct a fieldworker to the best musicians, or they may suggest many "simply good" musicians. This attitude is reflective of the culture's values. As technology advanced, researchers graduated from depending on wax cylinders and the phonograph to digital recordings and video cameras, allowing recordings to become more accurate representations of music studied. These technological advances have helped ethnomusicologists be more mobile in the field, but have also let some ethnomusicologists shift back to the "armchair analysis" of Stumpf and Hornbostel.[34] Since video recordings are now considered cultural texts, ethnomusicologists can conduct fieldwork by recording music performances and creating documentaries of the people behind the music, which can be accurately studied outside of the field.[46] Additionally, the invention of the internet and forms of online communication could allow ethnomusicologists to develop new methods of fieldwork within a virtual community. Heightened awareness of the need to approach fieldwork in an ethical manner arose in the 1970s in response to a similar movement within the field of anthropology.[47] Mark Slobin writes in detail about the application of ethics to fieldwork.[48] Several potential ethical problems that arise during fieldwork relate to the rights of the music performers. To respect the rights of performers, fieldwork often includes attaining complete permission from the group or individual who is performing the music, as well as being sensitive to the rights and obligations related to the music in the context of the host society. Another ethical dilemma of ethnomusicological fieldwork is the inherent ethnocentrism (more commonly, eurocentrism) of ethnomusicology. Anthony Seeger has done seminal work on the notion of ethics within fieldwork, emphasizing the need to avoid ethnocentric remarks during or after the field work process. Emblematic of his ethical theories is a 1983 piece that describes the fundamental complexities of fieldwork through his relationship with the Suyá Indians of Brazil.[1] To avoid ethnocentrism in his research, Seeger does not explore how singing has come to exist within Suyá culture, instead explaining how singing creates culture presently, and how aspects of Suyá social life can be seen through both a musical and performative lens. Seeger's analysis exemplifies the inherent complexity of ethical practices in ethnomusicological fieldwork, implicating the importance for the continual development of effective fieldwork in the study of ethnomusicology. |
14. フィールドワーク イリノイ大学音楽学名誉教授ブルーノ・ネトル[30]は、フィールドワークを「(音楽・文化などを)源流で直接視察すること」と定義し、「人類学と民族音 楽学が最も近いところにあるのは、フィールドワークの重要性である」と述べている。それは両分野の "特徴 "であり、組合員証のようなものだ」と述べている。しかし、民族音楽学のフィールドワークが人類学のフィールドワークと異なるのは、前者が「録音、撮影、 ビデオ撮影、[そして]テキスト収集の特別な問題」についてのより「実践的」な情報を必要とするからだと述べている[31]。また、民族音楽学のフィール ドワークは「主として他の人間との相互作用を伴う」ものであり、「日々の個人的な関係」が主であるとし、このことは学問のより「個人的」な側面を示してい る[33]。民族音楽学分野におけるフィールドワークの重要性は、フィールドワークを進めるための有効な方法の開発を必要としてきた。 15. フィールドワークの歴史 19世紀から20世紀半ばまで、消滅しつつある音楽文化(ヨーロッパ内外の)を保存しようとするヨーロッパの学者(民俗学者、民族学者、初期の民族音楽学 者の一部)が、蝋製のシリンダーに録音した写しや音声を収集していた[34]。その多くの録音は、比較音楽学のベルリン校にあるベルリン・フォノグラム・ アルキヴに保管されていたが、この学校はカール・シュトゥンプとその学生エーリヒ・モン・フォン・ホーンボステルと医学者オットー・アブラハムが創設した ものだった。シュトゥンプとホーンボステルは、これらの録音を研究し、ベルリン古文書館に保存し、現代の民族音楽学の基礎を築いたのである。しかし、シュ トゥンプフやホルンボステルの「アームチェアー・アナリシス」の方法は、自らフィールドワークに参加することはほとんどなく、他の研究者のフィールドワー クを使うというものであった。このことは、シュトゥンプフやホーンボステルが、現在、フィールドワークの経験を研究の主要な要素として使われている同時代 の研究者たちとは異なる点である[35]。 民族音楽学が「アームチェア分析」からフィールドワークへと移行したのは、第二次世界大戦後の時期に民族音楽学者が比較音楽学の分野から距離を置こうとし たことを反映している[citation needed] フィールドワークは、民族音楽学者を個人または演奏者のグループから切り離す「アームチェア分析」とは対照的に、音楽の創造者から最も正しい印象や意味を 収集するために対面での交流を強調した[35]。 シュトゥンプフとホーンボステルだけが「アームチェア」分析を使われた学者ではなかった。他の学者も、自分たちが行っていない録音やトランスクリプション を分析していた。例えば、ベーラ・バルトークはその著作『ハンガリーの民俗音楽』の中で、ハンガリー民謡の様々な特徴を分析している。バルトークは、自ら の録音をもとにしながらも、ヴィカル・ベーラ(Béla Vikar; Vikar Béla)、ゾルタン・コダーイ(Zoltán Kodály)、ラースゾ・ライタ(Lászo Lajtha)といった他の音楽家のトランスクリプションに依拠した。これらの転写は録音と印刷の形式で提供され、バルトークの資料の大部分を形成してい る[36]。 1935年、雑誌『American Anthropologist』にジョージ・ヘルツォークが執筆した「Plains Ghost Dance and Great Basin Music」と題された論文が掲載される。ヘルツォークはホーンボステルとシュトゥンプの助手であった。Herzogは、James Mooney (Bureau of American Ethnology)、Natalie Curtis、Alice C. Fletcherによる書き起こしなど、「入手できた」資料と「文献にある」資料をもとに執筆しています。ヘルツォークはゴースト・ダンス・ソングの構造 とメロディーの輪郭を分析している。彼はゴースト・ダンス音楽の「対になるパターン」が多くのアメリカ先住民の部族の音楽に存在し、それらは部族から部族 へと移行していった可能性があると述べている[37]。 1950年代後半に書かれたヤープ・クンストは音の録音と転写を目的としたフィールドワークについて書いている。クンストは録音された音のコレクションで ある様々な「フォノグラム・アーカイヴ」をリストアップしている。その中には、シュトゥンプフによって設立されたアーカイブも含まれている[38]。 他の発展として、1950年代と1960年代には、「アームチェア」分析とは対照的に、フィールドワークの拡大が見られた。1950年、David McAllesterはナバホの音楽、特にエネミーウェイの儀式の音楽についての研究を実施した。この研究は、『エネミー・ウェイ・ミュージック』として 出版された。A Study of Social and Esthetic Values As Seen in Navaho Music "として出版された。その中でマカレスターは、音楽そのものだけでなく、エネミーウェイの儀式の手順も詳述している[39]。 エネミー・ウェイの音楽もさることながら、音楽に対する意識の分析からナバホの文化的価値を探った。インタビューに答えてくれた人たちに、マカレスターは こんな質問表を渡した。 - 歌うときに太鼓をたたく人がいるが、他にどんなものが使われているか? - 歌い方を習ったとき、人はどう言ったか? - 歌うときの声の出し方はいろいろあるのでしょうか? - 特にきれいに聞こえる歌はあるかな? - どんなメロディーが好きか:(聖歌のようなメロディーと、もっと変化に富んだメロディーを使って説明しよう)。 - 男性だけの歌はありますか?[女性専用?子供専用?][40]。 民族音楽学者のアラン・メリアムはマカレスターの作品を評して、「1954年に発表された作品を『先駆的』と言うのは奇妙だが、まさにそうである」と述べ ている[41]。 彼はマカレスターの作品を「ナバホ族の価値体系の観点から、音楽を文化と、文化を音楽と関連づける」ものであると説明している[41]。メリアムがレ ビューを発表した1956年の時点では、そのような仕事のアイデアは「民族音楽学者に驚くほどまれにしか起こらなかった」[41]。 1964年に出版された彼の著作『音楽の人類学』において、メリアムは「民族音楽学は、その目的についての知識が著しく制限されたアマチュアのフィール ド・コレクターに苦しめられてきた」と書いている。このような収集家は、重要なポイントは単に音楽の音を集めることであり、この音はしばしば差別なく、例 えばサンプリングの問題を考えずに採取され、そしてそれについて何かをするために研究所の労働者に単に引き渡せばよいという仮定の下で活動している」 [42]。 同じ著作の中でメリアムは「民族音楽学者がフィールドで何をするかは、最も広い意味でとらえた彼自身の方法論の定式化によって決まる」と述べている。 フィールドワークは複数の調査領域を持ちうるが、メリアムはそのうちの6つを挙げている。 1. 1.音楽的物質文化:楽器の分類、楽器に対する文化的認識。 2. 歌のテキスト 3. 音楽のカテゴリー:「民衆自身によって、分離可能な様々なタイプの歌として想定されたもの」。 4. 音楽家。音楽家の養成と音楽家になるための手段」「音楽家に対する認識」。 5. 文化の他の側面との関係で、音楽の使われ方と機能。 6. 創造的な文化活動としての音楽 "音楽が引き出される源は何か"[43]。 ブルーノ・ネトルは、20世紀初頭のフィールドワークを音楽の抽出と表現しているが、これについては別のところで分析している。しかし、1920年から 1960年にかけて、フィールドワーカーは音楽システム全体の地図を作成することを望み、より長くフィールドに滞在するようになる。1950年代以降は、 観察するだけでなく、音楽文化に参加する者も現れた[44]。 マントル・フッドもこの実践について書いている。フッドはインドネシアの音楽家から、スレンドロ音階の音程やレバブの弾き方について学んでいた。彼はイン ドネシアの音楽の特徴や音楽の「社会的・経済的な評価」に関心を持っていた[45]。 1980年代までに、少なくとも北米の民族音楽学の伝統においては、参加観察者の方法論が標準となった[44]。 このようなフィールドワークの歴史は別として、ネットルはインフォーマント、つまりフィールドワーカーが調査し、インタビューする人々について書いてい る。インフォーマントには音楽文化の全体像が含まれているわけではないし、その文化の理想像を表す必要もない。ネトルによれば、音楽的能力にはベル型の カーブがある。あるコミュニティでは、大多数は自分の音楽が「単にうまい」だけである。彼らは最大の関心事である。しかし、コミュニティが誰をインフォー マントとして推薦しているかを見ることも価値がある。人々はフィールドワーカーに最高の音楽家を指示するかもしれないし、多くの「単にうまい」音楽家を提 案するかもしれない。このような態度は、その文化の価値観を反映している。 技術の進歩に伴い、研究者はワックスシリンダーや蓄音機からデジタル録音やビデオカメラに頼るようになり、録音は研究対象の音楽をより正確に表現すること ができるようになった。こうした技術の進歩は、民族音楽学者の現場での機動力を高める一方で、一部の民族音楽学者をStumpfとHornbostelの 「アームチェア分析」へと回帰させることになった[34]。 [また、インターネットやオンラインコミュニケーションの発明により、民族音楽学者は、仮想コミュニティ内で新たなフィールドワークの方法を開発すること ができる。 倫理的な方法でフィールドワークに取り組む必要性への高い意識は、人類学の分野での同様の動きに呼応して1970年代に生まれました。マーク・スロビン は、フィールドワークへの倫理の適用について詳しく書いています。演奏者の権利を尊重するために、フィールドワークでは、音楽を演奏するグループや個人か ら完全に許可を得ることと、ホスト社会の文脈で音楽に関連する権利と義務に敏感であることがしばしば含まれる。 民族音楽学のフィールドワークにおけるもうひとつの倫理的ジレンマは、民族音楽学に内在するエスノセントリズム(より一般的にはヨーロッパ中心主義)であ る。アンソニー・シーガーは、フィールドワークにおける倫理の概念について画期的な研究を行い、フィールドワークの過程あるいはその後に、民族中心主義的 な発言を避ける必要性を強調した。彼の倫理観を象徴するのが、ブラジルの先住民であるスヤ族との関係を通じてフィールドワークの基本的な複雑さを説明した 1983年の作品である[1]。 研究における民族中心主義を避けるために、シーガーはスヤ族の文化において歌がどのように存在するようになったかを探らず、歌が現在の文化をいかに創造 し、音楽と演奏の両方のレンズを通じてスヤ族の社会生活の側面をいかに見ることができるかを説明している。シーガーの分析は、民族音楽学のフィールドワー クにおける倫理的実践の複雑さを例証しており、民族音楽学の研究において効果的なフィールドワークを継続的に発展させることの重要性を暗示している。 |
| Systematized Fieldwork In his 2005 paper "Come Back and See Me Next Tuesday," Nettl asks whether ethnomusicologists can, or even should practice a unified field methodology as opposed to each scholar developing their own individual approach.[32] Nettl considers several factors when sampling music from different cultures. The first thing is that in order to discover the best representation of any culture, it is important to be able to “discern between ordinary experience and ideal,” all while considering the fact that “the ‘ideal’ musician may also know and do things completely outside the ken of the rest.”[49] Another factor is the process of selecting teachers, which depends on what the fieldworker wishes to accomplish. Regardless of whatever method a fieldworker decides to use to conduct research, fieldworkers are expected to “show respect for their material and for the people with whom they work.”[50] As Nettl explains, ethnomusicology is a field heavily relies on both the collection of data and the development of strong personal relationships, which often cannot be quantified by statistical data. He summarizes Bronisław Malinowski's classification of anthropological data (or, as Nettl applies it, ethnomusicological data) by outlining it as three types of information: 1) texts, 2) structures, and 3) the non-ponderable aspects of everyday life. The third type of information, Nettl claims is the most important because it captures the ambiguity of experience that cannot be captured well through writing.[32] He cites another attempt made by Morris Friedrich, an anthropologist, to classify field data into fourteen different categories in order to demonstrate the complexity that information gathered through fieldwork contains. There are a myriad of factors, many of which exist beyond the researcher's comprehension, that prevent a precise and accurate representation of what one has experienced in the field. As Nettl notices, there is a current trend in ethnomusicology to no longer even attempt to capture a whole system or culture, but to focus on a very specific niche and try to explain it thoroughly. Nettl's question, however, still remains: should there be a uniform method for going about this type of fieldwork? Alan Merriam addresses issues that he found with ethnomusicological fieldwork in the third chapter of his 1964 book, The Anthropology of Music. One of his most pressing concerns is that, as of 1964 when he was writing, there had been insufficient discussion among ethnomusicologists about how to conduct proper fieldwork. That aside, Merriam proceeds to characterize the nature of ethnomusicological fieldwork as being primarily concerned with the collection of facts. He describes ethnomusicology as both a field and a laboratory discipline. In these accounts of the nature of ethnomusicology, it seems to be closely related to a science. Because of that, one might argue that a standardized, agreed-upon field method would be beneficial to ethnomusicologists. Despite that apparent viewpoint, Merriam conclusively claims that there should be a combination of a standardized, scientific approach and a more free-form analytical approach because the most fruitful work he has done has come from combining those two rather than separating them, as was the trend among his contemporaries.[5] Even Merriam's once progressive notion of a balanced approach came into question as time passed. Specifically, the idea that ethnomusicology is or can be at all factual. In a 1994 book, May it Fill Your Soul: Experiencing Bulgarian Music, Timothy Rice uses enlightenment philosophy to substantiate his opinion that fieldwork cannot be used as fact. The philosophy he works with involves theorizing over the distinction between objectivity and subjectivity. In order to ground those debates in ethnomusicology, he equates musicology to objectivity and musical experience to subjectivity.[51] Rice uses the philosophical attitudes that Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, and Paul Ricoeur take towards objectivity and subjectivity to state that human perception of the world is inherently subjective because the only way in which humans can interpret what goes on around them is through symbols. Human preconceptions of those symbols will always influence the ways in which an individual might process the world around them. Applying that theory to music and ethnomusicology, Rice brings back the terms of musicology and musical experience. Because one's experience of music is simply an interpretation of preconceived symbols, one cannot claim musical experience as factual. Thus, systematizing fieldwork like one would a scientific field is a futile endeavor. Instead, Rice asserts that any attempt to engage with someone else's musical experience, which cannot be truly understood by anyone except that person, must be confined to individual analysis.[51] Characterizing the musical experience of a whole culture, according to Rice's logic, is not possible. Another argument against the objectivity and standardization of fieldwork comes from Gregory Barz and Tim Cooley in the second chapter of their book, Shadows in the Field: New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology. In this chapter, entitled "Confronting the Field(Note): In and Out of the Field," they claim that a researcher's field work will always be personal because a field researcher in ethnomusicology, unlike a field researcher in a hard science, is inherently a participant in the group they are researching just by being there. To illustrate the disparity between those subjective, participatory experiences that ethnomusicological fieldworkers have and what typically gets published as ethnomusicological literature, Barz and Cooley point out the difference between field research and field notes. While field research attempts to find the reality, field notes document a reality. The issue, according to Barz and Cooley, is that field notes, which capture the personal experience of the researcher, are often omitted from whatever final writing that researcher publishes.[52] |
16. 体系化されたフィールド
ワーク 2005年の論文「Come Back and See Me Next Tuesday」の中で、ネットルは民族音楽学者が、それぞれの学者が独自のアプローチを開発するのとは対照的に、統一されたフィールドの方法論を実践で きるのか、あるいは実践すべきなのかを問うている[32]。まず、どのような文化であっても、その最良の表現を発見するためには、「普通の経験と理想を見 分ける」ことができることが重要であり、同時に「『理想』の音楽家は、他の人々の常識から完全に外れたことも知っていて行うかもしれない」[49] という事実を考慮しなければならない。もう一つの要因は、フィールドワーカーが何を達成したいかによって、教師を選択するプロセスも異なるということであ る。ネットルが説明するように、民族音楽学はデータの収集と強い個人的関係の構築の両方に大きく依存する分野であり、それはしばしば統計的データでは定量 化できないものである。彼は、ブロニスワフ・マリノフスキーによる人類学的データの分類を、3つのタイプの情報としてまとめ、民族音楽学的データに応用し ている。1)テキスト、2)構造、3)日常生活の非考察的側面。また、人類学者のモリス・フリードリッヒがフィールドデータを14種類に分類し、フィール ドワークで得られた情報がいかに複雑なものであるかを示す試みも紹介されている[32]。そこには無数の要因があり、その多くは研究者の理解を超えて存在 し、フィールドで経験したことの正確な表現を妨げているのである。ネットルが指摘するように、民族音楽学では、もはやシステムや文化の全体を捉えようとは せず、極めて特殊なニッチに焦点を当て、それを徹底的に説明しようとする傾向がある。しかし、このようなフィールドワークを行うための統一された方法はあ るのだろうか、というのがネトルの疑問である。 アラン・メリアムは1964年に出版した著書『音楽の人類学』の第3章で、民族音楽学のフィールドワークで見つけた問題点を取り上げている。彼の最も切実 な懸念のひとつは、執筆中の1964年時点で、適切なフィールドワークの実施方法について民族音楽学者の間で十分な議論が行われていなかったことである。 それはさておき、メリアムは民族音楽学のフィールドワークの性格を、事実の収集に主眼を置いたものであるとして、その説明を進めている。彼は民族音楽学を フィールドとラボの両方の学問分野として記述している。このように民族音楽学は科学と密接な関係にあるように思われる。そのため、標準化され、合意された フィールド・メソッドは、民族音楽学者にとって有益であると主張する人もいるかもしれない。そのような見かけ上の視点にもかかわらず、メリアムは、標準化 された科学的アプローチとより自由な分析的アプローチとの組み合わせがあるべきであると結論付けている。 かつては進歩的であったメリアムのバランスの取れたアプローチという概念も、時が経つにつれて疑問視されるようになる。具体的には、民族音楽学が事実に即 している、あるいは事実であり得るという考えである。ティモシー・ライスは1994年の著書『May it Fill Your Soul: Experiencing Bulgarian Music』で、フィールドワークは事実として使われることはないという意見を実証するために、啓蒙主義的な哲学を使っている。彼が扱う哲学は、客観性と 主観性の区別をめぐる理論的なものである。ライスはマルティン・ハイデガー、ハンス・ゲオルク・ガダマー、ポール・リクールが客観性と主観性に対してとっ ている哲学的態度を用いて、人間が自分の周りで起こっていることを解釈できる唯一の方法が象徴を通してであるため、世界の人間の認識は本質的に主観的であ ると述べている[51]。その象徴に対する人間の先入観は、個人が自分の周りの世界をどのように処理するかに常に影響を与える。この理論を音楽と民族音楽 学に当てはめると、ライスは音楽学と音楽体験という言葉を持ち帰る。音楽体験は先入観に基づく記号の解釈に過ぎないから、音楽体験を事実として主張するこ とはできない。したがって、フィールドワークを科学分野のように体系化することは、無駄な努力である。その代わりに、ライスは、その人以外には真に理解さ れることのない他人の音楽体験に関与する試みは、個人分析に限定されなければならないと主張する[51] ライスの論理によれば、文化全体の音楽体験を特徴づけることは不可能である。 フィールドワークの客観性と標準化に対するもう一つの主張は、Gregory BarzとTim Cooleyの著書『Shadows in the Field』の第2章に書かれている。民族音楽学におけるフィールドワークの新たな展望」と題されたこの章では、グレゴリー・バーズとティム・クーリー が、フィールドワークの客観性と標準化に対する反論を述べている。この章では、「フィールドに立ち向かう(注)」と題されています。なぜなら、民族音楽学 のフィールド研究者は、ハードサイエンスのフィールド研究者と異なり、そこにいるだけで研究対象集団の参加者であることが本質だからである。民族音楽学の フィールドワーカーが持つこうした主観的で参加型の体験と、一般的に民族音楽学の文献として出版されるものとの間の格差を説明するために、バーズとクー リーはフィールドリサーチとフィールドノートの違いを指摘している。フィールド・リサーチが現実を見つけようとするのに対し、フィールド・ノートは現実を 記録するものである。バーズとクーリーによれば、問題は、研究者の個人的な経験を捕らえるフィールドノートが、その研究者が出版するどんな最終的な文章か らもしばしば省かれることである[52]。 |
| Ethical concerns and best
practices Heightened awareness of the need to approach fieldwork in an ethical manner arose in the 1970s in response to a similar movement within the field of anthropology.[47] Mark Slobin writes in detail about the application of ethics to fieldwork.[48] Several potential ethical problems that arise during fieldwork relate to the rights of the music performers. To respect the rights of performers, fieldwork often includes attaining complete permission from the group or individual who is performing the music, as well as being sensitive to the rights and obligations related to the music in the context of the host society. Another ethical dilemma of ethnomusicological fieldwork is the inherent ethnocentrism (more commonly, eurocentrism) of ethnomusicology. Anthony Seeger, Emeritus Professor of Ethnomusicology at UCLA,[53] has done seminal work on the notion of ethics within fieldwork, emphasizing the need to avoid ethnocentric remarks during or after the field work process. Emblematic of his ethical theories is a 1983 piece that describes the fundamental complexities of fieldwork through his relationship with the Suyá Indians of Brazil.[1] To avoid ethnocentrism in his research, Seeger does not explore how singing has come to exist within Suyá culture, instead explaining how singing creates culture presently, and how aspects of Suyá social life can be seen through both a musical and performative lens. Seeger's analysis exemplifies the inherent complexity of ethical practices in ethnomusicological fieldwork, implicating the importance for the continual development of effective fieldwork in the study of ethnomusicology. In recent decades, ethnomusicologists have paid greater attention to ensuring that their fieldwork is both ethically conducted and provides a holistic sense of the community or culture under study. As the demographic makeup of ethnomusicologists conducting research grows more diverse, the field has placed a renewed emphasis on a respectful approach to fieldwork that avoids stereotyping or assumptions about a particular culture. Rather than using European music as a baseline against which music from all other cultures is compared, researchers in the field often aim to place the music of a certain society in the context only of the culture under study, without comparing it to European models. In this way, the field aims to avoid an "us vs. them" approach to music.[32] Nettl and other scholars hope to avoid the perception of the "ugly ethnomusicologist," which carries with it the same negative connotations as the "ugly American" traveler. Many scholars, from Ravi Shankar to V. Kofi Agawu, have criticized ethnomusicology for, as Nettl puts it, "dealing with non-European music in a condescending way, treating it as something quaint or exotic."[54] Nettl recalls an angry young man from Nigeria who asked the researcher how he could rationalize the study of other cultures' music. Nettl couldn't come up with an easy answer, and posits that ethnomusicologists need to be careful to respect the cultures they study and avoid treating valuable pieces of culture and music as just one of many artifacts they study.[55] Part of the problem, Nettl notes, is that the vast majority of ethnomusicologists are "members of Western society who study non-Western music,"[54] contributing to the perception that wealthy, white individuals are taking advantage of their privilege and resources. Researchers want to avoid the perception — accurate or exaggerated — that they're entering poorer and less technologically advanced communities, treating residents like test subjects, gleaning all they can, and then penning condescending reports about the quaintness of native music.[55] Researchers are optimistic that increased diversity within the field of ethnomusicology will help alleviate some ethical concerns. With more fieldwork of Western music and societies being conducted by researchers from underrepresented cultures — a reversal from the norm — some believe the field will reach a happy equilibrium. Author Charles Keil suggests that as "more of 'them' may want to study 'us,' a more interested anthropology will emerge ... in the sense of intersubjective, intercultural ... critical, revolutionary."[56] American ethnomusicologist and Wesleyan University professor Mark Slobin notes that most ethical concerns stem from interactions that occur during fieldwork between the researcher and the informant, or member of the community being studied. Nettl, in a 2005 paper, described the feeling of being an outsider approaching a community — in this case, Native American — that he wanted to study. He said ethnomusicologists often face feelings of trepidation as they attempt to get to know the local populace and culture while attempting to avoid being exploitative. Researchers have different methods, but Nettl's is to be patient, as he obeys a Native American man's instruction to "come back and see me next Tuesday," even though the man has plenty of free time and could sing to Nettl in the moment.[32] Another way to ensure ethnomusicologists gain a complete understanding of the community they're studying is simply to spend more time in it. In 1927, George Herzog spent two months with the Pima tribe in Arizona, an amount of time that would be considered short by today's standards — where periods of fieldwork can often last longer than a year. But Herzog recorded several hundred songs during that time, establishing a precedent for increasingly long field studies that have yielded more and more recordings. A lengthy period of fieldwork isn't useful, though, without proper techniques for ensuring the researcher gets a representative sampling of the music in a community. When he worked with the Blackfoot people, Nettl said he wasn't too concerned with whether the singer teaching him about Blackfoot music was good or bad, but did assume he would be representative of all Blackfoot singers. But Nettl soon gained a new perspective, and "no longer assumed that all informants in an indigenous society would tell me the same thing; I had discarded the idea of essential homogeneity."[57] Despite discarding this assumption, Nettl acknowledges that by only interviewing one person, he is relying heavily on that person's ability to articulate a whole society's culture and musical traditions.[32] There are myriad other ethical considerations that arise in the field, and Slobin attempts to summarize and explain some that he's come across or heard about. Ethnomusicologists may face dilemmas related to their roles as archivists and historians, such as whether to purchase a rare, one-of-a-kind instrument and preserve it, or leave it with musicians who created it. They may encounter controversy over whether they are allowed to watch, participate in, or record various songs or dances, or over who should be allowed to view videos or other products of fieldwork after the researcher has returned home.[48] |
17. 倫理的な懸念とベストプラ
クティス 倫理的な方法でフィールドワークに取り組む必要性に対する意識の高まりは、1970年代に人類学の分野でも同様の動きがあったことに呼応して生まれまし た。演奏者の権利を尊重するために、フィールドワークでは、音楽を演奏するグループや個人から完全に許可を得ることと、ホスト社会の文脈で音楽に関連する 権利と義務に敏感であることがしばしば含まれる。 民族音楽学のフィールドワークにおけるもう一つの倫理的ジレンマは、民族音楽学に内在するエスノセントリズム(より一般的にはヨーロッパ中心主義)であ る。UCLAの民族音楽学名誉教授であるアンソニー・シーガーは[53]、フィールドワークにおける倫理の概念について、フィールドワークの過程またはそ の後に民族中心的な発言を避ける必要性を強調し、重要な研究を行っている。彼の倫理観を象徴するのが、1983年にブラジルのスヤ族との関係を通じて フィールドワークの基本的な複雑さを説明した作品である[1]。研究において民族中心主義を避けるために、シーガーは、歌がスヤ族の文化の中でどのように 存在するようになったのかを探らず、歌がいかに文化を現在作り出すか、またスヤ族の社会生活の側面を音楽とパフォーマンスの両方のレンズを通していかに見 ることができるかを説明している。シーガーの分析は、民族音楽学のフィールドワークにおける倫理的実践の複雑さを例証しており、民族音楽学の研究において 効果的なフィールドワークを継続的に発展させることの重要性を暗示している。 ここ数十年、民族音楽学者は、フィールドワークを倫理的に実施し、研究対象のコミュニティや文化の全体像を把握することに、より大きな関心を寄せていま す。研究を行う民族音楽学者の人口構成がより多様化するにつれ、この分野では、特定の文化に対するステレオタイプや思い込みを避け、敬意を払ったフィール ドワークへのアプローチが再び重視されるようになっています。ヨーロッパの音楽を基準にして他のすべての文化の音楽を比較するのではなく、ある社会の音楽 をヨーロッパの音楽と比較するのではなく、その文化だけの文脈の中に位置づけることを目指すことが多い。このように、この分野は音楽に対する「我々対彼 ら」のアプローチを避けることを目的としている[32]。 ネットルや他の学者たちは、「醜いアメリカ人」旅行者と同じように否定的な意味合いを持つ「醜い民族音楽学者」という認識を避けたいと考えている。ラ ヴィ・シャンカールからV. コフィ・アガウまで多くの学者が、ネットルに言わせれば「非ヨーロッパの音楽を見下したように扱い、古風でエキゾチックなものとして扱う」民族音楽学を批 判してきた[54]。ネットルは、ナイジェリア出身のある若者が、他の文化の音楽を研究することをどう合理化できるかと研究者に聞いてきたことに怒ってい たと回想する。ネットルは簡単な答えを思いつかず、民族音楽学者は研究する文化を尊重し、文化や音楽の貴重な部分を研究する多くの人工物の一つにすぎない ものとして扱わないように注意する必要があると仮定している[55]。 問題の一つは、民族音楽学者の大半が「非西洋音楽を研究する西洋社会の一員」[54]であり、裕福な白人がその特権と資源を利用しているという認識を助長 しているとネットルは指摘している。研究者は、正確であろうと誇張であろうと、自分たちがより貧しく技術的に進んでいないコミュニティに入り込み、住民を 被験者のように扱い、できる限りのことを聞き出し、そして先住民の音楽の古風さについて見下したレポートを書いているという認識を避けたいのである [55]。 研究者たちは、民族音楽学の分野での多様性が高まることで、倫理的な懸念が軽減されるだろうと楽観視しています。西洋の音楽や社会に関するフィールドワー クが、これまでとは逆に、代表的な文化圏の研究者によって行われるようになれば、この分野は幸福な均衡に達するだろうと考える人もいる。作家のチャール ズ・ケイルは、「より多くの『彼ら』が『我々』を研究したいと思うようになれば、より関心の高い人類学が現れるだろう...間主観的、異文化間...批判 的、革命的という意味において」[56]と示唆している。アメリカの民族音楽学者でウェスリアン大学教授のマーク・スロビンは、倫理的懸念は研究者と情報 提供者、つまり研究対象のコミュニティのメンバーの間でフィールドワーク中に生じる相互作用から生じると指摘する。ネットルは2005年の論文で、自分が 研究したいコミュニティ(この場合はネイティブ・アメリカン)に近づく部外者であるという感覚を述べています。彼は、民族音楽学者はしばしば、搾取的であ ることを避けようとしながら、地元の住民や文化を知ろうとするため、恐怖の感情に直面することがあると述べている。研究者の手法はさまざまだが、ネトルの 場合は、ネイティブ・アメリカンの男性が「次の火曜日にまた来てくれ」という指示に従いながら、その男性は自由な時間がたっぷりあって、その場でネトルに 歌ってくれるかもしれないのに、我慢することである[32]。 民族音楽学者が研究対象のコミュニティを完全に理解するためのもう一つの方法は、単純にそのコミュニティでより多くの時間を過ごすことである。1927 年、ジョージ・ヘルツォークはアリゾナ州のピマ族に2ヶ月間滞在したが、フィールドワークの期間が1年以上に及ぶことが多い今日の基準からすれば、短い期 間とみなされるかもしれない。しかし、ヘルツォークはその間に数百曲を録音し、長期にわたる現地調査の先例を作り、より多くの録音を得ることができた。し かし、長期間のフィールドワークは、研究者がそのコミュニティの音楽を代表するサンプリングを確実に得るための適切な技術なしには、役に立たない。ブラッ クフット族と仕事をしたとき、ネットルは、ブラックフット族の音楽を教えてくれる歌手の良し悪しにはあまりこだわらず、ブラックフット族の歌手を代表する ような歌手を想定していたという。しかし、ネットルはすぐに新しい視点を得て、「先住民社会のすべての情報提供者が同じことを話すとは思わなくなり、本質 的な同質性という考えを捨てた」[57]。このように仮定を捨てたものの、ネットルは一人にしかインタビューしないことによって、その人が社会全体の文化 や音楽の伝統を表現する能力に大きく依存していることを認めている[32]。 このほかにも倫理的な配慮は無数にあるが、スロビンがこれまでに遭遇したり、耳にしたことのあるものをまとめ、解説しています。例えば、民族音楽学者は、 希少な一点ものの楽器を購入して保存するか、その楽器を作った音楽家に残すかといった、記録保管者や歴史家としての役割に関連したジレンマに直面すること がある。また、様々な歌や踊りを見たり、参加したり、録音したりすることが許されるかどうか、あるいは研究者が帰国した後にフィールドワークのビデオやそ の他の成果物を見ることが許されるのは誰であるかという論争に遭遇することもある[48]。 |
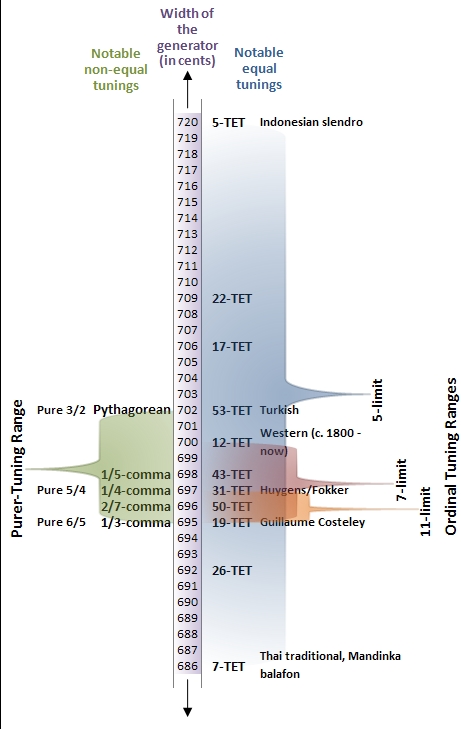 Theoretical issues and debates Theoretical issues and debatesUniversals Musicologists have long pondered the existence of universals in music. Despite the trope of music being a “universal language”, we have yet to find anyone that can indisputably point out concrete characteristics that all types of music have in common. If one were to ascertain one or multiple universals found in music, it would create a basis for which all music is defined on, which would drastically change the way that music study is conducted or regarded. Ethnomusicology is (debatably) a comparative and subjective field. Having a concrete definition of music would create a way for ethnomusicologists to objectively evaluate music and come up with more concrete conclusions based on this. It would also remove much of the bias within the field of ethnomusicology. Additionally, the definition of the field of ethnomusicology relies on an understood meaning of the word “music”; For these reasons, universals are highly sought after. Despite this, it is unknown whether or not such universals could even exist, which is why there is still a debate among ethnomusicologists. In a journal published in 1971 called Ethnomusicology,[58] this debate was carried out among renowned ethnomusicologists from the Society of Ethnomusicology, as outlined below, which set forth the recurring ideas around this topic in the field. Ethnomusicologists initially started to question the possibility of universals because they were searching for a new approach to explain musicology that differed from Guido Adler's. Ethnomusicologists worldwide have realized that culture has an important role in shaping aesthetic responses to music. This realization sparked controversy in the community, with debates questioning what people consider music, and whether perceptions of consonance and dissonance have a biological or cultural basis. Belief in universal traits of music was characteristic of nineteenth-century scholarship. Musicologists like Longfellow had written that Music is the universal language of mankind. The search for musical universalities has remained a topic amongst ethnomusicologists since Wilhelm Wundt, who tried to prove that "all 'primitive' peoples have monophonic singing and use intervals. Most musicians and even some teachers of Wundt's time believed that music was a universal language, resulting in the development of scholarship that dealt with only one kind of music and treated all other kinds as true relatives if distant of the Western canon. The assumption seemed to be that the basic principles of Western music were universally valid because it was the only "true" music. Later, by the 1990s it had become increasingly difficult to view the world of music without including some discussion about the notion of universals. Charles Seeger, for instance, categorized his interpretation of musical universals by using inclusion-exclusion styled Venn-diagrams to create five types universals, or absolute truths, of music. Universals in music are as hard to come by as universals in language since both potentially have a universal grammar or syntax. Dane Harwood noted that looking for causality relationships and "deep structure" (as postulated by Chomsky) is a relatively fruitless way to look for universals in music. In "The Universal Language." In The Study of Ethnomusicology: Thirty-One Issues and Concepts Bruno Nettl asserts that music is not a universal language and is more of a dialect because of the influence of culture on its creation and interpretation. Nettl shares the belief with his colleagues that trying to find a universal in music is unproductive because there will always be at least one instance proving that there is no musical universals.[59] Nettl asserts that music is not the universal language, but musics are not as mutually unintelligible as languages. One should study the music of each society in its own terms and learn it individually, referred to as music's dialects rather than music's languages. Nettl concludes his writing by stating that despite the wide variety of musics, the ways in which people everywhere have chosen to sing and play are more alike than the boundaries of the imaginable might suggest. There are other ethnomusicologists that note the invailidity of music as a universal language. For example, George List writes, "I once knew a missionary who assured me that the Indians to whom he had ministered on the west coast of Mexico neither sang nor whistled." and ethnomusicologist David P. McAllester writes, "Any student of man must know that somewhere, someone is doing something that he calls music but nobody else would give it that name. That one exception would be enough to eliminate the possibility of a real universal."[60] As a result of this gamesmanship of ethnomusicologists to poke holes in universals, focus shifted from trying to find a universal to trying to find near-universals, or qualities that may unite the majority of the world's musics. In Some Thoughts on "Universals" in World Music,[60] McAllester claims there are no absolute universals in music, but there are plenty near-universals in that all music has some tonal center, and establishes a tendency that emits a feeling and the performers of that music influences the way in which that tendency is felt or realized. Music transforms experience and each person feels something when they hear it. Music is the actualization of the mystical experience for everybody. The universality of music exists in its ability to effect the human-mind. McAllester was a believer in near universals, he wrote, "I will be satisfied if nearly everybody does it," which is why he postulated that nearly all music has a tonal center, has a tendency to go somewhere, and also has an ending. However McAllester's main point is that music transforms the everyday humdrum into something else, bringing about a heightened experience. He likens music to having an out of body experience, religion, and sex. It is music's ability to transport people mentally, that is in his opinion a near universal that almost all musics share. ●In response to McAllester's Universal Perspectives on Music, Klaus P. Wachsmann counters that even a near universal is hard to come by because there are many variables when considering a very subjective topic like music and music should not be removed from culture as a singular variable. There is a universal understanding that music is not the same everywhere, and a conversation of the universality of music can only be held when omitting the word "music", or "universals", or both. Wachsmann thinks that resemblance may be the main influencer of what we call music and what we don't. His approach, instead of finding a universal, was to create an amalgam of relations for sound and psyche: "(1) the physical properties of the sounds, (2) the physiological response to the acoustic stimuli, (3) the perception of sounds as selected by the human mind that is programmed by previous experiences, and (4) the response to the environmental pressures of the moment.[61] In this tetradic schema lies an exhaustive model of the universals in music." However, Wachsmann does allow that they all had some influenced experience and this belief is echoed by another ethnomusicologist who shares the belief that the universal lies in the specific way music reaches the listener. "Whatever it communicates is communicated to the members of the in-group only, whoever they may be. This is as true of in-groups in our own society as in any other. Does "classical" music communicate to every American? Does rock and roll communicate to every parent?" This relativity goes to prove that people are used to thinking of a certain phenomenon that marries indescribable components that we resemble to what we know as music from our reference. It is also here that Wachsmann acknowledges that part of the problem of identifying universals in music is that it requires a set definition of music, but he doesn’t think that the lack of a definition does not need to “disturb us unduly because usage will decide whether the emphasis is on primarily utilitarian speech or on speech that creates "special time" in a culture. And in any case, phenomena do have a way of belonging to more than one kind of continuum at the same time”. Folklore specializing ethnomusicologist George List, in his book "On the Non-universality of Musical Perspectives",[62] is in agreement with all within the discussion by saying that there is something unique that music produces, arguing that it always possesses significance to the group that it is produced by/around: “ Whatever [music] communicates is communicated to the members of the in-group only, whoever they may be. This is as true of in-groups in our own society as in any other”(List, 399). However, List deviates from McAllister, however, in saying that the “weakness” in his idea regarding music as a producer of “heightened experience” is that “it applies equally well to other arts, not only to music”, and therefore cannot be a universality of music, since it can’t be defined as a sole characteristic of music. List takes this thinking to Mcallister’s notion of music possessing tendency as well, stating that “all art forms, one might say every human activity, are patterned and show some form of organization, show ‘tendencies’.” Additionally, List acknowledges the problem of talking about universality in music while there isn’t an objective definition of music itself: “But words, as the [common definition suggests, are lexically meaningful while music is not. Since music is abstract how do we study and assess its production of ‘heightened experience’.”[63] Dane Harwood, in response to this debate, approached the question of universality in music in his article “Universals in Music: A Perspective from Cognitive Psychology”,[63] years after the initial debate, from a psychology perspective. His view is that universals in music are not a matter of specific musical structure or function—but of basic human cognitive and social processes construing and adapting to the real world. He calls this the “information processing approach”, and argues that one must “examine music as a complex auditory stimulus which is somehow perceived, structured, and made meaningful by the human perceptual and cognitive system. From this point of view, we can search for perceptual and cognitive processes which all human beings apply to musical sound, and thus identify some processing universal”. He argues that this would adjust for the differences in context with which music is defined, produced, and observed, which would lead to insight into. “if there are universal cultural processes operating on musical information”. It is here that he takes a more technical turn and points to different musical phenomena and their relation to the way that humans process what they’re listening to. He argues that music is both a cultural and individual phenomenon, yet culture is something individuals learn about their worlds which is shared with others in the group. One aspect of music is tuning, and recent work has shown that many musical traditions' tuning's notes align with their dominant instrument's timbre's partials[64] and fall on the tuning continuum of the syntonic temperament, suggesting that tunings of the syntonic temperament (and closely related temperaments) may be a potential universal,[65] thus explaining some of the variation among musical cultures (specifically and exclusively with regard to tuning and timbre) and possible limits on that variation. |
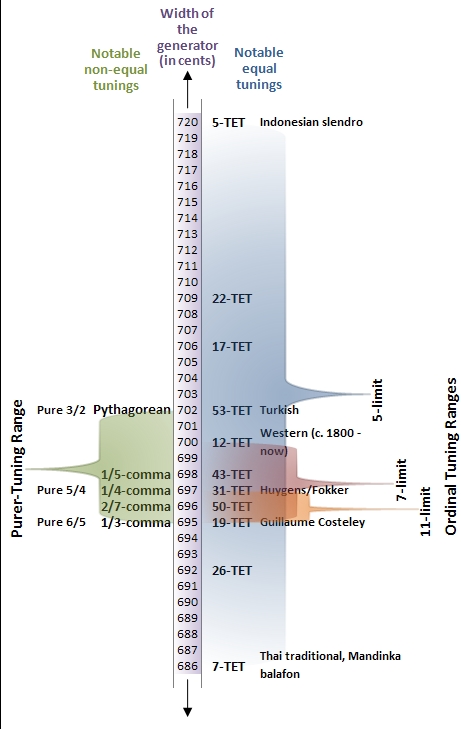 Note
the number of Western and non-Western tunings that occur within the
valid tuning range of the syntonic
temperament.(音律の有効な調律範囲内に存在する西洋式と非西洋式の調律の数に注目せよ) Note
the number of Western and non-Western tunings that occur within the
valid tuning range of the syntonic
temperament.(音律の有効な調律範囲内に存在する西洋式と非西洋式の調律の数に注目せよ)18. 理論的な問題点と議論 普遍性 音楽学者は長い間、音楽における普遍的なものの存在について考えてきた。音楽は「世界共通語」であるという表現があるにもかかわらず、すべてのタイプの音 楽に共通する具体的な特徴を明確に指摘できる人はまだ見つかっていない。もし、音楽に共通する普遍的なものを一つ、あるいは複数見つけることができれば、 それはすべての音楽を定義する根拠となり、音楽研究のあり方や評価を大きく変えることになるはずだ。民族音楽学は(議論の余地があるにせよ)比較の対象と なる主観的な分野である。音楽の具体的な定義があれば、民族音楽学者が音楽を客観的に評価し、それに基づいてより具体的な結論を導き出すことができるよう になる。また、民族音楽学という分野の中の偏りを取り除くことができるだろう。また、民族音楽学という学問の定義は、「音楽」という言葉の意味を理解して いるかどうかにかかっており、そのため、普遍性が強く求められている。にもかかわらず、そのような普遍的なものが存在しうるかどうかは不明であり、そのた め民族音楽学者の間でも議論が続いている。1971年に発行された雑誌『Ethnomusicology』[58]では、民族音楽学会の著名な民族音楽学 者たちによって、以下のような議論が行われ、この分野で繰り返される考え方が示されている。 民族音楽学者が最初に普遍性の可能性に疑問を持ち始めたのは、グイド・アドラーとは異なる新しい音楽学の説明の仕方を模索していたからである。世界中の民 族音楽学者が、音楽に対する美的反応の形成には文化が重要な役割を担っていることに気づきました。この気づきは、人々が何を音楽とみなすのか、また、子音 と不協和音の知覚は生物学的または文化的根拠があるのか、といった議論を巻き起こし、コミュニティの中で論争を巻き起こした。音楽の普遍的な特性に対する 信念は、19世紀の学問の特徴であった。ロングフェローのような音楽学者は、「音楽は人類の普遍的な言語である」と書いている。音楽の普遍性の探求は、 「すべての『原始人』は単旋律で歌い、音程を使う」ということを証明しようとしたヴィルヘルム・ヴント以来の民族音楽学者の間で、トピックとして残り続け ている。ヴントの時代、音楽家の多くは、そして一部の教師でさえも、音楽は普遍的な言語であると信じていた。その結果、一種類の音楽だけを扱い、他のすべ ての種類の音楽を、西洋の正典からは遠く離れていても、真の親族として扱う学問が発達した。西洋音楽が唯一の「真の」音楽であるため、その基本原理は普遍 的に有効であるという前提があったようだ。その後、1990年代には、普遍という概念についての議論を抜きにして、音楽の世界を見ることは難しくなってい た。例えば、チャールズ・シーガーは、音楽の普遍性についての解釈を、包含-排除型のヴェンダイアグラムを使って、5種類の音楽の普遍性、あるいは絶対的 な真理を作り出しました。音楽における普遍は、言語における普遍と同様に、普遍的な文法や構文を持っている可能性があるため、手に入れることが困難です。 デーン・ハーウッドは、因果関係や「深い構造」(チョムスキーが仮定したもの)を探すことは、音楽における普遍性を探す上で比較的実りのない方法であると 述べています。 "普遍の言葉 "で。民族音楽学の研究』において。Thirty-One Issues and Concepts ブルーノ・ネトルは、音楽は普遍的な言語ではなく、その創造と解釈に文化の影響を受けているため、むしろ方言に近いと主張している。ネトルは、音楽は普遍 的な言語ではないが、音楽は言語のように相互に理解できないものではないと主張している。しかし、音楽は言語のように相互に理解できないものではない。そ れぞれの社会の音楽をそれぞれの言葉で研究し、音楽の言語ではなく音楽の方言と呼ばれるものを学ぶべきである。ネットルは最後に、音楽は多種多様であるに もかかわらず、人々が歌い、演奏するために選択した方法は、想像力の境界線が示唆するよりも類似していると述べて、彼の文章を締めくくった。世界共通語と しての音楽の難しさを指摘する民族音楽学者はほかにもいる。例えば、ジョージ・リストは「私はかつて、メキシコ西海岸で伝道していたインディアンが歌も口 笛も吹かないと断言した宣教師を知っている」と書き、民族音楽学者デビッド・P・マカラスターは「人間を研究する者なら、どこかで誰かが、自分は音楽と呼 ぶが、他の誰もその名を与えないことをしていることを知っているはずだ」と書いている。その一つの例外は、真の普遍の可能性を排除するのに十分である」 [60]。このように民族音楽学者たちが普遍に穴を開けようとする駆け引きをした結果、普遍を見つけることから、近普遍、つまり世界の音楽の大部分を統合 するような特質を見つけることに焦点が移っていったのである。 ●マカレスターの「音楽の普遍的視点」に対して、クラウス・P・ワックスマンは、音楽のような非常に主観的なテーマを考える場合、多くの変数があるため、 普遍に近いものでさえ難しい、音楽は単一変数として文化から外すべきではないと反論している。音楽はどこでも同じではないという普遍的な理解があり、音楽 の普遍性を語るには、「音楽」という言葉、あるいは「普遍」という言葉、あるいはその両方を省いて初めて成立するのである。ヴァハスマンは、我々が何を音 楽と呼び、何を音楽と呼ばないかについては、類似性が主な影響因子であるかもしれないと考えている。彼のアプローチは、普遍的なものを見つけるのではな く、音と精神のための関係のアマルガムを作ることでした。「1)音の物理的特性,(2)音響刺激に対する生理的反応,(3)過去の経験によってプログラム された人間の心が選択する音の知覚,(4)その時々の環境圧力に対する反応。 この四元的なスキーマに,音楽における普遍性の網羅的なモデルがある」[61]。しかし、ヴァハスマンは、彼らがみな何らかの影響を受けた経験を持ってい ることを認めており、この信念は、音楽がリスナーに届く特定の方法に普遍性があるという信念を共有する別の民族音楽学者も同じことを言っている。「音楽が 伝えるものは、それが誰であれ、内集団のメンバーだけに伝えられる。このことは、私たちの社会における内集団についても、他の社会と同様である。クラシッ ク音楽は、すべてのアメリカ人に伝わるのだろうか。ロックンロールは、すべての親に伝わるのか?この相対性は、私たちが基準として知っている音楽と、私た ちが似ている何とも言えない構成要素を結婚させるある種の現象を、人々が考えることに慣れていることを証明することになる。また、ここでワックスマンは、 音楽における普遍性を特定することの問題の一つは、それが音楽の一定の定義を必要とすることであると認めながらも、定義がないことが「使用法が、主として 実用的な発話に重点を置くか、それとも文化の中で「特別な時間」を作り出す発話に重点を置くかを決めるので、過度に我々を妨げる必要はない」とは考えてい ないのである。そして、いずれにせよ、現象は同時に複数の種類の連続体に属するということがあるのです」。 民俗学専門の民族音楽学者であるジョージ・リストは、その著書「音楽的視点の非普遍性について」[62]の中で、音楽が生み出すものには固有のものがある とし、音楽が生み出す集団/周囲に対して常に意義を持っていると主張して、議論内のすべての意見に同意している。「音楽が伝えるものは,それが誰であれ, 内集団の成員だけに伝えられる。このことは,われわれの社会における内集団についても,他の社会と同様に当てはまる」(List, 399)。しかし、リストは、「高められた経験」の生産者としての音楽に関する考え方の「弱点」は、「それは音楽だけでなく、他の芸術にも等しく当てはま る」ので、音楽の唯一の特徴として定義できない以上、音楽の普遍性とはなり得ないと言って、マカリスターから逸脱しているのである。リストはこの考え方 を、音楽が傾向を持つというマッカリスターの概念にも当てはめ、「すべての芸術形態、1つはすべての人間の活動と言えるかもしれないが、パターン化され、 何らかの形の組織を示し、『傾向』を示している」と述べている。さらに、リストは、音楽そのものの客観的な定義がない中で、音楽の普遍性を語ることの問題 を認めている。「しかし、言葉は、[一般的な定義が示すように]語彙的に意味があるのに対して、音楽はそうではない。音楽が抽象的である以上、その「高め られた経験」の生成をどのように研究し評価すればよいのだろうか」[63]。 この議論に対して、デイン・ハーウッドは論文「音楽における普遍性」で音楽における普遍性の問題にアプローチしている。最初の議論から数年後、デイン・ ハーウッドは「音楽における普遍性:認知心理学からの視点」[63]という論文で、心理学の観点から音楽の普遍性の問題にアプローチしている。彼の見解 は、音楽における普遍性とは、特定の音楽の構造や機能の問題ではなく、現実世界を解釈し適応する人間の基本的な認知的・社会的プロセスの問題であるという ことである。彼はこれを「情報処理アプローチ」と呼び、「音楽を、人間の知覚・認知システムによって何らかの形で知覚・構造化・意味づけされた複雑な聴覚 刺激として考察する」必要があると主張する。この観点から、すべての人間が音楽の音に適用する知覚・認知プロセスを探索し、何らかの処理普遍性を特定する ことができる」。これは、音楽が定義され、生産され、観察される文脈の違いを調整するものであり、その結果、次のような洞察が得られると主張している。 「音楽情報に作用する普遍的な文化的プロセスが存在するかどうか」である。ここで彼はより専門的な方向に進み、さまざまな音楽現象と、人間が聴いているも のを処理する方法との関係を指摘する。音楽は文化的かつ個人的な現象であり、文化とは個人が自分の世界について学び、それを集団の中で他の人と共有するも のである、と彼は主張する。 音楽の1つの側面は調律であり、最近の研究では多くの音楽伝統の調律の音はその支配的な楽器の音色の部分音と一致し[64]、音律の調律の連続体に該当す ることが示されており、音律の調律(および密接に関連する音律)は潜在的な普遍性である可能性を示唆している[65]。したがって、音楽文化間の(調律と 音色に関して特別かつ限定的)変動の一部とその変動に対する考えられる限界を説明しているのだ。 |
| Linguistics and semiotics It is often the case that interests in ethnomusicology stem from trends in anthropology, and this no different for symbols. In 1949, anthropologist Leslie White wrote, "the symbol is the basic unit of all human behavior and civilization," and that use of symbols is a distinguishing characteristic of humans.[66] Once symbolism was at the core of anthropology, scholars sought to examine music "as a symbol or system of signs or symbols," leading to the establishment of the field of musical semiotics.[66] Bruno Nettl discusses various issues relating ethnomusicology to musical semiotics, including the wide variety of culturally dependent, listener-derived meanings attributed to music and the problems of authenticity in assigning meaning to music.[67] Some of the meanings that musical symbols can reflect can relate to emotion, culture, and behavior, much in the same way that linguistic symbols function. The interdisciplinarity of symbolism in anthropology, linguistics, and musicology has generated new analytical outlooks (see Analysis) with different focuses: Anthropologists have traditionally conceived of whole cultures as systems of symbols, while musicologists have tended to explore symbolism within particular repertories. Structural approaches seek to uncover interrelationships between symbolic human behaviors.[68] In the 1970s, a number of scholars, including musicologist Charles Seeger and semiotician Jean-Jacques Nattiez, proposed using methodology commonly employed in linguistics as a new way for ethnomusicologists to study music.[69][70] This new approach, widely influenced by the works of linguist Ferdinand de Saussure, philosopher Charles Sanders Peirce, and anthropologist Claude Lévi-Strauss, among others, focused on finding underlying symbolic structures in cultures and their music.[67] In a similar vein, Judith Becker and Alton L. Becker theorized the existence of musical "grammars" in their studies of the theory of Javanese gamelan music. They proposed that music could be studied as symbolic and that it bears many resemblances to language, making semiotic study possible.[71] Classifying music as a humanity rather than science, Nattiez suggested that subjecting music to linguistic models and methods might prove more effective than employing the scientific method. He proposed that the inclusion of linguistic methods in ethnomusicology would increase the field's interdependence, reducing the need to borrow resources and research procedures from exclusively other sciences.[70] John Blacking 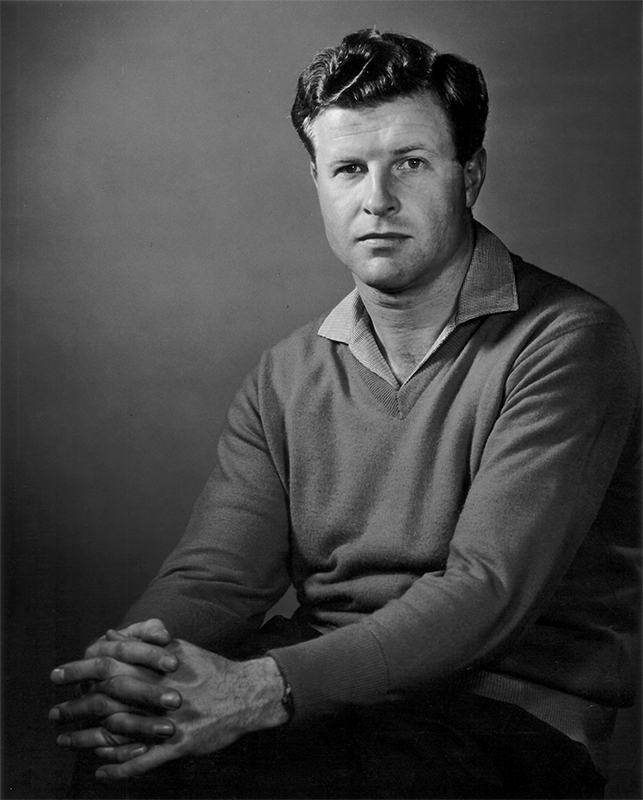 John Blacking was another
ethnomusicologist who sought to create an
ethnomusicological parallel to linguistic models of analysis. In his
work on Venda music, he writes, "The problem of musical description is
not unlike that in linguistic analysis: a particular grammar should
account for the processes by which all existing and all possible
sentences in the language are generated."[72] Blacking sought more than
sonic description. He wanted to create a musical analytical grammar,
which he coined the Cultural Analysis of Music, that could incorporate
both sonic description and how cultural and social factors influence
structures within music. Blacking desired a unified method of musical
analysis that "...can not only be applied to all music, but can explain
both the form, the social and emotional content, and the effects of
music, as systems of relationships between an infinite number of
variables."[72] Like Nattiez, Blacking saw a universal grammar as a
necessary for giving ethnomusicology a distinct identity. He felt that
ethnomusicology was just a "meeting ground" for anthropology of music
and the study of music in different cultures, and lacked a
distinguishing characteristic in scholarship. He urged others in the
field to become more aware and inclusive of the non-musical processes
that occur in the making of music, as well as the cultural foundation
for certain properties of the music in any given culture, in the vein
of Alan Merriam's work. John Blacking was another
ethnomusicologist who sought to create an
ethnomusicological parallel to linguistic models of analysis. In his
work on Venda music, he writes, "The problem of musical description is
not unlike that in linguistic analysis: a particular grammar should
account for the processes by which all existing and all possible
sentences in the language are generated."[72] Blacking sought more than
sonic description. He wanted to create a musical analytical grammar,
which he coined the Cultural Analysis of Music, that could incorporate
both sonic description and how cultural and social factors influence
structures within music. Blacking desired a unified method of musical
analysis that "...can not only be applied to all music, but can explain
both the form, the social and emotional content, and the effects of
music, as systems of relationships between an infinite number of
variables."[72] Like Nattiez, Blacking saw a universal grammar as a
necessary for giving ethnomusicology a distinct identity. He felt that
ethnomusicology was just a "meeting ground" for anthropology of music
and the study of music in different cultures, and lacked a
distinguishing characteristic in scholarship. He urged others in the
field to become more aware and inclusive of the non-musical processes
that occur in the making of music, as well as the cultural foundation
for certain properties of the music in any given culture, in the vein
of Alan Merriam's work.Some musical languages have been identified as more suited to linguistically focused analysis than others. Indian music, for example, has been linked more directly to language than music of other traditions.[67] Critics of musical semiotics and linguistic-based analytical systems, such as Steven Feld, argue that music only bears significant similarity to language in certain cultures and that linguistic analysis may frequently ignore cultural context.[73] |
19. 言語学と記号論 民族音楽学への関心が人類学の動向から生まれることはよくあることで、記号についても同様である。1949年に人類学者のレスリー・ホワイトが「記号はす べての人間の行動と文明の基本単位である」と書き、記号の使用が人間の特徴であるとした[66]。記号論が人類学の核となると、学者たちは「記号または記 号のシステムとして」音楽を検証しようとし、音楽記号論の分野の確立に至った[66]。 [ブルーノ・ネトル(Bruno Nettl)は、民族音楽学と音楽記号論に関連する様々な問題を論じており、文化的に依存し、リスナーが音楽に帰結する意味の多様性や、音楽に意味を付与 する際の真正性の問題などを挙げている[67]。音楽記号が反映できる意味の一部は、言語記号の機能と同じように感情、文化、行動と関係することがある。 人類学、言語学、音楽学における象徴主義の学際性は、異なる焦点を持つ新しい分析的展望(「分析」を参照)を生み出している。人類学者は伝統的に文化全体 を象徴のシステムとして考え、音楽学者は特定のレパートリーにおける象徴を探求する傾向があった。構造的なアプローチは象徴的な人間の行動間の相互関係を 明らかにしようとするものである[68]。 1970年代には、音楽学者であるチャールズ・シーガーや記号学者であるジャン=ジャック・ナティエスを含む多くの学者が、民族音楽学者が音楽を研究する ための新しい方法として言語学でよく使われる方法論を使うことを提案していた[69][70]。この新しいアプローチは言語学者のフェルディナンド・ド・ ソシュール、哲学者のチャールズ・サンダース・パイス、人類学者のクロード・レヴィ=ストロースなどの著作から広く影響を受け、文化やその音楽に根底にあ る象徴構造を見つけることに焦点を当てている[67]。 同様の流れで、ジュディス・ベッカーとアルトン・L・ベッカーはジャワのガムラン音楽の理論の研究において、音楽の「文法」の存在を理論化している。彼ら は、音楽は象徴的なものとして研究でき、言語と多くの類似点を持つため、記号論的な研究が可能であると提案している[71] 音楽を科学というよりも人間性に分類するナティエスは、音楽を言語的なモデルや手法で扱う方が、科学的手法を採用するより効果的であると示唆する。彼は民 族音楽学に言語的手法を取り入れることで、この分野の相互依存性を高め、他の科学から資源や研究手順を独占的に借りる必要性を減らすことを提案している [70]。 ジョン・ブラッキング(再掲) 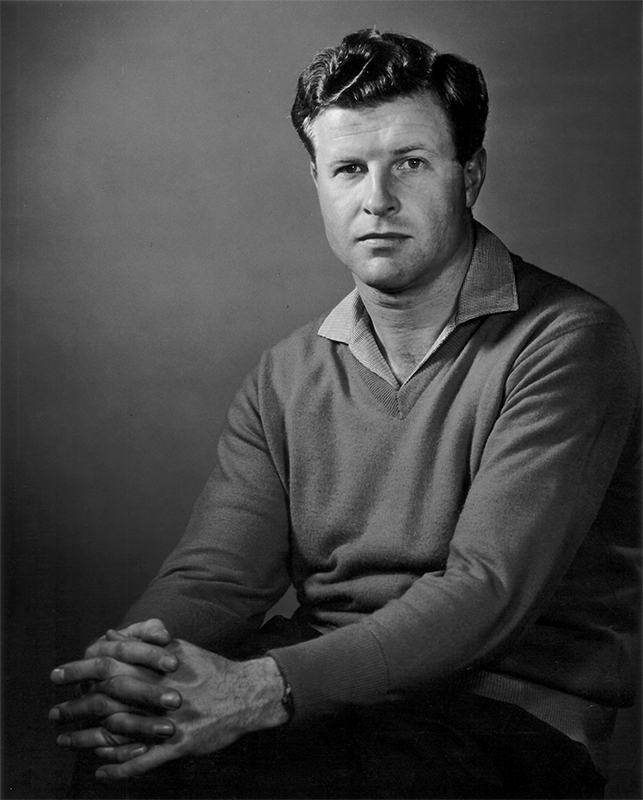 ジョ
ン・ブラッキングは言語学的な分析モデルに民族音楽学的な並列を作り出そうとしたもう一人の民族音楽学者であった。ヴェンダ音楽に関する著作の中
で、
彼は「音楽記述の問題は言語分析におけるそれと似ていない。特定の文法は、言語におけるすべての既存およびすべての可能な文が生成される過程を説明しなけ
ればならない」と書いている[72]。彼は、音の記述と文化的、社会的要因がどのように音楽の中の構造に影響を与えるかの両方を取り入れることができる、
音楽の文化分析と呼ばれる音楽分析文法を作りたかったのである。ブラッキングは「...すべての音楽に適用できるだけでなく、音楽の形式、社会的・感情的
内容、効果の両方を、無限の変数の間の関係のシステムとして説明できる」音楽分析の統一的方法を望んでいた[72]。ナティエスのように、ブラッキングは
民族音楽学に独特のアイデンティティを与えるために普遍的文法を必要だと考えていた。彼は民族音楽学が音楽の人類学と異なる文化における音楽の研究の「出
会いの場」に過ぎず、学問的に際立った特徴を欠いていると感じていた。彼は、アラン・メリアムの仕事のように、音楽が作られる際に生じる非音楽的なプロセ
スや、ある文化における音楽の特性の文化的基盤について、この分野の人々がもっと認識し、包括的になるよう促したのである。 ジョ
ン・ブラッキングは言語学的な分析モデルに民族音楽学的な並列を作り出そうとしたもう一人の民族音楽学者であった。ヴェンダ音楽に関する著作の中
で、
彼は「音楽記述の問題は言語分析におけるそれと似ていない。特定の文法は、言語におけるすべての既存およびすべての可能な文が生成される過程を説明しなけ
ればならない」と書いている[72]。彼は、音の記述と文化的、社会的要因がどのように音楽の中の構造に影響を与えるかの両方を取り入れることができる、
音楽の文化分析と呼ばれる音楽分析文法を作りたかったのである。ブラッキングは「...すべての音楽に適用できるだけでなく、音楽の形式、社会的・感情的
内容、効果の両方を、無限の変数の間の関係のシステムとして説明できる」音楽分析の統一的方法を望んでいた[72]。ナティエスのように、ブラッキングは
民族音楽学に独特のアイデンティティを与えるために普遍的文法を必要だと考えていた。彼は民族音楽学が音楽の人類学と異なる文化における音楽の研究の「出
会いの場」に過ぎず、学問的に際立った特徴を欠いていると感じていた。彼は、アラン・メリアムの仕事のように、音楽が作られる際に生じる非音楽的なプロセ
スや、ある文化における音楽の特性の文化的基盤について、この分野の人々がもっと認識し、包括的になるよう促したのである。音楽言語の中には、言語学的な分析に適しているものとそうでないものがあることが確認されている。例えばインド音楽は他の伝統の音楽よりも直接的に言語と 結びついている[67]。スティーブン・フェルドなどの音楽記号論や言語ベースの分析システムの批判者は、音楽は特定の文化においてのみ言語と大きな類似 性を持ち、言語分析はしばしば文化的文脈を無視する可能性があると主張している[73]。 |
| Comparison Since ethnomusicology evolved from comparative musicology, some ethnomusicologists' research features analytical comparison. The problems arising from using these comparisons stem from the fact that there are different kinds of comparative studies with a varying degree of understanding between them.[21] Beginning in the late 60s, ethnomusicologists who desired to draw comparisons between various musics and cultures have used Alan Lomax's idea of cantometrics.[74] Some cantometric measurements in ethnomusicology studies have been shown be relatively reliable, such as the wordiness parameter, while other methods are not as reliable, such as precision of enunciation.[75] Another approach, introduced by Steven Feld, is for ethnomusicologists interested in creating ethnographically detailed analysis of people's lives; this comparative study deals with making pairwise comparisons about competence, form, performance, environment, theory, and value/equality.[29] Bruno Nettl has noted as recently as 2003 that comparative study seems to have fallen in and out of style, noting that although it can supply conclusions about the organization of musicological data, reflections on history or the nature of music as a cultural artifact, or understanding some universal truth about humanity and its relationship to sound, it also generates a great deal of criticism regarding ethnocentrism and its place in the field.[76] |
20. 比較 民族音楽学は比較音楽学から発展してきたため、民族音楽学者の研究の中には分析的な比較を特徴とするものがある。60年代後半から、様々な音楽・文化間の 比較を望む民族音楽学者は、アラン・ローマックスのカントメトリックの考えを使った[74]。民族音楽学研究におけるカントメトリックの測定は、語気強度 のパラメータのように比較的信頼できるものもあれば、発音精度のようにそれほど信頼できない方法もあることが示されている[75]。 [この比較研究は、能力、形式、演奏、環境、理論、価値/平等について一対比較することを扱うものである。 [29]ブルーノ・ネトルは2003年の時点で、比較研究は流行り廃りがあるようだと指摘しており、音楽学的データの構成に関する結論、歴史や文化的人工 物としての音楽の性質に関する考察、人類と音との関係性に関する何らかの普遍的真理の理解などを提供できるものの、民族中心主義やその位置に関する多くの 批判も発生させていると指摘している[76]。 |
| Insider/outsider epistemology The relevance and implications of insider and outsider distinctions within ethnomusicological writing and practice has been a subject of lengthy debate for decades, invoked by Bruno Nettl, Timothy Rice, and others. The question that causes such debate lies in the qualifications for an ethnomusicologist to research another culture when they represent an outsider, dissecting a culture that doesn't belong to them. Historically, ethnomusicological research was tainted with a strong bias from Westerners in thinking that their music was superior to the musics they researched. From this bias grew an apprehension of cultures to allow ethnomusicologists to study them, thinking that their music would be exploited or appropriated. There are benefits to ethnomusicological research, i.e. the promotion of international understanding, but the fear of this "musical colonialism"[77] represents the opposition to an outsider ethnomusicologist in conducting his or her research on a community of insiders. In The Study of Ethnomusicology: Thirty-One Issues and Concepts, Nettl discusses personal and global issues pertaining to field researchers, particularly those from a Western academic background. In a chapter that recounts his field recordings among Native Americans of the northern plains, for instance, he attempts to come to terms with the problematic history of ethnographic fieldwork, and envision a future trajectory for the practice in the 21st century and beyond.[32] Considering that ethnomusicology is a field that intersects in a vast array of other fields in the social sciences and beyond, it focuses on studying people, and it is appropriate to encounter the issue of "making the unfamiliar, familiar," a phrase coined by William McDougall that is well known in social psychology.[78] As in social psychology, the "unfamiliar" is encountered in three different ways during ethnomusicological work: 1) two different cultures come into contact and elements of both are not immediately explicable to the other; 2) experts within a society produce new knowledge, which is then communicated to the public; and 3) active minorities communicate their perspective to the majority.[78] Nettl has also been vocal about the effect of subjective understanding on research. As he describes, a fieldworker might attempt immersing themselves into an outsider culture to gain full understanding. This, however, can begin to blind the researcher and take away the ability to be objective in what is being studied. The researcher begins to feel like an expert in a culture's music when, in fact, they remain an outsider no matter the amount of research, because they are from a different culture. The background knowledge of each individual influences the focus of the study because of the comfort level with the material. Nettl characterizes the majority of outsiders as "simply members of Western society who study non-Western music, or members of affluent nations who study the music of the poor, or maybe city folk who visit the backward villages in their hinterland."[79] This points to possible Eurocentric origins of researching foreign and exotic music. Within this outsider/insider dynamic and framework unequal power relations come into focus and question. In addition to his critiques of the outsider and insider labels, Nettl creates a binary that roughly equates to Western and Nonwestern. He points out what he feels are flaws in Western thinking through the analyses of multiple societies, and promotes the notion of collaborating, with a greater focus on acknowledging the contribution of native experts. He writes, "The idea of joint research by an 'insider' and an 'outsider' has been mentioned as a way of bridging the chasms."[80] In spite of his optimism, the actualization of this practice has been limited and the degree to which this can solve the insider/outsider dilemma is questionable. He believes that every concept is studied through a personal perspective, but "a comparison of viewpoints may give the broadest possible insight."[81] The position of ethnomusicologists as outsiders looking in on a music culture, has been discussed using Said's theory of Orientalism. This manifests itself in the notion that music championed by the field may be, in many ways, a Western construction based on an imagined or romanticized view of "the Other" situated within a colonial mindset.[82] According to Nettl, there are three beliefs of insiders and members of the host culture that emerge that lead to adverse results. The three are as follows: (1) "Ethnomusicologists come to compare non-Western musics or other "other" traditions to their own... in order to show that the outsider's own music is superior," (2)Ethnomusicologists want to use their own approaches to non-Western music;" and (3) "They come with the assumption that there is such a thing as African or Asian or American Indigenous music, disregarding boundaries obvious to the host."[80] As Nettl argues, some of these concerns are no longer valid, as ethnomusicologists no longer practice certain orientalist approaches that homogenize and totalize various musics. He explores further intricacies within the insider/outsider dichotomy by deconstructing the very notion of insider, contemplating what geographic, social, and economic factors distinguish them from outsiders. He notes that scholars of "more industrialized African and Asian nations" see themselves as outsiders in regards to rural societies and communities.[80] Even though these individuals are in the minority, and ethnomusicology and its scholarship is generally written from a western perspective, Nettl disputes the notion of the native as the perpetual other and the outsider as the westerner by default.[citation needed] Timothy Rice is another author who discusses the insider/outsider debate in detail but through the lens of his own fieldwork in Bulgaria and his experience as an outsider trying to learn Bulgarian music. In his experience, told through his book May it Fill Your Soul: Experiencing Bulgarian Music,[51] he had a difficult time learning Bulgarian music because his musical framework was founded in a Western perspective. He had to "broaden his horizons"[51] and try instead to learn the music from a Bulgarian framework in order to learn to play it sufficiently. Although he did learn to play the music, and the Bulgarian people said that he had learned it quite well, he admitted that "there are still areas of the tradition (...) that elude my understanding and explanation. (...) Some sort of culturally sensitive understanding (...) will be necessary to close this gap."[83] Ultimately, Rice argues that despite the impossibility of being objective one's work ethnomusicologists may still learn much from self-reflection. In his book, he questions about whether or not one can be objective in understanding and discussing art and, in accordance with the philosophies of phenomenology, argues that there can be no such objectivity since the world is constructed with preexisting symbols that distort any "true" understanding of the world we are born into. He then suggests that no ethnomusicologist can ever come to an objective understanding of a music nor can an ethnomusicologist understand foreign music in the same way that a native would understand it. In other words, an outsider can never become an insider. However, an ethnomusicologist can still come to a subjective understanding of that music, which then shapes that scholar's understanding of the outside world. From his own scholarship, Rice suggests "five principles for the acquisition of cognitive categories in this instrumental tradition" among Bulgarian musicians.[84] However, as an outsider, Rice notes that his "understanding passed through language and verbal cognitive categories" whereas the Bulgarian instrumental tradition lacked "verbal markers and descriptors of melodic form" so "each new student had to generalize and learn on his own the abstract conceptions governing melodies without verbal or visual aids."[85] With these two different methods for learning music, an outsider searching for verbal descriptions versus an insider learning from imitating, represent the essential differences between Rice's culture and the Bulgarian culture. These inherent musical differences blocked him from reaching the role of an insider. Not only is there the question of being on the outside while studying another culture, but also the question of how to go about studying one's own society. Nettl's approach would be to determine how the culture classifies their own music.[86] He is interested in the categories they would create to classify their own music. In this way, one would be able to distinguish themselves from the outsider while still having slight insider insight. Kingsbury believes it is impossible to study a music outside of one's culture, but what if that culture is your own?[87] One must be aware of the personal bias they may impose on the study of their own culture. Kingsbury, an American pianist and ethnomusicologist, decided to reverse the common paradigm of a Westerner performing fieldwork in a non-western context, and apply fieldwork techniques to a western subject. In 1988 he published Music, Talent, and Performance: A Conservatory Cultural System, which detailed his time studying an American northeastern conservatory. He approached the conservatory as if it were a foreign land, doing his best to disassociate his experiences and prior knowledge of American conservatory culture from his study. In the book, Kingsbury analyzes conservatory conventions he and his peers may have overlooked, such as the way announcements are disseminated, to make assertions about the conservatory's culture. For example, he concludes that the institutional structure of the conservatory is "strikingly decentralized."[88] In light of professors' absences, he questions the conservatory's commitment to certain classes. His analysis of the conservatory contains four main elements: a high premium on teachers' individuality, teachers' role as nodal points that reinforce a patron-client-like system of social organization, this subsequent organization's enforcement of the aural traditions of musical literacy, and the conflict between this client/patron structure and the school's "bureaucratic administrative structure."[89] Ultimately, it seems, Kingsbury thinks the conservatory system is inherently flawed. He emphasizes that he doesn't intend to "chide" the conservatory, but his critiques are nonetheless far from complimentary.[89] Another example of western ethnomusicologists studying their native environments comes from Craft's My Music: Explorations of Music in Daily Life. The book contains interviews from dozens of (mostly) Americans of all ages, genders, ethnicities, and backgrounds, who answered questions about the role of music in their lives. Each interviewee had their own unique, necessary, and deeply personal internal organization of their own music. Some cared about genre, others organized the music important to themselves by artist. Some considered music deeply important to them, some did not care about music at all.[90] |
21. インサイダー/アウトサイ
ダー認識論 民族音楽学の著作と実践におけるインサイダーとアウトサイダーの区別の妥当性と意味合いは、ブルーノ・ネトルやティモシー・ライスなどによって、何十年に もわたって長い議論の対象になってきた。このような議論を引き起こす問題は、民族音楽学者がアウトサイダーとして、自分たちのものではない文化を解剖する 場合、他の文化を研究する資格があるかということにある。歴史的に見れば、民族音楽学的な研究は、西洋人が自分たちの音楽の方が優れていると考える強いバ イアスに汚染されていた。この偏見から、自分たちの音楽が利用されたり流用されたりするのではないかと、民族音楽学者に研究を許可する文化に対する懸念が 発展していたのです。民族音楽学的研究には国際理解の促進という利点があるが、この「音楽的植民地主義」[77]への恐怖は、アウトサイダーの民族音楽学 者がインサイダーのコミュニティで研究を行うことへの反発を表している。 The Study of Ethnomusicology: ネットルは、『民族音楽学研究:31の課題と概念』の中で、フィールド研究者、特に西洋の学問的背景を持つ研究者に関わる個人的、世界的な問題を論じてい る。例えば,北部の平原でネイティブ・アメリカンを対象に行ったフィールド・レコーディングを回顧する章では,民族誌的フィールドワークの問題史と折り合 いをつけ,21世紀以降の実践のための将来の軌道を構想しようとしている。 [また、民族音楽学が社会科学やそれ以外の膨大な分野と交差する分野であることを考慮すると、人間を研究することに焦点を当て、社会心理学でよく知られて いるウィリアム・マクドゥーガルによって作られた言葉、「見慣れないものを、見慣れさせる」という問題に遭遇することは適切である[78]。社会心理学の ように、民族音楽学の仕事において「見慣れない」ものは3種類の方法で遭遇することになる。1)2つの異なる文化が接触し、両方の要素が他方に対してすぐ には説明できない、2)社会内の専門家が新しい知識を生み出し、それが一般大衆に伝達される、3)活発な少数派が自分たちの視点を多数派に伝達する [78]、などである。 ネットルは、主観的な理解が研究に与える影響についても言及している。彼は、フィールドワーカーは、完全な理解を得るために、外部の文化に没頭しようとす るかもしれないと述べています。しかし、これは研究者の目を曇らせ、研究内容を客観視する能力を奪うことになる。研究者は、ある文化圏の音楽の専門家であ るかのように錯覚してしまいますが、実際には、いくら研究しても、異なる文化圏の人間である以上、アウトサイダーであることに変わりはないのです。各人の 背景知識が研究の焦点に影響を与えるのは、その材料に対する快適さのレベルによるものです。ネットルはアウトサイダーの大半を「単に非西洋音楽を研究する 西洋社会のメンバー、あるいは貧しい人々の音楽を研究する豊かな国のメンバー、あるいは後背地の村々を訪れる都会の人々」と特徴づけている[79]。これ は、外国や異国の音楽を研究することがヨーロッパ中心主義に由来する可能性を指摘するものである。このアウトサイダー/インサイダーのダイナミズムと枠組 みの中で、不平等な力関係が焦点となり、疑問視されることになる。 アウトサイダーとインサイダーというレッテルに対する批判に加えて、ネットルは西洋と非西洋をほぼ等しくする二項対立を作り出している。彼は、複数の社会 の分析を通じて、西洋の考え方の欠点を指摘し、ネイティブの専門家の貢献を認めることに重点を置いて、共同作業の概念を推進している。彼は、「『インサイ ダー』と『アウトサイダー』による共同研究のアイデアは、溝を埋める方法として言及されてきた」と書いている[80]。彼の楽観論にもかかわらず、この実 践の実現は限られており、インサイダー/アウトサイダーのジレンマをどの程度解決できるかは疑問視されている。彼は、あらゆる概念は個人的な視点を通じて 研究されるが、「視点の比較は最も広い洞察を与えるかもしれない」[81]と考えている。 音楽文化を覗くアウトサイダーとしての民族音楽学者の立場は、サイードのオリエンタリズムの理論を用いて議論されてきた。これは、この分野によって支持さ れる音楽が、多くの点で植民地的な考え方の中に位置する「他者」についての想像またはロマンチックな見解に基づく西洋の構築物かもしれないという概念に現 れている[82]。 ネトルによれば、悪影響をもたらす内部関係者とホスト文化のメンバーの3つの信念が出現しているという。その3つとは次のようなものである。(1)「民族 音楽学者は、部外者の音楽が優れていることを示すために、非西洋の音楽や他の「他の」伝統を自分たちの音楽と比較しようとする」、(2)「民族音楽学者は 非西洋音楽に自分たちのアプローチを使いたがる」、(3)「アフリカやアジアやアメリカの先住民音楽というものがあるという前提で、ホストにとって明白な 境界線を無視してやってくる」。 「ネットルが主張するように、民族音楽学者はもはや様々な音楽を均質化し、全体化する特定の東洋主義的アプローチを実践していないため、これらの懸念のい くつかはもはや有効ではない。彼は、インサイダーという概念そのものを解体し、地理的、社会的、経済的要因によってアウトサイダーと区別されるものは何か を考えることによって、インサイダー/アウトサイダーの二分法におけるさらなる複雑さを探求している。彼は「より工業化されたアフリカやアジア諸国」の学 者たちが農村社会やコミュニティに関して自分たちをアウトサイダーと見なしていると指摘している[80]。これらの人々は少数派であり、民族音楽学とその 学問は一般的に西洋の視点から書かれているにもかかわらず、ネットルはネイティブを永遠の他者とし、アウトサイダーをデフォルトで西洋人として捉える考え 方に異議を唱えている[引用者註:1]。 ティモシー・ライスもまた、ブルガリアでの自身のフィールドワークと、ブルガリア音楽を学ぼうとするアウトサイダーとしての経験を通じて、インサイダー/ アウトサイダーの議論を詳細に論じている著者である。彼の著書『May it Fill Your Soul: Experiencing Bulgarian Music』[51]で語られている彼の経験では、彼の音楽の枠組みが西洋の視点に基づいていたため、ブルガリア音楽を学ぶのに困難があったとされてい る。ブルガリア音楽を十分に演奏できるようになるためには、「視野を広げて」[51]、ブルガリアの枠組みで音楽を学ぼうとしなければならなかったのであ る。彼は音楽を演奏できるようになったし、ブルガリアの人々も彼が非常によく学んだと言ったが、彼は「伝統の中にはまだ私の理解と説明を妨げている部分が ある(...)」と認めている。(中略)このギャップを埋めるためには、ある種の文化的に敏感な理解(...)が必要だろう」[83]と述べている。 最終的にライスは、自分の仕事を客観視することは不可能であるにもかかわらず、民族音楽学者は自己反省から多くを学ぶことができると論じている。著書の中 で彼は、芸術を理解し、議論する際に客観的でありうるかどうかを問い、現象学の哲学に従って、世界は既成の象徴によって構築されており、我々が生まれなが らにして持っている世界のいかなる「真の」理解も歪められているから、そのような客観性はありえない、と論じている。そして、民族音楽学者がある音楽を客 観的に理解することはできないし、民族音楽学者が外国の音楽を先住民が理解するのと同じように理解することもできないことを指摘する。つまり、アウトサイ ダーがインサイダーになることはありえない。しかし、民族音楽学者がその音楽を主観的に理解することは可能であり、それがその学者の外界に対する理解を形 成するのである。しかし、部外者であるライスは、自分が「言語と言語的認知カテゴリーを通じて理解が進んだ」のに対して、ブルガリアの器楽の伝統には「旋 律形式の言語的指標と記述子」が欠けており、「新しい学生はそれぞれ、言葉や視覚的補助なしにメロディを支配する抽象概念を一般化して自力で学習しなけれ ばならなかった」と指摘している[84]。 「このように、音楽を学ぶための2つの異なる方法、つまり、言葉による説明を求める部外者と模倣から学ぶ内部者というのは、ライスの文化とブルガリアの文 化との本質的な違いを表しているのである。このような音楽的な差異が、ライスがインサイダーとしての役割を果たすことを阻んでいた。 このように、ネトルはブルガリアの文化を学ぶ上で、「外から」だけでなく、「自国を」どう学ぶかという問題にも取り組んでいる。ネットルのアプローチは、 その文化が自分たちの音楽をどのように分類しているかを見極めることである[86]。彼は、自分たちの音楽を分類するために彼らが作るであろうカテゴリー に関心を持つ。このようにして、人はわずかなインサイダー的洞察を持ちつつも、アウトサイダーと自分とを区別することができるだろう。キングスベリーは自 分の文化の外にある音楽を研究することは不可能であると信じているが、その文化が自分のものであった場合はどうだろうか[87]。 アメリカのピアニストであり民族音楽学者であるキングスベリーは、西洋人が非西洋の文脈でフィールドワークを行うという一般的なパラダイムを逆手にとり、 西洋人の対象にフィールドワークの手法を適用することを決意した。1988年、彼は『音楽・才能・演奏』を出版した。1988年に出版した『音楽、才能、 演奏:音楽院の文化システム』では、アメリカ北東部の音楽院を研究していたときのことを詳しく紹介している。彼は、音楽院を異郷の地としてとらえ、自分の 経験やアメリカの音楽院文化に関する予備知識を切り離すことに全力を尽くした。この本でキングスベリーは、自分たちが見落としている音楽院の慣習、例えば 発表の仕方などを分析し、音楽院の文化について主張している。例えば、彼は音楽院の組織構造が「著しく分散化」していると結論づけ[88]、教授陣の不在 を考慮し、音楽院の特定のクラスへのコミットメントに疑問を呈している。彼の音楽院に対する分析は、教師の個性を重視すること、パトロンとクライアントの ような社会組織のシステムを強化する結節点としての教師の役割、この後続の組織による音楽的リテラシーの聴覚的伝統の強制、そしてこのクライアント/パト ロン構造と学校の「官僚的管理構造」との間の対立という4つの主要要素を含む[89]。最終的には、キングスベリは音楽院のシステムが本質的に欠陥がある と考えているようだ。彼は音楽院を「非難」するつもりはないと強調しているが、それでも彼の批評は褒め言葉とは程遠いものである[89]。 西洋の民族音楽学者が生まれ育った環境を研究しているもう一つの例は、クラフトの『マイ・ミュージック』からきている。日常生活における音楽の探求』 (Craft's My Music: Explorations of Music in Daily Life)。この本には、年齢、性別、民族、背景を問わず数十人の(主に)アメリカ人が、生活における音楽の役割についての質問に答えたインタビューが収 められている。インタビューに答えてくれた人たちはそれぞれ、自分たちの音楽について、ユニークで、必要で、深く個人的な内部組織を持っていました。ある 人はジャンルを気にし、ある人は自分にとって重要な音楽をアーティスト別に整理していました。ある者は音楽を自分にとって深く重要だと考え、ある者は音楽 に全く関心がなかった[90]。 |
| Applied Ethnomusicology Applied ethnomusicology uses music as a device to build bridges and create positive change in the world. “Today applied ethnomusicology is established as one of the strongest branches of ethnomusicology”. Jeff Titon thinks of ethnomusicology as the study of people making music, where applied ethnomusicology is “a music centered intervention into a particular community whose purpose is to benefit that community, for example a social improvement, a musical benefit, a cultural good, or an economic advantage.” [91] Applied ethnomusicology is people-focused and guided by ethical and humanitarian principles. The first time that the term applied ethnomusicology appeared in an official SEM publication was is 1964 when The Anthropology of Music [92] Alan Merriam wrote “The ultimate aim of the study of man involves the question of whether one is searching knowledge for its own sake or is attempting to provide solutions for practically applied problems.” The purpose of an applied ethnomusicology is the latter, knowledge for the sake of positive impact on humanitarian issues. Thus, a part of applied ethnomusicology is advocacy as opposed to solely participating as the observer. This includes working with a community to move social initiatives forward, and “acting as an intermediary between cultural insiders and outsiders”. [93] Applied ethnomusicology became widely known in the 1990s but many fieldworkers were practicing it long before the name was established. For example, David McAllester and Bruno Nettl’s fieldwork on Enemy Way music [94] is very much an example of applied ethnomusicology, where ethical values were closely considered and where the approach itself is comprehensive and designed to share understanding for the betterment of the Navajo nation. Here is an example of how applied ethnomusicology goes further than just considering music’s role within culture, but what music is “conceived to be” within a culture. [95] Clearly, a crucial part of applied ethnomusicology is fieldwork and the way in which fieldwork is conducted as well as the way the fieldworker speaks on and acts towards the subject matter post-fieldwork. In an interview David McAllester revealed how he saw his role after conducting fieldwork in the Navajo nation, “ And my experience, once I got among the Navajos, caused me to drop out of anthropology. I dropped the scientific point of view to a large extent, and I became…um, an advocate of the Navajos, rather than an objective viewer. And I was certainly among those in ethnomusicology who began to value the… the views of the people who make the music, more than the value of the trained scholars who were studying it.”[96] This is the essence of applied ethnomusicology, to find a to play in the research you conduct during and after conducting research. |
22. 応用民族音楽学 応用民族音楽学は、音楽を道具として、世界に橋をかけ、前向きな変化を起こすために使われる。「今日、応用民族音楽学は民族音楽学の最も強力な一部門とし て確立されている」。ジェフ・ティトンは民族音楽学を音楽を作る人々の研究であると考えており、応用民族音楽学は「音楽を中心に特定のコミュニティに介入 し、そのコミュニティ、例えば社会的改善、音楽的利益、文化的利益、経済的利益などの利益を目的とする」ものである[91]という。[91] 応用民族音楽学は人に焦点を当て、倫理的・人道的原則によって導かれるものである。応用音楽民族学という用語がSEMの公式出版物に初めて登場したのは、 1964年の『音楽の人類学』[92]アラン・メリアムが「人間の研究の究極の目的は、それ自身のために知識を探求しているのか、それとも実際に適用され る問題に対する解決策を提供しようとしているのかという問題を含んでいる」と書いた時であった。応用民族音楽学の目的は後者であり、人道的な問題に対して ポジティブな影響を与えるための知識である。したがって、応用民族音楽学の一部は、単にオブザーバーとして参加するのとは対照的に、アドボカシーである。 これには、社会的イニシアチブを前進させるためにコミュニティと協働することや、「文化的インサイダーとアウトサイダーの間の仲介者として行動する」こと が含まれる[93]。応用民族音楽学は1990年代に広く知られるようになったが、その名称が確立するずっと以前から多くのフィールドワーカーが実践して いた[93]。例えば、David McAllesterとBruno NettlによるEnemy Way音楽に関するフィールドワーク[94]はまさに応用民族音楽学の一例であり、倫理的価値が綿密に検討され、アプローチ自体が包括的でナバホ族の改善 のために理解を共有するように設計されている。これは、応用民族音楽学が、単に文化の中での音楽の役割を考えるだけでなく、文化の中で音楽が「どうあるべ きか」を考えている例である。明らかに、応用民族音楽学の重要な部分は、フィールドワークとフィールドワークの実施方法、そしてフィールドワーカーが フィールドワーク後に対象に対して語る方法と行動する方法である [95]。David McAllesterはインタビューの中で、ナバホ族でフィールドワークを行った後、自分の役割をどのように考えていたかを明らかにしている。科学的な視 点は捨て、客観的に見るのではなく、ナバホ族の擁護者になった。そして私は、民族音楽学において、音楽を研究している訓練された学者の価値よりも、音楽を 作っている人たちの見解に価値を置くようになった人たちの一人であることは確かである」[96] これは応用民族音楽学の本質で、研究中や研究した後に、自分が行う研究の中で果たすべき役割を見つけることなのである。 |
| Ethnomusicology and Western music Early in the history of the field of ethnomusicology, there was debate as to whether ethnomusicological work could be done on the music of Western society, or whether its focus was exclusively toward non-Western music. Some early scholars, such as Mantle Hood, argued that ethnomusicology had two potential focuses: the study of all non-European art music, and the study of the music found in a given geographical area.[97] However, even as early as the 1960s some ethnomusicologists were proposing that ethnomusicological methods should also be used to examine Western music. For instance, Alan Merriam, in a 1960 article, defines ethnomusicology not as the study of non-Western music, but as the study of music in culture.[9] In doing so he discards some of the 'external' focus proposed by the earlier (and contemporary) ethnomusicologists, who regarded non-Western music as more relevant to the attention of scholars. Moreover, he expands the definition from being centered on music to including the study of culture as well. Modern ethnomusicologists, for the most part, consider the field to apply to western music as well as non-western.[98] However, ethnomusicology, especially in the earlier years of the field, was still primarily focused on non-western cultures; it is only in recent years that ethnomusicological scholarship involved more diversity with respect to both the cultures being studied and the methods by which these cultures may be studied.[47] Ian Pace has discussed how questions regarding what exactly is within ethnomusicology's purview tend to be political rather than scholarly questions.[99] He also states that biases become readily apparent when examining how ethnomusicologists approach Western vs non-Western music.[99] Despite the increased acceptance of ethnomusicological examinations of Western music, modern ethnomusicologists still focus overwhelmingly on non-Western music. One of the few major examinations of Western art music from an ethnomusicological focus, as well as one of the earliest, is Henry Kingsbury's book Music, Talent, and Performance.[87] In his book, Kingsbury studies a conservatory in the north-eastern United States. His examination of the conservatory uses many of the traditional fieldwork methods of ethnomusicology; however, Kingsbury was studying a group which he is a member of.[87] Part of his approach was to think of his own culture as primitive and tribal to lend it a sense of 'otherness', upon which much of anthropology's theory is based (Kingsbury cites J.M. Weatherford's ethnography of US Congress[100] as the reason he chose this technique).[87] Bruno Nettl, when writing about signs and symbols, addressed symbolism in Western music culture.[101] He cites a specific example of a music analyst interpreting music Beethoven in a literal fashion according to various pieces of literature.[102] The analyst assigns direct meanings to motifs and melodies according to the literature. Nettl states that this reveals how members of Western music culture are inclined to view art music as symbolic.[103] Some ethnomusicological work focuses less on either Western or non-Western music specifically. For example, Martin Stokes' work regarding various aspects of identity addresses many cultures, both Western and non-Western.[104] Stokes wrote about gender as it relates to music in various cultures, including Western, analyzing the fairly common phenomena of musicians seemingly presiding over events that are often related to issues of gender, or how a culture may seek to "desex" musicians as a form of control.[105] The insights that Stokes makes are not exclusive to any culture. Stokes also dedicates much of his writing on identity, nationality, and location to how this manifests in Western music. He notes the presence of Irish music in migrant communities in England and American as a way in which individuals locate themselves in the world.[106] Because ethnomusicology is not limited to the study of music from non-Western cultures, it has the potential to encompass various approaches to the study of the many musics around the world and emphasize their different contexts and dimensions (cultural, social, material, cognitive, biological, etc.) beyond their isolated sound components. Thus, Western popular music is also subject to ethnomusicological interest. This ethnomusicological work has been called urban ethnomusicology.[107] Thomas Turino has written about the influence of the media on consumerism in Western society and that it is a bi-directional effect.[108] A large part of self-discovery and feeling accepted in social groups is related to common musical tastes. Record companies and producers of music recognize this reality and respond by catering to specific groups. In the same way that "sounds and imagery piped in over the radio and Internet and in videos shape adolescent sense of gendered selves as well as generational and more specific cohort identities," so do individuals shape the media's marketing responses to musical tastes in Western popular music culture. The culmination of identity groups (teenagers in particular) across the country represents a significant force that can shape the music industry based on what is being consumed. |
23. 民族音楽学と西洋音楽 民族音楽学の歴史の初期には、民族音楽学は西洋社会の音楽に対して行われるのか、それとも非西洋の音楽に対してのみ焦点が当てられるのかという議論があっ た。マントル・フッドのような初期の学者の中には、民族音楽学には2つの潜在的な焦点があると主張していた:すべての非ヨーロッパの芸術音楽の研究、そし て与えられた地理的な地域で見つけられた音楽の研究である[97]。 しかし、1960年代には早くも一部の民族音楽学者は民族音楽学の方法が西洋音楽を調べるためにも使われるべきであると提案していた。例えば、アラン・メ リアムは1960年の論文で民族音楽学を非西洋音楽の研究としてではなく、文化における音楽の研究として定義している[9]。その際、彼は非西洋音楽をよ り研究者の注意に値するものとして考えていた初期の(そして現代の)民族音楽学者によって提案された「外部」焦点をいくつか取り除いている。さらに、彼は その定義を音楽中心から文化研究にも拡大した。 現代の民族音楽学者は、ほとんどの場合、この分野が西洋音楽だけでなく非西洋音楽にも適用されると考えている[98]。しかし、民族音楽学は、特にこの分 野の初期には、まだ主に非西洋文化に焦点を当てていた。民族音楽学の研究は、研究されている文化とこれらの文化を研究することができる方法の両方に関し て、より多様性を伴うのは近年になってからである[47]。イアン・ペイスは、何が正確に民族音楽学の範囲内にあるのかという疑問が、学術的な疑問という よりもむしろ政治的な疑問となる傾向があることを論じている[99]。また、民族音楽学者が西洋音楽と非西洋音楽にどのようにアプローチするかを検討する と、その偏りが容易に明らかになると述べている[99]。 西洋音楽の民族音楽学的検証が受け入れられつつあるにもかかわらず、現代の民族音楽学者は依然として非西洋音楽に圧倒的に焦点を合わせている。西洋の芸術 音楽について民族音楽学的な視点から考察した数少ない主要な作品のひとつが、ヘンリー・キングスベリーの著書『音楽、才能、そして演奏』である[87]。 彼の音楽院の調査は民族音楽学の伝統的なフィールドワークの方法の多くを使用しているが、キングスベリーは彼自身がメンバーであるグループを研究していた [87]。彼のアプローチの一部は、人類学の理論の多くが基づいている「他者性」の感覚を貸すために彼自身の文化を原始的で部族のように考えることだった (キングスベリーはこの手法を選んだ理由としてJ・M・ウェザーフォードの米国議会の民族誌[100]を引用している)[87]。 ブルーノ・ネトルは記号とシンボルについて書く際に西洋音楽文化における象徴主義を取り上げた[101]。 彼は音楽分析家が様々な文献に従って音楽のベートーベンを文字通りに解釈する具体例を挙げている[102]。 分析家は文献に従ってモチーフとメロディに直接的な意味を付与しているのである。ネットルは、これは西洋の音楽文化のメンバーが芸術音楽を象徴的に見る傾 向があることを明らかにするものだと述べている[103]。 民族音楽学的な研究の中には、西洋音楽と非西洋音楽のどちらにもあまり焦点を当てないものもある。例えば、アイデンティティの様々な側面に関するマーティ ン・ストークスの研究は西洋と非西洋の両方の多くの文化を扱っている[104]。ストークスは西洋を含む様々な文化における音楽に関連するジェンダーにつ いて書き、しばしばジェンダーの問題に関連するイベントを音楽家が主宰しているように見えるかなり共通の現象や、文化がコントロールの形態として音楽家の 「脱俗」をいかに追求するかも分析する[105] ストークスの行う考察はどの文化に限定されるものではない. ストークスはまた、アイデンティティ、国籍、場所に関する著作の多くを、それが西洋音楽においてどのように現れるかに捧げている。彼はイギリスやアメリカ の移民コミュニティにおけるアイルランド音楽の存在を、個人が世界の中で自分自身を位置づけるための方法として指摘している[106]。 民族音楽学は非西洋文化圏の音楽の研究に限定されないため、世界中の多くの音楽を研究するための様々なアプローチを包含し、孤立した音の構成要素を超え て、その異なる文脈や次元(文化的、社会的、物質的、認知的、生物学的など)を強調する可能性を秘めている。したがって、西洋のポピュラー音楽も民族音楽 学的な興味の対象である。この民族音楽学的な作業は都市民族音楽学と呼ばれている[107]。 Thomas Turinoは、西洋社会における消費主義に対するメディアの影響について、それは双方向の効果であると書いている[108]。自己発見や社会集団に受け 入れられたと感じることの大部分は、共通の音楽の嗜好に関連している。レコード会社や音楽プロデューサーはこの現実を認識し、特定のグループに対応するこ とで対応している。ラジオやインターネットやビデオに流れる音やイメージが、思春期のジェンダーの自己認識や世代やより具体的な集団のアイデンティティを 形成する」のと同じように、個人は西洋ポピュラー音楽文化における音楽の好みに対するメディアのマーケティング反応を形成しているのである。全米のアイデ ンティティ・グループ(特にティーンエイジャー)の集大成は、消費されるものに基づいて音楽業界を形成しうる大きな力を示しているのである。 |
| Ethics Ethics is vital in the Ethnomusicology field because the product that comes out of fieldwork can be the result of the interaction between two cultures. Applying ethics to this field will confirm that each party is comfortable with the elements in the product and ensure that each party is compensated fairly for their contribution. To learn more about the monetary effects after a work is published, please see the copyright section of this page. Ethics is defined by Merriam-Webster as, "the principles of conduct governing an individual or a group."[109] In historical primary documents, there are accounts of interactions between two cultures. An example of this is Hernán Cortés' personal journal during his exploration of the world, and his interaction with the Aztecs. He takes note of every interaction as he is a proxy the Spanish monarchy. This interaction was not beneficial to both parties because Cortes as a soldier conquered the Aztecs and seized their wealth, goods, and property in an unjust manner.[110] Historically, interactions between two different cultures have not ended in both parties being uplifted. In fieldwork, the ethnomusicologist travels to a specific country with the intent to learn more about the culture, and while she is there, she will use her ethics to guide her in how she interacts with the indigenous people.[72] In the Society of Ethnomusicology, there is a committee on ethics that publishes the field's official Position Statement on Ethics. Because ethnomusicology has some fundamental values that stem from anthropology, some of the ethics in ethnomusicology parallel some ethics in anthropology as well. The American Anthropology Association have statements about ethics and anthropological research which can be paralleled to ethnomusicology's statement. Mark Slobin, a twentieth century ethnomusicologist, observes that discussion on ethics has been founded on several assumptions, namely that: 1) "Ethics is largely an issue for 'Western' scholars working in 'non-Western' societies"; 2) "Most ethical concerns arise from interpersonal relations between scholar and 'informant' as a consequence of fieldwork"; 3) "Ethics is situated within...the declared purpose of the researcher: the increase of knowledge in the ultimate service of human welfare." Which is a reference to Ralph Beals; and 4) "Discussion of ethical issues proceeds from values of Western culture." Slobin remarks that a more accurate statement might acknowledge that ethics vary across nations and cultures, and that the ethics from the cultures of both researcher and informant are in play in fieldwork settings.[48] Some case scenarios for ethically ambiguous situations that Slobin discusses include the following:[48] 1. The discovery of a rare musical instrument leads to the debate of whether it should be preserved in a museum or left in its native culture to be played, but not necessarily preserved. 2. The filming of a documentary video brings up the issues of consent from those who are being filmed. Additionally, the film should not necessarily be shown if the producer is not present to answer questions or clarify the video's content if there are questions from the audience. 3. Deciding how the monetary gains of a musical production should be distributed is a more prominent case of ethical concern. 4. Attaining partial permission in the field is usually not enough to justify filming or recording; every person in the group should consent to the presence of a recording device. 5. Whether truthful but possibly condemning information about a group is a situation that should be treated with extreme caution. Any information that could cause trouble for the musicians may need to be censored. Slobin's discussion of ethical issues in ethnomusicology was surprising in that he highlights the ethnomusicology community's apathy towards the public discussion of ethical issues, as evidenced by the lackluster response of scholars at a large 1970 SEM meeting. Slobin also points out a facet of ethical thinking among ethnomusicologists in that many of the ethical rules deal with Westerners studying in non-Western, third world countries. Any non-Western ethnomusicologists are immediately excluded from these rules, as are Westerner's studying Western music. He also highlights several prevalent issues in ethnomusicology by using hypothetical cases from an American Anthropological Association newsletter and framing them in terms of ethnomusicology. For example: "You bring a local musician, one of your informants, to the West on tour. He wants to perform pieces you feel inappropriately represent his tradition to Westerns, as the genre reinforces Western stereotypes about the musician's homeland... do you have the right to overrule the insider when he is on your territory?"[48] Ethnomusicologists also tend towards the discussion of ethics in sociological contexts. Timothy Taylor writes on the byproducts of cultural appropriation through music, arguing that the 20th century commodification of non-western musics serves to marginalize certain groups of musicians who are not traditionally integrated into the western music production and distribution industries.[111] Slobin also mentions cultural and musical appropriation, noting that there is an ethical concern with musical appropriation being portrayed as appreciation and the “long-term appropriation and profiteering of minority musics by the music industry.”[56] Steven Feld also argues that ethnomusicologists also have their place in analyzing the ethics of popular music collaboration, such as Paul Simon's work with traditional zydeco, Chicano, and South African beats on Graceland. He provides some evidence for Slobin's statement in his article, Notes on World Beat, as he notes that inherently imbalanced power dynamics within musical collaboration can contribute to cultural exploitation.[28] According to Feld’s article, it seems as though the party that is “appreciating” a type of music ultimately reaps more benefits, such as “economic rewards and artistic status,” than the party whose work is appropriated.[112] For example, The Rolling Stones paid homage to Muddy Waters by “utilizing many aspects of [the] original recorded performance style from the 1950’s” and claimed that the cover version brought “free” publicity to the Muddy Waters.[113] However, as Feld mentions, this statement is an arrogant one, since it implies that “it takes a recording by The Rolling Stones to bring recognition to the artistic contributions of a Muddy Waters.”[112] Feld’s question of how to “measure appropriation of original creative product” when there is always a “lesser trickle down of economic payback” remains unanswered.[112] Another ethical issue that Feld brings up is the power dynamics within record companies. The companies themselves make the most money and major contract artists can produce their own work and “tak[e] economic/artistic risks commensurate with their sales.”[114] On the other hand, the musicians, who play the role of “wage laborers” as well as “bearers and developers of musical traditions and idioms,” gain the least and have the most to lose, since they offer their labor and aspects of their culture in the hopes that “royalty percentages, spinoff jobs, tours, and recording contracts might follow from the exposure and success of records.”[115] When talking about ethics in ethnomusicology it is imperative that I remain specific about who it applies to. An ethnomusicologist must consider ethics if he comes from a culture that is different from the culture that he wants to conduct his research on. An ethnomusicologist that conducts research on a culture that is their own may not have to weigh ethics. For example, music scholar, Kofi Agawu writes about African music and all of its significant aspects. He mentions the dynamics of music among the generations, the significance of the music, and the effects of the music on the society. Agawu highlights that some scholars glaze over the spirit of African music and argues that this is problematic because the spirit is one of the most essential components in the music. Agawu is also a scholar from Africa, more specifically Ghana, so he knows more about the culture because he is a part of that culture. Being a native of the culture that one is studying is beneficial because of the instinctive insight that one has been taught since birth.[116] However, a native fieldworker may experience a slight ethical dilemma as they research their own community, given that there are concerns that “arise from interpersonal relations between scholar and ‘informant’ as a consequence of fieldwork.”[117] According to Clint Bracknell, who studies Aboriginal song traditions of Nyungar and happens to have grown up there as well, Indigenous researchers can “use ethnomusicology as a platform” to “engage with, learn, and invigorate their own regional music traditions, particularly those that are presently endangered and under-researched” in order to “contribute to the diversity of music studied, supported, and sustained worldwide."[118] However, they also risk “expos[ing] the vital organs of their culture” as well as the “outsider” misinterpreting their culture.[119] If the native fieldworker’s community does not want them to reveal or record their cultural practices, the fieldworker experiences the dilemma of how much they can reveal in the face of a “cultural grey out” without crossing the line.[120] The fieldworker must consider whether or not they can maintain the musical diversity worldwide while simultaneously respecting their community's wishes. Martin Rudoy Scherzinger, another twentieth-century ethnomusicologist, contests the claim that copyright law is inherently conducive to exploitation of non-Westerners by Western musicologists for a variety of reasons some of which he quotes from other esteemed ethnomusicologists: some non-Western pieces are uncopyrightable because they are orally passed down, some "sacred songs are issued forth by ancient spirits or gods" giving them no other to obtain copyright, and the concept of copyright may only be relevant in "commercially oriented societies". Furthermore, the very notion of originality (in the West especially) is a quagmire in and of itself. Scherzinger also brought several issues to the forefront that also arise with metaphysical interpretations of authorial autonomy because of his idea that Western aesthetical interpretation is not different than non-Western interpretation. That is, all music is "for the good of mankind" yet the law treats it differently.[121] |
24. 倫理(民族音楽学と倫理) 民族音楽学の分野では、フィールドワークの成果物が2つの文化の相互作用の結果であることがあるため、倫理観が不可欠となる。この分野に倫理を適用するこ とで、各当事者が製品に含まれる要素に納得し、各当事者がその貢献に対して公正に補償されることを確認することができる。作品発表後の金銭的な影響につい ては、本ページの著作権の項をみよ。 倫理はMerriam-Websterによって「個人またはグループを支配する行動原則」と定義される[109]。歴史的な一次資料には、2つの文化間の 相互作用の記述がある。この例として、エルナン・コルテスが世界を探検し、アステカ族と交流しているときの個人的な日記がある。彼はスペイン王朝の代理人 として、あらゆる交流を記録している。この交流は、コルテスが軍人としてアステカを征服し、その富、財、財産を不当な方法で奪ったため、双方にとって有益 ではなかった[110]。歴史的に見ても、二つの異なる文化の交流は、双方が高揚することでは終わらないのである。フィールドワークでは、民族音楽学者は その文化についてより深く知ることを意図して特定の国を訪れ、そこにいる間、先住民との関わり方において倫理を指針として用いることになる[72]。 民族音楽学会には倫理委員会があり、倫理に関する公式見解を公表している。民族音楽学には人類学に由来する基本的な価値観があるため、民族音楽学の倫理は 人類学の倫理と類似している部分がある。アメリカ人類学会の倫理と人類学的研究についての声明は、民族音楽学の声明と類似している。 20世紀の民族音楽学者であるマーク・スロービンは、倫理に関する議論がいくつかの前提の上に成り立っていることを指摘している。1)「倫理は、主に『非 西洋』社会で活動する『西洋』学者の問題である」、2)「倫理的懸念のほとんどは、フィールドワークの結果として学者と『情報提供者』の間の対人関係から 生じる」、3)「倫理は、研究者の宣言した目的(人類の福祉への究極の貢献としての知識の増加)の中に位置づけられる」。これはラルフ・ビールズへの言及 である、そして4)"倫理的問題の議論は西洋文化の価値観から進む"。スロビンは、より正確な声明は、倫理が国や文化によって異なること、そして研究者と 情報提供者の両方の文化からの倫理がフィールドワークの設定に作用していることを認めるかもしれないと述べている[48]。 スロビンが論じている倫理的に曖昧な状況のケースシナリオには、次のようなものがある[48]。 1. 珍しい楽器の発見により、その楽器を博物館に保存すべきか、それともその文化圏に残して演奏させるべきかという議論が起こるが、必ずしも保存する必要はな い。 2. ドキュメンタリービデオの撮影は、撮影される側の同意の問題を提起する。さらに、観客から質問があった場合、プロデューサーが質問に答えたり、ビデオの内 容を明らかにするために同席しない場合、必ずしも上映すべきではない。 3. 音楽制作の金銭的利益の分配方法を決定することは、より顕著な倫理的懸念のあるケースである。 4. 4.撮影や録音を正当化するには、現場で一部の許可を得るだけでは不十分で、グループ内の全員が録音装置の存在に同意する必要があります。 5. 5.あるグループに関する真実であるが非難される可能性のある情報は、細心の注意を払って扱われるべき状況である。ミュージシャンに迷惑をかける可能性の ある情報は、検閲する必要があるかもしれません。 民族音楽学の倫理的問題についてのスロビンの議論は、1970年の大規模なSEM会議での学者たちの冴えない反応に見られるように、倫理的問題の公開討論 に対する民族音楽学コミュニティの無関心を強調している点で驚くべきものであった。 また、Slobinは民族音楽学者の倫理的思考の一面として、倫理規則の多くが非西洋、第三世界の国々で学ぶ西洋人について扱っていることを指摘してい る。西洋人以外の民族音楽学者は、西洋音楽を研究する西洋人と同様、これらの規則から即座に排除される。 また、アメリカ人類学会のニュースレターに掲載された仮想の事例を使い、民族音楽学の観点で枠をはめ、民族音楽学に蔓延するいくつかの問題を浮き彫りにし ている。例えば 「あなたは、情報提供者の一人である地元の音楽家を、ツアーで西洋に連れてきました。そのジャンルは、その音楽家の故郷に対する西洋の固定観念を強化する ものであるため、西洋人に対してその伝統を不適切に表現しているとあなたが感じる曲を、彼は演奏したがっている...あなたは、彼があなたの領土にいると きに、内部の人間を覆す権利があるだろうか? 民族音楽学者もまた、社会学的な文脈で倫理を論じる傾向がある。ティモシー・テイラーは音楽を通しての文化的流用の副産物について書いており、20世紀に おける非西洋音楽の商品化は、西洋の音楽生産と流通産業に伝統的に組み込まれていない特定のグループの音楽家を疎外するのに役立つと論じている [111]。 [また、スロビンは文化的・音楽的流用についても言及し、音楽的流用が鑑賞として描かれることや「音楽産業によるマイノリティ音楽の長期的流用と利益供 与」に対する倫理的懸念があると指摘している[56]。スティーブンフェルドも民族音楽学者は、ポールサイモンの「グレースランド」におけるザイデコ、チ カーノ、南アフリカの伝統音楽と連携する作業のような大衆音楽の連携の倫理分析にも位置づけられると論じている。彼は自身の論文『Notes on World Beat』において、音楽的コラボレーションにおける本質的に不均衡なパワー・ダイナミクスが文化的搾取を助長しうることを指摘し、スロビンの発言にいく つかの根拠を示している[28] フェルドの論文によれば、あるタイプの音楽を「鑑賞」している側が、その作品を流用された側よりも「経済的報酬や芸術的地位」といった利益を最終的に得て いるように見えるのである。 [例えば、ローリング・ストーンズはマディ・ウォーターズにオマージュを捧げ、「1950年代に録音されたオリジナルの演奏スタイルの多くの側面を利用」 し、そのカバー版はマディ・ウォーターズに「無料の」宣伝効果をもたらしたと主張している[112]。 [しかし、フェルドが言及するように、この発言は「マディ・ウォーターズの芸術的貢献に対する認識をもたらすにはローリング・ストーンズの録音が必要だ」 ということを暗示しており、傲慢なものである[112]。フェルドが提起するもうひとつの倫理的問題は、レコード会社内のパワー・ダイナミクスの問題であ る[112]。会社自身が最も金を稼ぎ、主要な契約アーティストは自らの作品を制作し、「売り上げに見合った経済的/芸術的リスクを取ることができる」 [114]。他方、「賃金労働者」であると同時に「音楽の伝統とイディオムの担い手と開発者」としての役割を果たしている音楽家は、「印税率、スピンオフ 的仕事、ツアー、レコードの露出と成功から得られるかもしれない」という期待から彼らの労働と文化の側面とを提供するので、最も得られず失うものも多いの である[115]。 民族音楽学の倫理について語るとき、それが誰に適用されるかを具体的にしておくことが肝要である。民族音楽学者は、自分が研究を行いたい文化とは異なる文 化の出身である場合、倫理を考慮しなければならない。自分の国の文化について研究する民族音楽学者は、倫理を考慮する必要はないかもしれません。例えば、 音楽学者のKofi Agawuは、アフリカの音楽とその重要な側面すべてについて書いている。彼は、世代間の音楽の力学、音楽の意義、社会に対する音楽の影響について言及し ている。アガウは、アフリカ音楽の精神を軽視する学者がいることを指摘し、精神は音楽にとって最も重要な要素の一つであるため、これは問題であると論じて いる。アガウはアフリカ、特にガーナ出身の学者であり、その文化の一部であるため、その文化についてより深く知っている。しかし、「フィールドワークの結 果として学者と『情報提供者』の間の対人関係から生じる懸念」があることから、ネイティブのフィールドワーカーは自分たちのコミュニティを調査する際に、 若干の倫理的ジレンマを経験するかもしれない[116]。 先住民の歌の伝統を研究しているクリント・ブラックネルは、ニョンガーで育ったこともあり、先住民研究者は「民族音楽学をプラットフォームとして使用」 し、「自分たちの地域の音楽伝統、特に現在絶滅の危機にあり、研究されていない伝統に関わり、学び、活性化」し、「世界中で研究、支援、維持されている音 楽の多様性に貢献することができます」と述べている [117] 。 「しかし、彼らは「自分たちの文化の重要な器官をさらけ出す」だけでなく、「外部の人間」が自分たちの文化を誤解するリスクも抱えている」[119]。ネ イティブのフィールドワーカーのコミュニティが彼らの文化習慣を明らかにしたり記録することを望まない場合、フィールドワーカーは「文化のグレーアウト」 に直面しながらも、どれだけ境界を越えずに明らかにできるのかというジレンマに直面する。 120] フィールドワーカーはコミュニティの希望を尊重しながら同時に世界の音楽の多様性を維持できるのか検討しなければならない。 もう一人の20世紀の民族音楽学者であるマーティン・ルドイ・シェルジンガーは、著作権法が西洋の音楽学者による非西洋人の搾取を本質的に助長するという 主張に対して、他の著名な民族音楽学者から引用した様々な理由から反論している。非西洋の楽曲の中には口承で伝えられているために著作権が発生しないもの もあり、「神聖な歌は古代の霊や神によって発せられる」ために著作権を得る以外にない、また著作権の概念は「商業指向社会」でしか意味をなさないかもしれ ない、などだ。さらに、(特に西洋では)オリジナリティという概念自体が泥沼である。また、シャジンガーは、西洋の美学的解釈は非西洋の解釈と変わらない という考えから、著作者の自律性に関する形而上学的解釈でも生じるいくつかの問題を前面に押し出している。つまり、全ての音楽は「人類のために」あるにも かかわらず、法はそれを異なるものとして扱っているのである[121]。 |
| Gender Gender concerns have more recently risen to prominence in the methodology of ethnomusicology. Modern researchers often criticize historical works of ethnomusicology as showing gender-biased research and androcentric theoretical models that do not reflect reality. There are many reasons for this issue. Historically, ethnomusicological fieldwork often focused on the musical contributions of men, in line with the underlying assumption that male-dominated musical practices were reflective of musical systems of a society as a whole. Other gender-biased research may have been attributed to the difficulty in acquiring information on female performers without infringing upon cultural norms that may not have accepted or allowed women to perform in public (reflective of social dynamics in societies where men dominate public life and women are mostly confined to the private sphere.[122]). Finally, men have traditionally dominated fieldwork and institutional leadership positions and tended to prioritize the experiences of men in the cultures they studied.[123] With a lack of accessible female informants and alternative forms of collecting and analyzing musical data, ethnomusicological researchers such as Ellen Koskoff believe that we may not be able to fully understand the musical culture of a society. Ellen Koskoff quotes Rayna Reiter, saying that bridging this gap would explain the "seeming contradiction and internal workings of a system for which we have only half the pieces."[123] Women contributed extensively to ethnomusicological fieldwork from the 1950s onward, but women's and gender studies in ethnomusicology took off in the 1970s.[124] Ellen Koskoff articulates three stages in women's studies within ethnomusicology: first, a corrective approach that filled in the basic gaps in our knowledge of women's contributions to music and culture; second, a discussion of the relationships between women and men as expressed through music; third, integrating the study of sexuality, performance studies, semiotics, and other diverse forms of meaning-making.[124] Since the 1990s, ethnomusicologists have begun to consider the role of the fieldworker's identity, including gender and sexuality, in how they interpret the music of other cultures. Until the emergence of notions like feminist ethnomusicology in late 1980s (which derived its momentum from Third Wave feminism), women within ethnomusicology were limited to serve as interpreters of content created and recorded by men.[125] Despite the historical trend of overlooking gender, modern ethnomusicologists believe that studying gender can provide a useful lens to understand the musical practices of a society. Considering the divisions of gender roles in society, ethnomusicologist Ellen Koskoff writes: "Many societies similarly divide musical activity into two spheres that are consistent with other symbolic dualisms", including such culture-specific, gender-based dualisms as private/public, feelings/actions, and sordid (provocative)/holy.[126] In some cultures, music comes to reflect those divisions in such a way that women's music and instrumentation is viewed as "non-music" as opposed to men's "music".[127] These and other dualities of musical behavior can help demonstrate societal views of gender, whether the musical behavior supports or subverts gender roles. In her analysis, Koskoff pinpoints a way in which this "symbolic dualism" manifests itself literally: the relationship between the form or shape of one's instrument and the player's gender identity; Koskoff's research demonstrates that often, "the life-giving roles of either sex are seen or reproduced in their shape or playing motion."[127] Moving outside the analytical scope of gender and adopting a more intersectional lens, Koskoff also remarks on how female musical behavior is affiliated with heightened sexuality, with numerous different cultures holding similar yet unique criteria of eroticized dance movements (e.g. "among the Swahili...all-female gathering where young women do hip-rotations to learn the 'right' sexual movements).[126] It is here where Koskoff integrates notions of the private vs. public sphere, examining how in certain cultures, female musical performance is not only linked to notions of heightened female sexuality, it is also associated with "implied or real prostitution,[128]" thus insinuating a potential class hierarchy differentiating the society subcultures surrounding private vs. public female musical performance. The tendency for public music performed by single women of child-bearing age to be associated with sex,[129] while performances by older or married women tends to downplay or even deny their sexuality,[130] suggests not only that music performance is linked to societal perception of a woman’s sexual viability decreasing with age or marriage, but also that female sexuality is often necessarily included in the expression of a feminine gender through musical performance. The cloistering and separation of women’s music actually offer a way for women to relate to one another or to understand and express their gender identity through musical practice within a more women-centric space.[127] The private, intimate nature of some women’s music can also lead to secret protest behavior when that music is brought into the public sphere. Koskoff indicates that secret symbolic behavior and language coded into women’s performance may communicate private messages to other women in the community, allowing these performers to speak out against an unwanted marriage, mock a possible suitor, or even express homosexuality without the male audience catching on.[131] As such, music performance may confirm and maintain these gender inequalities and social/sexual dynamics, may protest norms as it maintains them, or it may actually challenge and threaten the established order.[132] One example of musical performance traditions that confirm social/sexual dynamics may be the trend of prioritizing a female musician’s physical appeal over her technical musical skill when judging her performance, which shows a devaluation of female musical expression in favor of objectification of the feminine physicality through the public gaze.[127] Koskoff recalls that women musicians who do manage to become popular in mainstream culture may start to take on masculine-coded musical qualities, even if it was their expression of femininity through performance that initially elicited their acclaim.[133] Since Koskoff’s book was published, contemporary ethnomusicologists have continued to study the practices and dynamics she cites in more detail. In “Sounds of Power: An Overview of Musical Instruments and Gender”, Veronica Doubleday extends the examination of feminine gender expression in music performance to the use of specific musical instruments. She reiterates that in patriarchal societies, the role of a man in a marriage tends to be one of ownership and control, while a married woman often takes on a position of submission and subordination. As such, Doubleday suggests that when constructing a relationship with their instruments, men may incorporate their cultural expectation of dominance, whereas women may be unlikely to take power over an instrument in the same way.[134] If the physical allure of a female musician takes priority over her technique, female gender expression through music performance may be confined to that which upholds traditional notions of female beauty and objectification. Doubleday relates this to the distinction of “suitable” instruments for women as those that require no physical exertions that may disrupt the graceful portrait of the woman, or instruments that take an accompaniment role to the performer’s singing.[135] Exploring more modern musical traditions, ethnomusicologist Gibb Schreffler recounts the role of Punjabi women in music in the context of migration in “Migration Shaping Media: Punjabi Popular Music in a Global Historical Perspective”. As women are often the bearers of tradition in Punjabi culture, they hold important roles in many traditional Punjabi rituals, including those that involve music, which help enable emigrants to maintain Punjabi culture wherever they are.[136] Schreffler also notes that as a result of migration, bhangra music has enabled the reformation of traditional gender roles in the public sphere through the performance of music: “In creating a ‘dance floor,’ women were allowed to mingle with men in ways they had not done before”.[137] Similarly, in “Music and the Negotiation of Orthodox Jewish Gender Roles in Partnership ‘Minyanim’”, a study of gender dynamics within Orthodox Jewish culture as disrupted by minyanim partner dance, Dr. Gordon Dale documents how partnership minyanim dance may actively reinterpret Orthodox Jewish religious law in establishing a new context for women's performance.[138] The grounding of a new female music performance tradition in religion is particularly noteworthy considering the ways in which women are often excluded from religious music, both in the Orthodox Jewish consideration of female singing as inappropriate or weaponized sexual behavior that conflicts with expectations of modesty,[139] and across diverse cultural spheres, as shown in Hagedorn’s example of the batá drum.[138] In this instance, feminine musical expression becomes a highly political issue, with right-wing Orthodox men insisting it was impossible for a man to hear a woman singing without experiencing it as a sexual act, and male partnership minyan participants concluding instead that certain considerations of modesty were not applicable in the context of their prayer.[140] Therefore, a woman’s singing voice could also be considered a sound of gender liberation against Orthodox power structures.[139] Dale explains that while religious women's music initiatives from other cultures such as Indonesian women chanting from the Qur’an as described by Anne Rasmussen, this type of partnership mynamin requires Orthodoxy to actually create a new religious space in which “men and women can express their religious and feminist values side by side”.[140] Though restrictions on the availability of female roles in worship mean that minyamin must focus more on gender-based partnership than on explicit equality, partnership minyamin still forge a unique musical prayer space in Jewish culture that listens to and encourages women’s voices.[140] He describes one interaction with an older woman who was personally uncomfortable leading religious worship, but greatly appreciated observing other women in that role. Simply singing alongside women in an unrestrained manner served as a comfortable and fulfilling way for her to practice feminism.[141] There is much room for additional study on the expression of gender through musical performance, including the ways that musical performance can disrupt binary delineations of gender identity and promote the expression of transgender and/or non-binary genders. Koskoff briefly acknowledges that it is possible for performers to “cross over into opposite gender domains, displaying behaviors normally associated with the opposite sex”, which has greater implications for the way that music performance enables the performance of gender identity.[130] As a result of these new considerations from within the field, efforts to better document and preserve women's contributions to ethnomusicology have increased. With a particular focus on collecting ethnomusicological works (as well as literature from related fields) that address gender inequities within musical performance as well as musical analysis, feminist musicologists Bowers and Bareis published the Biography on Music and Gender – Women in Music,[142] which is arguably the most comprehensive collection compiling ethnomusicological literature meeting this analytical criteria. Although it is not an ethnomusicological book, another Susan McClary's watershed book Feminine Endings (1991) shows "relationships between musical structure and socio-cultural values" and has influenced ethnomusicologists perception of gender and sexuality within the discipline itself.[143] There is a general understanding that Western conceptions of gender, sexuality, and other social constructions do not necessarily apply to other cultures and that a predominantly Western lens can cause various methodological issues for researchers.[144] The concept of gender in ethnomusicology is also tied to the idea of reflexive ethnography, in which researchers critically consider their own identities in relation to the societies and people they are studying. For example, Katherine Hagedorn uses this technique in Divine Utterances: The Performance of Afro-Cuban Santeria.[145] Throughout her description of her fieldwork in Cuba, Hagedorn remarks how her positionality, through her whiteness, femaleness, and foreignness, afforded her luxuries out of reach of her Cuban counterparts, and how the magnitude of difference in her experience and existence in Cuba was exacerbated by Cuba's economic turmoil after the fall of the Soviet Union during the Cuban Revolution. Her positionality also put her in an "outsider" perspective on Cuban culture and affected her ability to access the culture as a researcher on Santeria. Her whiteness and foreignness, she writes, allowed her to circumvent intimate inter-gender relations centered around performance using the bata drum. Unlike her Cuban female counterparts who faced stigma, she was able to learn to play the bata and thus formulate her research.[145] Today, the society for ethnomusicology is actively dedicating itself to increasing the presence and stature of gender/sexuality/LGBTQ/feminist scholarship within our respective music societies through forums like The Gender and Sexualities Taskforce within the society for ethnomusicology.[146] The society for ethnomusicology has additionally established awards to celebrate work and research conducted within this intersectional subfield of ethnomusicology. Specifically, the society of ethnomusicology developed the Marcia Herndon Prize,[147] which was created to honor exceptional ethnomusicological work in gender and sexuality including, but not limited to, works that focus upon lesbian, gay, bisexual, two-spirited, homosexual, transgendered and multiple gender issues and communities, as well as to commemorate the deeply influential contributions of Herndon to the field in these arenas. Specifically, Herndon is championed for co-editing Music, Gender, and Culture,[148] a collection of fifteen essays (all authored by women) inspired by the Heidelberg meeting of the Music and Gender Study Group of the International Council for Traditional Music,[149] making key comparisons between the philosophies and behaviors between male and female ethnomusicologists and musicians. This work has prompted a great deal of dialogue among ethnomusicologists and scholars of related fields, including Virginia Giglio, Ph.D., who reviewed Herndon's seminal work, identifying central themes of spirituality, female empowerment, and culturally-defined gender-related duties as specific areas for further exploration among modern feminist ethnomusicologists[150] |
25. ジェンダー(民族音楽学とジェンダー) ジェンダーの問題は、近年、民族音楽学の方法論において顕著になってきている。現代の研究者はしばしば、民族音楽学の歴史的著作を、ジェンダーに偏った研 究、現実を反映しないアンドロセントリックな理論モデルを示していると批判する。この問題には多くの理由がある。歴史的には、民族音楽学のフィールドワー クは、男性の音楽的貢献に焦点を当てることが多く、これは男性優位の音楽的実践が社会全体の音楽システムを反映しているという根本的な前提に沿ったもので あった。また、ジェンダーに偏った研究は、女性が公の場で演奏することを認めない文化的規範に抵触することなく女性演奏家の情報を得ることが困難であった ことが原因かもしれない(男性が公的生活を支配し、女性はほとんど私的領域に閉じ込められている社会力学の反映[122])。最後に、伝統的に男性が フィールドワークと組織の指導的立場を支配し、研究対象の文化における男性の経験を優先する傾向がある[123]。アクセス可能な女性インフォーマントや 音楽データの収集と分析の代替形態が不足しているため、エレン・コスコフなどの民族音楽学研究者は、ある社会の音楽文化を完全に理解することはできないか もしれないと考えている。エレン・コスコフはレイナ・レイターの言葉を引用し、このギャップを埋めることで「我々が半分のピースしか持っていないシステム の一見した矛盾と内部の仕組み」を説明することができると述べている[123]。 1950年代以降、女性は民族音楽学のフィールドワークに広く貢献してきたが、民族音楽学における女性研究およびジェンダー研究は1970年代に本格化し た[124]。 エレン・コスコフは、民族音楽学における女性研究の3つの段階を明示している。第一に、音楽と文化に対する女性の貢献に関する我々の知識における基本的な ギャップを埋める修正的アプローチ、第二に、音楽を通じて表現される女性と男性の関係についての議論、第三に、セクシュアリティ、パフォーマンス研究、記 号論、その他の多様な意味形成の形態の研究を統合している[124]。 1990年代以降、民族音楽学者は、他の文化の音楽をどのように解釈するかについて、ジェンダーやセクシュアリティを含むフィールドワーカーのアイデン ティティの役割を考慮するようになった[124]。1980年代後半にフェミニスト民族音楽学のような概念(それは第三波フェミニズムから勢いを得た)が 出現するまでは、民族音楽学の中の女性は男性によって作られ記録された内容の解釈者として奉仕することに制限されていた[125]。 ジェンダーを見過ごす歴史的傾向にもかかわらず、現代の民族音楽学者はジェンダーを研究することが社会の音楽的実践を理解するために有用なレンズを提供で きると考えている。社会におけるジェンダーの役割分担を考慮し、民族音楽学者エレン・コスコフは「多くの社会は同様に音楽活動を他の象徴的二元論と一致す る2つの領域に分ける」、例えば、プライベート/パブリック、感情/行動、卑劣(挑発)/神聖といった文化特有の、ジェンダーに基づく二元論を含んでいる [126]と書いている。 [126] ある文化では、女性の音楽や楽器演奏が男性の「音楽」に対して「非音楽」とみなされるように、音楽がこれらの区分を反映するようになる [127] 音楽行動のこれらや他の二元性は、音楽行動がジェンダーロールを支持するか覆すかに関わらず、ジェンダーに対する社会的見解を示すのに役立つことがある。 コスコフの分析では、この「象徴的二元論」が文字通りに現れる方法として、楽器の形やフォルムと演奏者のジェンダー・アイデンティティとの関係を挙げてい る。コスコフの研究は、しばしば「男女どちらかの命を与える役割がその形や演奏動作に見られる、あるいは再現される」ことを実証している[127]。 また、ジェンダーの分析範囲から外れ、より交差的なレンズを採用することで、コスコフは、女性の音楽的な振る舞いがいかに高いセクシュアリティと結びつい ているかを指摘し、多数の異なる文化がエロティックなダンスの動きについて類似していながらも独自の基準を持っている(例:「スワヒリ族の間で」)。 コスコフはここで私的対公的領域の概念を統合し、ある文化において女性の音楽演奏がいかに女性のセクシュアリティの高まりの概念と結びついているかだけで なく、「暗黙の、あるいは実際の売春[128]」とも結びついていることを検証し、私的対公的女性の音楽演奏を取り巻く社会のサブカルチャーを差別化する 潜在的階層をほのめかしているのである。 出産適齢期の独身女性によって演奏される公共の音楽がセックスと関連づけられる傾向がある一方で[129]、高齢あるいは既婚女性による演奏はセクシュア リティを軽視あるいは否定する傾向さえあることから[130]、音楽演奏が女性の性的生存能力が年齢あるいは結婚によって低下するという社会的認識と結び ついているだけでなく、音楽演奏を通じて女性のジェンダーを表現するのに、必ずしも性的能力が含まれていることが多いことが示唆されている。女性音楽の隠 蔽と分離は、実際には女性同士が関係し、より女性中心の空間の中で音楽的実践を通して自分のジェンダー・アイデンティティを理解し表現する方法を提供する [127]。いくつかの女性音楽のプライベートで親密な性質は、その音楽が公共圏にもたらされたときに秘密の抗議行動につながる可能性もある。コスコフ は、女性の演奏にコード化された秘密の象徴的行動や言語がコミュニティの他の女性にプライベートなメッセージを伝え、これらの演奏者が男性の観客に気づか れることなく望まない結婚に反対を表明し、求婚者をあざ笑い、同性愛を表現することさえ可能にすると示している[131]。 そのように、音楽パフォーマンスはこれらのジェンダー不平等や社会/性的ダイナミクスを確認し維持するかもしれないが、維持しながら規範に抗議し、実際に 既存の秩序に挑戦し脅かすこともあるのである[132]。 [132]社会的/性的ダイナミクスを確認する音楽演奏の伝統の一例は、女性ミュージシャンの演奏を判断する際に技術的な音楽スキルよりも身体的な魅力を 優先させるという傾向かもしれない。コスコフは、主流文化において人気を得ることができた女性ミュージシャンは、最初に彼らの賞賛を引き出したのが演奏を 通しての女性らしさの表現だったとしても、男性的にコードされた音楽の性質を持ち始めることがあると回想している[133]。 コスコフの著書が出版されて以来、現代の民族音楽学者たちは、彼女が挙げた実践とダイナミクスをより詳細に研究し続けている。Sound of Power: Veronica Doubledayは、"An Overview of Musical Instruments and Gender "の中で、音楽演奏における女性的なジェンダー表現に関する考察を、特定の楽器の使い方まで広げている。家父長制の社会では、結婚における男性の役割は所 有と支配であることが多く、結婚した女性はしばしば服従と従属の立場をとることを彼女は再確認している。そのため、楽器との関係を構築するとき、男性は文 化的な支配の期待を取り入れるかもしれないが、女性は同じように楽器を支配する可能性は低いかもしれない[134]。女性音楽家の身体的魅力が技術よりも 優先されると、音楽演奏による女性のジェンダー表現は、女性の美と対象化に関する伝統的概念を支持するものにとどまる可能性がある。ダブルデイによれば、 女性にとって「ふさわしい」楽器とは、女性の優美な肖像を崩すような肉体的労力を必要としない楽器、もしくは演奏者の歌の伴奏の役割を担う楽器という区別 である[135]。より現代の音楽伝統を探求する民俗音楽学者ギブ・シュレフラーは、移民の文脈での音楽におけるパンジャビ女性の役割を 「Migration Shaping Media: Migration Shaping Media: Punjabi Popular Music in a Global Historical Perspective "の中で、民族音楽学者ギブ・シュレフラー(Gibb Schreffler)は、移民の文脈におけるパンジャブ人女性の音楽の役割について述べている。シュレフラーはまた、移住の結果として、バングラ音楽が 音楽の演奏を通じて公共圏における伝統的な性別役割の改革を可能にしたと述べている。「『ダンスフロア』を作ることで、女性はそれまでできなかった方法で 男性と交わることが許された」[137]。 同様に、ゴードン・デール博士は、ミニャニム・パートナーダンスによって破壊された正統派ユダヤ文化におけるジェンダー・ダイナミクスの研究である「パー トナーシップ "ミニャニム "における正統派ユダヤ人のジェンダーロールの音楽と交渉」において、女性のパフォーマンスのための新しい文脈を確立するにあたって、パートナーシップミ ニャニム・ダンスが正統派ユダヤ教の宗教法をいかに活発に解釈し直すことができるかを記している[138]。 正統派ユダヤ教では、女性の歌は慎み深さへの期待に反する不適切な、あるいは武器化された性的行動であると考えられており [139] 、またハゲドンのバタドラムの例に示されるように、多様な文化圏にわたって、女性が宗教音楽からしばしば排除されていることを考えれば、宗教における新し い女性の音楽パフォーマンスの伝統の根拠付けは特に注目すべきことであろう [138]. この例では、女性的な音楽表現は非常に政治的な問題となり、右派の正教会の男性は、男性が女性の歌を性的行為として経験せずに聞くことは不可能であると主 張し、男性のパートナーシップによるミニアンの参加者は、謙虚さについてのある配慮は彼らの祈りの文脈では適用できないと代わりに結論付けている [138]。 したがって、女性の歌声は正統派の権力構造に対するジェンダー解放の音とも考えられる[139]。デールは、アン・ラスムセンが述べたようにコーランから 唱えるインドネシアの女性のような他の文化からの宗教的女性の音楽の取り組みに対し、この種のパートナーシップマイナミンは「男性と女性が並んで彼らの宗 教とフェミニストの価値を表現できる」新しい宗教空間を実際に作るよう正統派に求めている[140]と説明している。 [礼拝における女性の役割の利用可能性に関する制限は、ミニャミンが明確な平等性よりもジェンダーに基づいたパートナーシップに焦点を当てなければならな いことを意味するが、それでもパートナーシップミニャミンは女性の声を聞き、奨励するユダヤ文化におけるユニークな音楽の祈りの空間を形成する[140] 彼は、個人的に宗教礼拝を導くことに気が進まないが、他の女性がその役割を果たすのを大いに評価したある年配女性との交流を記述している。自由奔放に女性 たちと一緒に歌うだけで、彼女にとってフェミニズムを実践するための快適で充実した方法として機能していた[141]。 音楽演奏がジェンダー・アイデンティティの二元的な区分を破壊し、トランスジェンダーやノンバイナ リ・ジェンダーの表現を促進する方法を含め、音楽演奏によるジェンダー表現についてさらに研究する 余地は大いにある。コスコフは演奏者が「反対の性別の領域に渡り、通常反対の性別に関連する行動を表示する」ことが可能であることを簡潔に認めており、こ れは音楽演奏がジェンダーアイデンティティの演奏を可能にする方法に対してより大きな意味を持っている[130]。 このような分野内での新たな考察の結果、民族音楽学に対する女性の貢献をよりよく記録し、保存するための取り組みが活発化した。特に、音楽演奏や音楽分析 におけるジェンダーの不平等を扱った民族音楽学的著作(および関連分野の文献)を集めることに焦点を当て、フェミニスト音楽学者のバワーズとバレイスは 『音楽とジェンダー-音楽における女性』(Biography on Music and Gender - Women in Music)を出版し、この分析基準を満たしている民族音楽学文献をまとめた最も包括的なコレクションだと言える[142]。民族音楽学的な本ではない が、もう一人のスーザン・マクラリーの分水嶺となった本であるFeminine Endings(1991年)は「音楽構造と社会文化的価値との関係」を示しており、民族音楽学者自身のジェンダーとセクシャリティに対する認識に影響を 与えている[143]。 ジェンダー、セクシャリティ、その他の社会構築に関する西洋の概念は必ずしも他の文化に適用されず、主に西洋のレンズは研究者にとって方法論の問題を様々 引き起こすことがあるということが一般に認識されている[144]。 民族音楽学におけるジェンダーの概念は、研究者が自分自身のアイデンティティを研究対象の社会や人々との関係において批判的に考察する反射的民族誌の考え 方とも結びついている。例えば、キャサリン・ハゲドンは『Divine Utterances』でこの手法を用いている。キューバでのフィールドワークの記述を通して、ハゲドンは、白人であること、女性であること、外国人であ ることを通して、自分の立場がキューバの同胞には手の届かない贅沢を与えていたこと、キューバでの彼女の経験と存在における違いの大きさがキューバ革命中 のソ連崩壊後のキューバの経済混乱により悪化したことを述べている[145]。また、彼女の立場は、キューバ文化に対して「アウトサイダー」の視点を持 ち、サンテリア研究者としての文化へのアクセス能力に影響を与えた。彼女は、白人であることと外国人であることが、バタ・ドラムを使ったパフォーマンスを 中心とした男女間の親密な関係を回避することを可能にしたと書いている。スティグマに直面するキューバ人女性とは異なり、彼女はバタを演奏することを学ぶ ことができ、それによって研究を形成することができたのである[145]。 今日、民族音楽学会は、民族音楽学会のジェンダー・セクシュアリティ・タスクフォースなどのフォーラムを通じて、それぞれの音楽学会におけるジェンダー・ セクシュアリティ・LGBTQ・フェミニストの学問の存在と地位を高めることに積極的に取り組んでいる[146]。民族音楽学会は、さらにこの民族音楽学 の交差するサブフィールドで行われた仕事と研究を称えるために賞を設立している。具体的には、民族音楽学会はマーシャ・ハーンドン賞[147]を創設し、 レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、二刀流、同性愛、トランスジェンダー、マルチジェンダーの問題やコミュニティに焦点を当てた作品を含むが、それに限ら ず、ジェンダーとセクシャリティにおける優れた民族音楽学の仕事を称え、また、これらの領域においてこの分野に深く影響を与えたハーンドンによる貢献を記 念して創設されている。特に、国際伝統音楽協議会の音楽とジェンダー研究会のハイデルベルグ会合に触発された15本のエッセイ(すべて女性が執筆)を集め た『音楽、ジェンダー、文化』[148]を共同編集し、男性と女性の民族音楽学者や音楽家の間の哲学や行動の間の重要な比較をしていることが支持されてい る[149]。この作品は民族音楽学者や関連分野の学者の間で多くの対話を促し、ヴァージニア・ギリオ博士がハーンドンの代表的な作品をレビューし、精神 性、女性のエンパワメント、文化的に定義されたジェンダー関連の義務といった中心テーマを現代のフェミニスト民族音楽学者の間でさらに探求すべき特定の領 域として特定した[150]。 |
| Mass media In the first chapter of his book Popular Music of the Non-Western World,[151] Peter Manual examines the effect technology has had on non-western music by discussing its ability to disseminate, change, and influence music around the world. He begins with a discussion about definitions of genres, highlighting the difficulties in distinguishing between folk, classical, and popular music, within any one society. By tracing the historical development of the phonograph, radio, cassette recordings, and television, Manuel shows that, following the practice set in the western world, music has become a commodity in many societies, that it no longer has the same capacity to unite a community, to offer a kind of "mass catharsis" as one scholar put it. He stresses that any modern theoretical lens from which to view music must account for the advent of technology. Martin Stokes uses his book Ethnicity, Identity and Music[152] to examine how the presence of records, tapes, and CD's, and the ability to listen to music removed from its social setting affects identity and social boundaries. Stokes mentions how modernity and new technology has created a separation between place or "locale" (referring to the physical setting of social activity as situated geographically) and space (the location from where the music is being played and listened to.) Stokes calls the separation from space and place, "relocation" and refers to it as an "anxiety ridden process." Stokes believes that music plays an essential role to how individuals "relocate" themselves, claiming that music is unmatched by any other social activity in its ability to evoke and organize collective memory. Stokes also claims that the presence of records, tapes and CD's creates the ability to present experiences of specific places "with an intensity and power and simplicity unmatched." Stokes also touches upon the differences and social boundaries that each "place" holds. Claiming that each "place" organizes "hierarchies of moral and political order" and with each specific evocation of "place," defines the moral and political community to relation to the space in which the listener finds themselves. The possibility of the instant evocation of musical "place" allows individuals to "locate," and identify themselves in a plurality of ways, allowing a unique mix of places and social boundaries. Stokes also goes on to mention how the control of media systems by state-controlled governments, through ownership of its channels is a tool which authoritarian states use. Such control is not certain, as the meanings cannot be totally controlled and the citizens of said state can simply turn off the radio state or tune into another. Stokes believes the technological advancements in sound reproduction has democratized recording and listening, and thus, "weakened the grip of state and music industry monopolies." The book Music and Technocultures by René T. Lysloff and Leslie C. Gay Jr.[153] speaks upon the nature of the rise of technology. They believe that as technology increases, as does its social consequences. Such technologies do not change the social configurations which existed before new technologies, but instead the people that engage with and use these technologies change, instead. Lysloff and Gay use the emergence of the use of MP3s as an example. The MP3 file format can be combined with other software's to give tools that link online communities of music consumers with vast databases of music files, which individuals then have easy access to gigabytes of digital information. The existence of MP3s and these software's then allows for the new possibilities for the exchange of music and gives greater control to the selection of music to the end user, undermining the power of the popular music industries. Such technologies also allow unsigned artists to distribute their own recordings on an unthinkable scale. Later within the book Gay and Lysloff go on to speak on the effects of technological control on consumer practices. Gay and Lysloff go on to say that "Popular music musicians today are shaped first as 'consumers of technology,' in which musical practices align with consumer practices. Even within the "architectonic" structure of malls and acoustic spaces, they are built to connect with consumer practices, defining territory and motivating shoppers. |
26. マスメディア Peter Manualは、彼の著書Popular Music of the Non-Western Worldの第1章において、テクノロジーが世界中の音楽を普及させ、変化させ、影響を与える能力について議論することによって、テクノロジーが非西洋音 楽に及ぼした影響を検証している[151]。彼は、ジャンルの定義についての議論から始め、一つの社会の中で、民族音楽、クラシック音楽、ポピュラー音楽 を区別することの難しさを強調している。蓄音機、ラジオ、カセットテープ、テレビなどの歴史的な発展をたどることで、マニュエルは、西欧諸国の慣行に従っ て、音楽が多くの社会で商品となり、ある学者の言うように、もはやコミュニティを団結させ、一種の「集団カタルシス」を提供する能力を持たなくなったこと を示している。彼は、音楽を見るための現代的な理論的レンズは、テクノロジーの出現を考慮に入れなければならないと強調している。 マーティン・ストークスは著書『エスニシティ、アイデンティティ、音楽』[152]を使って、レコード、テープ、CDの存在や、社会的環境から離れた音楽 を聴く能力がアイデンティティや社会的境界線にどう影響を与えるかを検証している。ストークスは、近代化と新しいテクノロジーによって、場所あるいは「ロ ケール」(地理的に位置する社会活動の物理的な設定を指す)と空間(音楽が再生され聴かれている場所)の分離が生じたことを言及し、空間と場所からの分離 を「再配置」と呼び、それを「不安に満ちた過程」と呼んでいる。ストークスは、音楽が個人の「リロケーション」の方法に不可欠な役割を果たすと考えてお り、集団的記憶を呼び起こし、組織化する能力において、音楽は他のどの社会的活動とも比べものにならないと主張している。また、レコードやテープ、CDの 存在は、特定の場所での体験を「比類なき強度とパワー、シンプルさ」で提示する能力を生み出すとストークスは主張しています。さらにストークスは、それぞ れの「場」が持つ差異や社会的な境界線についても触れています。それぞれの「場所」が「道徳的・政治的秩序のヒエラルキー」を組織し、「場所」を具体的に 呼び起こすごとに、リスナーが見つけた空間との関係において、道徳的・政治的コミュニティが定義されると主張している。音楽的な「場所」を瞬時に呼び起こ すことができるため、個人が「場所を特定」し、複数の方法で自分自身を識別することができ、場所と社会の境界がユニークに混ざり合うことができるのです。 ストークスはさらに、国家が支配する政府がチャンネルを所有することによってメディア・システムをコントロールすることが、権威主義国家が使う手段である ことにも触れている。このようなコントロールは確実なものではなく、その国家の市民は単にラジオ国家を消したり、別のラジオにチャンネルを合わせたりする ことができるからである。ストークスは、音の再生における技術の進歩が録音と聴取を民主化し、その結果、"国家と音楽産業の独占のグリップを弱めた "と考えている。 レネ・T・リスロフとレスリー・C・ゲイ・ジュニアによる「音楽とテクノカルチャー」[153]は、テクノロジーの台頭の本質について述べている。彼ら は、技術が増大すればするほど、その社会的帰結もまた増大すると考えている。そのようなテクノロジーは新しいテクノロジー以前に存在していた社会構成を変 えるのではなく、そのテクノロジーに関わり、使用する人々が代わりに変化するのである。ライスロフとゲイは、MP3の使われ方の出現を例として挙げてい る。MP3ファイル形式は、他のソフトウェアと組み合わせることで、音楽消費者のオンライン・コミュニティと膨大な音楽ファイルのデータベースを結びつけ るツールとなり、個人はギガバイト単位のデジタル情報に容易にアクセスできるようになる。MP3やソフトウェアの存在は、音楽の交換に新たな可能性をもた らし、エンドユーザーに音楽の選択権を与え、大衆音楽産業の力を弱めることになる。また、このようなテクノロジーは、無名のアーティストが自分の録音物を 想像もつかないような規模で流通させることを可能にする。この本の後半で、ゲイとリスロフは、技術的コントロールが消費者の習慣に及ぼす影響について述べ ている。ゲイとリスロフは、「今日のポピュラー音楽のミュージシャンは、まず『テクノロジーの消費者』として形成されており、そこでは音楽的実践が消費者 の実践と一致している」と言い切っている。ショッピング・モールや音響空間という「建築的」な構造の中でさえ、それらは消費者の実践と結び付き、領域を定 義し、買い物客を動機付けるように作られている。 |
| Copyright Copyright is defined as "the exclusive right to make copies, license, and otherwise exploit a literary, musical, or artistic work, whether printed, audio, video, etc."[154] It is imperative because copyright is what dictates where credit and monetary awards should be allocated. While ethnomusicologists conduct fieldwork, they sometimes must interact with the indigenous people. Additionally, since the purpose of the ethnomusicologists being in a particular country is so that she can collect information to make conclusions. The researchers leave their countries of interest with interviews, videos, text, along with multiple other sources of valuable. Rights surrounding music ownership are thus often left to ethics. The specific issue with copyright and ethnomusicology is that copyright is an American right; however, some ethnomusicologists conduct research in countries that are outside of the United States. For example, Anthony Seeger details his experience while working with the Suyá people of Brazil and the release of their song recordings. The Suyá people have practices and beliefs about inspiration and authorship, where the ownership roots from the animals, spirits, and "owned" by entire communities. In the American copyright laws, they ask for a single original author, not groups of people, animals, or spirits. Situations like Seeger's then result in the indigenous people not being given credit or sometime into being able to have access to the monetary wealth that may come along with the published goods. Seeger also mentions that in some cases, copyright will be granted, but the informant-performer, the researcher, the producer, and the organization funding the research –earns the credit that the indigenous people deserve." "[155] Martin Scherzinger mentions how copyright is dealt with in the Senegal region of Africa. The copyright benefits, such as royalties, from music are allocated to the Senegalese government, and then the government in turn hosts a talent competition, where the winner receives the royalties. Scherzinger offers a differing opinion on copyright, and argues that the law is not inherently ethnocentric.[121] He cites the early ideology behind copyright in the 19th century, stating that spiritual inspiration did not prohibit composers from being granted authorship of their works. Furthermore, he suggests that group ownership of a song is not significantly different from the collective influence in Western classical music of several composers on any individual work. A solution to some of the copyright issue that the ethnomusicology is having is to push for the broadening of the copyright laws in the United States. To broaden is equivalent to changing who can be cited as the original author of a piece of work to include the values that specific societies have. In order for this to be done, ethnomusicologists have to find a common ground amongst the copyright issues that they have encountered collectively. |
27. 著作権 著作権とは、「印刷物、音声、映像などの文学、音楽、芸術作品の複製、使用許諾、その他の利用を行う排他的権利」[154]と定義される。著作権は、クレ ジットや賞金の分配を決めるものであるため、必須である。民族音楽学者がフィールドワークを行う際、先住民との交流が必要な場合がある。さらに、民族音楽 学者が特定の国に滞在する目的は、結論を出すための情報を収集することである。研究者は、インタビュー、ビデオ、テキスト、その他複数の貴重な情報源を携 えて、対象国を後にする。音楽の所有権をめぐる権利は、このようにしばしば倫理に委ねられている。 著作権と民族音楽学の具体的な問題は、著作権がアメリカの権利であることである。しかし、民族音楽学者の中には、アメリカ以外の国で研究を行う者もいる。 例えば、アンソニー・シーガーは、ブラジルのスヤ族と仕事をし、彼らの歌の録音を公開したときの経験を詳しく述べている。Suyá族には、インスピレー ションと著作権に関する習慣と信念があり、所有権のルーツは動物、精霊、そしてコミュニティ全体が「所有」している。アメリカの著作権法では、人、動物、 精霊のグループではなく、一人の原作者を求めている。その結果、先住民は信用を得られず、出版物に付随する金銭的な富にアクセスすることができなくなるの です。シーガーはまた、著作権が認められる場合もあるが、情報提供者、研究者、制作者、そして研究資金を提供する組織が、先住民が受けるべき信用を得るこ とになると述べている[155]。"[155] マーティン・シャージンガー氏は、アフリカのセネガル地方で著作権がどのように扱われているかについて言及している。音楽から得られるロイヤリティなどの 著作権の利益はセネガル政府に配分され、政府が今度はタレント・コンテストを開催し、優勝者がロイヤリティを受け取るというものだ。シャージンガーは著作 権について異なる意見を述べ、法律は本質的に民族中心的ではないと主張している[121]。彼は、19世紀の著作権の背後にある初期の思想を引用し、精神 的インスピレーションは、作曲家に作品の著作権を認めることを禁止するものではなかったと述べている。さらに彼は、曲の集団所有は、西洋のクラシック音楽 において複数の作曲家が個々の作品に与える集団的影響と大きくは異ならないことを示唆している[121]。 民族音楽学が抱えている著作権問題のいくつかの解決策は、アメリカにおける著作権法の幅を広げることを推し進めることである。広げるというのは、作品の原 作者として引用できる人物を、特定の社会が持つ価値観を含めて変更することに相当する。そのためには、民族音楽学者が集団で遭遇してきた著作権問題の中か ら共通項を見つけなければならない。 |
| Identity The origins of music and its connections to identity have been debated throughout the history of ethnomusicology. Thomas Turino defines "self," "identity," and "culture" as patterns of habits, such that tendencies to respond to stimuli in particular ways repeat and reinscribe themselves.[156] Musical habits and our responses to them lead to cultural formations of identity and identity groups. For Martin Stokes, the function of music is to exercise collective power, creating barriers among groups. Thus, identity categories such as ethnicity and nationality are used to indicate oppositional content.[157] Just as music reinforces categories of self-identification, identity can shape musical innovation. George Lipsitz's 1986 case study of Mexican-American music in Los Angeles from the 1950s to the 1980s posits that Chicano musicians were motivated to integrate multiple styles and genres in their music to represent their multifaceted cultural identity.[158] By incorporating Mexican folk music and modern-day barrio influences, Mexican rock-and-roll musicians in LA made commercially successful postmodern records that included content about their community, history, and identity.[159] Lipsitz suggests that the Mexican community in Los Angeles reoriented their traditions to fit the postmodern present. Seeking a "unity of disunity", minority groups can attempt to find solidarity by presenting themselves as sharing experience with other oppressed groups. According to Lipsitz, this disunity creates a disunity that furthermore engenders a "historical bloc," made up of numerous, multifaceted, marginalized cultures. Lipsitz noted the bifocal nature of the rock group Los Lobos is particularly exemplary of this paradox. They straddled the line by mixing traditional Mexican folk elements with white rockabilly and African American rhythm and blues, while simultaneously conforming to none of the aforementioned genres. That they were commercially successful was unsurprising to Lipsitz- their goal in incorporating many cultural elements equally was to play to everyone. In this manner, in Lipsitz's view, the music served to break down barriers in its up front presentation of "multiple realities".[158] Lipsitz describes the weakening effect that the dominant (Los Angeles) culture imposes on marginalized identities. He suggests that the mass media dilutes minority culture by representing the dominant culture as the most natural and normal.[159] Lipsitz also proposes that capitalism turns historical traditions of minority groups into superficial icons and images in order to profit on their perception as "exotic" or different. Therefore, the commodification of these icons and images results in the loss of their original meaning. Minorities, according to Lipsitz, cannot fully assimilate nor can they completely separate themselves from dominant groups. Their cultural marginality and misrepresentation in the media makes them aware of society's skewed perception of them.[159] Antonio Gramsci suggests that there are "experts in legitimization", who attempt to legitimize dominant culture by making it look like it is consented by the people who live under it. He also proposes that the oppressed groups have their own "organic intellectuals" who provide counter-oppressive imagery to resist this legitimization.[160] For example, Low riders used irony to poke fun at popular culture's perception of desirable vehicles, and bands like Los Illegals provided their listening communities with a useful vocabulary to talk about oppression and injustice.[159] Michael M.J. Fisher breaks down the following main components of postmodern sensibility: "bifocality or reciprocity of perspectives, juxtaposition of multiple realities-intertextuality, inter-referentiality, and comparisons through families of resemblance."[161] A reciprocity of perspectives makes music accessible inside and outside of a specific community. Chicano musicians exemplified this and juxtaposed multiple realities by combining different genres, styles, and languages in their music.[159] This can widen the music's reception by allowing it to mesh within its cultural setting, while incorporating Mexican history and tradition. Inter-referentiality, or referencing relatable experiences, can further widen the music's demographic and help to shape its creators' cultural identities. In doing so, Chicano artists were able to connect their music to "community subcultures and institutions oriented around speech, dress, car customizing, art, theater, and politics."[159] Finally, drawing comparisons through families of resemblance can highlight similarities between cultural styles. Chicano musicians were able to incorporate elements of R&B, Soul, and Rock n' Roll in their music.[159] Music is not only used to create group identities, but to develop personal identity as well. Frith describes music's ability to manipulate moods and organize daily life.[162] Susan Crafts studied the role of music in individual life by interviewing a wide variety of people, from a young adult who integrated music in every aspect of her life to a veteran who used music as a way to escape his memories of war and share joy with others.[163] Many scholars have commented on the associations that individuals develop of "my music" versus "your music": one's personal taste contributes to a sense of unique self-identity reinforced through the practices of listening to and performing certain music.[164] As part of a broader inclusion of identity politics (see Gender), ethnomusicologists have become increasingly interested in how identity shapes ethnomusicological work. Fieldworkers have begun to consider their positions within race, economic class, gender, and other identity categories and how they relate to or differ from cultural norms in the areas they study. Katherine Hagedorn's 2001 Book Divine Utterances: The Performance of Afro-Cuban Santería is an example of experiential ethnomusicology, which "...incorporates the author's voice, interpretations, and reactions into the ethnography, musical and cultural analysis, and historical context."[165] The book received the Society for Ethnomusicology's prestigious Alan P. Merriam prize in 2002, marking a broad acceptance of this new method in the institutions of ethnomusicology.[166] |
28. アイデンティティ 音楽の起源とアイデンティティとの関連は、民族音楽学の歴史を通じて議論されてきた。トーマス・トゥリノは「自己」、「アイデンティティ」、「文化」を習 慣のパターンとして定義しており、特定の方法で刺激に反応する傾向が繰り返され、自己を再認識するようになっている[156]。音楽的習慣とそれらに対す る我々の反応はアイデンティティとアイデンティティグループの文化的形成につながる。マーティン・ストークスにとって、音楽の機能は集団的な力を行使する ことであり、集団の間に障壁を作り出すことである。したがって、民族や国籍といったアイデンティティーのカテゴリーは対立的な内容を示すために使われる [157]。 音楽が自己認識のカテゴリーを強化するのと同様に、アイデンティティは音楽の革新を形成することができる。ジョージ・リプシッツによる1986年の 1950年代から1980年代のロサンゼルスにおけるメキシコ系アメリカ人音楽の事例研究は、チカノミュージシャンが彼らの多面的な文化的アイデンティ ティを表現するために複数のスタイルとジャンルを音楽に統合する動機付けがあったとしている。 メキシコ民謡と現代のバリオの影響を取り入れることによって、ロサンゼルスにおけるメキシコ系ロックンロールミュージシャンは彼らのコミュニティ、歴史、 アイデンティティについての内容を含むポストモダンのレコードを作って商業的に成功している [159] リプシッツはロサンゼルスでのメキシココミュニティがポストモダンの現代に合わせて伝統を再方向付けたと示唆する。不統一の統一」を求めるマイノリティグ ループは、自分たちが他の抑圧されたグループと経験を共有していると示すことによって、連帯を見つけようとすることができる。リプシッツによれば、この不 統一がさらに、多数の、多面的な、周縁化された文化からなる「歴史的ブロック」を生み出すのである。 リプシッツは、ロック・グループ、ロス・ロボスの二律背反的な性質が、このパラドックスの特に典型的な例であると指摘する。彼らは、伝統的なメキシコの民 謡の要素と白人のロカビリーやアフリカ系アメリカ人のリズム&ブルースを混ぜ合わせながら、同時に前述のどのジャンルにも属さないという境界線をまたいで いたのである。彼らが商業的に成功したことは、リプシッツにとって当然のことだった。多くの文化的要素を等しく取り入れた彼らの目標は、すべての人のため に演奏することだったのだ。このようにして、リプシッツの見解では、音楽は「複数の現実」を正面から提示することによって、障壁を取り除く役割を果たした [158]。 リプシッツは支配的な(ロサンゼルスの)文化が周縁化されたアイデンティティに課す弱体化効果について述べている。彼は、マスメディアが支配的な文化を最 も自然で正常なものとして表現することによってマイノリティ文化を希釈することを示唆している[159]。またリプシッツは、資本主義がマイノリティ集団 の歴史的伝統を「エキゾチック」あるいは異なるものとして認識して利益を得るために表面的なアイコンやイメージに変えていることを提案している。したがっ て、これらのアイコンやイメージの商品化は、その本来の意味を失わせる結果となる。 リプシッツによれば、マイノリティは完全に同化することも、支配的な集団から完全に切り離すこともできない。アントニオ・グラムシは「正統化の専門家」が 存在することを示唆しており、彼らは支配的な文化がその下で暮らす人々によって同意されているように見せかけることによって、それを正統化しようとするの である。彼はまた、抑圧された集団はこの正当化に抵抗するために反抑圧的なイメージを提供する彼ら自身の「有機的知識人」を持っていると提案している [160]。 例えば、ローライダーは大衆文化の望ましい車に対する認識をからかうために皮肉を使い、ロスイレガルズなどのバンドは彼らのリスニングコミュニティに抑圧 や不正について話すための有用なボキャブラリーを提供した[159]。 マイケル・M・J・フィッシャーはポストモダンの感性の主な構成要素を次のように分類している。「視点の二重性あるいは相互性、複数の現実の並置-相互文 脈性、相互参照性、類似家族による比較」[161] 視点の相互性は、特定のコミュニティの内外で音楽にアクセスできるようにする。チカーノのミュージシャンはこれを例証し、彼らの音楽の中で異なるジャン ル、スタイル、言語を組み合わせることによって複数の現実を並置した[159]。これは、メキシコの歴史と伝統を取り入れながら、その文化的設定の中で噛 み合わせることによって、音楽の受容を拡大することが可能である。相互参照性、つまり相対的な経験を参照することは、音楽の人口層をさらに広げ、そのクリ エイターの文化的アイデンティティを形成するのに役立つ。そうすることで、チカーノ・アーティストは自分たちの音楽を「話し方、服装、車のカスタマイズ、 芸術、演劇、政治を中心としたコミュニティのサブカルチャーや制度」に結びつけることができた[159]。最後に、類似性のある家族を通して比較を描くこ とは、文化様式の間の類似性を強調することができる。チカーノのミュージシャンはR&B、ソウル、ロックンロールの要素を彼らの音楽に取り入れる ことができた[159]。 音楽は集団のアイデンティティを作るために使われるだけでなく、個人のアイデンティティを発展させるためにも使われる。フリスは、音楽が気分を操作し、日 常生活を組織化する能力について述べている[162] スーザン・クラフトは、生活のあらゆる面で音楽を統合する若い成人から、戦争の記憶から逃れ、他者と喜びを共有する方法として音楽を使う退役軍人まで、幅 広い人々にインタビューし、個人の生活における音楽の役割を研究した[163]。 [多くの学者が、個人が「私の音楽」対「あなたの音楽」という連想を展開することについてコメントしている。個人の趣味は、特定の音楽を聴いたり演奏した りする実践を通じて強化されるユニークな自己アイデンティティの感覚に寄与する[164]。 アイデンティティ・ポリティクス(「ジェンダー」を参照)の広範な包摂の一環として、民族音楽学者は、アイデンティティが民族音楽学的作業をいかに形成す るかについて、ますます関心を持つようになっている。フィールドワーカーは、人種、経済階級、ジェンダー、その他のアイデンティティのカテゴリーにおける 自分の位置、そしてそれらが研究対象地域の文化的規範とどのように関連し、あるいは異なっているかを考慮するようになったのである。Katherine Hagedornの2001年の著書『Divine Utterances: この本は、2002年に民族音楽学会の権威あるアラン・P・メリアム賞を受賞し、民族音楽学の機関においてこの新しい方法が広く受け入れられたことを示し ている[166]。 |
| Nationalism (Main article: Musical
nationalism § Ethonomusicological perspectives) Ethnomusicological inquiries frequently involve a focus on the relationship between music and nationalist movements across the world, necessarily following the emergence of the modern nation-state as a consequence of globalization and its associated ideals, in contrast to a pre-imperialist world. [167] In the latter half of the 19th century, song collectors motivated by the legacy of folkloric studies and musical nationalism in Southern and Eastern Europe collected folk songs for use in the construction of a pan-Slavic identity.[168] Collector-composers became "national composers" when they composed songs that became emblematic of a national identity. Namely, Frederic Chopin gained international recognition as a composer of emblematic Polish music despite having no ancestral ties to the Polish peasantry[169] Other composers such as Béla Bartók, Jean Sibelius, Edvard Grieg, and Nikolai Rimsky Korsakov utilized as well as contributed to the growing archives of recorded European folk songs to compose songs for the benefit of the nationalist governments of their respective countries.[168] The French musicologist Radolphe d'Erlanger undertook a project of reviving older musical forms in Tunisia in order to reconstruct "Oriental music," playing on instruments such as the ud and ghazal. Performing ensembles using such instruments were featured at the 1932 Congress of Arab Music in Cairo.[170] Globalization →"World Music and Globalization" |
29. ナショナリズム 民族音楽学的な研究は、世界各地の音楽と民族主義運動の関係に焦点を当てることが多く、帝国主義以前の世界とは対照的に、グローバル化とそれに伴う理想の 結果としての近代国民国家の出現に必然的に従うことになる。 19世紀後半、南欧や東欧における民俗学や音楽的ナショナリズムの遺産に動機づけられた歌曲収集家たちは、汎スラヴ的アイデンティティの構築に用いるため に民謡を収集した[168]。収集家の作曲家は、ナショナル・アイデンティティを象徴する歌を作曲すると「民族作曲家」となる。すなわち、フレデリック・ ショパンは、ポーランドの農民と先祖のつながりがないにもかかわらず、ポーランド音楽を象徴する作曲家として国際的に認知された[169]。ベーラ・バル トーク、ジャン・シベリウス、エドヴァルド・グリーグ、ニコライ・リムスキ・コルサコフといった他の作曲家たちは、それぞれの国の国家主義政府のために曲 を作曲し、ヨーロッパの民謡を記録したアーカイブがますます発展しつつあるので利用するとともに、その貢献もした[168]。 フランスの音楽学者ラドルフ・デルランジェは、チュニジアで古い音楽形式を復活させ、ウードやガザルなどの楽器で演奏する「東洋音楽」を再構築するプロ ジェクトに着手した[168]。1932年にカイロで開催されたアラブ音楽会議では、こうした楽器を使ったアンサンブルの演奏が紹介された。 30. グローバリゼーション →「ワールドミュージックとグローバリゼーション」 |
| Cognition (Culture
in music cognition) Cognitive psychology, neuroscience, anatomy, and similar fields have endeavored to understand how music relates to an individual's perception, cognition, and behavior. Research topics include pitch perception, representation and expectation, timbre perception, rhythmic processing, event hierarchies and reductions, musical performance and ability, musical universals, musical origins, music development, cross-cultural cognition, evolution, and more. From the cognitive perspective, the brain perceives auditory stimuli as music according to gestalt principles, or "principles of grouping." Gestalt principles include proximity, similarity, closure, and continuation. Each of the gestalt principles illustrates a different element of auditory stimuli that cause them to be perceived as a group, or as one unit of music. Proximity dictates that auditory stimuli that are near to each other are seen as a group. Similarity dictates that when multiple auditory stimuli are present, the similar stimuli are perceived as a group. Closure is the tendency to perceive an incomplete auditory pattern as a whole—the brain "fills in" the gap. And continuation dictates that auditory stimuli are more likely to be perceived as a group when they follow a continuous, detectable pattern.[186] The perception of music has a quickly growing body of literature. Structurally, the auditory system is able to distinguish different pitches (sound waves of varying frequency) via the complementary vibrating of the eardrum. It can also parse incoming sound signals via pattern recognition mechanisms.[187] Cognitively, the brain is often constructionist when it comes to pitch. If one removes the fundamental pitch from a harmonic spectrum, the brain can still "hear" that missing fundamental and identify it through an attempt to reconstruct a coherent harmonic spectrum.[188] Research suggests that much more is learned perception, however. Contrary to popular belief, absolute pitch is learned at a critical age, or for a familiar timbre only.[189][190] Debate still occurs over whether Western chords are naturally consonant or dissonant, or whether that ascription is learned.[191][192] Relation of pitch to frequency is a universal phenomenon, but scale construction is culturally specific.[193] Training in a cultural scale results in melodic and harmonic expectations.[194] Cornelia Fales has explored the ways that expectations of timbre are learned based on past correlations. She has offered three main characteristics of timbre: timbre constitutes a link to the external world, it functions as perceptualization's primary instrument and it is a musical element that we experience without informational consciousness. Fales has gone into in-depth exploration of humankind's perceptual relation to timbre, noting that out of all of the musical elements, our perception of timbre is the most divergent from the physical acoustic signal of the sound itself. Growing from this concept, she also discusses the "paradox of timbre", the idea that perceived timbre exists only in the mind of the listener and not in the objective world. In Fales' exploration of timbre, she discusses three broad categories of timbre manipulation in musical performance throughout the world. The first of these, timbral anomaly by extraction, involves the breaking of acoustic elements from the perceptual fusion of timbre of which they were part, leading to a splintering of the perceived acoustic signal (demonstrated in overtone singing and didjeridoo music). The second, timbral anomaly by redistribution, is a redistribution of gestalt components to new groups, creating a "chimeric" sound composed of precepts made up of components from several sources (as seen in Ghanaian balafon music or the bell tone in barbershop singing). Finally, timbral juxtaposition consists of juxtaposing sounds that fall on opposing ends of a continuum of timbral structure that extends from harmonically based to formant-structured timbres (as demonstrated again in overtone singing or the use of the "minde" ornament in Indian sitar music). Overall, these three techniques form a scale of progressively more effective control of perceptualization as reliance on the acoustic world increases. In Fales' examinations of these types of timbre manipulation within Inanga and Kubandwa songs, she synthesizes her scientific research on the subjective/objective dichotomy of timbre with culture-specific phenomena, such as the interactions between music (the known world) and spiritual communication (the unknown world).[195] Cognitive research has also been applied to ethnomusicological studies of rhythm. Some ethnomusicologists believe that African and Western rhythms are organized differently. Western rhythms may be based on ratio relationships, while African rhythms may be organized additively. In this view, that means that Western rhythms are hierarchical in nature, while African rhythms are serial.[196] One study that provides empirical support for this view was published by Magill and Pressing in 1997. The researchers recruited a highly experienced drummer who produced prototypical rhythmic patterns. Magill and Pressing then used Wing & Kristofferson's (1973)[197] mathematical modeling to test different hypotheses on the timing of the drummer. One version of the model used a metrical structure; however, the authors found that this structure was not necessary. All drumming patterns could be interpreted within an additive structure, supporting the idea of a universal ametrical organization scheme for rhythm.[198] Researchers have also attempted to use psychological and biological principles to understand more complex musical phenomena such as performance behavior or the evolution of music, but have reached few consensuses in these areas. It is generally accepted that errors in performance give insight into perception of a music's structure, but these studies are restricted to Western score-reading tradition thus far.[199] Currently there are several theories to explain the evolution of music. One of theories, expanded on by Ian Cross, is the idea that music piggy-backed on the ability to produce language and evolved to enable and promote social interaction.[200] Cross bases his account on the fact that music is a humanly ancient art seen throughout nearly every example of human culture. Since opinions vary on what precisely can be defined as "music", Cross defines it as "complexly structured, affectively significant, attentionally entraining, and immediately—yet indeterminately—meaningful," noting that all known cultures have some art form that can be defined in this way.[201] In the same article, Cross examines the communicative power of music, exploring its role in minimizing within-group conflict and bringing social groups together and claiming that music could have served the function of managing intra and inter-group interactions throughout the course of human evolution. Essentially, Cross proposes that music and language evolved together, serving contrasting functions that have been equally essential to the evolution of humankind. Additionally, Bruno Nettl has proposed that music evolved to increase efficiency of vocal communication over long distances, or enabled communication with the supernatural.[202] |
31. コグニション(音楽認知の
文化) 認知心理学、神経科学、解剖学などの分野では、音楽が個人の知覚、認知、行動にどのように関わるかを理解しようと試みている。研究テーマは、音程知覚、表 現と期待、音色知覚、リズム処理、イベントの階層と還元、音楽演奏と能力、音楽の普遍性、音楽の起源、音楽の発達、異文化間認知、進化などである。 認知の観点からは、脳はゲシュタルト原理、すなわち "グループ化の原理 "に従って聴覚刺激を音楽として認識する。ゲシュタルト原理には、近接性、類似性、閉鎖性、継続性などがある。それぞれのゲシュタルト原理は、聴覚刺激を グループとして、あるいは音楽の1つの単位として認識させる異なる要素を示している。近接性とは、互いに近接した聴覚刺激がグループとして認識されること を指示するものである。類似性とは、複数の聴覚刺激が存在する場合、類似した刺激はグループとして知覚されることを指示する。閉鎖性とは、不完全な聴覚パ ターンを全体として知覚する傾向のことで、脳はそのギャップを「埋める」。そして、継続性は、聴覚刺激が連続的で検出可能なパターンに従っている場合にグ ループとして知覚される可能性が高くなることを指示する[186]。 音楽の知覚については、急速に文献が発展している。構造的には、聴覚系は鼓膜の相補的な振動によって異なる音程(様々 な周波数の音波)を識別することができる。また、パターン認識メカニズムによって、入力された音信号を解析することができる[187]。認知的には、脳は 音程に関してしばしば構築主義的である。調和スペクトルから基音ピッチを削除しても、脳はその失われた基音を「聞く」ことができ、コヒーレントな調和スペ クトルを再構築する試みを通じてそれを識別することができる[188]。 しかし、研究によって、それ以上のものが学習された知覚であることが示唆されている。一般的な信念に反して、絶対音感は臨界年齢で、あるいは馴染みのある 音色に対してのみ学習される[189][190]。西洋の和音が自然に子音か不協和音か、あるいはその帰属が学習されるかどうかについて未だに議論が起こ る[191][192]。周波数への音程の関連は普遍的現象だが、音階構築は文化的に特異だ[193]。文化的音階での訓練はメロディーとハーモニーの期 待値に帰結する[194]。 コーネリア・ファレスは、音色への期待が過去の相関関係からどのように学習されるかを研究してきた。音色は外界とリンクしていること、知覚の主要な道具と して機能していること、そして私たちが情報意識なしに経験する音楽的要素であることです。ファレズは、音色の知覚が、音楽のあらゆる要素の中で、音の物理 的な音響信号そのものと最も乖離していることを指摘し、人類の音色に対する知覚の関係について深く掘り下げている。この概念から発展して、彼女は「音色の パラドックス」、つまり認識された音色はリスナーの心の中にのみ存在し、客観的な世界には存在しないという考えも述べている。Falesは音色に関する考 察の中で、世界中の音楽演奏における音色操作を3つのカテゴリーに大別して論じている。まず、抽出による音色の異常は、音響的な要素を、それが構成してい た音色の知覚的な融合から切り離し、知覚される音響信号を分裂させるものです(倍音唱法やディジュリドゥ音楽で実証されています)。第二に、再分配による 音色の異常は、ゲシュタルトの構成要素を新しいグループに再分配し、複数のソースからの構成要素からなるプリセプトからなる「キメラ」サウンドを作り出す (ガーナのバラフォン音楽、バーバーショップ歌手のベルトーンに見られる)。最後に、音色的並置は、和声的な音色からフォルマント的な音色まで、音色構造 の連続体の両端に位置する音を並置することである(倍音唱法やインドのシタール音楽における「ミンデ」装飾の使用に再び示されるように)。全体として、こ れら3つの技法は、音響世界への依存度が高まるにつれて、知覚の制御が徐々に効果的になるスケールを形成している。イナンガとクバンドワの歌におけるこれ らのタイプの音色操作の検討において、彼女は音色の主観/客観の二項対立に関する科学的研究と、音楽(既知の世界)と精神的コミュニケーション(未知の世 界)の相互作用といった文化固有の現象とを統合している[195]。 認知研究は、リズムの民族音楽学的研究にも応用されている。民族音楽学者の中には、アフリカのリズムと西洋のリズムは異なる構成になっていると考える人も いる。西洋のリズムは比率の関係に基づいているのに対し、アフリカのリズムは加法的に組織されている可能性がある。この見解では、西洋のリズムは本質的に 階層的であり、アフリカのリズムは直列的であることを意味する[196] この見解に対する経験的なサポートを提供する一つの研究が1997年にマギルとプレッシングによって発表されている。研究者たちは、原型的なリズムパター ンを作り出す経験豊富なドラマー を採用した。そして、Magill と Pressing は Wing & Kristofferson (1973)[197] の数理モデリングを使って、ドラマー のタイミングに関する異なる仮説を検証した。このモデルの 1 つのバージョンでは、計量的な構造が使われましたが、著者らはこの構造は必要ないことを見つけま した。しかし、この構造は必要ないことがわかった。すべてのドラムパターンは加算構造の中で解釈することができ、リズムのための普遍的なアメトリカル組織 スキームの考えを支持した[198]。 また、演奏行動や音楽の進化など、より複雑な音楽現象を理解するために、心理学や生物学の原理を使う試みも行われているが、この分野ではほとんど意見が一 致していない。演奏における誤差が音楽の構造に対する知覚に洞察を与えることは一般に受け入れられているが、これらの研究は今のところ西洋の楽譜読解の伝 統に限定されている[199]。現在、音楽の進化を説明するいくつかの理論がある。イアン・クロスによって拡張された理論の1つは、音楽が言語を生み出す 能力におんぶに抱っこで、社会的相互作用を可能にし促進するために進化したという考えである[200]。クロスは、音楽が人類の文化のほぼすべての例を通 して見られる人類的に古い芸術であるという事実に基づいて彼の説明をしている。同じ論文で、クロスは音楽のコミュニケーション力を検証し、集団内の対立を 最小化し、社会集団を一つにまとめる役割を探り、音楽が人類の進化の過程で集団内外の相互作用を管理する機能を果たした可能性があると主張している。クロ スは、音楽と言語が共に進化し、対照的な機能を果たしながら、人類の進化に等しく不可欠であったことを提唱している。さらにブルーノ・ネトルは、音楽は長 距離の音声コミュニケーションの効率を高めるために進化した、あるいは超自然とのコミュニケーションを可能にするために進化したと提案している [202]。 |
| Decolonizing Ethnomusicology The idea of decolonization is not new to the field of ethnomusicology. As early as 2006, the idea became a central topic of discussion for the Society for Ethnomusicology.[203] In humanities and education studies, the term decolonization is used to describe "an array of processes involving social justice, resistance, sustainability, and preservation.[203] However, in ethnomusicology, decolonization is considered to be a metaphor by some scholars.[203] Linda Tuhiwai Smith, a professor of indigenous studies in New Zealand, offered a look into the shift decolonization has taken: "decolonization, once viewed as the formal process of handing over the instruments of government, is now recognized as a long-term process involving the bureaucratic, cultural, linguistic and psychological divesting of colonial power."[204] For ethnomusicology, this shift means that fundamental changes in power structures, worldviews, academia, and the university system need to be analyzed as a confrontation of colonialism.[203] A proposed decolonized approach to ethnomusicology involves reflecting on the philosophies and methodologies that constitute the discipline.[205] The decolonization of ethnomusicology takes multiple paths. These proposed approaches are: i) ethnomusicologists addressing their roles as scholars, ii) the university system being analyzed and revised, iii) the philosophies, and thus practices, as a discipline being changed.[203] The Fall/Winter 2016 issue of the Society of Ethnomusicology's Student News contains a survey about decolonizing ethnomusicology to see their readers' views on what decolonizing ethnomusicology entailed. The different themes were: i) decentering ethnomusicology from the United States and Europe, ii) expanding/transforming the discipline, iii) recognizing privilege and power, and iv) constructing spaces to actually talk about decolonizing ethnomusicology among peers and colleagues.[206] One of the issues proposed by Brendan Kibbee for "decolonizing" ethnomusicology is how scholars might reorganize the disciplinary practices to broaden the base of ideas and thinkers. One idea posed is that the preference and privilege of the written word more than other forms of media scholarship hinders a great deal of potential contributors from finding a space in the disciplinary sphere.[207] The possible influence of the Western bias against listening as an intellectual practice could be a reason for a lack of diversity of opinion and background within the field.[207] The colonial aspect comes from the European prejudices regarding subjects' intellectual abilities derived from the Kantian belief that the act of listening being seen as a "danger to the autonomy of the enlightened liberal subject."[207] As colonists reorganized the economic global order, they also created a system that tied social mobility to the ability to assimilate European schooling, forming a meritocracy of sorts.[207] Many barriers keep "postcolonial" voices out of the academic sphere such as the inability to recognize intellectual depth in local practices of knowledge production and transmission. If ethnomusicologists start to rethink the ways in which they communicate with one another, the sphere of academia could be opened to include more than just the written word, allowing new voices to participate.[207] Another topic of discussion for decolonizing ethnomusicology is the existence of archives as a legacy of colonial ethnomusicology or a model for digital democracy.[208] Comparative musicologists used archives such as the Berlin Phonogramm-Archiv to compare the musics of the world. The current functions of such public archives within institutions and on the internet has been analyzed by ethnomusicologists.[209] Activists and ethnomusicologists working with archives of recorded sound, like Aaron Fox, associate professor at Columbia University, have undertaken recovery and repatriation projects as an attempt at decolonizing the field. Another ethnomusicologist who has developed major music repatriation projects is Diane Thram, who works with the International Library of African Music.[210] Similar work has been dedicated towards film and field video.[209] |
32. 民族音楽学の脱植民地化 脱植民地化という考え方は、民族音楽学の分野では新しいものではない。2006年には早くもこの考えは民族音楽学会の中心的な話題となった[203]。 人文学や教育学では、脱植民地化という言葉は「社会正義、抵抗、持続性、保存を含む一連のプロセス」を表すために使われている[203]。 しかし民族音楽学では、脱植民地化は一部の学者によって比喩だと考えられている。 ニュージーランドの先住民研究教授、リンダ・トゥハイヴァイスは脱植民地化が取った転換について考察している[203]。脱植民地化は、かつては政府の道 具を引き渡す形式的なプロセスとみなされていたが、今では官僚的、文化的、言語的、心理的に植民地権力を切り離すことを含む長期的なプロセスとして認識さ れている」[204]。 「民族音楽学にとって、この変化は権力構造、世界観、学問、大学システムにおける根本的な変化が植民地主義との対決として分析される必要があることを意味 する[203]。 民族音楽学に対して提案されている脱植民地化されたアプローチは、学問を構成する哲学と方法論について反映させるものである[205]。 民族音楽学の脱植民地化には、複数の道筋がある。これらの提案されたアプローチは、i)民族音楽学者が学者としての役割に取り組むこと、ii)大学のシス テムが分析され改訂されること、iii)学問としての哲学、ひいては実践が変化することである[203] 民族音楽学会の学生ニュースの2016年秋冬号には、民族音楽学の脱植民地化について読者の意見を見るためにアンケートが掲載されている。異なるテーマ は、i)米国とヨーロッパからの民族音楽学の脱中心化、ii)学問の拡大/変革、iii)特権と権力の認識、iv)仲間や同僚の間で民族音楽学の脱植民地 化について実際に話すための空間の構築、であった[206]。 ブレンダン・キビーが民族音楽学の「脱植民地化」のために提案した問題の一つは、学者たちがアイデアや思想家の裾野を広げるために学問的実践をどのように 再編成しうるかということである。207]知的実践としてのリスニングに対する西洋的な偏見の影響が、分野内の意見や背景の多様性の欠如の理由である可能 性がある。 [207] 植民地的な側面は、聴くという行為が「啓蒙された自由主義的主体の自律性に対する危険」と見なされるというカント派の信念から派生した、対象の知的能力に 関するヨーロッパの偏見から来る[207] 植民地主義者は経済グローバル秩序を再編する際に、社会的流動性をヨーロッパの学校教育を同化する能力に結びつけるシステムを作り、ある種の能力主義社会 を形成している [207] 知識生産と伝達のローカルな実践における知的深さを認識できないなど多くの障壁によって、「ポストコロニアル」の声は学問領域から遠のいていくことにな る。もし民族音楽学者が互いにコミュニケーションをとる方法を再考し始めれば、学問の領域は単なる書き言葉以上のものを含むように開かれ、新しい声が参加 できるようになるかもしれない[207]。 比較音楽学者はベルリン・フォノグラム・アルキヴのようなアーカイブを世界の音楽を比較するために使われた。コロンビア大学の准教授であるアーロン・ フォックスのように、録音された音のアーカイブを扱う活動家や民族音楽学者は、この分野を脱植民地化する試みとして、回収や返還のプロジェクトに取り組ん でいる[209]。また、International Library of African Musicで活動しているDiane Thramは、主要な音楽の返還プロジェクトを展開している民族音楽学者である[210]。 |
| Ethnicity Giving a strict definition to ethnicity is considered difficult by many scholars, but it can be best understood in terms of the creation and preservation of boundaries, in contrast to the social "essences" in the gaps between these boundaries.[211] In fact, ethnic boundaries can both define and maintain social identities, and music can be used in local social situations by members of society to create such boundaries.[211] The idea of authenticity becomes relevant here, where authenticity is not a property of the music or performance itself, but is a way of telling both insiders and outsiders that this is the music that makes one's society unique.[212] Authenticity can also be seen as the idea that a certain music is inextricably bound to a certain group or physical place.[213] It can give insight into the question of the "origin" of music, in that it by definition bears connection to the geographical, historical, and cultural aspects of music.[213] For instance, holding that particular aspects of African-American music are actually fundamentally African is critical to claims of authenticity in the global African diaspora.[214] In terms of how authenticity can be connected to the concept of place, consider the concept of authenticity in Jewish music throughout the Jewish diaspora. "Jewish" music is bound to both the Land of Israel and the ancient Temple of Jerusalem.[215] Although groups are self-defining in how they express the differences between self and other, colonization, domination, and violence within developing societies cannot be ignored.[216] In a society, often dominant groups brutally oppress minority ethnicities from their classification systems. Music can be used as a tool to propagate dominant classifications in such societies, and has been used as such by new and developing states especially through control of media systems.[217] Indeed, though music can help define a national identity, authoritarian states can control this musical identity through technology, in that they end up dictating what citizens can listen to.[218] Governments often value music as a symbol, which can be used to promote supra-national entities.[219] They often use this to argue the right to participate in or control a significant cultural or political event, such as Turkey's involvement in the Eurovision Song Contest.[219] Historically, anthropologists have believed that ethnomusicologists deal with something that by definition cannot be synonymous with the social realities of the present world.[220] In response, ethnomusicologists sometimes present a concept of society that purely exists within an all-encompassing definition of music.[220] Ethnomusicologist Charles Seeger agrees with this, giving an example of how Suya society (in Brazil) can be understood in terms of its music. Seeger notes how "Suya society was an orchestra, its village was a concert hall, and its year a song."[221] Music helps one understand oneself in relation to people, places, and times.[222] It informs one's sense of physical place—a musical event (such as a collective dance) uniquely evokes collective memories and experiences of place. Both ethnomusicologists and anthropologists believe that music provides the means by which political and moral hierarchies are developed.[223] Music allows people to comprehend both identities and physical places, as well as the boundaries that divide them.[224] Gender is another area where boundaries are "performed" in music.[225] Instruments and instrumental performance can contribute to a society's definition of gender, in that behaviour of performers conforms to the gender expectations of society (e.g. men should not display effort, or women should feign reluctance to perform).[226] Issues of ethnicity and music intersect with gender studies in fields like historical musicology, the study of popular music, and ethnomusicology. Indeed, gender can be seen as a symbol of social and political order, and controlling gender boundaries is thus a means of controlling such order. Gender boundaries reveal the most deeply intrinsic forms of domination in a society, that subsequently provide a template for other forms of domination.[226] However, music can also provide a means of pushing back against these boundaries by blurring the boundary between what is traditionally considered male and female.[226] When one listens to foreign music, one tries to make sense of it in terms of one's own (familiar) music and musical worldviews, and this internal struggle can be seen as a power struggle between one's musical views and the other, foreign ones.[227] Sometimes, musicians celebrate ethnic plurality in problematic ways, in that they collect genres, and subsequently alter and reinterpret them in their own terms.[227] Societies often publicize so-called multi-cultural music performances simply for the promotion of their own self-image.[219] Such staged folklore begins to greatly diverge from the celebration of ethnic plurality it purportedly represents, and the music and dance being performed become meaningless when presented so entirely out of context.[219] In such a scenario, which is seen very commonly, the meaning of the performance is both created and controlled by the performers, the audience, and even the media of the society the performance takes place in.[219] Music rarely remains stable in contexts of social change -- "culture contact" causes music to be altered to whatever new culture it has come in contact with.[228] In this way, minority communities can internalize the outside world through music—a kind of sense-making.[228] They become able to deal with and control a foreign world on their own (musical) terms.[228] Indeed, such integration of musical difference is an integral aspect of the creation of a musical identity, which can be seen in Seeger's description of the Brazilian Suya, who took music from an outside culture and made it their own as an "assertion of identity in a multi-ethnic social situation."[228] In addition, consider the development of East Indian culture. Many of the trademarks of East Indian society, such as the caste system and the Bhojpuri form of the Hindi language, are becoming obsolete, which erodes their concept of ethnic identity.[229] In light of these conditions, music has begun to play an unprecedented role in the concept of East Indian ethnic identity[229] Music can also play a transformative part in the formation of the identities of urban and migrant communities, which can be seen in the diverse and distinct musical cultures in the melting pot of communities in the US.[230] In the case of colonialism, the colonizer and the colonized end up repeatedly exchanging musical ideas.[231] For instance, in the Spanish colonization of the indigenous Native Americans, the resulting mestizo music reflects the intersection of these two culture spheres, and even gave way to new modes of musical expression bearing aspects of both cultures.[231] Ethnicities and class identities have a complicated relationship. Class can be seen as the relative control a group has over economic (relating to means of production), cultural, political, and social assets in various social areas.[232] In the case of migrant communities, the divide between the concepts of ethnicity and class blur (for instance, one ethnic group/class level provides cheap labor for the other, such as in the case of Latinx Mexican immigrants performing cheap farming labor for White Americans).[230] This blurring can also be seen in Zimbabwe, where White settlers determined a hierarchical social order divided by ethnicity: Blacks, others "coloureds," Asians, and Whites (who were at the top of the hierarchy).[232] The concept of "geographical heritage" (where one cannot change where one's ancestors come from) contributed to this concept of immutability of this constructed hierarchy; White settlers enforced the ranks of this hierarchy through their definition of how "civilized" each ethnic group was (Whites being the most civilized).[232] However, one cannot simply match a class with a single musical style, as musical styles reflect the complex and often contradictory aspects of the society as a whole.[233] Marxist subcultural theory proposes that subcultures borrow and alter traits from the dominant culture to create a newly diverse range of available traits where the signs of the dominant culture remain, but are now part of a new and simultaneously subversive whole.[233] In fact, ethnicities are similar to classes in many ways. They are often either defined or excluded based on the rules of the dominant classificatory system of the society.[234] Thus, ethnic minorities are forced to figure out how to create their own identities within the control of the dominant classifications.[234] Ethnic minorities can also use music in order to resist and protest the dominant group. This can be seen in European Jews, African Americans, Malaysian-Chinese, and even in the Indonesian-Chinese, who expressed resistance through Chinese theater performances.[235] |
33. エスニシティ=民族性 エスニシティに厳密な定義を与えることは多くの学者によって困難であると考えられているが、境界の創造と維持という観点から、これらの境界の間の隙間にあ る社会的「本質」と対照的に最もよく理解されることができる[211]。 [211] 実際、民族の境界は社会的アイデンティティを定義し維持することができ、音楽はそのような境界を作り出すために社会のメンバーによってローカルな社会的状 況で使われることができる[211] 真正性の考え方はここで関連しており、真正性は音楽やパフォーマンス自体の特性ではなく、これが自分の社会をユニークにしている音楽だと内部者と外部者の 両方に伝える方法である。 [212] 真正性はまた、ある音楽がある集団や物理的な場所と密接に結びついたものであるという考えとみなすことができる[213]。音楽の地理的、歴史的、文化的 側面と定義的に関係を持つという点で、それは音楽の「起源」の問題に対して洞察を与えることができる。 [213] 例えば、アフリカ系アメリカ人音楽の特定の側面が実際には基本的にアフリカ系であるとすることは、グローバルなアフリカ系ディアスポラにおける真正性の主 張にとって重要である[214] 真正性が場所の概念といかに結び付けられるかという点で、ユダヤ系ディアスポラにおけるユダヤ音楽の真正性の概念を考えてみる。「ユダヤ人」音楽はイスラ エルの土地とエルサレムの古代の神殿の両方と結び付いている[215]。 集団は自己と他者の間の差異をどのように表現するかという点で自己定義的であるが、発展途上社会における植民地化、支配、暴力は無視できない[216]。 社会においては、しばしば支配的集団がその分類体系から少数民族を残酷に抑圧する。音楽はそのような社会における支配的な分類を広めるための道具として使 われることがあり、特にメディアシステムのコントロールを通じて新・発展途上国によってそのように使われてきた[217]。実際、音楽は国民のアイデン ティティを定めるのに役立つが、権威主義の国家は、結局は国民が何を聴くことができるかについて決定するという意味で、テクノロジーを通じてこの音楽のア イデンティティをコントロールすることができるのである[218]。 [219]政府はしばしば、ユーロビジョン・ソング・コンテストへのトルコの参加のような重要な文化的または政治的イベントへの参加または支配の権利を主 張するためにこれを使う。 歴史的に人類学者は、民族音楽学者は定義上、現在の世界の社会的現実と同義になりえないものを扱っていると考えてきた[220]。これに対して、民族音楽 学者は純粋に音楽のすべてを網羅する定義の中に存在する社会の概念を提示することがある[220] 民族音楽学者のチャールズ・シーガーはこれに同意し、ブラジルのスヤ社会がその音楽の観点から理解できることを例としてあげている。シーガーは「スヤ社会 はオーケストラであり、その村はコンサートホールであり、その年は歌であった」と記している[224]。 音楽は人が人、場所、時間との関係において自分自身を理解することを助ける[222]。音楽は物理的な場所の感覚を知らせ、(集団ダンスのような)音楽イ ベントは場所に関する集団の記憶と経験を独自に呼び起こす。民族音楽学者も人類学者も、音楽は政治的・道徳的ヒエラルキーが形成される手段を提供すると考 えている[223]。音楽によって人々はアイデンティティと物理的場所の両方、そしてそれらを隔てる境界線を理解することができるようになる。 楽器や楽器演奏は、演奏者の振る舞いが社会のジェンダー的期待に適合するという点で、社会のジェンダーの定義に貢献することができる(例えば、男性は努力 を見せるべきではない、女性は演奏に消極的なふりをするべき)[226] 民族性と音楽の問題は歴史音楽学、ポピュラー音楽研究、民族音楽学などの分野でのジェンダー研究との交差を見せることがある。実際、ジェンダーは社会的・ 政治的秩序の象徴とみなすことができ、ジェンダーの境界をコントロールすることはそのような秩序をコントロールする手段である。しかし、音楽は伝統的に男 性と女性として考えられているものの間の境界を曖昧にすることによって、これらの境界を押し返す手段を提供することもできる[226]。 外国の音楽を聴くとき、人は自分の(慣れ親しんだ)音楽や音楽の世界観でその意味を理解しようとするが、この内輪もめは、自分の音楽観と他の、外国の音楽 観との間の権力闘争と見ることができるだろう。音楽家がジャンルを収集し、その後それらを自分たちの言葉で変更し再解釈するという問題のある方法で民族の 複数性を祝うこともある。社会はしばしば、いわゆる多文化音楽のパフォーマンスを、単に自分たちの自己イメージの宣伝のために公表している。このような演 出されたフォークロアは、それが称している民族の多元性の祝典から大きく乖離し始め、演奏される音楽やダンスは、完全に文脈から外れて提示されると無意味 なものとなってしまう。ごく普通に見られるこのようなシナリオでは、パフォーマンスの意味は、演者、観客、さらにはパフォーマンスが行われる社会のメディ アによって創られ、コントロールされることになる。 このようにして、マイノリティのコミュニティは音楽を通して外界を内面化することができる-一種の意味づけ[228]-彼らは自分たちの(音楽の)用語で 外界を扱い、コントロールすることができるようになる。 [実際、このような音楽的差異の統合は音楽的アイデンティティの創造に不可欠な側面であり、それはシーガーが「多民族社会状況におけるアイデンティティの 主張」として外部文化の音楽を取り入れ、それを自分たちのものにしたブラジルのスヤについて述べたことに見ることができる[228] さらに、東インド文化の発展について考えてみると、東インド社会のトレードマークの多くは、音楽的アイデンティティの創造に不可欠なものである。カースト 制度やヒンディー語のボジュプリ形式といった東インド社会の商標の多くは陳腐化しつつあり、それは彼らの民族的アイデンティティの概念を侵食する [229]。こうした状況を踏まえ、音楽は東インドの民族的アイデンティティの概念においてかつてない役割を果たすようになった[229] また都市や移民のコミュニティのアイデンティティ形成において音楽が変革的役割を果たすことがあるが、それはアメリカにおけるコミュニティのるつぼにおけ る多様かつ異なる音楽文化に見て取ることが可能であろう。 [例えば、スペインによるアメリカ先住民の植民地化において、結果として生じたメスティーソ音楽はこれら二つの文化圏の交わりを反映し、さらには両文化の 側面を持つ新しい音楽表現様式をもたらした[231]。 エスニシティと階級的アイデンティティは複雑な関係を持っている。階級は、ある集団が様々な社会的領域において経済的(生産手段に関連する)、文化的、政 治的、社会的資産を相対的に支配していると見ることができる[232] 移民コミュニティの場合、エスニシティと階級の概念の間の境界は曖昧である(例えば、一方のエスニックグループ/階級レベルは他方に安い労働力を提供して おり、ラテン系のメキシコ移民は白人アメリカ人に安い農業労働を提供しているという事例)[230] このぼかしは、白人入植者が民族によって分けられる階層的社会秩序を定めたジンバブエにも見ることができる。黒人、その他の「有色人種」、アジア人、そし て白人(彼らはヒエラルキーの頂点にいた)。地理的遺産」(自分の祖先がどこから来たかを変えることができない)という概念は、この構築されたヒエラル キーの不変性の概念に貢献した。白人入植者は、各民族がどれだけ「文明的」であるかの定義を通じてこの階層のランクを強制した(白人が最も文明的) [232]。 しかし、音楽スタイルは社会全体の複雑でしばしば矛盾する側面を反映しているので、単純に階級を単一の音楽スタイルに合わせることはできない[233] マルクス主義のサブカルチャー理論は、サブカルチャーが支配的文化の徴候が残っているが、今は新しい、同時に破壊的な全体の一部であるような、新たに多様 で利用できる徴候の範囲を作り出すために支配的文化から特徴を借りて変更すると提案する[233] 実際、民族は多くの点で階級と類似している。彼らはしばしば社会の支配的な分類システムのルールに基づいて定義されるか排除される[234]。 したがって、少数民族は支配的な分類のコントロールの中で彼ら自身のアイデンティティをいかに創造するかを考えなければならない[234] 少数民族は支配集団に抵抗し抗うために音楽を使うこともできる。これはヨーロッパのユダヤ人、アフリカ系アメリカ人、マレーシア系中国人、さらには中国演 劇のパフォーマンスを通じて抵抗を表明したインドネシア系中国人に見ることができる[235]。 |
| Medical
Ethnomusicology. Scholars have characterized medical ethnomusicology as "a new field of integrative research and applied practice that explores holistically the roles of music and sound phenomena and related praxes in any cultural and clinical context of health and healing". Medical ethnomusicology often focuses specifically on music and its effect on the biological, psychological, social, emotional, and spiritual realms of health. In this regard, medical ethnomusicologists have found applications of music to combat a broad range of health issues; music has found usage in the treatment of autism, dementia, AIDS and HIV, while also finding use in social and spiritual contexts through the restoration of community and the role of music in prayer and meditation. Recent studies have also shown how music can help to alter mood and serve as cognitive therapy.[236] |
34. 医療民族音楽学
(Medical Ethnomusicology) 医療民族音楽学は、「健康と癒しという文化的・臨床的状況における音楽と音響現象の役割と関連する実践を総合的に探求する、統合的研究と応用実践の新分 野」と学者たちは位置づけています。医療民族音楽学では、音楽と、それが健康の生物学的、心理的、社会的、感情的、精神的領域に及ぼす影響に特に焦点を当 てることが多い。音楽は自閉症、認知症、エイズ、HIVの治療に使われる一方、コミュニティの回復や、祈りや瞑想における音楽の役割を通じて、社会的・精 神的な文脈でも使われていることが分かっているのです。最近の研究では、音楽がいかに気分を変えるのに役立ち、認知療法として機能するかも示されている [236]。 |
| Ethnochoreology Definition The definition of ethnochoreology stands to have many similarities with the current way of studying of ethnomusicology. With ethnochoreology's roots in anthropology taken into account, and by the way that it is studied in the field, dance is most accurately defined and studied within this academic circle as two parts: as "an integral part of a network of social events" and "as a part of a system of knowledge and belief, social behavior and aesthetic norms and values".[238] That is, the study of dance in its performance aspects—the physical movements, costumes, stages, performers, and accompanied sound- along with the social context and uses within the society where it takes place. Beginnings Because of its growth alongside ethnomusicology, the beginning of ethnochoreology also had a focus on the comparative side of things, where the focus was on classifying different styles based on the movements used and the geographical location in a way not dissimilar to Lomax. This is best shown in "Benesh Notation and Ethnochoreology" in 1967 which was published in the ethnomusicology journal, where Hall advocates using the Benesh notation as a way of documenting dance styles so that it is "possible to compare styles and techniques in detail — even 'schools' within one style — and individual variations in execution from dancer to dancer."[239] In the seventies and eighties, like with ethnomusicology, ethnochoreology had a focus on a very specific communicative type of "folklore music" performed by small groups and the context and performance aspects of dance were studied and emphasized to be a part of a whole "folkloric dance" that needed to be preserved. This was influenced by the same human centered "thick description" way of study that had moved into ethnomusicology. However, at this time, the sound and dance aspects of the performances studied were still studied and analyzed a bit separately from the context and social aspects of the culture around the dance.[240] Current Beginning in the mid eighties, there has been a reflexively interpretive way of writing about dance in culture that is more conscious of the impact of the scholar within the field and how it affects the culture and its relationship with the dance that the scholar is looking into.[240] For example, because most scholars until this point were searching for the most "authentic" folk, there was a lack of study on individual performers, popular dances, and dances of subgroups groups within a culture such as women, youth, and members of the LGBT community. In contrast, this newer wave of study wanted a more open study of dance within a culture. Additionally, there was a shift for a more mutual give and take between the scholar and the subjects, who in field work, also assist the scholars as teachers and informants.[241] Differences with Ethnomusicology Although there are many similarities between ethnochoreology and ethnomusicology, there is a large difference between the current geographical scope of released studies. For example, from the beginning of ethnomusicology, there was a large focus on African and Asian musics, due to them seeming to have the most deviation from their norm while ethnochoreology, also beginning in Europe, has long had extensive studies of the Eastern European "folk dances" with relatively little of African and Asian dances, however American studies have delved into Native American and Southeast Asian dance.[242] However, the very basis of this being a difference could be challenged on the basis that many European ethnomusicological and ethnochoreological studies have been done on the "home" folk music and dance in the name of nationalism. Organizations "ICTM Study Group on Ethnochoreology". International Council for Traditional Music., beginning in 1962 as a Folk Dance Commission before giving itself its current name in the early seventies. With the objectives of promoting research, documentation, and interdisciplinary study of dance; providing a forum for cooperation among scholars and students of ethnochoreology by means of international meetings, publications, and correspondence; and contributing to cultural and societal understandings of humanity through the lens of dance, the Study Group meets biennially for a conference. The "Congress on Research in Dance"., CORD for short, currently known as the Dance Studies Association (DSA) after merging with the Society of Dance History Scholars began 1964. CORD's purposes are stated to be to encourage research in all aspects of dance and related fields;to foster the exchange of ideas, resources, and methodologies through publications, international and regional conferences and workshops; and to promote the accessibility of research materials. CORD publishes a peer-reviewed scholarly journal known as, The Dance Research Journal, twice annually. |
35. 民族舞踊学 定義 エスノコレオロジー(民族舞踊学)の定義は、現在の民族音楽学の研究方法と多くの類似点があるように思われる。エスノコレオロジーが人類学に根ざしている ことを考慮すると、この学問領域では、ダンスは「社会的事象のネットワークの不可欠な部分」と「知識と信念、社会行動、美的規範と価値のシステムの一部」 [238]として、最も正確に定義・研究されていることになる。 始まり 民族音楽学と並行して発展してきたため、民族舞踊学の始まりも比較の側面が強く、使われる動きや地理的な場所によって異なるスタイルを分類するという、 ローマックスと似て非なる方法に焦点が当てられていた。このことは、1967年に民族音楽学の雑誌に発表された「ベネシュ記譜法と民族音楽学」によく表れ ています。ホールは、ダンスのスタイルを記録する方法としてベネシュ記譜法を使うことを提唱し、「スタイルやテクニック、さらにはひとつのスタイルの中の 「派」、ダンサーによって異なる個々の実行方法を詳細に比較できる」ようにしたのです。70年代から80年代にかけて、民族音楽学と同様に、エスノコレオ ロジーでは、小さな集団によって演じられる非常に特殊なコミュニケーション型の「民俗音楽」に焦点が当てられ、ダンスの文脈やパフォーマンスの側面は、保 存すべき「民俗舞踊」全体の一部として研究・強調された。これは、民族音楽学に移ってきたのと同じ人間中心の「厚い記述」の研究方法の影響を受けている。 しかし、この頃はまだ、研究されるパフォーマンスの音や踊りの側面は、踊りを取り巻く文化の文脈や社会的側面と少し分けて研究・分析されていた。 現在 80年代半ばから、文化におけるダンスについて、その分野の学者が与える影響や、その学者が調べているダンスと文化との関係をより意識した、反射的な解釈 の書き方が見られるようになったのです。たとえば、それまでの学者の多くは、最も「本物」のフォークを探し求めていたため、個々のパフォーマーやポピュ ラーダンス、女性や若者、LGBTコミュニティのメンバーといった文化内のサブグループ集団のダンスに関する研究が不足していました。これに対して、この 新しい研究の波は、文化の中のダンスについてのよりオープンな研究を求めています。また、フィールドワークでは、研究者は教師として、また情報提供者とし て研究者を支援します。 民族音楽学との違い エスノコレオロジーとエスノミュージックの間には多くの類似点があるが、現在発表されている研究の地理的範囲には大きな違いがある。例えば、民族音楽学は 当初からアフリカやアジアの音楽が最も規範から逸脱しているとされ、大きな関心を集めていた。一方、民族舞踊学はヨーロッパで始まり、東ヨーロッパの「民 族舞踊」が長く研究されてきたが、アフリカやアジアの舞踊は比較的少なく、アメリカの研究はネイティブアメリカンと東南アジアの舞踊に踏み込んでいる [242]。しかし、ヨーロッパではナショナリズムの名のもとに、「本場」の民族音楽・舞踊を対象とした民族音楽学・民族舞踊学研究が多く行われてきたこ とを根拠に、この違いが問われる可能性がある。 組織 「ICTM民族舞踊研究会」。国際伝統音楽評議会。1962年に民族舞踊委員会として始まり、70年代初頭に現在の名称になった。舞踊の研究、記録、学際 的な研究を促進すること、国際会議、出版、通信によって民族舞踊学の学者や学生が協力する場を提供すること、舞踊というレンズを通して文化や社会の人間理 解に貢献することを目的に、研究会は2年ごとに会議を開催している。 「ダンス研究会議」、略してCORDは、ダンス史研究者協会と合併し、現在はダンス研究協会(DSA)として知られているが、1964年に始まった。 CORDの目的は、ダンスとその関連分野のあらゆる側面における研究を奨励し、出版物、国際・地域会議、ワークショップを通じてアイデア、リソース、方法 論の交換を促進し、研究資料の入手を促進することにあるとされている。CORDは、査読付きの学術誌「The Dance Research Journal」を年2回発行している。 |
| List
of ethnomusicologists. Choreomusicology Ethnochoreology Society for Ethnomusicology Fumio Koizumi Prize for Ethnomusicology List of musicologists List of musicology topics Musicology Prehistoric music Smithsonian Folkways Sociomusicology World music International Council for Traditional Music Society for Ethnomusicology |
民族音楽学者の一覧。 舞踏音楽学 民族舞踏学 民族音楽学会 民族音楽学小泉文夫賞 音楽学者の一覧 音楽学トピックの一覧 音楽学 先史時代の音楽 スミソニアン・フォークウェイズ 社会音楽学 ワールドミュージック 国際伝統音楽評議会 民族音楽学会 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnomusicology | https://www.deepl.com/ja/translator |
 【再掲】 【再掲】Jaap Kunst (12 August 1891 – 7 December 1960) was a Dutch musicologist. He is credited with coining the term "ethnomusicology" as a more accurate name for the field then known as comparative musicology. Kunst studied the folk music of the Netherlands and of Indonesia. His published work totals more than 70 texts.[1] Early life Kunst was born in 1891 in Groningen. Both of his parents were musicians, and his father was a music-school teacher. He began to study the violin at only 5 years old, and continued to play the instrument throughout his life.[2][3] Kunst was drawn toward folk music as a result of vacations to the island of Terschelling.[3] Kunst decided to pursue a career in law. While studying law, Kunst published the results of his first musical research.[4] Kunst earned a degree in law from the University of Groningen in 1917. and pursued a career in banking and law for the next two years.[2] However, he soon tired of this work.[4] Work in Indonesia In 1919, Kunst set out on a tour of the Dutch East Indies with a recently-formed musical trio. This group performed 95 times throughout Indonesia.[2] Kunst heard a gamelan ensemble for the first time at the Paku Alaman palace in Yogyakarta. Impressed, he decided to remain in Java to study Indonesian music, while the other members of his trio departed.[2] Taking a job as an official in the colonial government, Kunst remained in Java for fifteen years.[4] He married Kathy van Wely in 1921; she became a partner in Kunst's work.[2][4] Kunst was the first person to record gamelan music on wax cylinders. He amassed an archive of photographs, recordings, and instruments of Indonesian music.[2][4] He ceded much of his collection to the Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (now the National Museum of Indonesia).[2] Later activities In 1934, Kunst returned to the Netherlands, and he became the curator of Amsterdam's Colonial Museum (now the Royal Tropical Institute) in 1936.[2] Later, he became a lecturer at the University of Amsterdam.[4] Kunst first used the term "ethno-musicology" in his 1950 publication Musicologica. He stated: The name of our science is, in fact, not quite characteristic; it does not 'compare' any more than any other science. A better name, therefore, is that appearing on the title page of this book: ethno-musicology.[5] Ethnomusicology (with no hyphen) quickly replaced comparative musicology as the name of the field. This usage was influenced by the formation of the Society for Ethnomusicology in 1955. In 1956, Kunst released a bestselling album of folk songs, on Folkways Records, entitled Living Folksongs and Dance-Tunes from the Netherlands.[6] Kunst died in 1960 of throat cancer in Amsterdam.[4] Ideas Kunst believed musical study must take into account the cultural context of its creation. In his view, musicology was incomplete without ethnographic elements. Contrary to mainstream European scholarship at the time, Kunst believed that music from other continents was no less sophisticated than the music of Europe, and he often argued this point against others.[4] Legacy Since 1965, the Society for Ethnomusicology has offered an annual prize named after Kunst. Until 2018, the prize honored the most significant ethnomusicological article of the previous year by a society member. From 2019 onward, only researchers in their first 10 years of scholarship are eligible for the prize.[7] Writings with C. Kunst-van Wely. De Toonkunst van Bali. (Weltevreden, 1924; part 2 in Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde, LXV, Batavia, 1925) with R. Goris. Hindoe-Javaansche muziekinstrumenten. (Batavia, 1927; 2nd ed., revised, Hindu-Javanese Musical Instruments, 1968) A Study on Papuan Music (Weltevreden, 1931) Musicologisch onderzoek 1931 (Batavia, 1931) Over zeldzame fluiten en veelstemmige muziek in het Ngada- en Nagehgebied, West-Flores (Batavia, 1931) De toonkunst van Java (The Hague, 1934; English translation, Music in Java, 1949; 3rd ed., expanded, 1973) Een en ander over den Javaanschen gamelan (Amsterdam, 1940; 4th ed. 1945) Music in Flores: A Study of the Vocal and Instrumental Music Among the Tribes Living in Flores (Leiden, 1942) Music in Nias (Leiden, 1942) Around von Hornbostel's Theory of the Cycle of Blown Fifths (Amsterdam, 1948) The Cultural Background of Indonesian Music (Amsterdam, 1949) Begdja, het gamelanjongetje (Amsterdam, 1950) De inheemsche muziek in Westelijk Nieuw-Guinea (Amsterdam, 1950) Metre, Rhythm, and Multi-part Music (Leiden, 1950) Musicologica: A Study of the Nature of Ethnomusicology, Its Problems, Methods, and Representative Personalities (Amsterdam, 1950; 2nd ed., expanded, retitled Ethnomusicology, 1955; 3rd ed. 1959) Kultur-historische Beziehungen zwischen dem Balkan und Indonesien (Amsterdam, 1953, English translation, 1954) Sociologische bindingen in de muziek (The Hague, 1953) https://en.wikipedia.org/wiki/Jaap_Kunst |
 【再掲】 【再掲】ヤープ・クンスト(Jaap Kunst、1891 年8月12日 - 1960年12月7日)はオランダの音楽学者。当時比較音楽学として知られていた分野を、より正確な名称として「民族音楽学 (ethnomusicology)」と命名したことで知られる。クンストはオランダとインドネシアの民族音楽を研究した。出版された著作は70冊以上に 及ぶ[1]。 生い立ち クンストは1891年にフローニンゲンで生まれた。両親は音楽家で、父親は音楽学校の教師だった。わずか5歳でヴァイオリンを習い始め、生涯ヴァイオリン を弾き続けた[2][3]。 クンストは法律の道に進むことを決意。1917年にフローニンゲン大学で法学の学位を取得したクンストは、その後2年間、銀行と法律の仕事を追求した [2]が、すぐにこの仕事に飽きてしまった[4]。 インドネシアでの仕事 1919年、クンストは結成されたばかりの音楽トリオとともにオランダ領東インド諸島のツアーに出発。クンストはジョグジャカルタのパク・アラマン宮殿で 初めてガムラン・アンサンブルを聴いた。1921年にキャシー・ヴァン・ヴェリーと結婚し、彼女はクンストの活動のパートナーとなった[2][4]。 クンストはガムラン音楽をワックス・シリンダーに録音した最初の人物である。彼はインドネシア音楽の写真、録音、楽器のアーカイブを蓄積した[2] [4]。彼はコレクションの多くをKoninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen(現在のインドネシア国立博物館)に寄贈した[2]。 その後の活動 1934年、クンストはオランダに戻り、1936年にアムステルダムのコロニアル博物館(現在の王立熱帯研究所)の学芸員となった[2]。その後、アムス テルダム大学の講師となった[4]。 クンストが初めて「民族音楽学」という言葉を使ったのは、1950年に出版した『ムジコロジカ』の中である。彼はこう述べている: 私たちの科学の名前は、実際には、まったく特徴的ではありません。したがって、より良い名前は、本書のタイトルページにある「民族音楽学」である[5]。 民族音楽学(ハイフンなし)は、すぐに比較音楽学に取って代わり、この分野の名称となった。この用法は、1955年に民族音楽学会が結成されたことが影響 している。 1956年、クンストはフォークウェイズ・レコードから『Living Folksongs and Dance-Tunes from the Netherlands』というタイトルの民謡のベストセラー・アルバムをリリースした[6]。 クンストは1960年に咽頭癌のためアムステルダムで死去した[4]。 思想 クンストは、音楽研究はその創作の文化的背景を考慮に入れなければならないと考えていた。彼の考えでは、音楽学は民族誌的要素なしには不完全であった。当 時主流だったヨーロッパの学問とは異なり、クンストは他の大陸の音楽もヨーロッパの音楽に劣らず洗練されていると信じており、しばしばこの点を他の研究者 に反論していた[4]。 遺産 1965年以来、民族音楽学会はクンストの名を冠した賞を毎年授与している。2018年まで、この賞は学会員による前年の最も重要な民族音楽学的論文を称 えていた。2019年以降は、奨学生になってから10年目の研究者のみが受賞対象となる[7]。 文献 with C. Kunst-van Wely. De Toonkunst van Bali. (Weltevreden, 1924; part 2 in Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde, LXV, Batavia, 1925) with R. Goris. Hindoe-Javaansche muziekinstrumenten. (Batavia, 1927; 2nd ed., revised, Hindu-Javanese Musical Instruments, 1968) A Study on Papuan Music (Weltevreden, 1931) Musicologisch onderzoek 1931 (Batavia, 1931) Over zeldzame fluiten en veelstemmige muziek in het Ngada- en Nagehgebied, West-Flores (Batavia, 1931) De toonkunst van Java (The Hague, 1934; English translation, Music in Java, 1949; 3rd ed., expanded, 1973) Een en ander over den Javaanschen gamelan (Amsterdam, 1940; 4th ed. 1945) Music in Flores: A Study of the Vocal and Instrumental Music Among the Tribes Living in Flores (Leiden, 1942) Music in Nias (Leiden, 1942) Around von Hornbostel's Theory of the Cycle of Blown Fifths (Amsterdam, 1948) The Cultural Background of Indonesian Music (Amsterdam, 1949) Begdja, het gamelanjongetje (Amsterdam, 1950) De inheemsche muziek in Westelijk Nieuw-Guinea (Amsterdam, 1950) Metre, Rhythm, and Multi-part Music (Leiden, 1950) Musicologica: A Study of the Nature of Ethnomusicology, Its Problems, Methods, and Representative Personalities (Amsterdam, 1950; 2nd ed., expanded, retitled Ethnomusicology, 1955; 3rd ed. 1959) Kultur-historische Beziehungen zwischen dem Balkan und Indonesien (Amsterdam, 1953, English translation, 1954) Sociologische bindingen in de muziek (The Hague, 1953) https://en.wikipedia.org/wiki/Jaap_Kunst |
 このHP
は、科学研究費補助金「中米・カリブにおける感覚のエスノグラフィーに関する実証研究」21K18363,
の助成を受けたものである。
このHP
は、科学研究費補助金「中米・カリブにおける感覚のエスノグラフィーに関する実証研究」21K18363,
の助成を受けたものである。
Links
リ ンク
文 献
そ
の他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆