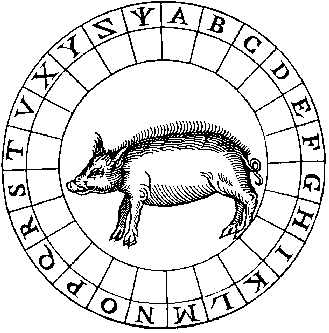ラ・メトリ『人間=機械論』ノート
L'homme machine revisited in post-modern era
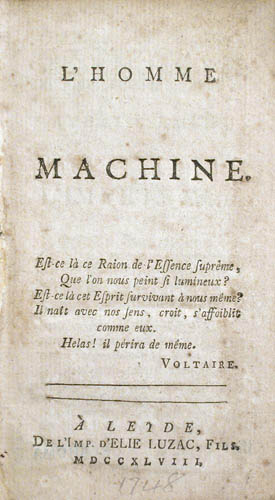

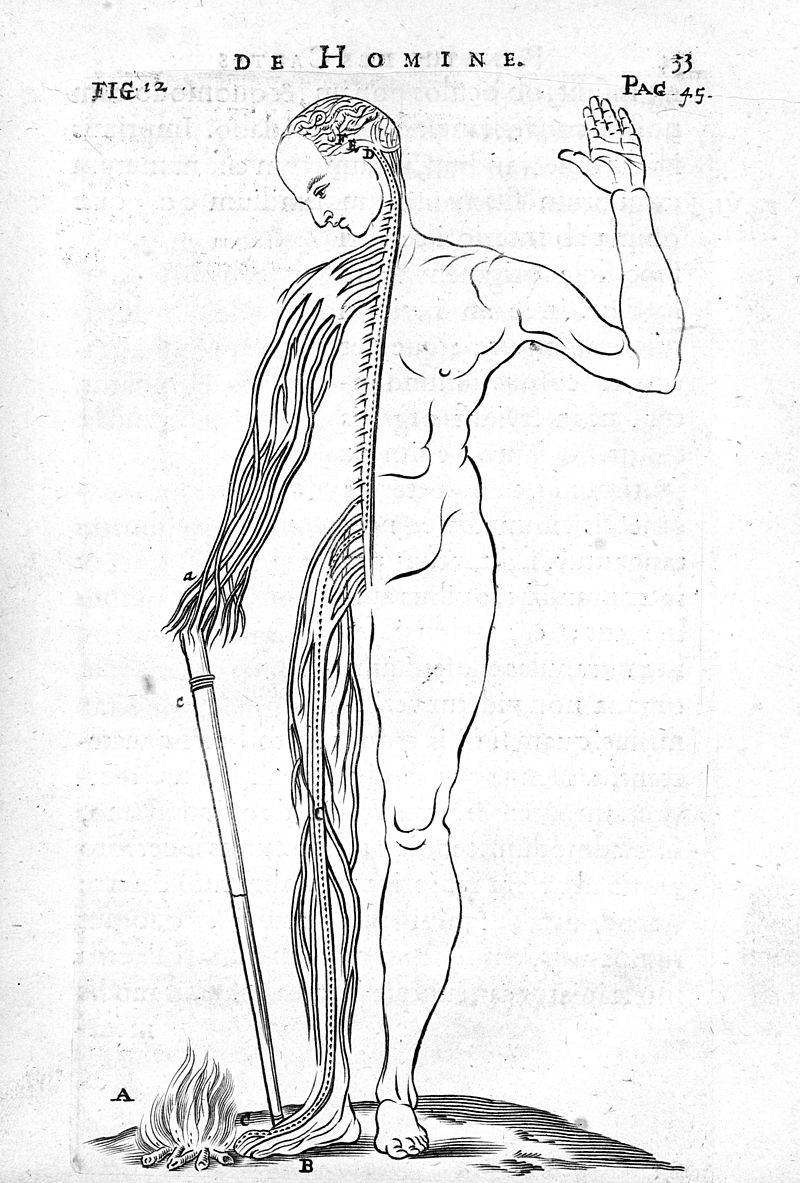
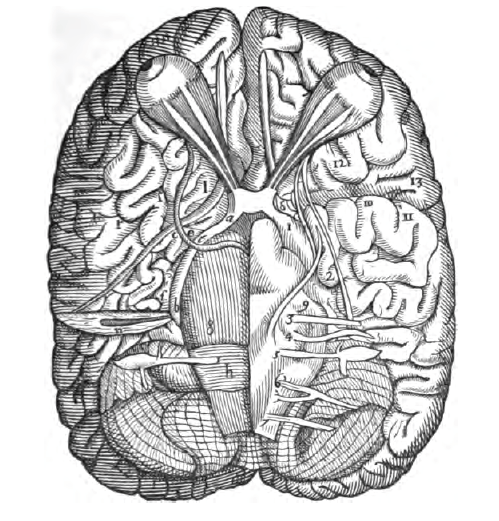
ラ・メトリ『人間=機械論』ノート
L'homme machine revisited in post-modern era
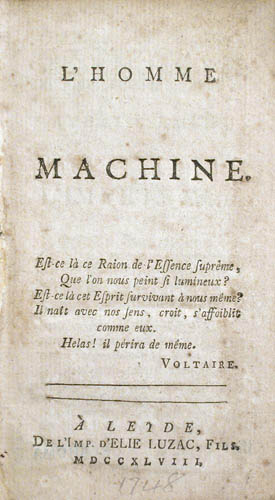

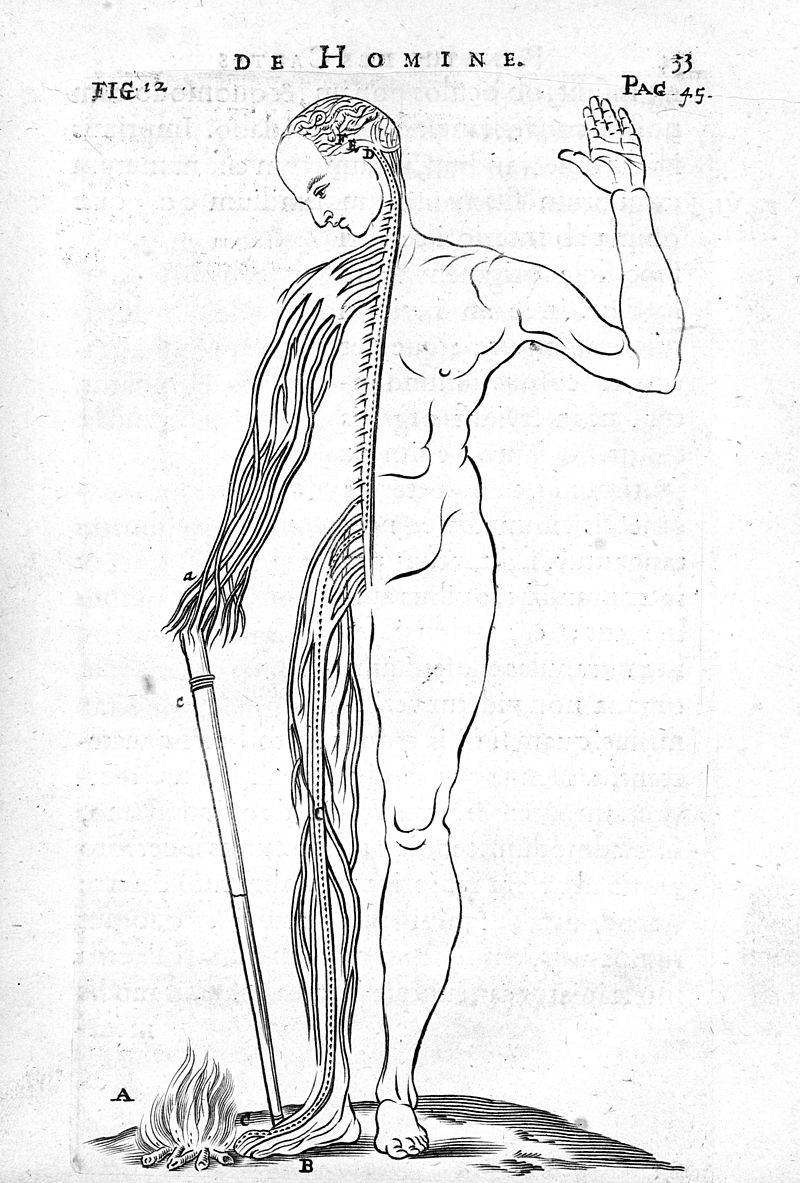
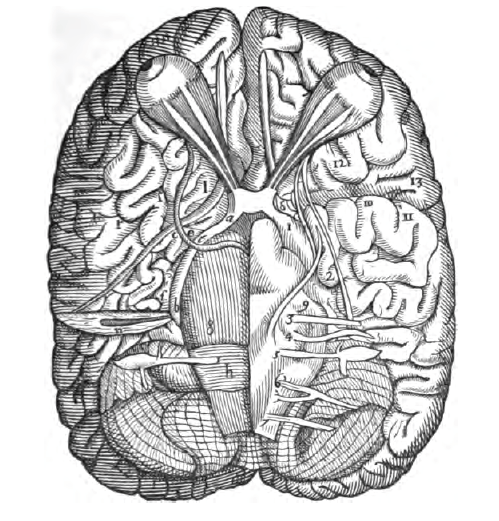
Page de titre de l'édition
originale./La Mettrie/essin anatomique (1662) décrivant le système
nerveux./Dessin anatomique (1573) décrivant la morphologie du cerveau./
「人間は身体的感覚(sensibilité physique) によっていったん動き始めると,そのあらゆる行為を必然的に行っていく、ひとつの機械である」Claude Adrien Helvétius(1715-1771)
★英訳からの重訳テキストへのサイト内タグジャンプはこちら(オリジナルテキスト)L'homme machine (Man a Machine).(重訳『人間=機械論』)
| Julien Offray de La
Mettrie (French: [ɔfʁɛ də la metʁi]; November 23, 1709[1] – November
11, 1751) was a French physician and philosopher, and one of the
earliest of the French materialists of the Enlightenment. He is best
known for his work L'homme machine (Man a Machine).[2] La Mettrie is most remembered for taking the position that humans are complex animals and no more have souls than other animals do. He considered that the mind is part of the body and that life should be lived so as to produce pleasure (hedonism). His views were so controversial that he had to flee France and settle in Berlin. |
ジュリアン・オフレイ・ド・ラ・メトリ(フランス語:[ɔfʁɛ,
1709[1] 11月23日 -
1751年11月11日)は、フランスの医師、哲学者で、啓蒙主義におけるフランスの最も早い唯物論者の一人であった。著書『機械としての人間』
(L'homme machine)が最もよく知られている[2]。 ラ・メトリは、人間は複雑な動物であり、他の動物と同様に魂を持っていないとする立場をとったことで最もよく知られている。彼は、心は身体の一部であり、 人生は快楽を生み出すように生きるべきであると考えた(快楽主義)。そのため、彼はフランスを脱出し、ベルリンに移住した。 |
| La Mettrie was born at
Saint-Malo in Brittany on November 23, 1709, and was the son of a
prosperous textile merchant. His initial schooling took place in the
colleges of Coutances and Caen. After attending the Collège du Plessis
in Paris, he seemed to have acquired a vocational interest in becoming
a clergyman, but after studying theology in the Jansenist schools for
some years, his interests turned away from the Church. In 1725, La
Mettrie entered the College d'Harcourt to study philosophy and natural
science, probably graduating around 1728. At this time, D'Harcourt was
pioneering the teaching of Cartesianism in France.[3] In 1734, he went
on to study under Hermann Boerhaave, a renowned physician who,
similarly, had originally intended on becoming a clergyman. It was
under Boerhaave that La Mettrie was influenced to try to bring changes
to medical education in France.[4] |
ラ・メトリは、1709年11月23日、ブルターニュのサン・マロで、
繊維商として栄えた息子のもとに生まれた。初めはクタンスとカーンのカレッジで教育を受けた。パリのコレージュ・デュ・プレシに入学し、聖職者になること
を志したようだが、数年間ヤンセニスト派の学校で神学を学んだ後、その関心は教会から遠のいた。1725年、ラ・メトリはダルクール大学に入学し、哲学と
自然科学を学び、おそらく1728年頃に卒業した。1734年、高名な医師であったヘルマン・ボエルハーヴェに師事するが、彼もまた元々は聖職者になるつ
もりであった。ボエルハーヴェのもとで、ラ・メトリはフランスの医学教育に変化をもたらそうとする影響を受けた[4]。 |
| Medical career After his studies at D'Harcourt, La Mettrie decided to take up the profession of medicine. A friend of the La Mettrie family, François-Joseph Hunauld, who was about to take the chair of anatomy at the Jardin du Roi, seems to have influenced him in this decision. For five years, La Mettrie studied at faculty of medicine in Paris, and enjoyed the mentorship of Hunauld.[3] In 1733, however, he departed for Leiden to study under the famous Herman Boerhaave. His stay in Holland proved to be short but influential. In the following years, La Mettrie settled down to professional medical practice in his home region of Saint-Malo, disseminating the works and theories of Boerhaave through the publication and translation of several works. He married in 1739 but the marriage, which produced two children, proved an unhappy one. In 1742 La Mettrie left his family and travelled to Paris, where he obtained the appointment of surgeon to the Gardes Françaises regiment, taking part in several battles during the War of the Austrian Succession. This experience would instill in him a deep aversion to violence which is evident in his philosophical writings. Much of his time, however, was spent in Paris, and it is likely that during this time he made the acquaintance of Maupertuis and the Marquise de Châtelet.[3] |
医学の道へ ダルクールで学んだ後、ラ・メトリは医学の道に進むことを決意する。この決断は、ラ・メトリ家の友人で、ジャルダン・デュ・ロワの解剖学教授に就任しよう としていたフランソワ=ジョゼフ・ユノーの影響によるものであったようだ。ラ・メトリは5年間、パリの医学部で学び、ユノルドの指導を受けることになる [3]。 しかし、1733年、有名なヘルマン・ボアハーヴェに師事するため、ライデンに向けて出発した。オランダでの滞在は短期間であったが、大きな影響を与え た。その後、ラ・メトリは故郷のサン・マロで開業し、いくつかの著作の出版や翻訳を通じて、ボエルハーヴェの著作や理論を広めた。1739年に結婚した が、2人の子供をもうけ、不幸な結婚生活となった。1742年、ラ・メトリは家族を残してパリに渡り、ガール・フランセーズ連隊の外科医に任命され、オー ストリア継承戦争でいくつかの戦いに参加した。この経験は、彼に暴力に対する深い嫌悪感を植え付け、彼の哲学的な著作の中にも表れている。しかし、多くの 時間はパリで過ごし、その間にモーペルテュイやシャトレ侯爵夫人と知り合ったようである[3]。 |
| It was in these years, during an
attack of fever, that he made observations on himself with reference to
the action of quickened blood circulation upon thought, which led him
to the conclusion that mental processes were to be accounted for as the
effects of organic changes in the brain and nervous system. This
conclusion he worked out in his earliest philosophical work, the
Histoire naturelle de l'âme (1745). So great was the outcry caused by
its publication that La Mettrie was forced to quit his position with
the French Guards, taking refuge in Leiden. There he developed his
doctrines still more boldly and completely in L'Homme machine, a
hastily written treatise based upon consistently materialistic and
quasi-atheistic principles.[3] La Mettrie's materialism was in many
ways the product of his medical concerns, drawing on the work of
17th-century predecessors such as the Epicurean physician Guillaume
Lamy.[5] The ethical implications of these principles would later be worked out in his Discours sur le bonheur; La Mettrie considered it his magnum opus.[6] Here he developed his theory of remorse, i.e. his view about the inauspicious effects of the feelings of guilt acquired at early age during the process of enculturation. This was the idea which brought him the enmity of virtually all thinkers of the French Enlightenment, and a damnatio memoriae[7] which was lifted only a century later by Friedrich Albert Lange in his Geschichte des Materialismus. |
この頃、熱病にかかった彼は、血液循環の促進が思考に及ぼす影響につい
て自分自身を観察し、その結果、精神のプロセスは脳と神経系における有機的変化の影響として説明されるべきであるという結論に至ったのである。この結論
は、彼の最も初期の哲学的著作である「Histoire naturelle de
l'âme」(1745)に結実した。この著作が出版されると大きな反響を呼び、ラ・メトリはフランス衛兵の職を辞してライデンに避難することを余儀なく
された。ラ・メトリの唯物論は、エピキュリアン派の医師ギヨーム・ラミーなどの17世紀の先達の仕事を参考にして、多くの点で彼の医学的関心から生まれた
ものであった[5]。 これらの原則の倫理的な意味合いは後に『Discours sur le bonheur』としてまとめられ、ラ・メトリはこれを自分の最高傑作と考えた[6]。ここで彼は反省の理論、つまり幼い頃に文化的な過程で身につけた罪 悪感の不吉な効果に関する彼の見解を展開した。これは、フランス啓蒙主義のほぼすべての思想家から敵視され、1世紀後にフリードリヒ・アルベルト・ランゲ が『唯物論の歴史』で持ち上げたdamnatio memoriae[7]となった思想である。 |
| Philosophy Julien de La Mettrie is considered one of the most influential determinists of the eighteenth century. He believed that mental processes were caused by the body. He expressed these thoughts in his most important work Man a Machine. There he also expressed his belief that humans worked like a machine. This theory can be considered to build off the work of Descartes and his approach to the human body working as a machine.[8] La Mettrie believed that man, body and mind, worked like a machine. Although he helped further Descartes' view of mechanization in explaining human bodily behavior, he argued against Descartes' dualistic view on the mind. His opinions were so strong that he stated that Descartes was actually a materialist in regards to the mind.[9] The philosopher David Skrbina considers La Mettrie an adherent of "vitalistic materialism": [10] To him, mind was a very real entity, and clearly it was embedded in a material cosmos. An obvious solution, therefore, was to see matter itself as inherently dynamic, capable of feeling, even intelligent. Motion and mind derive from some inherent powers of life or sentience that dwell in matter itself or in the organizational properties of matter. That view, sometimes called vitalistic materialism, is the one that LaMettrie—and later Diderot—adopted. Commentators often portray LaMettrie as a mechanist because it is assumed that anyone who denies the spiritual realm must see all things, and in particular all living things, as products of dead matter. It is quite common, even today, to equate materialism with mechanism. But, as has been noted, the two are logically independent. ...Though he obviously adopted the term ‘machine’ in his L’Homme Machine, it was in a specifically vitalistic sense. |
哲学 ジュリアン・ド・ラ・メトリは、18世紀において最も影響力のある決定論者の一人と考えられている。彼は、精神的なプロセスは身体によって引き起こされる と考えた。彼はこの考えを彼の最も重要な作品『機械としての人間』で表現した。そこでは、人間は機械のように働くという信念も表明している。この理論はデ カルトの仕事と、人間の体が機械のように働くという彼のアプローチを土台にしていると考えることができます[8]。ラ・メトリは人間、身体と精神が機械の ように働くと信じていたのです。彼は人間の身体的行動を説明する上でデカルトの機械化という見方をさらに後押ししたが、心についてはデカルトの二元論的な 見方に反論していた。彼の意見は非常に強く、デカルトは心に関して実は唯物論者であると述べている[9]。 哲学者のデヴィッド・スクルビナはラ・メトリを「生命論的唯物論」の信奉者とみなしている[10]。[10] 彼にとって、心は非常に現実的な存在であり、明らかに物質的な宇宙の中に埋め込まれているものであった。従って、明白な解決策は、物質そのものを本質的に 動的であり、感情を持ち、知性を持つことができると見なすことであった。運動と心は、物質そのもの、あるいは物質の組織的性質に宿る、生命や感覚を持つ固 有の力 に由来する。このような考え方は、活力的唯物論と呼ばれることもあり、ラメットリや後にディドロが採用した考え方である。ラメットリーを機械論者と呼ぶ論 者が多いのは、霊的領域を否定する者は、万物、特に生物を死んだ物質の産物と見なすに違いないと思われているからである。今日でも、唯物論と機械論を同一 視することはよくあることである。しかし、すでに述べたように、この2つは論理的に独立したものである。...彼は『人間機械』の中で明らかに「機械」と いう言葉を採用したが、それは特に生命論的な意味においてであった。 |
| Man and the animal Prior to Man a Machine he published The Natural History of the Soul in 1745. He argued that humans were just complex animals.[9] A great deal of controversy emerged due to his belief that "from animals to man there is no abrupt transition".[11] He later built on that idea: he claimed that humans and animals were composed of organized matter. He believed that humans and animals were only different in regards to the complexity that matter was organized. He compared the differences between man and animal to those of high quality pendulum clocks and watches stating: "[Man] is to the ape, and to the most intelligent animals, as the planetary pendulum of Huygens is to a watch of Julien Le Roy".[11] The idea that essentially no real difference between humans and animals existed was based on his findings that sensory feelings were present in animals and plants.[12] While he did recognize that only humans spoke a language, he thought that animals were capable of learning a language. He used apes as an example, stating that if they were trained they would be "perfect [men]".[8] He further expressed his ideas that man was not very different from animals by suggesting that we learn through imitation as do animals. His beliefs about humans and animals were based on two types of continuity. The first being weak continuity, suggesting that humans and animals are made of the same things but are organized differently. His main emphasis however was on strong continuity, the idea that the psychology and behavior between humans and animals was not all that different. |
人間と動物 人間という機械』に先立ち、彼は1745年に『魂の博物誌』を出版した。彼は人間は複雑な動物に過ぎないと主張した[9]。「動物から人間への急激な移行 はない」という彼の信念のために多くの論争が生まれた[11]。彼は後にその考えを基に、人間と動物が組織的な物質で構成されていると主張した。彼は人間 と動物が異なるのは、物質が組織化されている複雑さに関してだけであると考えた。彼は人間と動物の違いを高級な振り子時計や腕時計に例えて、次のように述 べた。人間と動物の違いを高級な振り子時計や腕時計に例えて、「人間は猿にとって、そして最も知的な動物にとって、ホイヘンスの惑星の振り子がジュリア ン・ル・ロワの時計にとってそうであるように」[11]と述べている。人間と動物の間に本質的に本当の違いは存在しないという考えは、動物や植物に感覚的 感情が存在しているという彼の発見に基づいている[12]。彼は人間だけが言語を話すことを認識していたが、動物は言語を学習する能力があると考えたので あった。彼は猿を例にして、もし彼らが訓練されれば「完璧な(人間)」になると述べている[8]。さらに彼は、人間が動物と同じように模倣によって学ぶこ とを示唆して、人間が動物とあまり違わないという彼の考えを表現している。 人間と動物に関する彼の信念は2種類の連続性に基づいていた。一つは弱い連続性で、人間と動物は同じものからできているが、異なる組織であることを示唆し ている。しかし、彼が最も重視したのは強い連続性で、人間と動物の間の心理や行動はそれほど違わないという考えであった。 |
| Man a machine La Mettrie believed that man worked like a machine due to mental thoughts depending on bodily actions. He then argued that the organization of matter at a high and complex level resulted in human thought. He did not believe in the existence of God. He rather chose to argue that the organization of humans was done to provide the best use of complex matter as possible.[9] La Mettrie arrived at this belief after finding that his bodily and mental illnesses were associated with each other. After gathering enough evidence, in medical and psychological fields, he published the book.[13] Some of the evidence La Mettrie presented was disregarded due to the nature of it. He argued that events such as a beheaded chicken running around, or a recently removed heart of an animal still working, proved the connection between the brain and the body. While theories did build off La Mettrie's, his works were not necessarily scientific. Rather, his writings were controversial and defiant.[14] |
機械としての人間 ラ・メトリは、人間は精神的思考が身体的行為に依存するため、機械のように働くと考えた。そして、物質が高度で複雑なレベルで組織化された結果、人間の思 考が生まれたと主張した。彼は、神の存在を信じていなかった。むしろ彼は、人間の組織は複雑な物質をできるだけ有効に利用するために行われたと主張するこ とを選んだのである[9]。 ラ・メトリは自分の身体的な病気と精神的な病気が互いに関連していることを発見した後に、この信念に至った。医学と心理学の分野で十分な証拠を集めた後、 彼はこの本を出版した[13]。 ラ・メトリが提示した証拠の中には、その性質上、無視されるものもあった。彼は、首を切られた鶏が走り回ったり、最近摘出された動物の心臓がまだ動いてい たりするような出来事は、脳と身体の間のつながりを証明するものであると主張した。ラ・メトリーの理論が発展したとはいえ、彼の著作は必ずしも科学的とは いえない。むしろ、彼の著作は論争的であり、反抗的であった[14]。 |
| Human nature He further expressed his radical beliefs by asserting himself as a determinist, dismissing the use of judges.[8] He disagreed with Christian beliefs and emphasized the importance of going after sensual pleasure, a hedonistic approach to human behavior.[12] He further looked at human behavior by questioning the belief that humans have a higher sense of morality than animals. He noted that animals rarely tortured each other and argued that some animals were capable of some level of morality. He believed that as machines, humans would follow the law of nature and ignore their own interests for those of others.[9] |
人間性 彼はさらに、決定論者であることを主張し、裁判官の使用を否定することで、彼の過激な信念を表現した[8]。 彼はキリスト教の信念に同意せず、人間の行動に対する快楽主義的アプローチである、感覚的快楽を求めることの重要性を強調した[12]。 彼はさらに、人間が動物よりも道徳心が高いという信念に疑問を呈することで人間の行動に目を向けていた。彼は動物がお互いに拷問することはほとんどないこ とに注目し、一部の動物はある程度の道徳を持つことができると主張した。彼は機械として人間は自然の法則に従い、他人のために自分の利益を無視すると信じ ていた[9]。 |
| Influence La Mettrie most directly influenced Pierre Jean Georges Cabanis, a prominent French physician. He worked off La Mettrie's materialistic views but modified them in order to be not as extreme. La Mettrie's extreme beliefs were rejected strongly, but his work did help influence psychology, specifically behaviorism. His influence is seen in the reductionist approach of behavioral psychologists.[12] However, the backlash he received was so strong that many behaviorists knew very little to nothing about La Mettrie and rather built off other materialists with similar arguments.[9] |
影響力 ラ・メトリが最も直接的に影響を受けたのは、フランスの著名な医師であるピエール・ジャン・ジョルジュ・カバニスである。彼はラ・メトリーの唯物論的見解 を参考にしながらも、極端でないように修正した。ラ・メトリの極端な信念は強く否定されたが、彼の仕事は心理学、特に行動主義に影響を与えるのに役立っ た。しかし、彼が受けた反発は非常に強く、多くの行動主義者はラ・メトリについてほとんど何も知らず、むしろ同様の主張を持つ他の唯物論者から構築してい た[9]。 |
| Journey to Prussia La Mettrie's hedonistic and materialistic principles caused outrage even in the relatively tolerant Netherlands. So strong was the feeling against him that in 1748 he was compelled to leave for Berlin, where, thanks in part to the offices of Maupertuis, the Prussian king Frederick the Great not only allowed him to practice as a physician, but appointed him court reader. There La Mettrie wrote the Discours sur le bonheur (1748), which appalled leading Enlightenment thinkers such as Voltaire, Diderot and D'Holbach due to its explicitly hedonistic sensualist principles which prioritised the unbridled pursuit of pleasure above all other things.[5] |
プロイセンへの旅 ラ・メトリの快楽主義、唯物論は、比較的寛容なオランダでさえも激怒させた。プロイセン王フリードリヒ大王は、マウペルトゥイの働きかけもあって、ラ・メ トリの医師としての活動を許可しただけでなく、宮廷読書人に任命したのである。そこでラ・メトリは『享楽についての論考』(1748年)を書いたが、この 論考は、他のすべてのものよりも快楽の無制限な追求を優先するという、明らかに快楽主義的な官能主義によって、ヴォルテール、ディドロ、ドルバックといっ た啓蒙主義の主要思想家を愕然とさせた[5]。 |
| Death La Mettrie's celebration of sensual pleasure was said to have resulted in his early death. The French ambassador to Prussia, Tyrconnel, grateful to La Mettrie for curing him of an illness, held a feast in his honour. It was claimed that La Mettrie wanted to show either his power of gluttony or his strong constitution by devouring a large quantity of pâté de faisan aux truffes. As a result, he developed a gastric illness of some sort. Soon after he began suffering from a severe fever and eventually died.[3][8] Frederick the Great gave the funeral oration, which remains the major biographical source on La Mettrie's life. He declared: "La Mettrie died in the house of Milord Tirconnel, the French plenipotentiary, whom he had restored to life. It seems that the disease, knowing with whom it had to deal, was cunning enough to attack him first by the brain, in order to destroy him the more surely. A violent fever with fierce delirium came on. The invalid was obliged to have recourse to the science of his colleagues, but he failed to find the succor that his own skill had so often afforded as well to himself as to the public".[1]" Frederick further described him as a good devil and medic but a very bad author.[15] He was survived by his wife and a 5-year-old daughter. La Mettrie's collected Œuvres philosophiques appeared after his death in several editions, published in London, Berlin and Amsterdam. |
死 ラ・メトリは、官能的な快楽を謳歌した結果、早世したと言われている。プロイセン駐在のフランス大使ティルコネルは、ラ・メトリの病気が治ったことに感謝 し、彼のために祝宴を催した。その際、ラ・メトリは自分の大食漢ぶりと強靭な体質を示すために、大量のパテ・ド・ファイザン・オ・トリュフを食べたと言わ れている。その結果、彼は胃の病気のようなものを患ってしまった。間もなく激しい発熱に見舞われ、やがて死亡した[3][8]。 フリードリヒ大王は、ラ・メトリの生涯に関する主要な伝記資料である葬儀の演説を行った。彼はこう宣言した。「ラ・メトリは、彼が生き返らせたフランス全 権大使のティルコネル卿の家で死んだ。病気は相手をよく知っていて、より確実に彼を破壊するために、まず脳を攻撃するほど狡猾であったようだ。そして、激 しい発熱と譫妄(せんもう)が起こった。病人は同僚の科学に頼らざるを得なかったが、自分の腕前が一般人と同様に自分にもたらしてくれた救いを見つけるこ とができなかった」[1]。フレデリックはさらに、彼を「良い悪魔であり医者であったが、非常に悪い作家であった」と評している[15]。 彼は妻と5歳の娘に先立たれた。 ラ・メトリの『哲学的作品集』は、彼の死後、ロンドン、ベルリン、アムステルダムで出版され、いくつかの版が出ている。 |
| This article incorporates text
from a publication now in the public domain: Chisholm, Hugh, ed.
(1911). "Lamettrie, Julien Offray de". Encyclopædia Britannica. Vol. 16
(11th ed.). Cambridge University Press. pp. 129–130. |
|
| Selected works Histoire Naturelle de l'Âme. 1745 (anon.) École de la Volupté. 1746, 1747 (anon.) Politique du Médecin de Machiavel. 1746 (anon.) L'Homme Machine. 1748 (anon.) L'Homme Plante. 1748 (anon.) Ouvrage de Pénélope ou Machiavel en Médecine. 1748 (pseudonym: Aletheius Demetrius) Discours sur le bonheur ou Anti-Sénèque [Traité de la vie heureuse, par Sénèque, avec un Discours du traducteur sur le même sujet]. 1748 (anon.) L'Homme plus que Machine. 1748 (anon.) Système d'Épicure. 1750 (anon.) L'Art de Jouir. 1751 (anon.) |
|
| Collected works Œuvres philosophiques, 2 vols., Paris: Fayard 1984, 1987 ISBN 2-213-01839-1; ISBN 978-2-213-01983-3 [vol. 3] Ouvrage de Pénélope ou Machiavel en Médecine, Paris: Fayard 2002 ISBN 2-213-61448-2 Œuvres philosophiques, 1 vol., Paris: Coda 2004 ISBN 2-84967-002-2 |
|
| Critical editions of his major
works Aram Vartanian (ed.): La Mettrie's L'homme machine. A Study in the Origins of an Idea, (Princeton: Princeton University Press, 1960) John F. Falvey (ed.): La Mettrie. Discours sur le bonheur in Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, vol. cxxxiv (Banbury, Oxfordshire: The Voltaire Foundation, 1975) Ann Thomson (ed.): La Mettrie's Discours préliminaire. in Materialism and Society in the Mid-Eighteenth Century (Genève: Librairie Droz, 1981) Théo Verbeek (Ed.): Le Traité de l'Ame de La Mettrie, 2 vols. (Utrecht: OMI-Grafisch Bedrijf, 1988) |
|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Julien_Offray_de_La_Mettrie |
https://www.deepl.com/ja/translator |
★『人間=機械論』は、自由主義の医師兼哲学者Julien Offray de La Mettrie(1709-1751)が1748年にライデンで出版した作品である
| L'Homme Machine est
un ouvrage du médecin-philosophe libertin Julien Offray de La Mettrie
(1709-1751) paru en 1748 à Leyde1. Inspiré par le concept d'"animal-machine" formulé un siècle plus tôt par René Descartes dans son Discours de la Méthode, La Mettrie s'inscrit ici dans le mécanisme, courant philosophique qui aborde l'ensemble des phénomènes physiques suivant le modèle des liens de cause à effet (déterminisme) et plus largement une éthique radicalement matérialiste2. C'est par ce livre qu'il s'est fait connaître dans l’histoire de la philosophie, ne serait-ce que par son titre évocateur. |
『人間=機械論』は、自由主義の医師兼哲学者Julien
Offray de La Mettrie(1709-1751)が1748年にライデンで出版した作品である1。 ルネ・デカルトが1世紀前に『方法論序説』で打ち立てた「動物-機械」の概念に触発されたラ・メトリの作品は、あらゆる物理現象を原因と結果のモデル(決 定論)に従ってアプローチする哲学的傾向、より広くは根本的に物質主義の倫理観を持つメカニズムの一部である2。 彼が哲学史に名を残すことになったのは、この本を通じてであり、その刺激的なタイトルからしても、である。 |
| Un scientifique plus qu'un
philosophe Des recherches constituent pour La Mettrie un matériau plus précieux que les écrits de n'importe quel philosophe, Descartes compris, qui sont trop spéculatifs à ses yeux3. |
哲学者というより科学者 ラ・メトリーにとって、研究は、デカルトを含むどの哲学者の著作よりも貴重な材料であり、彼の目にはあまりにも思弁的に映るのである3。 |
| Positionnement philosophique Partant de ses connaissances en physiologie, que ne possèdent pas les philosophes, La Mettrie considère que, comme par le passé, les philosophes se trompent quand ils dissertent sur l’Homme. Les spéculations théoriques sont à ses yeux sans intérêt, seule en revanche la méthode empirique lui paraît légitime. Bien qu'inspiré par Descartes en tant qu'initiateur du mécanisme, et dès 1745, La Mettrie rejette « cet absurde système (...) que les bêtes sont de pures machines4. ». La Mettrie rejette vigoureusement toute forme de dualisme au profit du monisme. En d'autres termes, il rejette toute idée de Dieu, même celle des panthéistes, qui voient Dieu dans la nature, comme encore Voltaire, des années plus tard, y recherchera « le grand horloger ». Ses positions sont sans ambiguïté matérialistes : |
哲学的な立場 ラ・メトリは、哲学者が持っていない生理学の知識に基づいて、過去にそうであったように、哲学者が人間を論じるとき、間違っていると考えるのである。理論 的な思索には興味がなく、経験的な方法のみが正当であると考えたのだ。 メカニズムの創始者であるデカルトに触発され、1745年の時点で、ラ・メトリは「獣は純粋な機械であるというこの不条理なシステム(...)」を否定し ている4 。 4 ラ・メトリは、あらゆる二元論を徹底的に否定し、一元論を支持した。つまり、ヴォルテールが数年後に「偉大なる時計職人」を探すように、自然の中に神を見 出す汎神論者の考えさえも否定しているのである。 彼の立場は紛れもなく唯物論者である。 |
| « Qui sait si la raison de
l'existence de l'homme ne serait pas dans son existence même ?
Peut-être a-t-il été jeté au hasard sur la surface de la Terre [...]
semblable à ces champignons qui paraissent d'un jour à l'autre, ou à
ces fleurs qui bordent les fossés et couvrent les murailles.5 » |
【引用】「人間の存在理由は、その存在そのものにあるのではないのか
"と、誰にわかるだろう。おそらく、彼は地球の表面に無造作に投げ出されたのだろう[...]。ある日突然現れるキノコや、溝に沿って壁を覆う花のよう
に」5。 |
| Selon lui, c'est à tort que «
nous imaginons ou plutôt nous supposons une cause supérieure ». |
彼によると、「より高い原因を想像するというか、想定する」ことが間違
いなのだそうだ。 |
| « Concluons donc hardiment que
l'homme est une machine et qu'il n'y a dans tout l'Univers qu'une seule
substance. Ce n'est point ici une hypothèse [...], l'ouvrage de préjugé
ou de ma raison seule. [...] mais [...] le raisonnement le plus
vigoureux [...] à la suite d'une multitude d'observations physiques
qu'aucun savant ne contestera6. » |
"したがって、人間は機械であり、全宇宙にたった一つの物質しか存在し
ないと大胆に結論づけよう。これは仮説[...]でも、偏見や私の理性だけの仕事でもない。[しかし、[...]最も精力的な推論は、[...]どの科学
者も異議を唱えない多数の物理的観察に従ったものである6。 |
| Postérité Dès le xixe siècle, dans son Histoire du matérialisme, l'historien allemand Friedrich-Albert Lange compare La Mettrie à Copernic et Galilée : de même que ces derniers ont autrefois développé une image du cosmos dégagée de toute emprise religieuse, La Mettrie a traité la question de la conscience en dehors de toute considération métaphysique7. Les théories de La Mettrie anticipent les recherches en sciences cognitives et en neurobiologie, à la fin du xxe siècle8. De fait, en 1983, dans leurs livres respectifs, Le Cerveau Machine et L'Homme neuronal, le médecin Marc Jeannerod et le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux font état de leur dette intellectuelle à l'égard de La Mettrie 9 Et en 2013, le philosophe Yves Charles Zarka estime que le livre préfigure non seulement les techniques d'interactions homme-machine, qui se mettent en place à la fin du xxe siècle, mais la théorie de l'homme augmenté du transhumanisme10. |
後世の人々 19世紀には、ドイツの歴史家ランゲが『唯物論史』のなかで、ラ・メトリをコペルニクスやガリレオと比較している。後者がかつて宗教の影響を排除した宇宙 像を構築したように、ラ・メトリは形而上学的考察なしに意識の問題を扱った7。 ラ・メトリの理論は、20世紀末の認知科学や神経生物学の研究を先取りしたものである8。 実際、1983年、医師のマルク・ジャンヌローと神経生物学者のジャン・ピエール・シャングーは、それぞれの著書『神経機械』と『神経人間』の中で、ラ・ メトリーへの知的負託を表明している9。 そして2013年、哲学者のイヴ・シャルル・ザルカは、本書が20世紀末に整備されつつあるマンマシンインタラクションの技術だけでなく、トランスヒュー マニズムのオーグメント・マン理論をも予見していると考えている10。 |
| https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Homme_Machine. |
|
| Yves Charles Zarka, né le 14
mars 1950, est philosophe, professeur émérite à l'université de Paris
(Sorbonne). Il est global professor à l'université de Pékin et enseigne
à l'université Ca' Foscari de Venise, à l'université La Sapienza de
Rome. Il est fondateur et directeur de la revue Cités (PUF). Il a été directeur de recherche au CNRS, où il dirigeait le Centre d’histoire de la philosophie moderne et le Centre Thomas-Hobbes. Il a dirigé le centre PHILéPOL (philosophie, épistémologie et politique) de l'université Paris au sein duquel les recherches s'organisent sur le concept de « monde émergent ». Ses recherches portent sur la démocratie, les nouveaux enjeux environnementaux, la nouvelle configuration du pouvoir au niveau mondial, le cosmopolitisme et la tolérance. |
イヴ・シャルル・ザルカは1950年3月14日生まれ。哲学者、パリ大
学(ソルボンヌ大学)名誉教授。北京大学グローバル教授、ベネチアのカ・フォスカリ大学、ローマのラ・サピエンツァ大学で教鞭をとる。雑誌『Cités』
(PUF)の創刊者であり、ディレクター。 CNRSでは、近代哲学史研究センターとトーマス・ホッブズ研究センターの研究部長を務めた。パリ大学のPHILéPOLセンター(哲学、認識論、政治 学)を指揮し、「新興世界」の概念を中心に研究を組織している。研究テーマは、民主主義、新しい環境問題、グローバルレベルでの新しい権力構成、コスモポ リタニズム、寛容性など。 |
| Yves Charles Zarka est, de 1974
à 1988, professeur de philosophie dans le secondaire, puis il est
docteur en philosophie1, habilité à diriger des recherches. Il est directeur du Centre d'histoire de la philosophie moderne du CNRS (1996-2004) et du Centre Thomas-Hobbes du CNRS (1990-2002). Au CNED, il est nommé responsable de l'enseignement du CAPES et de l’agrégation externe et interne de philosophie (1997-2004). Yves Charles Zarka dirige à l'université Paris-Descartes l’équipe PHILéPOL (Centre de philosophie, d’épistémologie et de politique)2. Il assure la responsabilité d’un programme ANR intitulé DEMOENV « La démocratie face aux enjeux environnementaux » (2011-2015) auquel collabore PHILéPOL, l'IRSTEA et l'ICD-CREIDD (université de technologie de Troyes) et d'un autre programme sur « Territoires, population et citoyenneté en Europe ». Il dirige également un programme de l'IDEX de Sorbonne Paris Cité sur "La démocratie et les mutations de l'espace public en Europe" en collaboration avec le Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF) et Paris III (ICEE). Ces dernières années il a dirigé un autre programme ANR-Université de Paris Descartes (2006-2010) intitulé LEGICONTEST « Concurrences de légitimité, types de contestation et réforme de l’État ». |
1974年から1988年まで、イヴ・シャルル・ザルカは中学校で哲学
の教師をした後、哲学の博士号1 を取得し、研究の指導権を得た。 CNRS現代哲学史センター所長(1996-2004年)、CNRSトーマス・ホッブスセンター所長(1990-2002年)。CNEDでは、CAPES と哲学の外部・内部アグレガシオン(1997-2004)の教育責任者に任命される。イヴ・シャルル・ザルカは、パリ・デカルト大学のPHILéPOL チーム(哲学・認識論・政治学のためのセンター)2 のディレクターを務めている。また、PHILéPOL、IRSTEA、ICD-CREIDD(トロワ工科大学)が協力するDEMOENV「環境問題に直面 する民主主義」(2011-2015)というANRプログラムのほか、「欧州における領土、人口、市民権」というプログラムの責任者でもある。また、ソル ボンヌ・パリ・シテ校のIDEXで、パリ政治学院(CEVIPOF)およびパリ第3大学(ICEE)と共同で、「ヨーロッパにおける民主主義と公共空間の 変容」に関するプログラムを指導しています。近年は、LEGICONTEST "Competitions of legitimacy, types of contestation and state reform "と題したANR-University of Paris Descartesプログラム(2006-2010)を指導している。 |
| Professeur à l'université de
Paris, où il est titulaire de la chaire de philosophie politique3, Yves
Charles Zarka est également global professor à l'université de Pékin.
Il est visiting professor à l'université Ca' Foscari de Venise et à
l'université "La Sapienza" de Rome. Il donne également des
enseignements à l'université de New York, à l'université de Barcelone
ou encore à l'université de Porto Alegre (Brésil), etc. Outre un grand nombre d’ouvrages d’histoire de la philosophie politique (en particulier sur Hobbes, Machiavel, Foucault et autres)4 tous traduits en plusieurs langues, ses recherches se situent au carrefour de la philosophie contemporaine, de l’épistémologie des sciences sociales, et des sciences politiques. C’est dans ce cadre qu’il étudie les transformations de la démocratie, les nouvelles problématiques environnementales, l’idée cosmopolitique, etc. Aux PUF, il dirige trois collections : « Fondements de la politique », « Intervention philosophique », « Débats philosophiques » ; chez Armand Colin, « Émergences » ; chez Vrin, l'édition des Œuvres de Hobbes et la collection « Hobbes Supplementa »; chez Mimésis, la collection "Philosophie et société". Directeur de la revue Cités aux PUF (80 numéros parus)5. Il est également membre du comité de rédaction de la revue Archives de philosophie (de 1988 à 2017), du comité scientifique de la revue Droits (PUF), du British Journal for the History of Philosophy (Francis & Taylor, Londres), de la revue Science et Esprit (éditions Bellarmin, Ottawa)6, la revue Derechos y Libertades (Dykinson, Madrid). Le 28 mai 2015, Yves-Charles Zarka intervient avec Michel Field en tant que « Grand témoin » dans les Rencontres maçonniques La Fayette entre le Grand Orient de France et la Grande Loge Nationale de France7. |
パリ大学教授で政治哲学の講座を持ち3、イヴ・シャルル・ザルカは北京
大学のグローバル教授でもある。ヴェネチアのカ・フォスカリ大学およびローマのラ・サピエンツァ大学の客員教授を務める。また、ニューヨーク大学、バルセ
ロナ大学、ポルト・アレグレ大学(ブラジル)等でも教鞭をとっている。 政治哲学史に関する多くの著作(特にホッブズ、マキャベリ、フーコーなど)4 があり、そのすべてが数カ国語に翻訳されているほか、現代哲学、社会科学の認識論、政治学が交差する場所に位置している。この枠組みの中で、民主主義の変 容、新たな環境問題、コスモポリタン思想などを研究しているのである。 PUFでは、"Fondements de la politique", "Intervention philosophique", "Débats philosophiques", Armand Colinでは、"Émergences", Vrinでは、ホッブズの作品集と "Hobbes Supplementa", Mimésisでは "Philosophie et Societyété" を指導しています。PUFのジャーナル「シテス」ディレクター(80号発行)5. また、雑誌Archives de philosophieの編集委員(1988年から2017年まで)、雑誌Droits(PUF)の科学委員会、英国哲学史ジャーナル(Francis & Taylor、ロンドン)、雑誌Science et Esprit(éditions Bellarmin、オタワ)6 、雑誌Derechos y Libertades(Dykinson、マドリード)にも所属している。 2015年5月28日、イヴ=シャルル・ザルカは、ミシェル・フィールドとともに、グラン・オリエント・ド・フランスとグラン・ロジェ・ナショナル・ド・ フランスの間のRencontres maçonniques La Fayetteに「グラン・テモアン」として介入した7。 |
| https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Charles_Zarka |
https://www.deepl.com/ja/translator |
Man—Machine,
Julien Offray de La Mettrie; The moral advantages of La Mettrie’s view
of man
| A start on
thinking about materialism |
唯物論について考えることからはじめよう |
|
| Divine revelation |
||
| Some empirical
facts |
||
| Food |
||
| Other influences |
||
| Physical
constitution |
||
| The ability to
learn |
||
| Language |
||
| Imagination |
||
| Humanity’s assets |
||
| Attention |
||
| Man and the other
animals |
||
| Innocent criminals |
||
| The law of nature |
||
| The existence of
God |
||
| The law of nature |
||
| Self-moving body
parts |
||
| The ‘springs’ of
the human machine |
||
| More about the
organisation of the human body |
||
| Feeling and thought |
||
| Solving two
‘riddles’ |
||
| From sperm to man |
||
| Reconciling
ourselves to our ignorance . . |
(英語からの重訳)Man-Machine,
Julien Offray de La Mettrie; The moral advantages of La Mettrie’s view
of man, http://bactra.org/LaMettrie/Machine/
| Man a Machine Julien Offray de La Mettrie 1748 |
『人間機械論』 ジュリアン・オフレイ・デ・ラ・メトリ 1748年 |
| It
is not enough for a wise man to study nature and truth; he should dare
state truth for the benefit of the few who are willing and able to
think. As for the rest, who are voluntarily slaves of prejudice, they
can no more attain truth, than frogs can fly. I reduce to two the systems of philosophy which deal with man's soul. The first and older system is materialism; the second is spiritualism. The metaphysicians who have hinted that matter may well be endowed with the faculty of thought have perhaps not reasoned ill. For there is in this case a certain advantage in their inadequate way of expressing their meaning. In truth, to ask whether matter can think, without considering it otherwise than in itself, is like asking whether matter can tell time. It may be foreseen that we shall avoid this reef upon which Locke had the bad luck to shipwreck. The Leibnizians with their monads have set up an unintelligible hypothesis. They have rather spiritualized matter than materialized the soul. How can we define a being whose nature is absolutely unknown to us? Descartes and all the Cartesians, among whom the followers of Malebranche have long been numbered, have made the same mistake. They have taken for granted two distinct substances in man, as if they had seen them, and positively counted them. The wisest men have declared that the soul can not know itself save by the light of faith. However, as reasonable beings they have thought that they could reserve for themselves the right of examining what the Bible means by the word ``spirit,'' which it uses in speaking of the human soul. And if in their investigation, they do not agree with the theologians on this point, are the theologians more in agreement among themselves on all other points? Here is the result in a few words of all their reflections. If there is a God, he is the Author of nature was well as of revelation. He has given us the one to explain the other, and reason to make them agree. To distrust the knowledge that can be drawn from the study of animated bodies, is to regard nature and revelation as two contraries which destroy each other, and consequently to dare uphold the absurd doctrine, that God contradicts Himself in His various works and deceives us. If there is a revelation, it can not then contradict nature. By nature only can we understand the meaning of the words of the Gospel, of which experience is the only truly interpreter. In fact, the commentators before our time have only obscured the truth. We can judged of this by the author of the Spectacle of Nature. ``It is astonishing,'' he says concerning Locke, ``that a man who degrades our soul far enough to consider it a soul of clay should dare set up reason as judge and sovereign arbiter of the mysteries of faith, for,'' he adds, ``what an astonishing idea of Christianity one would have, if one were to follow reason.'' Not only do these reflections fail to elucidate faith, but they also constitute such frivolous objections to the method of those who undertake to interpret the Scripture, that I am almost ashamed to waste time in refuting them. The excellence of reason does not depend on a big word devoid of meaning (immateriality), but on the force, extent, and perspicuity of reason itself. Thus a ``soul of clay'' which should discover, at one glance, as it were, the relations and the consequences of an infinite number of ideas hard to understand, would evidently be preferable to a foolish and stupid soul, though that were composed of the most precious elements. A man is not a philosopher because, with Pliny, he blushes over the wretchedness of our origin. What seems vile is here the most precious of things, and seems to be the object of nature's highest art and most elaborate care. But as man, even though he should come from an apparently still more lowly source, would yet be the most perfect of all beings, so whatever the origin of his soul, if it is pure, noble, and lofty, it is a beautiful soul which dignifies the man endowed with it. Pluche's second way of reasoning seems vicious to me, even in his system, which smacks a little of fanaticism; for [on his view] if we have an idea of faith as being contrary to the clearest principles, to the most incontestable truths, we must yet conclude, out of respect for revelation and its author, that this conception is false, and that we do not yet understand the meaning of the words of the Gospel. Of the two alternatives, only one is possible: either everything is illusion, nature as well as revelation, or experience alone can explain faith. But what can be more ridiculous than the position of our author! Can one imagine hearing a Peripatetic say, ``We ought not to accept the experiments of Torricelli, for if we should accept them, if we should rid ourselves of the horror of the void, what an astonishing philosophy we should have!'' I have shown how vicious the reasoning of Pluche is in order to prove, in the first place, that if there is a revelation, it is not sufficiently demonstrated by the mere authority of the Church, and without any appeal to reason, as all those who fear reason claim: and in the second place, to protect against all assault the method of those who would wish to follow the path that I open to them, of interpreting supernatural things, incomprehensible in themselves, in the light of those ideas with which nature has endowed us. Experience and observation should therefore be our only guides here. Both are to be found throughout the records of the physicians who were philosophers, and not in the works of the philosophers who were not physicians. The former have traveled through and illuminated the labyrinth of man; they alone have laid bare those springs [of life] hidden under the external integument which conceals so many wonders from our eyes. They alone, tranquilly contemplating our soul, have surprised it, a thousand times, both in its wretchedness and in its glory, and they have no more despised it in the first estate, than they have admired it in the second. Thus, to repeat, only the physicians have a right to speak on this subject. What could the others, especially the theologians, have to say? Is it not ridiculous to hear them shamelessly coming to conclusions about a subject concerning which they have had no means of knowing anything, and from which on the contrary they have been completely turned aside by obscure studies that have led them to a thousand prejudiced opinions, - in a word, to fanaticism, which adds yet more to their ignorance of the mechanism of the body? |
賢者は自然や真理を研究するだけでは十分ではない。思考する意思と能力を持つ少数の人々のために、あえて真理を述べるべきなのだ。自ら進んで偏見の奴隷となっている残りの者たちは、カエルが飛ぶことができるのと同じように、真理に到達することはできない。 人間の魂を扱う哲学の体系を2つに分類する。第一の古い体系は唯物論であり、第二の体系は精神論である。 物質にも思考能力が備わっている可能性を示唆した形而上学者は、おそらく間違った推論をしてはいない。というのも、この場合、その意味を表現する方法が不 適切であることに、ある種の利点があるからである。実のところ、物質が考えることができるかどうかを問うのは、それ自体について考えるのでなければ、物質 が時間を知ることができるかどうかを問うようなものである。ロックが不運にも難破してしまったこの岩礁を避けることは、予見できるかもしれない。 ライプニッツ派のモナドは、理解しがたい仮説を立てた。彼らは魂を物質化したというよりも、むしろ物質を精神化したのである。本性がまったくわからない存在を、どうやって定義できるだろうか。 デカルトをはじめとするデカルト派も、マールブランシュの信奉者たちも、同じ過ちを犯している。彼らは、あたかも人間の中に2つの異なる物質があることを当然視し、あたかもそれを見たかのように数え上げた。 最も賢明な人々は、魂は信仰の光によらなければ自分自身を知ることはできないと宣言してきた。しかし、理性的な存在である彼らは、聖書が人間の魂について 語るときに使っている「霊」という言葉が何を意味するのかを調べる権利を自分たちに留保できると考えた。そして、もしこの点について神学者たちと意見が一 致しないのであれば、他のすべての点について神学者たちの意見は一致しているのだろうか? ここに、彼らのすべての考察の結果がいくつかの言葉で示されている。神が存在するとすれば、神は自然の創造者であると同時に啓示の創造者でもある。神は私たちに、一方を説明するために他方を与え、両者を一致させるために理性を与えた。 生体の研究から引き出される知識に不信感を抱くことは、自然と啓示を互いに破壊し合う相反するものとみなすことであり、その結果、神はそのさまざまな御業においてご自身と矛盾し、私たちを欺くという不合理な教義をあえて支持することになる。 啓示があるとすれば、それが自然と矛盾することはありえない。自然によってのみ、私たちは福音の言葉の意味を理解することができる。実際、私たちの時代以 前の注解者たちは、真理をあいまいにしてきたにすぎない。このことは、『自然の光景』の著者によって判断できる。私たちの魂を粘土の魂と見なすほど堕落さ せた人間が、信仰の神秘の裁判官として、また主権者として、あえて理性を立てるとは驚くべきことである。 このような考察は、信仰を解明できないばかりか、聖書を解釈しようとする人々の方法に対する軽薄な反論である。 理性の卓越性は、意味のない大きな言葉(非物質性)に左右されるのではなく、理性そのものの力、広がり、明瞭さに左右されるのである。したがって、理解し がたい無限の観念の関係や帰結を、いわば一目で発見する「粘土の魂」は、それが最も貴重な要素で構成されていたとしても、愚かで愚かな魂よりも好ましいこ とは明らかである。プリニウスと同じように、私たちの出自の惨めさに赤面するからといって、人は哲学者ではない。下劣に見えるものが、ここでは最も貴重な ものであり、自然の最高の芸術と最も精巧な配慮の対象であるように見える。しかし、たとえ人間がもっと卑しい源から生まれたとしても、あらゆる存在の中で 最も完全な存在であるように、魂の起源が何であれ、それが純粋で気高く、高尚であれば、それは美しい魂であり、それを与えられた人間を威厳づけるものであ る。 プルーシュの第二の推論の仕方は、狂信的な臭いが少しする彼の体系においても、私には悪意に満ちているように思われる。[彼の見解では]もし私たちが、最 も明確な原理や、最も疑いようのない真理に反するような信仰観念を持っているとしても、啓示とその作者への敬意から、この観念は誤りであり、私たちは福音 の言葉の意味をまだ理解していないと結論づけなければならない。 つまり、自然も啓示もすべてが幻想であるか、経験だけが信仰を説明できるか、である。しかし、著者の立場ほど滑稽なものがあるだろうか!トリチェッリの実 験を受け入れるべきではない。もし受け入れるとしたら、もし虚空の恐怖を取り除くとしたら、なんと驚くべき哲学を手に入れることになることか。 私がプルーシュの推論がいかに悪質であるかを示したのは、第一に、啓示があるとすれば、それは教会の権威だけでは十分に証明されず、理性を恐れるすべての 人々が主張するように、理性に訴えることなく証明されることを証明するためであり、第二に、それ自体では理解できない超自然的な事柄を、自然が我々に授け た観念の光の中で解釈するという、私が彼らに開いた道を歩もうとする人々の方法を、あらゆる攻撃から守るためである。したがって、ここでは経験と観察が唯 一の指針となる。この二つは、哲学者であった医師たちの記録の至るところに見られるが、医師でなかった哲学者たちの著作には見られない。前者は人間の迷宮 を旅して照らし出し、彼らだけが、私たちの目から多くの不思議を隠している外皮の下に隠されている[生命の]泉を裸にした。彼らはただ一人、私たちの魂を 静かに観察し、その惨めさにも栄光にも何千回となく驚かせ、第一の状態では軽蔑することもなく、第二の状態では賞賛することもなかった。繰り返すが、この テーマについて語る権利があるのは医師だけである。他の人たち、特に神学者たちが何を言うことができようか。彼らが恥ずかしげもなく、何一つ知るすべもな く、それどころか、曖昧な研究によって完全に脇に追いやられ、千差万別の偏見に満ちた意見、一言で言えば、身体のメカニズムに対する無知にさらに拍車をか ける狂信主義に導かれたテーマについて、結論を下すのを聞くのは滑稽ではないだろうか。 |
| But even though we have chosen the best guides, we shall still find many thorns and stumbling blocks in the way. Man is so complicated a machine that it is impossible to get a clear idea of the machine beforehand, and hence impossible to define it. For this reason, all the investigations have been vain, which the greatest philosophers have made à priori, that is to to say, in so far as they use, as it were, the wings of the spirit. Thus it is only à posteriori or by trying to disentangle the soul from the organs of the body, so to speak, that one can reach the highest probability concerning man's own nature, even though one can not discover with certainty what his nature is. Let us then take in our hands the staff of experience, paying no heed to the accounts of all the idle theories of the philosophers. TO be blind and to think one can do without this staff if the worst kind of blindness. How truly a contemporary writer says that the only vanity fails to gather from secondary causes the same lessons as from primary causes! One can and one even ought to admire all these fine geniuses in their most useless works, such men as Descartes, Malebranche, Leibnitz, Wolff and the rest, but what profit, I ask, has any one gained from their profound meditations, and from all their works? Let us start out then to discover not what has been thought, but what must be thought for the sake of repose in life. There are as many different minds, different characters, and different customs, as there are different temperaments. Even Galen knew this truth which Descartes carried so far as to claim that medicine alone can change minds and morals, along with bodies. (By the write of L'historie de l'âme, this teaching is incorrectly attributed to Hippocrates.) It is true that melancholy, bile, phlegm, blood etc., - according to the nature, the abundance, and the different combination of these humors - make each man different from another. In disease the soul is sometimes hidden, showing no sign of life; sometimes it is so inflamed by fury that it seems to be doubled; sometimes, imbecility vanishes and the convalescence of an idiot produces a wise man. Sometimes, again, the greatest genius becomes imbecile and looses the sense of self. Adieu then to all that fine knowledge, acquired at so high a price, and with so much trouble! Here is a paralytic who asks is his leg is in bed with him; there is a soldier who thinks that he still has the arm which has been cut off. The memory of his old sensations, and of the place to which they were referred by his soul, is the cause of this illusion, and of this kind of delirium. The mere mention of the member which he has lost is enough to recall it to his mind, and to make him feel all its motions; and this causes him an indefinable and inexpressible kind of imaginary suffering. This man cries like a child at death's approach, while this other jests. What was needed to change the bravery of Caius Julius, Seneca, or Petronius into cowardice or faintheartedness? Merely an obstruction in the spleen, in the liver, an impediment in the portal vein. Why? Because the imagination is obstructed along with the viscera, and this gives rise to all the singular phenomena of hysteria and hypochondria. What can I add to the stories already told of those who imagine themselves transformed into wolf-men, cocks or vampires, or of those who think that the dead feed upon them? Why should I stop to speak of the man who imagines that his nose or some other member is of glass? The way to help this man to regain his faculties and his own flesh-and-blood nose is to advise him to sleep on hay, lest he beak the fragile organ, and then to set fire to the hay that he may be afraid of being burned - a far which has sometimes cured paralysis. But I must touch lightly on facts which everybody knows. Neither shall I dwell long on the details of the effects of sleep. Here a tired soldier snores in a trench, in the middle of the thunder of hundreds of cannon. His soul hears nothing; his sleep is as deep as apoplexy. A bomb is on the point of crushing him. He will feel this less perhaps than he feels an insect which is under his foot. On the other hand, this man who is devoured by jealousy, hatred, avarice, or ambition, can never find any rest. The most peaceful spot, the freshest and most calming drinks are alike useless to one who has not freed his heart from the torment of passion. The soul and the body fall asleep together. As the motion of the blood is calmed, a sweet feeling of peace and quiet spreads through the whole mechanism. The soul feels itself little by little growing heavy as the eyelids droop, and loses its tenseness, as the fibres of the brain relax; thus little by little it becomes as if paralyzed and with it all the muscles of the body. These can no longer sustain the weight of the head, and the soul can no longer bear the burden of thought; it is in sleep as if it were not. Is the circulation too quick? the soul cannot sleep. Is the soul too much excited? the blood cannot be quieted: it gallops through the veins with an audible murmur/ Such are the two opposite causes of insomnia. A single fright in the midst of our dreams makes the heart beat at double speed and snatches us from needed and delicious repose, as a real grief or an urgent need would do. Lastly as the mere cessation of the functions of the soul produces sleep, there are, even when we are awake (or at least when we are half awake), kinds of very frequent short naps of the mind, vergers' dreams, which show that the soul does not always wait for the body to sleep. For if the soul is not fast asleep, it surely is not far from sleep, since it cannot point out a single object to which it has attended, among the uncounted number of confused ideas which, so to speak, fill the atmosphere of our brains like clouds. Opium is too closely related to the sleep it produces, to be left out of consideration here. This drug intoxicates, like wine, coffee, etc., each in its own measure and according to the dose. It makes a man happy in a state which would seemingly be the tomb of feeling, as it is the image of death. How sweet is this lethargy! The soul would long never to emerge from it. For the soul has been a prey to the most intense sorrow, but now feels only the joy of suffering past, and of sweetest peace. Opium alters even the will, forcing the soul which wished to wake and to enjoy life, to sleep in spite of itself. I shall omit any reference to the effect of poisons. Coffee, the well-known antidote for wine, by scourging the imagination, cures our headaches and scatters our cares without laying up for us, as wine does, other headaches for the morrow. But let us contemplate the soul in its other needs. The human body is a machine which winds its own springs. It is the living image of perpetual movement. Nourishment keeps up the movement which fever excites. Without food, the soul pines away, goes mad, and dies exhausted. The soul is a taper whose light flares up the moment before it goes out. But nourish the body, pour into its veins life-giving juices and strong liquors, and then the soul grows strong like them, as if arming itself with a proud courage, and the soldier whom water would have made to flee, grows bold and runs joyously to death to the sound of drums. Thus a hot drink sets into stormy movement the blood which a cold drink would have calmed. What power there is in a meal! Joy revives in a sad heart, and infects the souls of comrades, who express their delight in the friendly songs in which the Frenchman excels. The melancholy man alone is dejected, and the studious man is equally out of place [in such company]. |
しかし、たとえ最良のガイドを選んだとしても、その道には多くのいばらやつまずきがある。 人間は非常に複雑な機械であるため、事前に機械の明確な考えを得ることは不可能であり、したがって機械を定義することも不可能である。このため、偉大な哲 学者たちがアプリオリに、つまり、いわば精神の翼を使う限りにおいて行ってきた研究は、すべてむなしいものであった。いわば、魂を肉体の器官から切り離そ うとすることによってのみ、人間の本質が何であるかを確実に発見することはできなくても、人間自身の本質に関する最高の蓋然性に到達することができるので ある。 それでは、哲学者たちの戯言に耳を貸さず、経験の杖を手に取ろう。盲目でありながら、この杖なしでもやっていけると考えるのは、最悪の盲目である。二次的 な原因から、一次的な原因と同じ教訓を得ることができないのは、唯一の虚栄心である!デカルト、マレブランシュ、ライプニッツ、ヴォルフなど、最も役立た ずの作品に登場する優れた天才たちを賞賛することはできるし、賞賛すべきであるとさえ思う。それでは、これまで考えられてきたことではなく、人生の安息の ために考えなければならないことを発見することから始めよう。 さまざまな気質があるように、さまざまな心、さまざまな性格、さまざまな習慣がある。ガレノスでさえ知っていたこの真理を、デカルトは医学だけが肉体とと もに心や道徳を変えることができると主張するまでになった。(L'historie de l'âme』の記述によれば、この教えはヒポクラテスの誤りである)。憂鬱、胆汁、痰、血液など、これらの体液の性質、量、組み合わせの違いによって、人 間がそれぞれ異なるのは事実である。 病気のとき、魂は時には隠れていて、生きている気配を見せない。またある時は、最大の天才が無能になり、自己の感覚を失うこともある。高価な代償を払い、 苦労の末に手に入れた素晴らしい知識とはおさらばだ!自分の脚はベッドの中にあるのだろうかと尋ねる麻痺患者がいる。このような錯覚や錯乱の原因は、昔の 感覚と、それが魂によって指し示された場所の記憶にある。失った部位を思い出すには、その部位を口にするだけで十分であり、その部位のすべての動きを感じ させる。この男は死が近づくと子供のように泣き、この男は冗談を言う。カイアス・ユリウスやセネカやペトロニウスの勇敢さを、臆病さや気弱さに変えるため に何が必要だったのか。脾臓や肝臓、門脈に障害があるだけだ。なぜか?想像力が臓器とともに障害され、ヒステリーや心気症のような奇妙な現象を引き起こす からだ。 オオカミ男やコックや吸血鬼に変身した自分を想像する人たちや、死者が自分を食べていると考える人たちの話はすでに語られている。自分の鼻や他の部位がガ ラスだと想像する人の話を、なぜ私が止めなければならないのか。この男が自分の能力と生身の鼻を取り戻すのを助ける方法は、壊れやすい器官をくちばしにし ないように干し草の上で寝るように助言することである。しかし、私は誰もが知っている事実に軽く触れなければならない。 睡眠がもたらす影響の詳細についても、長くは触れない。疲れた兵士が塹壕の中でいびきをかいている。彼の魂は何も聞いていない。彼の眠りは脳溢血のように 深い。爆弾が彼を押しつぶそうとしている。爆弾が彼を押しつぶそうとしているのを、彼はおそらく、足の下にいる虫を感じるほどには感じないだろう。 一方、嫉妬、憎しみ、欲望、野心にむしばまれた人間は、決して安息を得ることができない。情熱の苦しみから心を解放していない者にとっては、最も安らげる場所も、最も新鮮で心を落ち着かせる飲み物も、同じように役に立たない。 魂と肉体は一緒に眠りに落ちる。血液の動きが落ち着くと、平和で静かな甘い感覚がメカニズム全体に広がる。魂は、まぶたが垂れ下がるにつれて少しずつ重く なり、脳の線維が弛緩するにつれて緊張を失っていくのを感じる。これらの筋肉はもはや頭の重さを支えることができず、魂はもはや思考の重荷に耐えることが できない。 血行が速すぎると、魂は眠ることができない。魂が興奮しすぎているのか、血液は静まることができない。夢を見ている最中に一度でも恐怖を感じると、心臓の 鼓動は倍速になり、本当の悲しみや緊急の必要性がそうさせるように、必要で美味しい安息から私たちを奪ってしまう。最後に、魂の機能が停止するだけでも睡 眠が生じるが、私たちが目覚めているときでさえ(あるいは少なくとも半分目覚めているときでさえ)、非常に頻繁に短時間の仮眠をとる種類の心、つまり ヴァージャーの夢があり、これは魂が常に肉体の眠りを待っているわけではないことを示している。いわば雲のように脳の大気を満たしている数え切れないほど の混乱した観念の中で、魂が注意を向けている対象をひとつも指摘できないのだから。 アヘンは、それがもたらす睡眠とあまりに密接な関係があるため、ここで考察の対象から外すことはできない。この薬物は、ワインやコーヒーなどと同じよう に、それぞれの量に応じた酔い方をする。一見、死のイメージのように、感情の墓場であるような状態でも、人を幸福にする。この無気力はなんと甘美なことだ ろう!魂はこの無気力から決して抜け出したくないと願うだろう。魂は最も激しい悲しみの餌食となったが、今は過去の苦しみと最も甘い平和の喜びだけを感じ るからだ。アヘンは意志さえも変質させ、目を覚まして人生を楽しみたいと願った魂を、自分自身にもかかわらず眠らせるのだ。毒物の影響については、ここで は言及を省略する。 ワインの解毒剤として知られるコーヒーは、想像力を奮い立たせることで、頭痛を治し、心配事を分散させる。しかし、魂が必要とする他のものについても考えてみよう。 人間の身体は、自分でゼンマイを巻く機械である。それは、絶え間ない運動の生きた姿である。栄養は、熱が興奮させる運動を維持する。食べ物がなければ、魂 は衰え、狂い、疲れ果てて死ぬ。魂は、火が消える瞬間に燃え上がるテーパーである。しかし、肉体に栄養を与え、生命を与えるジュースや強い酒を血管に注ぎ 込めば、魂はそれらのように強くなり、まるで誇り高き勇気で武装するかのようになる。このように、熱い飲み物は、冷たい飲み物なら静まるはずの血液を、嵐 のように躍動させる。 食事にはどんな力があるのだろう!悲しい心に喜びがよみがえり、仲間たちの魂に伝染し、フランス人が得意とする親しみやすい歌で喜びを表現する。憂鬱な男は一人で意気消沈し、勉強熱心な男も同じように[このような仲間には]ふさわしくない。 |
| Raw
meat makes animals fierce, and it would have the same effect on man.
This is so true that the English who eat meat red and bloody, and not
as well done as ours, seem to share more or less in the savagery due to
this kind of food, and to other causes which can be rendered
ineffective by education only. This savagery creates in the soul,
pride, hatred, scorn of other nations, indocility and other sentiments
which degrade the character, just as heavy food makes a dull and heavy
mind whose usual traits are laziness and indolence. Pope understood well the full power of greediness when he said: Catius is ever moral, ever grave Thinks who endures a knave is next a knave, Save just at dinner - then prefers no doubt A rogue with ven'son to a saint without. Elsewhere he says: See the same man in vigor, in the gout, Alone, in company, in place or out, Early at business and at hazard late, Mad at a fox chase, wise at a debate, Drunk at a borough, civil at a ball, Friendly at Hackney, faithless at White Hall. In Switzerland we had a bailiff by the name of M. Steigner de Wittghofen. When he fasted he was a most upright and even a most indulgent judge, but woe to the unfortunate man whom he found on the culprit's bench after he had had a large dinner! He was capable of sending the innocent like the guilty to the gallows. We think we are, and in fact we are, good men, only as we are gay or brave; everything depends on the way our machine is running. One is sometimes inclined to say that the soul is situated in the stomach, and that Van Helmont, who said that the seat of the soul was in the pylorus, made only the mistake of taking the part for the whole. To what excesses cruel hunger can bring us! We no longer regard even our own parents and children. We tear them to pieces eagerly and make horrible banquets of them; and in the fury with which we are carried away, the weakest is always the prey of the strongest. La grossesse, cette émule désirée des pâles couleurs, ne se contente pas d'amener le plus souvent à sa suites le goûts dépravés qui accompagnent ces deux états: elle a quelquefois fait exécuter à l'âme les plus affreux complots; effets d'une maine subite, qui étouffe jusqu'à la loi naturelle. Ce'st ainsi que le cerveau, cette matrice de l'esprit, se pervertit à sa manière, avec celle du corps. Quelle autre fureur d'homme ou de femme, dans ceux que la continence et la santé poursuivent! C'est peu pour cette fille timide et modeste d'avoir perdu toute honte et toute pudeur; elle ne regarde plus l'inceste, que comme une femme galante regarde l'adultère. Si ses besoins ne trouvent pas de prompts soulagements, ils ne se borneront point aux simples accidents d'une passion utérine, à la manie, etc.; cette malheureuse mourra d'un mal, dont il y a tant de médecins. One needs only eyes to see the necessary influence of old age on reason. The soul follows the progress of the body, as it does the progress of education. In the weaker sex, the soul accords also with delicacy of temperament, and from this delicacy follow tenderness, affection, quick feelings due more to passion than to reason, prejudices, and superstitions, whose strong impress can hardly be effaced. Man, on the other hand, whose brain and nerves partake of the firmness of all solids, has not only stronger features but also a more vigorous mind. Education, which women lack, strengthens his mind still more. Thus with such help of nature and art, why should not a man be more grateful, more generous, more constant in friendship, stronger in adversity? But, to follow almost exactly the thought of the author of the Lettres sur la Physiognomie, the sex which unites the charms of the mind and of the body with almost all the tenderest and most delicate feelings of the heart, should not envy us the two capacities which seem to have been given to man, the one merely to enable him better to fathom the allurements of beauty, and the other merely to enable him to minister better to its pleasure. It is no more necessary to be just as great a physiognomist as this author, in order to guess the quality of the mind from the countenance or the shape of the features, provided these are sufficiently marked, than it is necessary to be a great doctor to recognize a disease accompanied by all it marked symptoms. Look at the portraits of Locke, of Steele, of Boerhaave, of Maupertuis, and the rest, and you will not be surprised to find strong faces and eagle eyes. Look over a multitude of others, and you can always distinguish the man of talent from the man of genius, and often even an honest man from a scoundrel. For example it has been noticed that a celebrated poet combines (in his portrait) the look of a pickpocket with the fire of Prometheus. History provides us with a noteworthy example of the power of temperature. The famous Duke of Guise was so strongly convinced that Henry the Third, in whose power he had so often been, would never dare assassinate him, that he went to Blois. When the Chancellor Chiverny learned of the duke's departure, he cried, ``He is lost.'' After this fatal prediction had been fulfilled by the event, Chiverny was asked why he made it. ``I have known the king for twenty years,'' said he; ``he is naturally kind and even weakly indulgent, but I have noticed that when it is cold, it takes nothing at all to provoke him and send him into a passion.'' One nation is of heavy and stupid wit, and another quick, light and penetrating. Whence comes this difference, if not in part from the difference in foods, and difference in inheritance, and in part from the mixture of the diverse elements which float around in the immensity of the void? The mind, like the body, has its contagious diseases and its scurvy. Such is the influence of climate, that a man who goes from one climate to another, feels the change, in spite of himself. He is a walking plant which has transplanted itself; if the climate is not the same, it will surely either degenerate or improve. Furthermore, we catch everything from those with whom we come in contact; their gestures, their accent, etc.; just as the eyelid is instinctively lowered when a blow is foreseen, or (as for the same reason) the body of the spectator mechanically imitates, in spite of himself, all the motions of a good mimic. From what I have just said, it follows that a brilliant man is his own best company, unless he can find others of the same sort. In the society of the unintelligent, the mind grows rusty for lack of exercise, as at tennis a ball that is served badly is badly returned. I should prefer an intelligent man without an education, if he were still young enough, to a man badly educated. A badly trained mind is like an actor whom the provinces have spoiled. Thus, the diverse states of the soul are always correlative with those of the body. But the better to show this dependence, in its completeness and its causes, let us here make use of comparative anatomy; let us lay bare the organs of man and of animals. How can human nature be known, if we may not derive any light from an exact comparison of the structure of man and of animals? In general, the form and the structure of the brains of quadrupeds are almost the same as those of the brain of man; the same shape, the same arrangement everywhere, with this essential difference, that of all the animals man is the one whose brain is largest, and, in proportion to its mass, more convoluted than the brain of any other animal; then come the monkey, the beaver, the elephant, the dog, the fox, the cat. These animals are most like man, for among them, too, one notes the same progressive analogy in relation to the corpus callosum in which Lancisi - anticipating the late M. de la Peyronie - established the seat of the soul. The latter, however, illustrated the theory by innumerable experiments. Next after all the quadrupeds, birds have the largest brains. Fish have large heads, but these are void of sense, like the heads of many men. Fish have no corpus callosum, and very little brain, while insects entirely lack brain. I shall not launch out into any more detail about the varieties of nature, nor into conjectures concerning them, for there is an infinite number of both, as any one can see by reading no further than the treatises of Willis De Cerebro and De Anima Brutorum. |
生肉は動物を凶暴化させる。
赤くて血なまぐさい、しかも私たちほど上手くはない肉を食べるイギリス人は、多かれ少なかれ、この種の食べ物による野蛮さと、教育によってのみ効果がなく
なるその他の原因による野蛮さを共有しているようだ。この野蛮さは、プライド、憎しみ、他国への軽蔑、無教養など、人格を低下させる感情を魂に生み出す。 ローマ教皇は、貪欲の持つ力をよく理解していた: カティウスは常に道徳的であり、常に重大である。 カティウスは常に道徳的であり、常に厳格である、 晩餐の時だけは別だ。 ヴェンソンのいる悪党は、ヴェンソンのいない聖人よりも好きだ。 また、彼は言う: 元気な時も、痛風の時も、同じ男を見よ、 一人でも、仲間でも、場所でも、外でも、 仕事には早く、危険には遅く、 キツネ追いには狂い、議論には賢い、 自治区では酔い、舞踏会では礼儀正しい、 ハックニーでは友好的、ホワイトホールでは不誠実。 スイスにはヴィットホーフェンのシュタイグナーという廷吏がいた。断食しているときは、彼は非常に高潔で、寛容な裁判官であった。しかし、夕食をたらふく 食べた後、彼が罪人の席にいるのを見つけた不幸な男は悲惨であった!彼は罪のない人を、罪のある人と同じように絞首台に送ることができたのだ。 私たちは、自分がガイ(たくましい男)であるか勇敢であるかによって、自分が善人であると思うし、実際に善人であると思う。魂は胃の中にあり、魂の座は幽門にあると言ったヴァン・ヘルモントは、部分と全体を取り違えただけだと言いたくなることがある。 残酷な飢えは、私たちにどんな過剰なものをもたらすのだろう!私たちはもはや、自分の親や子供さえも顧みない。そして、その怒りに流され、弱い者は常に強い者の餌食となる。 そして、私たちが流される怒りの中で、最も弱い者は常に最も強い者の餌食となるのである。そのため、精神の母体である神経が、肉体と同じように変質してしまうのだ。 不摂生と健康が促進されるのは、男性であれ女性であれ、他にどんな苦しみがあるからだろう!この臆病で慎ましやかな少女は、すべての名誉と美貌を失ったか らと言って、それ以上侮辱を気にすることはない。その欲望は、心躍らせるようなものでなく、情熱的で、男らしく、などという単純な偶発的なものでしかな い。 老いが理性に及ぼす必要な影響を見るには、ただ目を凝らすだけでよい。魂は、教育の進歩がそうであるように、肉体の進歩に従う。弱い性別では、魂は気質の 繊細さとも一致し、この繊細さから、優しさ、愛情、理性よりも情熱に起因する素早い感情、偏見、迷信が生じ、その強い印象はなかなか消えない。一方、人間 は、脳と神経があらゆる固体の固さを帯びているため、顔立ちがしっかりしているだけでなく、精神も旺盛である。女性に欠けている教育は、彼の心をさらに強 くする。このように、自然と芸術の助けがあれば、男はより感謝し、より寛大になり、友情に厚く、逆境に強くなるはずではないか。しかし、『人相学への手 紙』の著者の考えにほぼ忠実に従えば、心と身体の魅力と、ほとんどすべての最も優しくて繊細な心の感情とを結びつける性は、人間に与えられたと思われる二 つの能力、すなわち、一方は美の魅力をよりよく理解できるようにするため、もう一方は美の喜びをよりよく味わえるようにするためだけの能力を、私たちにう らやましがらせてはならない。 この著者のように、人相学の大家でなくても、表情や顔立ちから心の質を推し量ることはできる。ロック、スティール、ボアハーヴェ、モウペルテュイなどの肖 像画を見れば、強い顔と鷲のような目を発見しても驚かないだろう。他の多くの人たちを見渡せば、才能のある人と天才的な人、そしてしばしば正直な人と悪党 を見分けることができる。たとえば、ある有名な詩人の肖像画には、スリのような風貌とプロメテウスの炎が組み合わされている。 歴史は、気温の力を示す特筆すべき例を教えてくれる。かの有名なギーズ公爵は、かつて権力を握っていたアンリ3世が自分を暗殺することなどあり得ないと強 く確信し、ブロワに向かった。シヴェルニー宰相は公爵の出発を知ると、「彼は失われた」と叫んだ。この致命的な予言が見事に的中した後、シヴェルニーはな ぜ予言をしたのかと尋ねられた。国王とは20年来の付き合いです」と彼は言った。「彼は生来親切で、弱々しくさえ甘やかされていますが、寒いときには、彼 を刺激して激情に走らせることなどまったく必要ないことに気づきました」。 ある国民は重く愚かな機知に富み、別の国民は素早く、軽く、鋭い。この違いはいったいどこから来るのだろう。その理由のひとつが、食物の違いや遺伝の違い によるものでなければ、また、その理由のひとつが、虚空の広大さを漂う多様な要素の混合によるものでなければ、これはいったい何なのだろう。身体と同じよ うに、心にも伝染病や壊血病がある。 気候の影響は大きく、ある気候から別の気候へと移っていく人間は、自分とは無関係にその変化を感じる。気候が同じでなければ、必ず退化するか改善するかのどちらかである。 同じ理由で)観客の身体は、自分にもかかわらず、優れたモノマネの動作をすべて機械的に真似るのである。 今述べたことから、聡明な人間は、同じようなタイプの人間を見つけられなければ、自分自身が最高の仲間であるということになる。テニスでサーブされたボー ルがうまく返せないように、知性のない人たちと一緒にいると、運動不足のために心が錆びついてしまう。私は、もし彼がまだ十分に若ければ、教育を受けてい ない知的な人間の方が、教育を受けていない人間よりも好きである。ひどく訓練された精神は、地方が台無しにした俳優のようなものだ。 このように、魂のさまざまな状態は、常に肉体の状態と相関関係にある。しかし、この依存関係を、その完全性と原因においてよりよく示すために、ここで比較 解剖学を利用しよう。人間と動物の構造を正確に比較することから何の光も得られないとしたら、どうして人間の本性を知ることができようか。 一般に、四足動物の脳の形と構造は、人間の脳の形とほとんど同じである。同じ形、同じ配置がいたるところにあるが、本質的な違いは、すべての動物の中で人 間の脳が最も大きく、その質量に比例して、他のどの動物の脳よりも入り組んでいることである。これらの動物は人間に最もよく似ている。なぜなら、これらの 動物の間でも、ランシジが(故ラ・ペイロニー氏に先駆けて)魂の座を確立した脳梁に関連して、同じような漸進的な類似が見られるからである。しかし後者 は、無数の実験によってこの理論を説明した。四足動物の次に脳が大きいのは鳥類である。魚類は頭が大きいが、これは多くの人間の頭のように感覚がない。魚 には脳梁がなく、脳はほとんどない。 なぜなら、ウィリスの『脳』(De Cerebro)と『脳』(De Anima Brutorum)を読めば誰でもわかるように、どちらも無限に存在するからである。 |
| I
shall draw the conclusions which follow clearly from these
incontestable observations: 1st, that the fiercer animals are, the less
brain they have; 2d, that this organ seems to increase in size in
proportion to the gentleness of the animal; 3d, that nature seems here
eternally to impose a singular condition, that the more one gains in
intelligence the more one loses in instinct. Does this bring gain or
loss? Do not think, however, that I wish to infer by that, that the size alone of the brain, is enough to indicate the degree of tameness in animals: the quality must correspond to the quantity, and the solids and liquids must be in that due equilibrium which constitutes health. If, as is ordinarily observed, the imbecile does not lack brain, his brain will be deficient in its consistency - for instance, in being too soft. The same thing is true of the insane, and the defects of their brains do not always escape our investigation. But if the causes of imbecility, insanity, etc., are not obvious, where shall we look for the causes of the diversity of all minds? They would escape the eyes of a lynx and of an argus. A mere nothing, a tiny fiber, something that could never be found by the most delicate anatomy, would have made of Erasmus and Fontenelle two idiots, and Fontenelle himself speaks of this very fact in one of his best dialogues. Willis has noticed in addition to the softness of the brain-substance in children, puppies and birds, that the corpora striata are obliterated and discolored in all these animals, and that the striations are as imperfectly formed as in paralytics. Il ajoute, ce qui est vrai, que l'homme a la protubérance annulaire fort grosse; et ensuite toujours diminutivement par dégrés, le singe et les autres animaux nommés ci-devant, tandis que le veau, le boeuf, le loup, la brebis, le cochon, etc. qui ont cette partie d'un tès petit volume, ont les nattes et testes fort gros. However cautious and reserved one may be about the consequences that can be deduced from these observations, and from many others concerning the kind of variation in the organs, nerves, etc., [one must admit that] so many different varieties cannot be the gratuitous play of nature. They prove at least the necessity for a good and vigorous physical organization, since throughout the animal kingdom the soul gains force with the body and acquires keenness, as the body gains strength. Let us pause to contemplate the varying capacities of animals to learn. Doubtless the analogy best framed leads the mind to think that the causes we have mentioned produce all the difference that is found between animals and men, although we must confess that our weak understanding, limited to the coarsest observations, cannot see the bonds that exist between cause and effect. This is a kind of harmony that philosophers will never know. Among animals, some learn to speak and sing; they remember tunes, and strike the notes as exactly as a musician. Others, for instance the ape, show more intelligence, and yet cannot learn music. What is the reason for this, except some defect in the organs of speech? But is this defect so essential to the structure that it could never be remedied? In a word, would it be absolutely impossible to teach the ape a language? I do not think so. I should choose a large ape in preference to any other, until by some good fortune another kind should be discovered, more like us, for nothing prevents there being such a one in regions unknown to us. The ape resembles us so strongly that naturalists have called it ``wild man'' or ``man of the woods.'' I should take it in the condition of the pupils of Amman, that is to say, I should not want it to be too young or too old; for apes that are brought to Europe are usually too old. I would choose the one with the most intelligent face, and the one which, in a thousand little ways, best lived up to its look of intelligence. Finally not considering myself worthy to be his master, I should put him in the school of that excellent teacher whom I have just named, or with another teacher equally skillful, if there is one. You know by Amman's work, and by all those who have interpreted his method, all the wonders he has been able to accomplish for those born deaf. In their eyes he discovered ears, as he himself explained, and in how short a time! In short he taught them to hear, speak, read, and write. I grant that a deaf person's eyes see more clearly and are keener than if he were not deaf, for the loss of one member or sense can increase the strength or acuteness of another, but apes see and hear, they understand what they hear and see, and grasp so perfectly the signs that are made to them, that I doubt not that they would surpass the pupils of Amman in any other game or exercise. Why then should the education of monkeys be impossible? Why might not the monkey, by dint of great pains, at last imitate after the manner of deaf mutes, the motions necessary for pronunciation. I do not dare decide whether the monkey's organs of speech, however trained, would be incapable of articulation. But, because of the great analogy between ape and man and because there is no known animal whose external and internal organs so strikingly resemble man's, it would surprise me if speech were absolutely impossible to the ape. Locke, who was certainly never suspected of credulity, found no difficulty in believing the story told by Sir William Temple in his memoirs, about a parrot which could answer rationally, and which had learned to carry on a kind of connected conversation, as we do. I know that people have ridiculed this great metaphysician; but suppose some one should have announced that reproduction sometimes take place without eggs or a female, would he have found many partisans? Yet M. Trembley has found cases where reproduction takes place without copulation and by fission. Would not Amman too have passed for mad if he had boasted that he could instruct scholars like his in so short a time, before he had happily accomplished the feat? His successes, have, however, astonished the world; and he, like the author of The History of the Polyps, has risen to immortality at one bound. Whoever owes the miracles that he works to his own genius surpasses, in my opinion, the man who owes his to chance. He who has discovered the art of adorning the most beautiful of kingdoms [of nature], and of giving it perfections that it did not have, should be ranked above an idle creator of frivolous systems, or a painstaking author of sterile discoveries. Amman's discoveries are certainly of a much greater value; he has freed men from the instinct to which they seemed to be condemned, and has given them ideas, intelligence, or in a word, a soul which they would never have had. What greater power than this! Let us not limit the resources of nature; they are infinite, especially when reinforced by great art. Could not the device which opens the Eustachian canal of the deaf, open that of apes? Might not a happy desire to imitate the master's pronunciation, liberate the organs of speech in animals that imitate so many other signs with such skill and intelligence? Not only do I defy any one to name any really conclusive experiment which proves my view impossible and absurd; but such is the likeness of the structure and functions of the ape to ours that I have very little doubt that if this animal were properly trained he might at last be taught to pronounce, and consequently to know, a language. Then he would no longer be a wild man, nor a defective man, but he would be a perfect man, a little gentleman, with as much matter or muscle as we have, for thinking and profiting by his education. The transition from animals to man is not violent, as true philosophers will admit. What was man before the invention of words and the knowledge of language? An animal of his own species with much less instinct than the others. In those days, he did not consider himself king over the other animals, nor was he distinguished from the ape, and from the rest, except as the ape itself differs from the other animals, i.e., by a more intelligent face. Reduced to the bare intuitive knowledge of the Leibnizians he saw only shapes and colors, without being able to distinguish between them: the same, old as young, child at all ages, he lisped out his sensations and his needs, as a god that is hungry or tired of sleeping, asks for something to eat, or for a walk. Words, languages, laws, sciences, and the fine arts have come, and by them finally the rough diamond of our mind has been polished. Man has been trained in the same way as animals. He has become an author, as they have become beasts of burden. A geometrician has learned to perform the most difficult demonstrations and calculations, as a monkey has learned to take his little hat off and on, and to mount his tame dog. All has been accomplished through signs, every species has learned what it could understand, and in this way men have acquired symbolic knowledge, still so called by our German philosophers. Nothing, as any one can see, is so simple as the mechanism of our education. Everything may be reduced to sounds or words that pass from the mouth of one through the ears of another into his brain. At the same moment, he perceives through his eyes the shape of the bodies of which these words are the arbitrary signs. But who was the first to speak? Who was the first teacher of the human race? Who invented the means of utilizing the plasticity of our organism? I cannot answer: the names of these first splendid geniuses have been lost in the night of time. But art is the child of nature, so nature must have long preceded it. We must think that the men who were the most highly organized, those on whom nature has lavished her richest gifts, taught the others. They could not have heard a new sound for instance, nor experienced new sensations, nor been struck by all the varied and beautiful objects that compose the ravishing spectacle of nature without finding themselves in the state of mind of the deaf man of Chartres, whose experience was first related by the great Fontenelle, when, at forty years, he heard for the first time, the astonishing sound of bells. Would it be absurd to conclude from this that the first mortals tried after the manner of this deaf man, or like animals and like mutes (another kind of animals), to express their new feeling by motions depending on the nature of their imagination, and therefore afterwards by spontaneous sounds, distinctive of each animal, as the natural expression of their surprise, their joy, their ecstasies and their needs? For doubtless those whom nature endowed with finer feeling had also greater facility in expression. |
これらの疑いようのない観察
から、私は明らかに導かれる結論を導き出そう:
第1に、獰猛な動物ほど脳が少ないこと、第2に、この器官は動物の優しさに比例して大きくなるようであること、第3に、自然は、知性を得れば得るほど本能
を失うという特異な条件を永遠に課しているように思われることである。これは得をもたらすのか、それとも損をもたらすのか。 質は量に対応し、固体と液体は健康を構成する適切な平衡状態になければならない。 通常観察されるように、無能力者に脳が欠けていないとすれば、その脳はその一貫性に欠けることになる。同じことが心神喪失者にも当てはまり、彼らの脳の欠 陥は常に我々の調査を免れない。しかし、無能や狂気などの原因が明らかでないとすれば、すべての心の多様性の原因をどこに求めればいいのだろうか。それら はオオヤマネコやアーガスの目から逃れられるだろう。エラスムスとフォントネルを二人の馬鹿にしたのは、最も繊細な解剖学では決して見つけることのできな い、単なる無、小さな繊維であった。 ウィリスは、子供、子犬、鳥類の脳実質が軟らかいことに加えて、これらの動物すべてにおいて線条体が抹消され変色していること、筋が麻痺患者と同様に不完 全に形成されていることに気づいた。さらに、これは事実であるが、人間は非常に大きな環状突起を持ち、次にサルや上に挙げた他の動物は、常に少しずつ減少 していくが、子牛、牛、狼、羊、豚などは、この部分の容積は非常に小さいが、非常に大きな辮髪と精巣を持つ、と付け加えている。 これらの観察から、また器官や神経などの変異の種類に関する他の多くの観察から推測される結果について、いかに慎重で控えめであろうとも、[人は]これほ ど多くの異なる種類が自然の無償の遊びであるはずがないことを認めなければならない。動物界全体を通じて、魂は肉体とともに力を増し、肉体が力を増すにつ れて鋭敏さを獲得するのだから。 動物の学習能力の違いについて考えてみよう。間違いなく、最もうまく組み立てられた類推は、これまで述べてきた原因が、動物と人間の間に見られるすべての違いを生み出していると思わせる。これは、哲学者には決してわからない種類の調和である。 動物のなかには、話したり歌ったりすることを学ぶものがいる。彼らは曲を覚え、音楽家のように正確に音を奏でる。一方、例えば猿のように、より知能が高い にもかかわらず、音楽を学ぶことができないものもいる。その理由は何だろう。発声器官に何らかの欠陥があるからではないだろうか。しかしこの欠陥は、決し て改善できないほど本質的な構造なのだろうか?つまり、猿に言葉を教えることは絶対に不可能なのだろうか?私はそうは思わない。 幸運にも、私たちにより似た別の種が発見されるまでは、私は他のどの類人猿よりも大型の類人猿を選ぶだろう。類人猿は私たちに非常によく似ているため、博 物学者はそれを「野生人」あるいは「森の人」と呼んでいる。つまり、若すぎても老けすぎてもいけない。ヨーロッパに持ち込まれる類人猿はたいてい老けすぎ ているからだ。私は、最も知的な顔立ちのもの、そして千差万別の小さな方法で、その知的な顔立ちに最もふさわしいものを選ぶだろう。最終的には、自分がそ の子の師匠になるにはふさわしくないと考え、先ほど名前を挙げた優秀な先生の学校に入れるか、同じように腕の立つ先生がいれば、その先生のところに入れる だろう。 アンマンの仕事ぶりや、彼の方法を解釈したすべての人たちによって、彼が生まれつき耳の聞こえない人たちに成し遂げた奇跡の数々を、あなたは知っているは ずだ。彼自身が説明したように、彼は彼らの目に耳を発見した!要するに、彼は彼らに聞き、話し、読み、書くことを教えたのだ。聾唖者の目が、聾唖者でない 場合よりも明瞭に見え、鋭敏であることは認める。しかし、類人猿は見たり聞いたりし、聞いたり見たりしたことを理解し、彼らに示された手話を完璧に理解す る。では、なぜサルの教育が不可能なのだろうか?猿が大変な苦労をして、ついには耳の不自由な唖のように、発音に必要な動作を真似るようにならないわけが ない。サルの発声器官がいかに訓練されたものであっても、発音ができないかどうかは、あえて判断しない。しかし、類人猿と人間との間には大きな類似性があ り、また、外的および内的器官が人間にこれほど酷似している動物は知られていないのだから、もし猿に発声が絶対に不可能だとしたら、それは驚きである。 ウィリアム・テンプル卿が回想録の中で語った、理性的な受け答えができ、私たちと同じように一種のつながりのある会話をするようになったオウムの話を、信 憑性を疑われたことのないロックが信じることに何の困難も感じなかった。人々がこの偉大な形而上学者を嘲笑したことは知っているが、もし誰かが、卵や雌が いなくても生殖が行われることがあると発表したとしたら、その人は多くの支持者を得ただろうか?しかし、M.トレンブリーは、交尾がなくても分裂によって 生殖が行われるケースを発見した。アンマンも、もし彼がその偉業をめでたく成し遂げる前に、彼のような学者を短期間で指導できると自慢していたら、気違い 扱いされたのではないだろうか?しかし、彼の成功は世界を驚嘆させた。彼は『ポリープの歴史』の著者と同じように、一気に不死身にのし上がったのである。 私の考えでは、奇跡を自分の才能に帰する者は、偶然に帰する者を凌駕する。最も美しい王国(自然)に装飾を施し、その王国になかった完全性を与える術を発 見した者は、軽薄なシステムを創造する無為な創造者や、不毛な発見をする苦心の作者よりも上位にランクされるべきである。アンマンの発見は、確かにもっと 大きな価値がある。彼は人間を、彼らが非難されているように思われる本能から解放し、彼らにアイデアや知性、一言で言えば、彼らが決して持つことのなかっ た魂を与えたのだ。これ以上の力があるだろうか! 自然の力を制限してはならない。自然の力は無限であり、特に偉大な芸術によって補強されたときには無限である。 耳の聞こえない人の耳管を開く装置が、猿の耳管を開くことはできないだろうか。師匠の発音を真似したいという幸福な願望が、他の多くのサインを巧みに、そ して知的に真似る動物の言語器官を解放することはできないだろうか?私の見解が不可能で不合理であることを証明するような、本当に決定的な実験を挙げる者 はいないどころか、類人猿の構造と機能が我々と似ていることから、この動物が適切に訓練されれば、ついに発音を教えられ、その結果、言語を知るようになる かもしれないと、私はほとんど疑わない。そうなれば、もはや野生の人間でも、欠陥のある人間でもなく、完全な人間、小さな紳士になる。 真の哲学者が認めるように、動物から人間への移行は暴力的なものではない。言葉が発明され、言葉を知る以前の人間とは何だったのか。同じ種の動物でありな がら、他の動物よりもはるかに本能が乏しかった。当時、人間は自分が他の動物の上に立つ王だとは思っていなかったし、類人猿やその他の動物から区別されて もいなかった。ライプニッツ派のような素朴な直観的知識に還元された彼は、形と色しか見ず、それらを区別することはできなかった。同じように、老いも若き も、子供も、あらゆる年齢で、彼は自分の感覚と欲求を口にした。 言葉、言語、法律、科学、そして芸術が生まれ、それらによってついに私たちの心のダイヤモンドの原石が磨かれた。人間は動物と同じように訓練されてきた。 動物が重荷を負わされる獣になったように、人間も作者になったのだ。幾何学者は、猿が小さな帽子を脱いだりかぶったりすることや、飼いならされた犬に馬乗 りになることを学んだように、最も難しい実演や計算を行うことを学んだ。あらゆる種が理解できることを学び、このようにして人間は象徴的知識を獲得してき た。 私たちの教育の仕組みほど単純なものはない。すべては、ある人の口から別の人の耳を通って、その人の脳に入る音や言葉に還元することができる。同時に、彼は目を通して、これらの言葉が恣意的な記号である身体の形を知覚する。 しかし、最初に言葉を発したのは誰か。人類最初の教師は誰か?私たちの器官の可塑性を利用する手段を発明したのは誰か?私は答えることができない。これらの最初の素晴らしい天才たちの名前は、時の夜の中で失われてしまった。しかし、芸術は自然の産物である。 最も高度に組織化された人たち、自然が最も豊かな恩恵を与えた人たちが、他の人たちに教えたと考えなければならない。例えば、新しい音を聞いたり、新しい 感覚を体験したり、自然の驚異的な光景を構成する多様で美しい対象すべてに心を打たれたりすることは、シャルトルの聾唖者が40歳のときに初めて鐘の驚く べき音を聞いたときのような心境に陥ることなしにはありえなかった。 このことから、最初の人間が、この聾唖者のように、あるいは動物や唖者(別の種類の動物)のように、想像力の性質に依存した運動によって新しい感覚を表現 しようとし、その結果、驚き、喜び、恍惚感、欲求の自然な表現として、それぞれの動物に特徴的な自発的な音によって表現しようとしたと結論づけるのは不合 理だろうか。間違いなく、自然がより繊細な感覚を授けた動物は、表現する能力もより高かったのだ。 |
| That
is the way in which, I think, men have used their feeling and their
instinct to gain intelligence and then have employed their intelligence
to gain knowledge. Those are the ways, so far as I can understand them,
in which men have filled the brain with the ideas, for the reception of
which nature made it. Nature and man have helped each other; and the
smallest beginnings have, little by little, increased, until everything
in the universe could be as easily described as a circle. As a violin string or a harpsichord key vibrates and gives forth sound, so the cerebral fibers, struck by waves of sound, are stimulated to render or repeat the words that strike them. And as the structure of the brain is such that when eyes well formed for seeing, have once perceived the image of objects, the brain can not help seeing their images and their differences, so when the signs of these differences have been traced or imprinted in the brain, the soul necessarily examines their relations - an examination that would have been impossible without the discovery of signs or the invention of language. At the time when the universe was almost dumb, the soul's attitude toward all objects was that of a man without any idea of proportion toward a picture or a piece of sculpture, in which he could distinguish nothing; or the soul was like a little child (for the soul was then in its infancy) who, holding in his hand small bits of straw or wood, sees them in a vague and superficial way without being able to count or distinguish them. But let some one attach a kind of banner, or standard, to this bit of wood (which perhaps is called a mast), and another banner to another similar object; let the first be known by the symbol 1, and the second by the symbol or number 2, then the child will be able to count the objects, and in this way he will learn all of arithmetic. As soon as one figure seems equal to another in its numerical sing, he will decide without difficulty that they are two different bodies, that 1+1 make 2, and 2+2 make 4, etc. This real or apparent likeness of figures is the fundamental basis of all truths and of all we know. Among these sciences, evidently those whose signs are less simple and less sensible are harder to understand than the others, because more talent is required to comprehend and combine the immense number of words by which such sciences express the truths in their province. On the other hand, the sciences that are expressed by the numbers or by other small signs, are easily learned; and without doubt this facility rather than its demonstrability is what has made the fortune of algebra. All this knowledge, with which vanity fills the balloon-like brains of our proud pedants, is therefore but a huge mass of words and figures, which form in the brain all the marks by which we distinguish and recall objects. All our ideas are awakened after the fashion in which the gardener who knows plants recalls all stages of their growth at sight of them. These words and the objects designated by them are so connected in the brain that it is comparatively rare to imagine a thing without the name or sign that is attached to it. I always use the word ``imagine,'' because I think that everything is the work of imagination, and that all the faculties of the soul can be correctly reduced to pure imagination in which they all consist. Thus judgment, reason, and memory are not absolute parts of the soul, but merely modifications of this kind of medullary screen upon which images of the objects painted in the eye are projected as by a magic lantern. But if such is the marvelous and incomprehensible result of the structure of the brain, if everything is perceived and explained by imagination, why should we divide the sensitive principle which thinks in man? Is not this a clear inconsistency in the partisans of the simplicity of the mind? For a thing that is divided can no longer without absurdity be regarded as indivisible. See to what one is brought by the abuse of language and by those fine words (spirituality, immateriality, etc.) used haphazard and not understood even by the most brilliant. Nothing is easier than to prove a system based, as this one is, on the intimate feeling and personal experience of each individual. If the imagination, or let us say, that fantastic part of the brain whose nature is as unknown to us as its way of acting, be naturally small or weak, it will hardly be able to compare the analogy or the resemblance of its ideas, it will be able to see only what is face to face with it, or what affects it very strongly; and how will it see all this! Yet it is always imagination which apperceives, and imagination which represents to itself all objects along with their names and symbols; and thus, once again, imagination is the soul, since it plays all the roles of the soul. By the imagination, by its flattering brush, the cold skeleton of reason takes on living and ruddy flesh, by the imagination the sciences flourish, the arts are adorned, the wood speaks, the echoes sigh, the rocks weep, marble breathes, and all inanimate objects gain life. It is imagination again which adds the piquant charm of voluptuousness to the tenderness of an amorous heart; which makes tenderness bud in the study of the philosopher and of the dusty pedant, which, in a word, creates scholars as well as orators and poets. Foolishly decried by some, vainly praised by others, and misunderstood by all; it follows not only in the train of the graces and of the fine arts, it not only describes but can also measure nature. It reasons, judges, analyzes, compares, and investigates. Could it feel so keenly the beauties of the pictures drawn for it, unless it discovered their relations? No, just as it cannot turn its thoughts on the pleasures of the senses, without enjoying their perfection or their voluptuousness, it cannot reflect on what it has mechanically conceived, without thus being judgment itself. The more the imagination or the poorest talent is exercised, the more it gains in embonpoint, so to speak, and the larger it grows. It becomes sensitive, robust, broad, and capable of thinking. The best of organisms has need of this exercise. Man's preeminent advantage is his organism. In vain all writers of books on morals fail to regard as praiseworthy those qualities that come by nature, esteeming only the talents gained by dint of reflection and industry. For whence come, I ask, skill, learning, and virtue, if not from a disposition that makes us fit to become skillful, wise, and virtuous? And whence again, comes this disposition, if not from nature? Only though nature do we have any good qualities; to her we owe all that we are. Why then should I not esteem men with good natural qualities as much as men who shine by acquired and as it were borrowed virtues? Whatever the virtue may be, from whatever source it may come, it is worthy of esteem; the only question is, how to estimate it. Mind, beauty, wealth, nobility, although the children of chance, all have their own value, as skill, learning and virtue all have theirs. Those upon whom nature has heaped her most costly gifts should pity those to whom these gifts have been refused; but, in their character of experts, they may feel their superiority without pride. A beautiful woman would be as foolish to think herself ugly, as an intelligent man to think himself a fool. An exaggerated modesty (a rare fault, to be sure) is a kind of ingratitude towards nature. An honest pride, on the contrary, is the mark of a strong and beautiful soul, revealed by manly features moulded by feeling. If one's organism is an advantage, and the preeminent advantage, and the source of all others, education is the second. The best made brain would be a total loss without it, just as the best constituted man would be but a common peasant, without knowledge of the ways of the world. But, on the other hand, what would be the use of the most excellent school, without a matrix perfectly open to the entrance and conception of ideas? Il est aussi impossible de donner une seule idée à un homme privé de tous les sens, que de faire un enfant à une femme à laquelle la nature aurait poussé la distraction jusqu'à oublier de faire une vulve, comme je l'ai vu dans une, qui n'avait ni fente, ni vagin, ni matrice, et qui pour cette raison fut démariée après dix ans de mariage. But if the brain is at the same time well organized and well educated, it is a fertile soil, well sown, that brings forth a hundredfold what it has received: or (to leave the figures of speech often needed to express what one means, and to add grace to truth itself) the imagination, raised by art to the rare and beautiful dignity of genius, apprehends exactly all the relations of the ideas it has conceived, and takes in easily an astounding number of objects, in order to deduce from them a long chain of consequences, which are again but new relations, produced by a comparison with the first, to which the soul finds a perfect resemblance. Such is, I think, the generation of intelligence. I say ``finds'' as I before gave the epithet ``apparent'' to the likeness of objects, not because I think that our senses are always deceivers, as Father Malebranche has claimed, or that our eyes, naturally a little unsteady, fail to see objects as they are in themselves (though microscopes prove this to us every day) but in order to avoid any dispute with the Pyrrhonians, among whom Bayle is well known. I say of truth in general what M. de Fontenelle says of certain truths in particular, that we must sacrifice it in order to remain on good terms with society. And it accords with the gentleness of my character, to a void all disputes unless to what conversation [!]. The Cartesians would here in vain make an onset upon me with their innate ideas. I certainly would not give myself a quarter of the trouble that M. Locke took, to attack such chimeras. In truth, what is the use of writing a ponderous volume to prove a doctrine which became an axiom three thousand years ago? According to the principles which we have laid down, and which we consider true; he who has the most imagination should be regarded as having the most intelligence or genius, for all these words are synonymous; and again, only by a shameful abuse [of terms] do we think that we are saying different things, when we are merely using different words, different sounds, to which no idea or real distinction is attached. The finest, greatest or strongest imagination is then the one most suited to the sciences as well as to the arts. I do not pretend to say whether more intellect is necessary to excel in the art of Aristotle or of Descartes than to excel in that of Euripides or of Sophocles, and whether nature has taken more trouble to make Newton than to make Corneille, though I doubt this. But it is certain that imagination alone, differently applied, has produced their diverse triumphs and their immortal glory. If one is known as having little judgment and much imagination, this means that the imagination has been left too much alone, has, as it were, occupied most of the time in looking at itself in the mirror of its sensations, has not sufficiently formed the habit of examining the sensations themselves attentively. [It means that the imagination] has been more impressed by images than by their truth or the likeness. Truly, so quick are the responses of the imagination that if attention, that key or mother of the sciences, does not do its part, imagination can do little more than run over and skim its objects. See that bird on the bough: it seems always ready to fly away. Imagination is like the bird, always carried onward by the turmoil of the blood and the animal spirits. One wave leaves a mark, effaced by the one that follows; the soul pursues it, often in vain: it must expect to regret the loss of that which it has not quickly enough seized and fixed. Thus, imagination, the true image of time, is being ceaselessly destroyed and renewed. Such is the chaos and the continuous quick succession of our ideas: they drive each other away even as one wave yields to another. Therefore, if imagination does not, as it were, use one set of its muscles to maintain a kind of equilibrium with the fibers of the brain, to keep its attention for a while upon an object that is on the point of disappearing, and to prevent itself from contemplating prematurely another object - [unless the imagination does all this], it will never be worthy of the fine name of judgment. It will express vividly what it has perceived in the same fashion: it will create orators, musicians, painters, poets, but never a single philosopher. On the contrary, if the imagination be trained from childhood to bridle itself and to keep from being carried away by its own impetuosity - an impetuosity which creates only brilliant enthusiasts - and to check, to restrain, its ideas, to examine them in all their aspects in order to see all sides of an object, then the imagination, ready in judgment, will comprehend the greatest possible sphere of objects, through reasoning; and its vivacity (always so good a sign in children, and only needing to be regulated by study and training) will be only a far-seeing insight without which little progress can be made in the sciences. Such are the simple foundations upon which the edifice of logic has been reared. Nature has built these foundations for the whole human race, but some have used them, while others have abused them. |
それは、人間が感覚と本能を
使って知性を獲得し、その知性を使って知識を獲得する方法だと思う。私が理解できる限りでは、このような方法で、人間は、自然がその受容のために作った観
念で脳を満たしてきたのである。自然と人間は互いに助け合い、小さな始まりが少しずつ大きくなり、宇宙のすべてが円のように簡単に表現できるようになっ
た。 バイオリンの弦やチェンバロの鍵盤が振動して音を出すように、音の波に打たれた大脳の繊維は刺激され、打った言葉を表現したり繰り返したりする。そして、 脳の構造が、見るためによく形成された目が物体の像を一旦認識すると、脳はその像と差異を見ずにはいられないようになっているように、これらの差異の徴候 が脳に辿り着き、あるいは刷り込まれると、魂は必然的にそれらの関係を調べる。宇宙がほとんど物言わぬものであった時代、あらゆる物体に対する魂の態度 は、何も区別できない絵や彫刻に対する割合の観念を持たない人間のようなものであった。あるいは、魂は、小さなわらや木の切れ端を手に持っても、それらを 数えることも区別することもできずに、ぼんやりと表面的な仕方で見ている小さな子供のようであった(当時、魂は幼児期であったから)。しかし、この木片 (おそらくマストと呼ばれる)に一種の旗(基準)を付け、別の同じような物には別の旗を付け、最初の旗を記号1で、2番目の旗を記号または数2で知らせる ようにすると、子供はその物体を数えることができるようになり、このようにして算数のすべてを学ぶようになる。ある図形が別の図形と数的に等しいように見 えると、子供はすぐに、1+1は2になり、2+2は4になるといったように、それらが2つの異なる物体であると難なく判断するようになる。 このような図形の現実的または見かけ上の類似性は、すべての真理とわれわれが知っているすべてのことの根本的な基礎である。これらの科学のうち、記号があ まり単純でなく、感覚的でないものは、他のものよりも理解するのが難しいのは明らかである。なぜなら、そのような科学は、その領域の真理を表現する膨大な 数の言葉を理解し、組み合わせるために、より多くの才能を必要とするからである。その一方で、数字やその他の小さな記号で表現される学問は、容易に学ぶこ とができる。間違いなく、その実証性よりもむしろこの容易さが、代数学を幸運なものにした。 虚栄心が高慢な女衒たちの風船のような脳を満たしているこれらの知識はすべて、言葉と図形の巨大な塊に過ぎない。植物を知っている庭師が、植物を見るとそ の成長のすべての段階を思い起こすのと同じように、私たちのすべての考えは呼び覚まされる。これらの単語とその単語によって指定される対象は、脳内で非常 に密接に結びついているため、その単語や記号のないものを想像することは比較的まれである。 私はいつも「想像する」という言葉を使うが、それはすべてが想像力の働きであり、魂のすべての能力は、それらすべてが構成する純粋な想像力に正しく還元で きると考えるからである。したがって、判断力、理性、記憶力は魂の絶対的な部分ではなく、目に描かれた対象物の像が魔法の提灯のように投影される、この種 の髄質スクリーンの改変にすぎない。 しかし、脳の構造がこのような驚異的で理解しがたい結果をもたらすのであれば、すべてが想像力によって知覚され説明されるのであれば、なぜ人間の中にある 思考する感受性の原理を分けなければならないのだろうか。これは、心の単純さを主張する人々にとって明らかな矛盾ではないだろうか。分割されたものは、も はや不条理なしに不可分なものと見なすことはできないからだ。言葉の乱用や、無造作に使われ、最も聡明な人にさえ理解されない言葉(霊性、非物質性など) によって、何がもたらされるかを見てみよう。 このシステムのように、各個人の親密な感情や個人的な経験に基づいたシステムを証明することほど簡単なことはない。もし想像力、言ってみれば脳の幻想的な 部分、その性質はその作用の仕方と同様、私たちには未知であるが、それが生まれつき小さかったり弱かったりすると、その観念の類似性や類似性を比較するこ とはほとんどできないだろう!そして、想像力は魂のすべての役割を果たすのである。想像力によって、そのお世辞を言う筆によって、理性の冷たい骨格は生き ているような赤い肉を帯び、想像力によって科学は栄え、芸術は飾られ、木は語り、響きはため息をつき、岩は泣き、大理石は呼吸し、すべての無生物は生命を 得る。情愛に満ちた心の優しさに官能的な魅力を加え、哲学者の学問に優しさを芽生えさせ、埃まみれの衒学者の学問に優しさを芽生えさせ、一言で言えば、学 者や演説家や詩人を生み出すのもまた想像力である。ある者には愚かに批評され、ある者にはむなしく賞賛され、そしてすべての者には誤解される。それは美学 や芸術の流れに従うだけでなく、自然を描写するだけでなく、自然を測ることもできる。理由をつけ、判断し、分析し、比較し、調査する。自分のために描かれ た絵の美しさを、その関係を見出さなければ、これほど鋭く感じることができるだろうか。いや、五感の快楽に思いを巡らせても、その完璧さや官能を味わうこ とができないのと同じように、機械的に思いついたことを反省しても、それ自体が判断になってしまう。 想像力や最も貧弱な才能が発揮されればされるほど、それはいわば袂を分かち、より大きくなる。想像力は敏感になり、頑強になり、幅広くなり、考えることができるようになる。最良の生物には、この運動が必要なのだ。 人間の卓越した利点は、その生物である。道徳に関する書物を書く者は皆、生まれつきの資質を賞賛に値するものと見なさず、反省と努力によって得られた才能 だけを尊んでいる。技術や学識や徳は、いったいどこから来るのだろうか。このような気質は、自然からではなく、いったいどこから来るのか。私たちが善良な 資質を備えているのは、ただ自然のおかげにほかならない。それなのに、なぜ私は、後天的な、いわば借り物の徳によって輝く人と同じように、生まれつきの優 れた資質を持つ人を尊敬しないのだろうか。徳が何であろうと、それがどのような源から来たものであろうと、それは尊敬に値する。心、美、富、気品は、偶然 の産物ではあるが、技術、学識、徳がすべてそうであるように、すべてそれなりの価値がある。自然が最も高価な贈り物を盛った者は、その贈り物を拒否された 者を憐れむべきだ。しかし、専門家としての性格上、慢心することなく自分の優位性を感じることができる。美しい女性が自分のことを醜いと思うのは、聡明な 男性が自分のことを愚かだと思うのと同じくらい愚かなことだ。大げさな謙遜(確かにまれな欠点だが)は、自然に対する一種の恩知らずである。それとは反対 に、素直な誇りは、強く美しい魂の印であり、感情によって形成された男らしい特徴によって明らかになる。 自分の器官が長所であり、卓越した長所であり、他のすべての長所の源であるとすれば、教育はその次である。どんなに優れた頭脳を持っていても、教育がなけ ればまったくの宝の持ち腐れである。しかし、他方で、最も優れた学校であっても、観念の入口と着想に対して完全に開かれた母型がなければ、何の役に立つだ ろうか?また、あらゆる感覚を私有化した人間に、唯一の観念を与えることも不可能であり、自然が気晴らしを与えてくれる女性に子供を産ませ、その女性が結 婚して6年経った後に結婚を破棄されるようなこともありえない。 しかし、もし脳が同時によく組織化され、よく教育されているならば、それはよく蒔かれた肥沃な土壌であり、受けたものを百倍にしてもたらす: あるいは(言いたいことを表現し、真理そのものに優美さを加えるために、しばしば必要とされる言葉の綾は置いておくとして)芸術によって稀有で美しい天才 の威厳にまで高められた想像力は、思いついた観念のすべての関係を正確に理解し、驚くほど多くの対象を容易に取り込み、そこから長い連鎖的な結果を導き出 す。これが知性の生成だと私は思う。私が「見いだす」と言ったのは、物体の類似性に「見いだす」という形容詞をつけたのと同じで、マールブランシュ神父が 主張したように、私たちの感覚は常に欺くものであると考えたり、生まれつき少し不安定な私たちの目は、物体をありのままに見ることができないと考えたりす るためではなく(このことは顕微鏡が日々証明しているが)、バイユがよく知られているピュロン派との論争を避けるためである。 私は一般的な真理について、フォントネル氏が特定の真理について述べているように、社会と良好な関係を保つためには真理を犠牲にしなければならないと言 う。そして、それは私の性格の優しさと一致している。カルテジアンたちは、ここで無駄に、生来の考えをもって私に襲いかかろうとするだろう。私は、このよ うなキメラを攻撃するために、M.ロックのような苦労の4分の1もするつもりはない。実のところ、三千年も前に公理となった教義を証明するために膨大な書 物を書くことに何の意味があろうか。 そしてまた、恥ずべき[用語の]乱用によってのみ、我々は異なることを言っているように思っている。 最も優れた、最も偉大な、あるいは最も強い想像力とは、科学にも芸術にも最も適したものである。アリストテレスやデカルトの芸術に秀でるために、エウリピ デスやソフォクレスの芸術に秀でるよりも多くの知性が必要かどうか、また、自然がニュートンを作るためにコルネイユを作るよりも多くの手間をかけたかどう か、私は言うつもりはない。しかし、想像力だけが、さまざまに応用されて、彼らのさまざまな勝利と不滅の栄光を生み出したことは確かである。 判断力が乏しく、想像力が豊かであると言われるとすれば、それは想像力があまりにもほったらかしにされすぎていて、いわば感覚という鏡の中で自分自身を眺 めることにほとんどの時間を費やしており、感覚そのものを注意深く吟味する習慣が十分に形成されていないことを意味する。[想像力は、イメージの真偽や類 似性よりも、イメージに強く印象づけられる。 想像力の反応は実に素早いので、科学の鍵であり母である注意力がその役割を果たさなければ、想像力はその対象を駆け巡り、かすめることしかできない。 枝の上にいる鳥を見よ。いつも飛び立とうとしているように見える。イマジネーションは鳥のようなもので、常に血と動物的霊魂の騒動に乗せられている。魂は それを追い求めるが、それはしばしば無駄である。このように、時間の真の姿である想像力は、絶え間なく破壊され、更新されている。 ある波が別の波に打ち勝つように、互いを追い払うのだ。したがって、もし想像力が、いわばその筋肉の一組を使って、脳の繊維と一種の均衡を保ち、消えよう としている対象にしばらくの間注意を向け続け、別の対象を早急に思い浮かべないようにしなければ--[想像力がこのようなことをすべてしない限り]、判断 という立派な名に値することはない。想像力は、知覚したものを同じやり方で生き生きと表現する。想像力は、弁士、音楽家、画家、詩人を生み出すことはあっ ても、哲学者を生み出すことはない。それとは反対に、想像力が子供の頃から自制し、自らの衝動性--この衝動性は、華麗な熱狂者だけを生み出す--に流さ れないように訓練され、その考えを抑制し、抑制するように訓練され、対象のあらゆる側面を見るために、その考えをあらゆる側面から検討するように訓練され るなら、判断の準備が整った想像力は、理性によって、対象の可能な限り大きな領域を理解するようになる; そして、その快活さ(子供には常に良い兆候であり、学習と訓練によって調整される必要があるだけである)は、科学をほとんど進歩させることができない、遠 くを見通す洞察力に過ぎなくなる。 このような単純な土台の上に、論理学の大建築が築かれてきたのである。自然は全人類のためにこの土台を築いたが、それを利用する者もいれば、悪用する者もいる。 |
| In
spite of all these advantages of man over animals, it is doing him
honor to place him in the same class. For, truly, up to a certain age,
he is more of an animal than they, since at birth he has less instinct.
What animal would die of hunger in the midst of a river of milk? Man
alone. Like that child of olden time whom a modern writer refers,
following Arnobius, he knows neither the foods suitable for him, nor
the water that can drown him, nor the fire that can reduce him to
ashes. Light a wax candle for the first time under a child's eyes, and
he will mechanically put his fingers in the flame as if to find out
what is the new thing that he sees. It is at his own cost that he will
learn of the danger, but he will not be caught again. Or, put the child
with an animal on a precipice, the child alone falls off; he drowns
where the animal would save itself by swimming. At fourteen or fifteen
years the child knows hardly anything of the great pleasures in store
for him, in the reproduction of his species; when he is a youth, he
does not know exactly how to behave in a game which nature teaches
animals so quickly. He hides himself as if he were ashamed of taking
pleasure, and of having been made to be happy, while animals frankly
glory in being Cynics. Without education, they are without prejudices.
For one more example, let us observe a dog and a child who have lost
their master on a highway: the child cries and does not know to what
saint to pray, while the dog, better helped by his sense of smell than
the child by his reason, soon finds his master. Thus nature made us to be lower than animals or at least to exhibit all the more, because of that native inferiority, the wonderful efficacy of education which alone raises us from the level of the animals and lifts us above them. But shall we grant this same distinction to the deaf and to the blind, to imbeciles, madmen, or savages, or to those who have been brought up in the woods with animals; to those who have lost their imagination through melancholia, or in short to all those animals in human form who give evidence of only the rudest instinct? No, all these, men of body but not of mind, do not deserve to be classed by themselves. We do not intend to hide from ourselves the arguments that can be brought forward against our belief and in favor of a primitive distinction between men and animals. Some say that there is in man a natural law, a knowledge of good and evil, which has never been imprinted on the heart of animals. But is this objection, or rather this assertion, based on observation? An assertion unfounded on observation may be rejected by a philosopher. Have we ever had a single experience which convinces us that man alone has been enlightened by a ray denied all other animals? If there is no such experience, we can no more know what goes on in animals' minds or even in the minds of other men, than we can help feeling what affects the inner part of our own being. We know that we think, and we feel remorse - an intimate feeling forces us to recognize this only too well; but this feeling in us is insufficient to enable us to judge the remorse of others. That is why we have to take others at their words, or judge them by the sensible and external signs we have noticed in ourselves when we experienced the same accusations of conscience and the same torments. In order to decide whether animals which do not talk have received the natural law, we must, therefore, have recourse to those signs to which I have just referred, if any such exist. The facts seem to prove it. A dog that bit the master who was teasing it, seemed to repent a minute afterwards; it looked sad, ashamed, afraid to show itself, and seemed to confess its guilt by a crouching and downcast air. History offers us a famous example of a lion which would not devour a man abandoned to its fury, because it recognized him as its benefactor. How much might it be wished that man himself always showed the same gratitude for kindnesses, and the same respect for humanity! Then we should no longer fear either ungrateful wretches, or wars which are the plague of the human race and the real executioners of the natural law. But a being to which nature has given such a precocious and enlightened instinct, which judges, combines, reasons, and deliberates as far as the sphere of its activity extends and permits, a being which feels attachment because of benefits received, and which leaving a master who treats it badly goes to seek a better one, a being with a structure like ours, which performs the same acts, has the same passions, the same griefs, the same pleasures, more or less intense according to the sway of the imagination and the delicacy of the nervous organization - does not such a being show clearly that it knows its faults and ours, understands good and evil, and in a word, has consciousness of what it does? Would its soul, which feels the same joys, the same mortification and the same discomfiture which we feel, remain utterly unmoved by disgust when it saw a fellow-creature torn to bits, or when it had itself pitilessly dismembered this fellow-creature? If this be granted, it follows that the precious gift now in question would not have been denied to animals: for since they show us sure signs of repentance, as well as of intelligence, what is there absurd in thinking that beings, almost as perfect machines as ourselves, are, like us, made to understand and to feel nature? Let no one object that animals, for the most part, are savage beasts, incapable of realizing the evil that they do; for do all men discriminate better between vice and virtue? There is ferocity in our species as well as in theirs. Men who are in the barbarous habit of breaking the natural law are not tormented as much by it, as those who transgress for the first time, and who have not been hardened by the force of habit. The same thing is true of animals as of men - both may be more or less ferocious in temperament, and both become more so by living with others like themselves. But a gentle and peaceful animal which lives among other animals of the same disposition and of gentle nurture, will be an enemy of blood and carnage; it will blush internally at having shed blood. There is perhaps this difference, that since among animals everything is sacrificed to their needs, to their pleasures, to the necessities of life, which they enjoy more than we, their remorse apparently should not be as keen as ours, because we are not in the same state of necessity as they. Custom perhaps dulls and perhaps stifles remorse as well as pleasures. But I will for a moment suppose that I am utterly mistaken in concluding that almost all the world holds a wrong opinion on this subject, while I alone am right. I will grant that animals, even the best of them, do not know the difference between moral good and evil, that they have no recollection of the trouble taken for them, of the kindness done them, no realization of their own virtues. [I will suppose], for instance, that this lion, to which I, like so many others, have referred, does not remember at all that it refused to kill the man, abandoned to its fury, in a combat more inhuman than one could find among lions, tigers and bears, put together. For our compatriots fight, Swiss against Swiss, brother against brother, recognize each other, and yet capture and kill each other without remorse, because a prince pays for the murder. I suppose in shot that the natural law has not been given to animals. What will be the consequences of this supposition? Man is not moulded from a costlier clay; nature has used but one dough, and has merely varied the leaven. Therefore if animals do not repent for having violated this inmost feeling which I am discussing, or rather if they absolutely lack it, man must necessarily be in the same condition. Farewell then to the natural law and all the fine treatises published about it! The whole animal kingdom in general would be deprived of it. But, conversely, if man cannot dispense with the belief that when health permits him to be himself, he always distinguishes the upright, humane, and virtuous, from those who are not human, virtuous, nor honorable: that it is easy to tell vice from virtue, by the unique pleasure and the peculiar repugnance that seems to be their natural effects, it follows that animals, composed of the same matter, lacking perhaps only one degree of fermentation to make it exactly like man's, must share the same prerogatives of animal nature, and that thus there exists no soul or sensitive substance without remorse. The following considerations will reinforce these observations. It is impossible to destroy the natural law. The impress of it on all animals is so strong, that I have no doubt that the wildest and most savage have some moments of repentance. I believe that that cruel maid of Chalons in Champagne must have sorrowed for her crime, if she really ate her sister. I think that the sam thing is true of all those who commit crimes, even involuntary or temperamental crimes: true of Gaston of Orleans who could not help stealing; of a certain woman who was subject to the same crime when pregnant, and whose children inherited it; of the woman who, in the same condition, ate her husband; of that other women who killed her children, salted their bodies, and ate a piece of them every day, as a little relish; of that daughter of a thief and cannibal who at twelve years followed in his steps, although she had been orphaned when she was a year old, and had been brought up by honest people; to say nothing of many other examples of which the records of our observers are full, all of them proving that there are a thousand hereditary vices and virtues which are transmitted from parents to children as those of the foster mother pass to the children she nurses. Now, I believe and admit that these wretches do not for the most part feel at the time the enormity of their actions. Bulimia, or canine hunger, for example, can stifle all feeling; it is a mania of the stomach that one is compelled to satisfy, but what remorse must be in store for those women, when the come to themselves and grow sober, and remember the crimes they have committed against those they held most dear! What a punishment for an involuntary crime which they could not resist, of which they had no consciousness whatever! However, this is apparently not enough for the judges. For of these women, of whom I tell, one was cruelly beaten and burned, and another was buried alive. I realize that all this is demanded by the interest of society. But doubtless it is much to be wished that excellent physicians might be the only judges. They alone could tell the innocent criminal from the guilty. If reason is the slave of a depraved or mad desire, how can it control the desire? But if crime carries with it its own more or less cruel punishment, if the most continued and most barbarous habit cannot entirely blot out repentance in the cruelest hearts, if criminals are lacerated by the very memory of their deeds, why should we frighten the imagination of weak minds, by a hell, by specters, and by precipices of fire even less real than those of Pascal? Why must we have recourse to fables, as an honest pope once said himself, to torment even the unhappy wretches who are executed, because we do not think that they are sufficiently punished by their own conscience, their first executioner? I do not mean to say that all criminals are unjustly punished; I only maintain that those whose will is depraved, and whose conscience is extinguished, are punished enough by their remorse when they come to themselves, a remorse, I venture to assert, from which nature should in this case have delivered unhappy souls dragged on by a fatal necessity. Criminals, scoundrels, ingrates, those in short without natural feelings, unhappy tyrants who are unworthy of life, in vain take a cruel pleasure in their barbarity, for there are calm moments of reflection in which the avenging conscience arises, testifies against them, and condemns them to be almost ceaselessly torn to pieces at their own hands. Whoever torments men is tormented by himself; and the sufferings that he will experience will be the just measure of those that he has inflicted. On the other hand, there is so much pleasure in doing good, in recognizing and appreciating what one receives, so much satisfaction in practising virtue, in being gentle, humane, kind, charitable, compassionate and generous (for this one word includes all the virtues), that I consider as sufficiently punished any one who is unfortunate enough not to have been born virtuous. We were not originally made to be learned; we have become so perhaps by a sort of abuse of our organic faculties, and at the expense of the State which nourishes a host of sluggards whom vanity has adorned with the name of philosophers. Nature has created us all solely to be happy - yes, all of us from the crawling worm to the eagle lost in the clouds. For this cause she has given all animals some share of natural law, a share greater or less according to the needs of each animal's organs when in normal condition. Now how shall we define natural law? It is a feeling that teaches us what we should not do, because we would not wish it to be done to us. Should I dare add to this common idea, that this feeling seems to me but a kind of fear or dread, as salutary to the race as to the individual; for may it not be true that we respect the purse and life of others, only to save our own possessions, our honor, and ourselves; like those Ixions of Christianity who love God and embrace so many fantastic virtues, merely because they are afraid of hell! You see that natural law is but an intimate feeling that, like all other feelings (thought included) belongs also to imagination. Evidently, therefore, natural law does not presuppose education, revelation, nor legislator, - provided one does not propose to confuse natural law with civil laws, in the ridiculous fashion of the theologians. The arms of fanaticism may destroy those who support these truths, but they will never destroy the truths themselves. I do not mean to call in question the existence of a supreme being; on the contrary it seems to me that the greatest degree of probability is in favor of this belief. But since the existence of this being goes no further than that of any other toward proving the need of worship, it is a theoretic truth with very little practical value. Therefore, since we may say, after such long experience, that religion does not imply exact honesty, we are authorized by the same reasons to think that atheism does not exclude it. Furthermore, who can be sure that the reason for man's existence is not simply the fact that he exists? Perhaps he was thrown by chance on some spot on the earth's surface, nobody knows how nor why, but simply that he must live and die, like the mushrooms which appear from day to day, or like those flowers which border the ditches and cover the walls. Let us not lose ourselves in the infinite, for we are not made to have the least idea thereof, and are absolutely unable to get back to the origin of things. Besides it does not matter for our peace of mind, whether matter be eternal or have been created, whether there be or be not a God. How foolish to torment ourselves so much about things which we can not know, and which would not make us any happier even were we to gain knowledge about them! But, some will say, read all such works as those of Fénelon, of Nieuwentyt, of Abadie, of Berham, of Rais, and the rest. Well! what will they teach me or rather what have they taught me? They are only tiresome repetitions of zealous writers, one of whom adds to the other only verbiage, more likely to strengthen than to undermine the foundations of atheism. The number of evidences drawn from the spectacle of nature does not give these evidences any more force. Either the mere structure of a finger, of an ear, of an eye, a single observation of Malpighi proves all, and doubtless much better than Descartes and Malebranche proved it, or all the other evidences prove nothing. Deists, and even Christians, should therefore be content to point out that throughout the animal kingdom the same aims are pursued and accomplished by an infinite number of different mechanisms, all of them however exactly geometrical. For what stronger weapons could there be with which to overthrow atheists? It is true that if my reason does not deceive me, man and the whole universe seem to have been designed for this unity of aim. The sun, air, water, the organism, the shape of bodies, - everything is brought to a focus in the eye as in a mirror that faithfully presents to the imagination all the objects reflected in it, in accordance with the laws required by the infinite variety of bodies which take part in vision. In ears we find everywhere a striking variety, and yet the difference of structure in men, animals, birds, and fishes, does not produce different uses. All ears are so mathematically made, that they tend equally to one and the same end, namely hearing. But would Chance, the deist asks, be a great enough geometrician to vary thus, at pleasure, the works of which she is supposed to be the author, without being hindered by so great a diversity from gaining the same end? Again, the deist will bring forward as a difficulty those parts of the animal that are clearly contained in it for future use, the butterfly in the caterpillar, man in the sperm, a whole polyp in each of its parts, the valvule in the oval orifice, the lungs in the foetus, the teeth in their sockets, the bones in the fluid from which they detach themselves and (in an incomprehensible manner) harden. And since the partisans of this theory, far from neglecting anything that would strengthen proof, never tire of piling up proof upon proof, they are willing to avail themselves of everything, even of the weakness of the mind in certain cases. Look, they say, at men like Spinoza, Vanini, Desbarreau, and Boindin, apostles who honor deism more than they harm it. The duration of their health was the measure of their unbelief, and one rarely fails, they add, to renounce atheism when the passions, with their instrument, the body, have grown weak. That is certainly the most that can be said in favor of the existence of God: although the last argument is frivolous in that these conversions are short, and the mind almost always regains its former opinions and acts accordingly, as soon as it has regained or rather rediscovered its strength in that of the body. That is, at least, much more than was said by the physician Diderot, in his Pensées Philosophiques, a sublime work that will not convince a single atheist. What reply can, in truth, be made to a man who says, ``We do not know nature; causes hidden in her breast might have produced everything. In your turn, observe the polyp of Trembley: does it not contain in itself the causes which bring about regeneration? Why then would it be absurd to think that there are physical causes by reason of which everything has been made, and to which the whole chain of this vast universe is so necessarily bound and held that nothing which happens, could have failed to happen, - causes, of which we are so invincibly ignorant that we have had recourse to a God, who, as some aver, is not so much as a logical entity? Thus to destroy chance is not to prove the existence of a supreme being, since there may be some other thing which is neither chance nor God - I mean, nature. It follows that the study of nature can only make unbelievers; and the way of thinking of all its more successful investigators proves this.'' |
このように人間が動物より優
れているにもかかわらず、人間を同じ階級に置くのは名誉なことである。というのも、ある年齢までは、人間の方が動物に近いからである。ミルクの川の中で飢
え死にする動物がいるだろうか?人間だけだ。アルノビウスに倣って現代の作家が言及した昔の子供のように、彼は自分に適した食べ物も、彼を溺れさせる水
も、彼を灰にする火も知らない。蝋燭を初めて子供の目の前で灯すと、子供は機械的に炎の中に指を入れ、まるで自分が見た新しいものが何であるかを知ろうと
する。危険を知るのは自分の代償だが、二度と捕まることはないだろう。動物が泳げば助かるところを、子どもは溺れてしまう。14、15歳の子どもは、自分
の種の繁殖という大きな楽しみをほとんど知らない。青少年になると、自然が動物に素早く教える遊びの中で、どのように振る舞えばいいのか正確に分からなく
なる。動物たちが皮肉屋であることを率直に誇っているのに対して、彼は喜びを得ること、幸せにされることを恥じるかのように身を隠す。教育がなければ、偏
見もない。もうひとつの例として、街道で主人を見失った犬と子供を観察してみよう。子供は泣きながら、どの聖人に祈ればいいのかわからない。 このように、自然は私たちを動物よりも低い存在にした。少なくとも、生まれつきの劣等感のために、私たちを動物のレベルから引き離し、動物の上に引き上げ る教育の素晴らしい効果を、よりいっそう発揮するようにしたのである。しかし、このような区別を、耳の聞こえない者、目の見えない者、無能な者、気違い、 野蛮人、森の中で動物と一緒に育った者、メランコリアによって想像力を失った者、要するに、人間の形をした動物のうち、最も初歩的な本能しか示さないもの すべてに認めるべきだろうか。いや、肉体はともかく、精神はそうでないこれらの人たちは、彼ら自身によって分類されるには値しない。 われわれの信念に反対し、人間と動物を原始的に区別することに賛成する論拠を、われわれ自身から隠すつもりはない。人間には自然法則があり、善悪の知識があるが、動物の心には決して刻み込まれていないと言う人がいる。 しかし、この反論は、いやむしろこの主張は、観察に基づいているのだろうか。観察に基づかない主張は、哲学者によって否定されるかもしれない。人間だけ が、他のすべての動物に否定された一筋の光によって啓発されたと確信させるような経験を、私たちはこれまでに一度でもしたことがあるだろうか。もしそのよ うな経験がないとすれば、動物の心の中、あるいは他の人間の心の中で何が起こっているのかを知ることはできない。私たちは、自分が考えていること、自責の 念を感じていることは知っている。だからこそ、私たちは他人の言葉をそのまま受け取るか、あるいは、私たち自身が同じように良心の呵責や苦しみを経験した ときに気づいた、感覚的で外見的な兆候によって判断しなければならないのである。 言葉を話さない動物が自然法則を受け取ったかどうかを判断するためには、もしそのような徴候が存在するならば、今述べたような徴候に頼らなければならな い。事実がそれを証明している。からかっていた主人に噛みついた犬は、その1分後には後悔したように見えた。悲しそうな、恥ずかしそうな、姿を見せるのを 恐れたような、しゃがみ込んでうつむいたような表情で罪を告白したように見えた。歴史には、ライオンの有名な例がある。ライオンは、怒りに身を任せた人間 を食い殺そうとはしなかった。人間自身が、親切に対して同じように感謝し、人間性を同じように尊重することを、どれほど望んだことだろう!そうすれば、恩 知らずの惨めな人間も、人類の疫病であり自然法則の真の実行者である戦争も、もはや恐れることはないだろう。 しかし、自然がこのような早熟で覚醒した本能を与えた存在、判断し、結合し、理由をつけ、その活動領域が広がり、許す限り熟慮する存在、受けた恩恵のため に愛着を感じ、ひどい扱いをする主人のもとを去り、より良い主人を探しに行く存在、私たちのような構造を持つ存在は、同じ行為を行い、私たちのような構造 を持つ、 同じ行為をし、同じ情熱、同じ悲哀、同じ快楽を持ち、想像力の揺れや神経組織の繊細さによって、その激しさは多かれ少なかれ変わる--そのような存在は、 自分の欠点と私たちの欠点を知り、善と悪を理解し、一言で言えば、自分のすることに自覚的であることをはっきりと示しているのではないだろうか。われわれ が感じるのと同じ喜び、同じ悔しさ、同じ落胆を感じるその魂は、仲間の生き物が引き裂かれるのを見たとき、あるいは自分自身がこの仲間の生き物を無情にも バラバラにしてしまったとき、嫌悪感にまったく動じないだろうか。もしこれが認められるなら、今問題になっている貴重な贈り物が動物に否定されることはな かったことになる。なぜなら、動物は知性と同様に悔悟の確かなしるしを私たちに示すのだから、私たちとほとんど同じ完全な機械である動物が、私たちと同じ ように、自然を理解し、自然を感じるようにできていると考えることのどこが不合理なのだろうか。 動物たちは、そのほとんどが野蛮な獣であり、自分たちが行う悪を理解することはできない。私たちの種にも彼らの種にも獰猛さがある。自然の掟を破る野蛮な 習慣を持つ人間は、初めて罪を犯し、習慣の力によって硬化していない人間ほど、それによって苦しめられることはない。動物にも人間にも同じことが言える。 どちらも多かれ少なかれ獰猛な気質を持つかもしれないし、自分と同じような他者と暮らすことでよりそうなる。しかし、穏やかで平和的な動物が、同じ気質を 持ち、穏やかに育った他の動物の中で生活すると、血と殺戮の敵になる。動物たちの間では、あらゆるものが彼らの必要性、楽しみ、生活必需品のために犠牲に され、彼らは我々よりもそれを享受している。習慣はおそらく、快楽と同様に自責の念を鈍らせ、抑圧する。 しかし、この問題に関して、ほとんどすべての世界が間違った意見を持っているのに対して、私だけが正しいと結論づけているのは、まったくの思い違いである と、ちょっとだけ考えてみよう。動物たちは、たとえどんなに優れた動物であっても、道徳的な善悪の区別がつかず、自分のためにしてくれた苦労や親切を思い 出すこともなく、自分自身の美徳に気づくこともない。[例えば、私が他の多くの人々と同じように言及したこのライオンは、ライオン、トラ、クマを合わせた ものよりも非人間的な戦いにおいて、その怒りに身を任せた人間を殺すことを拒否したことをまったく覚えていないと仮定する。私たちの同胞は、スイス人とス イス人、兄弟と兄弟として戦い、互いを認め合い、それでも反省することなく捕らえ、殺し合う。動物には自然法則が与えられていないのだろう。この仮定はど のような結果をもたらすだろうか。自然は一つの生地しか使わず、澱を変えただけである。したがって、もし動物たちが、私が論じているこの内なる感情を犯し たことを悔い改めないのであれば、いや、むしろ絶対的に欠如しているのであれば、人間も必然的に同じ状態にならざるを得ない。それでは、自然法則と、それ について出版されたすべての立派な論説に別れを告げよう!動物界全体が自然法則を失ってしまうのだ。しかし逆に、もし人間が、健康で自分自身であることを 許されているときには、まっすぐで、人間的で、高潔な者と、人間的でなく、高潔でなく、名誉のない者とを常に見分けることができるという信念を捨て去るこ とができないとすれば、人間は、悪と悪徳とを容易に見分けることができるということになる: 悪と徳とを見分けるのは、その自然な作用と思われる独特の快楽と独特の嫌悪感によって容易であることから、同じ物質からなる動物も、おそらくは人間とまっ たく同じにするための発酵の度合いを1度だけ欠くだけで、動物本性の同じ特権を共有しているに違いなく、したがって、後悔のない魂や感受性の強い物質は存 在しないことになる。次の考察は、これらの観察を補強するだろう。 自然法則を破壊することは不可能である。すべての動物に自然法則の印象は非常に強いので、最も野蛮な野生動物にも、悔い改める瞬間があることを私は疑わな い。シャンパーニュ地方のシャロンの残酷な女中も、本当に妹を食べたのなら、その罪を悲しんだに違いない。同じようなことが、たとえ非自発的な、あるいは 気質的な犯罪であっても、犯罪を犯すすべての人に当てはまると思う: 盗みをせずにはいられなかったオルレアンのガストン、妊娠中に同じ罪を犯し、その子供がそれを受け継いだある女性、同じ状態で夫を食べた女性、自分の子供 を殺し、その死体を塩漬けにし、毎日一切れずつ、ちょっとしたごちそうとして食べた女性; 泥棒と人食いの娘で、1歳のときに孤児となり、正直な人々に育てられたにもかかわらず、12歳にして彼の跡を継いだ者のこと。さて、私は、このような惨め な人たちが、ほとんどの場合、自分の行為の重大さをその時点では感じていないことを信じているし、認めている。例えば過食症や犬の飢えは、すべての感情を 押し殺してしまう!抵抗することもできず、自覚もなかった不本意な罪に対して、なんという罰だろう!しかし、裁判官たちにはこれだけでは不十分なようだ。 この女性たちのうち、一人は無残に殴られ、焼かれ、もう一人は生き埋めにされた。私は、これらすべてが社会の利益によって要求されていることを理解してい る。しかし間違いなく、優秀な医師だけが裁判官であってほしいと願っている。彼らだけが無実の犯罪者と有罪の犯罪者を見分けることができるのだから。もし 理性が堕落した、あるいは狂った欲望の奴隷だとしたら、どうやってその欲望をコントロールできるだろうか。 しかし、犯罪が多かれ少なかれ残酷な刑罰を伴うものであるならば、最も残酷な心の中で最も継続的で野蛮な習慣が悔悟の念を完全に消し去ることができないな らば、犯罪者が自分の行いの記憶そのものによって引き裂かれるならば、なぜわれわれは、パスカルのそれよりもさらに現実的でない地獄や妖怪や火の絶壁に よって、弱い心の想像力をおびえさせなければならないのだろうか。ある正直な教皇がかつて言ったように、処刑された不幸な惨めな者たちをも苦しめるため に、なぜ寓話に頼らなければならないのか。私は、すべての犯罪者が不当に罰せられていると言うつもりはない。私が主張するのは、意志が堕落し、良心が消滅 した者は、我に返ったときの自責の念によって十分に罰せられているということだけである。 犯罪者、悪党、恩知らず、要するに自然な感情を持たない者、生きるに値しない不幸な暴君たちは、無駄に自分の蛮行を残酷に楽しんでいる。人を苦しめる者は誰でも、自分自身を苦しめるのであり、その人が経験する苦しみは、自分が与えた苦しみの正当な尺度なのである。 一方、善を行うこと、自分が受けたものを認め感謝すること、徳を実践すること、穏やかであること、人道的であること、親切であること、慈善的であること、 思いやりがあること、寛大であること(この一言にはすべての徳が含まれる)には多くの喜びがあり、私は、不幸にして徳のある者に生まれなかった者は、十分 に罰せられたと考える。 われわれはもともと学問をするようにつくられたのではない。われわれはおそらく、われわれの器質的能力を一種の濫用によって、また、虚栄心が哲学者という 名で飾り立てた怠け者の群れを養う国家の犠牲によって、そうなってしまったのだ。そう、這う虫から雲の中に迷い込んだ鷲に至るまで、すべての人間がそうな のだ。この目的のために、自然はすべての動物に自然法則の分け前を与えたのである。 さて、自然法則とはどのようなものだろうか。それは、私たちがしてはならないことを教えてくれる感情である。この一般的な考え方にあえて付け加えれば、この感覚は一種の恐怖や恐れに過ぎないように思える! 自然法は、他のすべての感情(思考も含む)と同様に、想像力にも属する親密な感情にすぎないことがわかるだろう。したがって、自然法は、教育や啓示や立法者を前提としないことは明らかである。 狂信の腕は、これらの真理を支持する人々を滅ぼすことはあっても、真理そのものを滅ぼすことはない。 私は、至高の存在の存在に疑問を投げかけるつもりはない。しかし、この存在の存在は、崇拝の必要性を証明する上で、他の存在と何ら変わらないので、理論的 な真理であり、実際的な価値はほとんどない。したがって、これほど長い経験の後では、宗教は正確な正直さを意味しないと言えるので、同じ理由で、無神論は それを排除しないと考えることができる。 さらに、人間が存在する理由が、単に存在するという事実だけではないと誰が言い切れるだろうか。おそらく彼は、地表のある場所に偶然投げ出されたのだろ う。どのようにして、またなぜなのかは誰にもわからないが、ただ、日ごとに現れるキノコのように、あるいは溝を縁取り壁を覆う花のように、生きては死んで いくに違いない。 私たちは無限の中に身を置いてはいけない。なぜなら、私たちはそのようなことを少しも考えることができないし、物事の起源に立ち戻ることもできないから だ。それに、物質が永遠であろうと、創造されたものであろうと、神がいようといまいと、私たちの心の平安には関係ない。知ることもできず、たとえ知識を得 たとしても何一つ幸福にならないようなことについて、これほど自分を苦しめるのはなんと愚かなことだろう! しかし、フェネロンやニーウェンティ、アバディ、ベルハム、レイスなどの著作を読めと言う人もいるだろう。さて、そんなものが私に何を教えてくれるのだろ う。それらは熱心な作家たちのうんざりするような繰り返しに過ぎず、そのうちの一人は、無神論の土台を崩すというよりむしろ強化するような言葉を他の作家 に付け加えるだけである。自然の光景から引き出される証拠の数は、これらの証拠にそれ以上の力を与えない。指の構造、耳の構造、目の構造、マルピーギの たった一つの観察がすべてを証明するか、デカルトやマールブランシュが証明したよりもはるかに優れていることは間違いない。したがって、脱神論者は、そし てキリスト教徒でさえも、動物界全体を通じて、同じ目的が無限の異なるメカニズムによって追求され、達成されていることを指摘するだけで満足すべきであ る。無神論者を打倒するために、これ以上強力な武器があるだろうか。私の理性に惑わされなければ、人間も宇宙全体も、このように統一された目的のために設 計されているように思えるのは事実である。太陽も、空気も、水も、有機体も、物体の形も......あらゆるものが、鏡のように目の焦点に合わせられ、鏡 に映るすべての対象が、視覚を担う無限の多様な物体が要求する法則に従って、想像力に忠実に提示される。しかし、人間、動物、鳥、魚の構造の違いが、異な る用途を生み出すわけではない。すべての耳は数学的に作られており、同じ目的、すなわち聴覚に等しく向かっている。しかし、チャンスは、そのような多様性 によって同じ目的を達成することを妨げられることなく、自分が作者であるとされる作品を自由に変化させることができるほど、偉大な幾何学者であろうかと、 神学者は問うのである。また、脱神論者は、将来使用するために動物の中に明らかに含まれている部分、すなわち、毛虫の中の蝶、精子の中の人間、各部分の中 の全ポリプ、卵円孔の中の弁、胎児の中の肺、歯槽の中の歯、骨から離脱して(不可解な方法で)固まる液体の中の骨を、困難として持ち出すだろう。この説の 支持者たちは、証拠を補強するようなことを怠るどころか、証拠に証拠を積み重ねることに飽きることがない。スピノザ、ヴァニーニ、デバロー、ボインダンの ような人物を見よ、彼らは神学を害するよりも神学を尊ぶ使徒たちだと言う。彼らの健康状態が不信仰の尺度であり、その道具である肉体が衰弱した情念が無神 論を放棄するのに失敗することはめったにない、と彼らは付け加える。 最後の議論は軽薄であるが、このような改宗は短時間であり、精神は肉体の力を取り戻すか、むしろ再発見するとすぐに、ほとんど常に以前の意見を取り戻し、 それに従って行動するのである。これは少なくとも、医師ディドロがその『哲学論集』の中で述べた以上のことである。私たちは自然を知らない。自然の胸に隠 された原因がすべてを生み出しているのかもしれない。では、トレンブリーのポリープを観察してみよう。それなのに、なぜ物理的な原因があると考えることが 不合理なのだろうか。その原因によってすべてのものが作られ、この大宇宙の連鎖全体が必然的に結びつけられ、保持されているのである。なぜなら、偶然でも 神でもない別のもの、つまり自然が存在するかもしれないからである。自然を研究することは、不信心者を作ることにしかならない。そして、より成功した研究 者たちの考え方が、このことを証明している」。 |
| The
weight of the universe therefore far from crushing a real atheist does
not even shake him. All these evidences of a creator, repeated
thousands and thousands of times, evidence that are placed far above
the comprehension of men like us, are self-evident (however far one
push the argument) only to the anti-Pyrrhonians, or to those who have
enough confidence in their reason top believe themselves capable of
judging on the basis of certain phenomena, against which, as you see,
the atheist can urge others perhaps equally strong and absolutely
opposed. For if we listen to the naturalists again, they will tell us
that the very causes which, in a chemist's hands, by a chance
combination, made the first mirror, in the hands of nature made the
pure water, the mirror of the simple shepherdess; that the motion which
keeps the world going could have created it, that each body has taken
the place assigned to it by its own nature, that the air must have
surrounded the earth, and that iron and the other metals are produced
by the internal motions of the earth, for one and the same reason; that
the sun is as much a natural product as electricity, that it was not
made to warm the earth and its inhabitants, whom it sometimes burns,
any more than the rain was made to make the seeds grow, which it often
spoils; that the mirror and the water were no more made for people to
see themselves in, than were all other polished bodies with this same
property; that the eye is in truth a kind of glass in which the soul
can contemplate the image of objects as they are presented to it by
these bodies, but that it is not proved that this organ was really made
expressly for this contemplation, nor purposely placed in its socket,
and in short it may well be that Lucretius, the physician Lamy, and all
Epicureans both ancient and modern were right when they suggested that
the eye sees only because it is formed and placed as it is, and that,
given once for all, the same rules of motion followed by nature in the
generation and development of bodies, this marvelous organ could not
have been formed and placed differently. Such is the pro and the con, and the summary of those fine arguments that will eternally divide the philosophers. I do not take either side. ``Non nostrum inter vos tantas compenere lites.'' This is what I said to one of my friends, a Frenchman, as frank a Pyrrhonian as I, a man of much merit, and worthy of a better fate. He gave me a very singular answer in regard to the matter. ``It is true,'' he told me, ``that the pro and con should not disturb at all the soul of a philosopher, who sees that nothing is proved with clearness enough to force his consent, and that the arguments offered on one side are neutralized by those of the other. However,'' he continued, ``the universe will never be happy, unless it is atheistic.'' Here are this wretch's reasons. If atheism, said he, were generally accepted, all the forms of religion would then be destroyed and cut off at the roots. No more theological wars, no more soldiers of religion - such terrible soldiers! Nature infected with a sacred poison, would regain its rights and its purity. Deaf to all other voices, tranquil mortals would follow on the spontaneous dictates of their own being, the only commands which can never be despised with impunity and which alone can lead us to happiness through the pleasant paths of virtue. Such is natural law: whoever rigidly observes it is a good man and deserves the confidence of all the human race. Whoever fails to follow it scrupulously affects, in vain, the specious exterior of another religion; he is a scamp or a hypocrite whom I distrust. After this, let a vain people think otherwise, let them dare affirm that even probity is at stake in not believing in revelation, in a word that another religion than that of nature is necessary, whatever it may be. Such an assertion is wretched and pitiable; and so is the good opinion which each one gives us of the religion he has embraced! We do not seek here the votes of the crowd. Whoever raises in his heart altars to superstition, is bound to worship idols and not to thrill to virtue. But since all the faculties of the soul depend to such a degree on the proper organization of the brain and of the whole body, that apparently they are but this organization itself, the soul is clearly an enlightened machine. For finally, even if man alone had received a share of natural law, would he be any less a machine for that? A few more wheels, a few more springs than in the most perfect animals, the brain proportionally nearer the heart and for this very reason receiving more blood - any one of a number of unknown causes might always produce this delicate conscience so easily wounded, this remorse which is no more foreign to matter than to thought, and in a word all the differences that are supposed to exist here. Could the organism then suffice for everything? Once more, yes; since thought visibly develops with our organs, why should not the matter of which they are composed be susceptible of remorse also, when once it has acquired, with time, the faculty of feeling? The soul is therefore but an empty word, of which no one has any idea, and which an enlightened man should only use to signify the part in us that thinks. Given the least principle of motion, animated bodies will have all that is necessary for moving, feeling, thinking, repenting, or in a word for conducting themselves in the physical realm, and in the moral realm which depends upon it. Yet we take nothing for granted; those who perhaps think that all the difficulties have not yet been removed shall now read of experiments that will completely satisfy them. The flesh of all animals palpitates after death. This palpitation continues longer, the more cold blooded the animal is and the less it perspires. Tortoises, lizards, serpents, etc. are evidence of this. Muscles separated from the body contract when they are stimulated. The intestines keep up their peristaltic or vermicular motion for a long time. According to Cowper, a simple injection of hot water reanimates the heart and the muscles. A frog's heart moves for an hour or more after it has been removed from the body, especially when exposed to the sun or better still when placed on a hot table or chair. If this movement seem totally lost, one has only to stimulate the heart, and that hollow muscle beats again. Harvey made this same observation on toads. Bacon of Verulam in his treatise Sylva Sylvarum cites the case of a man convicted of treason, who was opened alive, and whose heart thrown into hot water leaped several times, each time less high, to the perpendicular height of two feet. Take a tiny chicken still in the egg, cut out the heart and you will observe the same phenomena as before, under almost the same conditions. The warmth of the breath alone reanimates an animal about to perish in the air pump. The same experiments, which we owe to Boyle and to Stenon, are made on pigeons, dogs, and rabbits. Pieces of their hearts beat as their whole hearts would. The same movements can be seen in paws that have been cut off from moles. The caterpillar, the worm, the spider, the fly, the eel - all exhibit the same phenomena; and in hot water, because of the fire it contains, the movement of the detached parts increases. A drunken soldier cut off with one stroke of his sabre an Indian rooster's head. The animal remained standing, then walked, and ran: happening to run against a wall, it turned around, beats its wings still running, and finally fell down. As it lay on the ground, all the muscles of this rooster kept on moving. That is what I saw myself, and almost the same phenomena can easily be observed in kittens or puppies with their heads cut off. Polyps do more than move after they have been cut in pieces. In a week they regenerate to form as many animals as there are pieces. I am sorry that these facts speak against the naturalists' system of generation; or rather I am very glad of it, for let this discovery teach us never to reach a general conclusion even on the ground of all known (and most decisive) experiments. Here we have many more facts than are needed to prove, in an incontestable way, that each tiny fiber or part of an organized body moves by a principle which belongs to it. Its activity, unlike voluntary motions, does not depend in any way on the nerves, since the movements in question occur in parts of the body which have no connection with the circulation. But if this force is manifested even in sections of fibers the heart, which is a composite of peculiarly connected fibers, must possess the same property. I did not need Bacon's story to persuade me of this. It was easy for me to come to this conclusion, both from the perfect analogy of the structure of the human heart with that of animals, and also from the very bulk of the human heart, in which this movement escapes our eyes only because it is smothered, and finally because in corpses all the organs are cold and lifeless. If executed criminals were dissected while their bodies are still warm, we should probably see in their hearts the same movements that are observed in the face-muscles of those that have been beheaded. The motive principle of the whole body, and even of its parts cut in pieces, is such that it produces not irregular movements, as some have thought, but very regular ones, in warm blooded and perfect animals as well as in cold and imperfect ones. No resource therefore remains open to our adversaries but to deny thousands and thousands of facts which every man can easily verify. If now any one ask me where is this innate force in our bodies, I answer that it very clearly resides in what the ancients called the parenchyma, that is to say, in the very substance of the organs not including the veins, the arteries, the nerves, in a word, that it resides in the organization of the whole body, and that consequently each organ contains within itself forces more or less active according to the need of them. Let us now go into some detail concerning these springs of the human machine. All the vital, animal, natural, and automatic motions are carried on by their action. Is it not in a purely mechanical way that the body shrinks back when it is struck with terror at the sight of an unforeseen precipice, that the eyelids are lowered at the menace of a blow, as some have remarked, and that the pupil contracts in broad daylight to save the retina, and dilates to see objects in darkness? Is it not by mechanical means that the pores of the skin close in winter so that the cold cannot penetrate to the interior of the blood vessels, and that the stomach vomits when it is irritated by poison, by a certain quantity of opium and by all emetics, etc.? that the heart, the arteries and the muscles contract in sleep as well as in waking hours, that the lungs serve as bellows continually in exercise, n'est-ce pas machinalement qu'agissent tous les sphincters de la vessie, du rectum, etc.? that the heart contracts more strongly than any other muscle? que les muscles érecteurs font dresser la verge dans l'homme, comme dans les animaux qui s'en battent le ventre, et même dans l'enfant, capable d'érection, pour peu que cette partie soit irritée? Ce qui prouve, pour le dire en passant, qu'il est un ressort singulier dans ce membre, encore peu connu, et qui produit des effets qu'on n'a point encoure bien expliqués, malgré toutes les lumières de l'anatomie. I shall not go into any more detail concerning all these little subordinate forces, well known to all. But there is another more subtle and marvelous force, which animates them all; it is the source of all our feelings, of all our pleasures, of all our passions, and of all our thoughts: for the brain has its muscles for thinking, as the legs have muscles for walking. I wish to speak of this impetuous principle that Hippocrates calls enormon (soul). This principle exists and has its seat in the brain at the origin of the nerves, by which it exercises its control over all the rest of the body. By this fact is explained all that can be explained, even to the surprising effect of maladies of the imagination. Mais, pour ne pas languir dans une richesse et un fécondité mal entendue, il faut se borner à un petit nombre de questions et de réflexions. Pourquoi la vue ou la simple idée d'une belle femme nous cause-t-elle des mouvements et des désirs singuliers? Ce qui se passe alors dans certains organes, vient-il de la nature même de ces organes? Point du toutl mais du commerce et de l'espèce de sympathie de ces muscles avec l'imagination. Il n'y a ici qu'un premier ressort excité par le bene placitum des anciens, ou par l'image de la beauté, qui en excite un autre, lequel était fort assoupi, quand l'imagination l'a éveillé: et comment cela, si ce n'est par le désordre et le tumulte du sang et des esprits, qui galopent avec une promptitude extraordinaire, et vont gonfler les corps caverneux? Puisqu'il est des commincations évidents entre la mère et l'enfant, et qu'il est dur de nier des fair rapportés par Tulpius et par d'autres écrivains aussi dignes de foi (il n'y en a point qui le soient plus), nous croirons que c'est par la même voie que le foetus ressent l'impétuoisité de l'imagination maternelle, comme une cire molle reçe;oit toutes sortes d'impressions; et que les mêmes traces, ou envies de la mère, peuvent s'imprimer sur le foetus, sans que cela puisse se comprendre, quoiqu'en disent Blondel et tous ses adhérenets. Ainsi nous faisons réparation d'honneur au P. Malebranche, beaucoup trop raillé de sa crédulité par les auteurs qui n'ont point observé d'assex près la nature et ont voulu l'assujettir à leur idées. Look at the portrait of the famous Pope who is, to say the least, the Voltaire of the English. The effort, the energy of his genius are imprinted upon his countenance. It is convulsed. His eyes protrude from their sockets, the eyebrows are raised with the muscles of the forehead. Why? Because the brain is in travail and all the body must share in such a laborious deliverance. If there were not an internal cord which pulled the external ones, whence would come all these phenomena? To admit a soul as explanation of them, is to be reduced to [explaining phenomena by] the operations of the Holy Spirit. In fact, if what thinks in my brain is not a part of this organ and therefore of the whole body, why does my blood boil, and the fever of my mind pass into my veins, when lying quietly in bed, I am forming the plan of some work or carrying on an abstract calculation? Put this question to men of imagination, to great poets, to men who are enraptured by the felicitous expression of sentiment, and transported by an exquisite fancy or by the charms of nature, of truth, or of virtue! By their enthusiasm, by what they will tell you they have experienced, you will judge the cause by its effects; by that harmony which Borelli, a mere anatomist, understood better than all the Leibnizians, you will comprehend the material unity of man. In short, if the nerve-tension which causes pain occasions also the fever by which the distracted mind looses its will-power, and if, conversely, the mind too much excited, disturbs the body (and kindles that inner fire which killed Bayle while he was still so young)l if an agitation rouses my desire and my ardent wish for what, a moment ago, I cared nothing about, and if in their turn certain brain impressions excite the same longing and the same desires, then why should we regard as double what is manifestly one being? In vain you fall back on the power of the will, since for one order that the will gives, it bows a hundred times to the yoke, And what wonder that in health the body obeys, since a torrent of blood and of animal spirits forces its obedience, and since the will has as ministers an invisible legion of fluids swifter than lightning and ever ready to do its bidding! But as the power of the will is exercised by means of the nerves, it is likewise limited by them. La meilleure volonté d'un amant épuisé, les plus violent desires lui rendront-ils sa vigueur perdue? Hélas! non; et elle en sera la première punie, parce-que, posées certaines circonstances, il n'est pas dans sa puissance de ne pas vouloir du plaisir. Ce que j'ai dit de la paralysie, etc. revient ici. Does the result of jaundice surprise you? Do you not know that the color of bodies depends on the color of the glasses through which we look at them, and that whatever is the color of the humors, such is the color of objects, at least for us, vain playthings of a thousand illusions? But remove this color from the aqueous humor of the eye, let the bile flow through its natural filter, then the soul having new eyes, will no longer see yellow. Again,. is it not thus, by removing cataract, or by injecting the Eustachian canal, that sight is restored to the blind, or hearing to the deaf? How many people, who were perhaps only clever charlatans, passed for miracle workers in the dark ages! Beautiful the soul, and powerful the will which can not act save by permission of the bodily conditions, and whose tastes change with age and fever! Should we, then, be astonished that philosophers have always had in mind the health of the body, to preserve the health of the soul, that Pythagoras gave rules for the diet as carefully as Plato forbade wine? The regime suited to the body is always the one with which sane physicians think they must begin, when it is a question of forming the mind, and of instructing it in the knowledge of truth and virtue; but these are vain words in the disorder of illness, and in the tumult of the senses. Without the precepts of hygiene, Epictetus, Socrates, Plato, and the rest preach in vain: all ethics is fruitless for one who lacks his share of temperance; it is the source of all virtues, as intemperance is the source of all vices. Is more needed, (for why lose myself in discussion of the passions which are all explained by the term, enormon, of Hippocrates) to prove that man is but an animal, or a collection of springs which wind each other up, without or being able to tell at what point in this human circle, nature has begun? If these springs differ among themselves, these differences consist only in their position and in their degrees of strength, and never in their nature; wherefore the soul is but a principle of motion or a material and sensible part of the brain, which can be regarded, without fear of error, as the mainspring of the whole machine, having a visible influence on all the parts. The soul seems even to have been made for the brain, so that all other parts of the system are but a kind of emanation from the brain. This will appear from certain observations, made on different embryos, which I shall now enumerate. This oscillation, which is natural or suited to our machine, and with which each fibre and even each fibrous element, so to speak, seems to be endowed, like that of a pendulum, cannot keep up forever. It must be renewed, as it loses strength, invigorated when it is tired, and weakened when it is disturbed by an excess of strength and vigor. In this alone, true medicine consists. The body is but a watch, whose watchmaker is the new chyle. Nature's first care, when the chyle enters the blood, is to excite in it a kind of fever which the chemists, who dream only of retorts, must have taken for fermentation. This fever produces a greater filtration of spirits, which mechanically animate the muscles and the heart, as if they had been sent there by order of the will. |
それゆえ、宇宙の重みは本物
の無神論者を押しつぶすどころか、揺さぶることさえない。何千回、何万回と繰り返されてきた創造主の証拠や、われわれのような人間の理解をはるかに超えた
ところにある証拠はすべて、反ピュロン派の人々や、ある現象に基づいて判断することができると信じられるほど自分の理性に自信を持っている人々にとっての
み、(どんなに議論を押し進めようとも)自明なのである。自然主義者の話をもう一度聞けば、化学者の手によって、偶然の組み合わせによって最初の鏡が作ら
れた原因が、自然の手によって、素朴な羊飼いの鏡である純水を作ったのだと言うだろう;
世界を動かしている運動が世界を創り出したのであり、それぞれの天体が、その天性によって割り当てられた場所を占めているのであり、空気が地球を取り囲ん
でいるのであり、鉄や他の金属が地球の内部運動によって生み出されるのも、同じ理由によるのであり、太陽は電気と同じように自然の産物であり、太陽が地球
とその住民を暖めるために創られたのではないのだ;
鏡も水も、同じ性質を持つ他のすべての磨かれた物体と同じように、人が自分の姿を見るために作られたのではないこと;
しかし、この器官が本当にこの観想のために特別に作られ、意図的にそのソケットに置かれたとは証明されていない、
つまり、ルクレティウス、医師ラミー、そして古今東西のエピクロス主義者たちが、眼が見えるのは眼がそのように形成され、配置されているからにほかならな
い。 これが賛否両論であり、哲学者たちを永遠に分裂させるであろう立派な議論の要約である。私はどちらの側にもつかない。 Non nostrum inter vos tantas compenere lites. これは私の友人の一人で、私と同じくらい率直なピュロン派のフランス人に言った言葉である。彼はこの件に関して非常に奇妙な答えを返してきた。彼は私に 言った、「賛否両論が哲学者の魂を揺さぶることはない。しかし、無神論的でない限り、宇宙は決して幸福にはならない」と彼は続けた。この哀れな男の理由は こうだ。無神論が一般に受け入れられれば、あらゆる宗教は根こそぎ破壊される。神学戦争も、宗教の兵士も、そんな恐ろしい兵士もいなくなる!神聖な毒に侵 された自然は、その権利と純粋さを取り戻すだろう。他のすべての声に耳を貸さず、平穏な人間は、自分自身の存在の自発的な命令に従うだろう。 これを厳格に守る者は善人であり、全人類の信頼に値する。これを厳格に守らない者は、他の宗教の見せかけの外見にうつつを抜かしている。 この後、うぬぼれの強い人々に、そうでないことを考えさせ、啓示を信じないことには高潔ささえも危うい、つまり、それが何であれ、自然の宗教とは別の宗教 が必要だと断言させる。このような主張は、惨めで哀れなものである。また、各自が受け入れている宗教について私たちに与える好意的な意見も同様である!私 たちはここで、群衆の票を求めるのではない。迷信の祭壇を心に掲げる者は、偶像を崇拝することになり、美徳に心をときめかせることはない。 しかし、魂のすべての能力は、脳と全身の適切な組織に依存し、見かけ上はこの組織そのものにすぎないのだから、魂は明らかに啓蒙された機械である。最後 に、たとえ人間だけが自然法則の分け前を得たとしても、そのために機械であることに変わりはないだろうか。最も完全な動物よりも車輪やバネが少し多かった り、脳が心臓に比例して近かったり、そのために血液が多かったり......未知の原因がいくつもあれば、傷つきやすいデリケートな良心や、物質にとって は思考と同じくらい異質なものである自責の念、そして一言で言えば、ここに存在すると考えられているすべての違いが常に生まれるかもしれない。では、有機 体だけですべてが足りるのだろうか?思考は器官とともに目に見える形で発達するのだから、器官を構成する物質もまた、時とともに感じる能力を獲得すれば、 自責の念に駆られるはずではないか。 それゆえ、魂とは、誰も思いつかないような空虚な言葉に過ぎず、悟りを開いた人間なら、私たちの中の思考する部分を意味する言葉として使うに過ぎない。少 なくとも運動原理があれば、生体を動かすために必要なもの、感じるために必要なもの、考えるために必要なもの、悔い改めるために必要なもの、一言で言え ば、肉体的な領域や、それに依存する道徳的な領域で自らを律するために必要なものはすべて備わっている。 まだすべての困難が取り除かれていないと考えている人たちは、これから、彼らを完全に満足させる実験を読むことになるだろう。 すべての動物の肉は死後、動悸がする。この動悸は、冷血で汗をかかない動物ほど長く続く。カメ、トカゲ、ヘビなどがその証拠である。 体から離れた筋肉は刺激を受けると収縮する。 腸は蠕動運動を長時間続ける。 カウパーによれば、お湯を注入するだけで心臓と筋肉が生き返る。 カエルの心臓は体内から取り出された後も1時間以上動き続け、特に日光に当てたり、熱いテーブルや椅子の上に置いたりすると、さらによくなる。この動きが 完全に失われたように見えても、心臓を刺激するだけで、その空洞の筋肉は再び鼓動する。ハーヴェイはこれと同じ観察をヒキガエルについても行っている。 ヴェルラムのベーコンは、その論文『シルヴァ・シルヴァラム』の中で、反逆罪で有罪判決を受けた男が生きたまま開腹され、熱湯に投げ入れられた心臓が数回跳ね上がり、そのたびに高さが低くなり、2フィートの高さまで垂直になった例を挙げている。 卵の中にいる小さなニワトリを取り出し、心臓を切り取ると、ほとんど同じ条件下で、前と同じ現象が観察される。呼吸の温かさだけで、空気ポンプの中で死にかけた動物が生き返るのだ。 ボイルとステノンに負うところが大きいが、同じ実験がハト、イヌ、ウサギでも行われている。心臓の一部が心臓全体と同じように鼓動する。モグラから切り落とされた前足にも同じ動きが見られる。 イモムシ、ミミズ、クモ、ハエ、ウナギ--すべて同じ現象が見られる。お湯の中では、火を含んでいるため、切り離された部分の動きが大きくなる。 酔っぱらった兵士が、サーベルの一撃でインディアンの雄鶏の首を切り落とした。その雄鶏は立ったまま、歩き、走った。壁にぶつかり、向きを変え、まだ走り ながら羽を打ち、ついに倒れた。地面に横たわっている間、この雄鶏のすべての筋肉が動き続けていた。これとほとんど同じ現象は、頭を切り落とされた子猫や 子犬でも簡単に観察できる。 ポリープは切り刻まれた後、動くだけではない。一週間もすれば再生し、切り刻まれた破片の数だけ動物が形成されるのだ。この発見は、たとえすべての既知の(そして最も決定的な)実験に基づいても、決して一般的な結論に達しないことを教えてくれるからだ。 ここには、組織化された身体のそれぞれの小さな繊維や部分が、その身体に属する原理によって動くということを、疑いようのない方法で証明するために必要な 以上の多くの事実がある。その活動は、随意運動とは異なり、神経には一切依存していない。しかし、この力が繊維の断面にさえ現れるのであれば、特殊につな がった繊維の複合体である心臓も、同じ性質を持っているに違いない。このことを説得するのにベーコンの話は必要なかった。人間の心臓と動物の心臓の構造が 完璧に類似していることからも、また人間の心臓の大きさからも、私がこの結論に達するのは簡単だった。処刑された犯罪者の体がまだ温かいうちに解剖すれ ば、斬首された人の顔の筋肉に観察されるのと同じ動きが、おそらく彼らの心臓にも見られるはずだ。 体全体、そして切り刻まれた部分でさえも、その運動原理は、温血動物や完全な動物にも、冷血動物や不完全な動物にも、一部の人が考えているような不規則な 動きではなく、非常に規則正しい動きを生み出すのである。したがって、敵対者には、誰もが容易に検証できる何千何万もの事実を否定する以外に道は残されて いない。 もし今、この生得的な力は私たちの身体のどこにあるのかと尋ねる人がいれば、私は、それは古代人が柔組織と呼んだもの、つまり、静脈、動脈、神経を含まな い器官の物質そのものに、つまり、全身の組織に存在し、その結果、各器官は、その必要性に応じて、多かれ少なかれ活動する力を自らの中に含んでいる、と はっきりと答える。 では、人間機械のこれらのバネについて、もう少し詳しく説明しよう。生命運動、動物運動、自然運動、自動運動はすべて、このバネの働きによって行われる。 予期せぬ断崖絶壁を目にして恐怖に襲われたとき、身体が縮こまるのも、打撃の威嚇にまぶたが下がるのも、ある人が指摘するように、純粋に機械的な方法によ るものではないだろうか。冬に皮膚の気孔が閉じて寒さが血管の内部まで伝わらないようにするのも、胃が毒や一定量のアヘンやあらゆる嘔吐薬などで刺激され ると嘔吐するのも、機械的な手段によるのではないだろうか?心臓や動脈や筋肉が睡眠中にも起きているときと同じように収縮するのも、肺が運動中に絶えずふ いごの役割を果たすのも、血管や直腸などの括約筋を機械的に動かすためではないだろうか? 心臓が他のどの筋肉よりも強く収縮することを? que les muscles érecteurs font dresser la verge dans l'homme des les animaux qui s'en battent le ventre, et même dans l'enfant, capable d'érection, pour peu que cette partie soit irritée? このことは、解剖学のあらゆる照明にもかかわらず、まだあまり知られていない、この臓器に特異な病変があること、そしてその病変が、まだはっきりと説明さ れていないことを物語っている。 誰もが知っているこのような小さな従属的な力については、これ以上詳しく説明しない。脳には、脚には歩くための筋肉があるように、考えるための筋肉があ る。私が話したいのは、ヒポクラテスが「魂」と呼ぶこの衝動的な原理についてである。この原理は、神経の起点である脳に存在し、その座を占めている。この 事実によって、想像力の病気がもたらす驚くべき影響に至るまで、説明できることはすべて説明できる。 しかし、その豊かさと理解されにくい病態に溺れないためには、ちょっとした疑問や反省に耳を傾ける必要がある。 なぜ、美しい女性の姿や単純なイメージが、特別な動きや願望を引き起こすのか?ある臓器で起こっていることは、その臓器の性質に起因しているのだろうか? その筋肉と想像力との交感神経の関係からきているのです。古代の恩恵、あるいは美のイメージによって興奮する第一の感情があり、それがまた別の感情を興奮 させる: また、それが、甚だしい速さで飛び出し、洞窟のような肉体を揺り動かすような、魂と精神の破壊と激動によるものでないとしたら、どうだろう。 母と子の間に明白な共通点があり、トゥルピウスや他の著名な作家が報告した公正な評価(これ以上のものはない)に耳を傾けることが必要であることから、私 たちは、胎児が母性的な想像力の非凡さを、溶けた氷のように受け取るのは、同じ方法によるのだと考える; そして、同じような痕跡、すなわち母親の羨望が胎児に刻み込まれるのであるが、ブロンデルやその仲間たちが言うように、そのことは理解できない。我々は P. マレブランシュは、自然を観察することなく、自分たちの思想を実現することを望んだ作家たちによって、その真価を大きく揺るがされている。 有名なポープの肖像画を見てください。彼は控えめに言っても、イギリス人のヴォルテールです。彼の天才の努力とエネルギーがその表情に刻み込まれている。 痙攣している。目は眼窩からはみ出し、眉は額の筋肉と一緒に盛り上がっている。なぜか?なぜなら、脳は苦難の中にあり、体全体がそのような苦難の解放を分 かち合わなければならないからだ。もし外的なものを引っ張る内的な紐がなかったら、これらの現象はいったいどこから来るのだろうか?それらの説明として魂 を認めるということは、聖霊の働きによって現象を説明することになる。 実際、もし私の脳で考えていることが、この器官の一部ではなく、したがって身体全体の一部でもないとしたら、ベッドに静かに横たわりながら、何かの仕事の 計画を立てたり、抽象的な計算をしたりしているときに、なぜ私の血液は沸騰し、心の熱が静脈に流れるのだろうか?この問いを、想像力の豊かな人たち、偉大 な詩人たち、情緒の巧みな表現にうっとりし、絶妙な空想や自然、真理、美徳の魅力に心を奪われている人たちにぶつけてみよう!単なる解剖学者であったボ レッリが、ライプニッツ派の誰よりもよく理解していた調和によって、人間の物質的な統一性を理解することができる。要するに、痛みを引き起こす神経の緊張 が、熱を引き起こし、それによって注意散漫になった心が意志力を失うのであれば、また逆に、あまりにも興奮した心が身体をかき乱すのであれば(そして、ま だ若かったバユルを殺したあの内なる炎を燃え上がらせるのであれば)l、興奮が私の欲望を奮い立たせ、ついさっきまで何とも思っていなかったことに熱烈な 願いを抱かせるのであれば、また、ある種の脳の印象が同じあこがれや同じ欲望を奮い立たせるのであれば、明らかに一つの存在であるものを、どうして二重の ものと見なす必要があるのだろうか。意志が与える一つの命令に対して、身体はその軛に百回屈服するのだから。健康な状態であれば、血液の奔流と動物霊の奔 流が身体を従わせ、意志は目に見えない流体の軍団を従者として従え、稲妻よりも速く、常に意志の命令に従う準備ができているのだから!しかし、意志の力は 神経によって行使されるので、神経によって制限される。虜にされた恋人の最も優れた意志は、より暴力的な欲望によって、その意志の力を削がれてしまうの か?というのも、ある状況に置かれたとき、il n'est pas dans sa puissance de ne pas voul du pleasure. 麻痺などについて私が言ったことが今ここに蘇る。 黄疸の結果に驚きますか?身体の色は、それを見る眼鏡の色に左右されること、そして、体液の色が何であれ、少なくとも我々にとっては、物体の色もまた、千 の幻想の虚しい玩具であることを知らないのか?しかし、目の房水からこの色を取り除き、胆汁を自然なフィルターを通して流せば、新しい目を持った魂はもは や黄色を見ることはない。白内障を取り除いたり、耳管に注射したりすることで、目の見えない人に視力が、耳の聞こえない人に聴力が回復するのではないだろ うか。暗黒の時代には、賢い詐欺師に過ぎなかったかもしれない人々が、どれほど奇跡を起こすと思われていたことだろう!魂は美しく、意志は力強く、肉体の 条件の許可なしには行動できず、その嗜好は年齢や熱によって変化する!では、哲学者たちが魂の健康を維持するために、常に肉体の健康を念頭に置いてきたこ と、ピタゴラスがプラトンにワインを禁じたのと同じくらい慎重に食事の規則を与えたことに、私たちは驚かなければならないのだろうか?まともな医師は、心 を形成し、真理と美徳の知識を教えようとするとき、肉体に適した体制から始めなければならないと考えるものである。エピクテトスも、ソクラテスも、プラト ンも、その他の人々も、衛生の戒律がなければ、無駄な説教をすることになる。 ヒポクラテスの "enormon "という言葉で説明されるような情念の議論になぜ没頭するのか)人間は動物にすぎず、この人間の輪のどの地点から自然が始まったかを知ることもできず、ま た知ることもできない、互いに巻き上げ合う泉の集まりにすぎないことを証明するために、もっと多くのことが必要だろうか。もしこれらのバネがそれ自身の間 で異なるとすれば、その違いは位置と強さの度合いにおいてのみであり、決してその性質においてではない。それゆえ、魂は運動の原理、あるいは脳の物質的で 感覚的な部分に過ぎず、誤りの恐れなしに、機械全体のゼンマイとみなすことができ、すべての部分に目に見える影響を及ぼす。魂は脳のために作られたように さえ見え、システムの他のすべての部分は、脳からの一種の発露にすぎない。このことは、これから列挙するさまざまな胚についての観察から明らかになるだろ う。 この振動は、われわれの機械にとって自然なもの、あるいは適したものであり、いわば振り子の振動のように、各繊維、さらには各繊維要素に備わっているよう に思われるが、永遠に維持し続けることはできない。力を失えば更新し、疲れたら活性化させ、過剰な力や活力によって乱されれば弱めなければならない。これ こそが真の医療である。 身体は時計であり、その時計師は新しい胆汁である。胆汁が血液に入るとき、自然が最初に行うことは、化学者がレトルトの夢ばかり見ているような一種の熱を 胆汁に起こさせ、発酵させることである。この熱は霊の濾過を促進し、あたかも意志によって送り込まれたかのように、機械的に筋肉と心臓を動かす。 |
| These
then are the causes or forces of life which thus sustain for a hundred
years that perpetual movement of the solids and liquids which is as
necessary to the first as to the second. But who can say whether the
solids contribute more than the fluids to this movement or vice versa?
All that we know is that the action of the former would soon cease
without the help of the latter, that is, without the help of the fluids
which by their onset rouse and maintain the elasticity of the blood
vessels on which their own circulation depends. From this it follows
that after death the natural resilience of each substance is still more
or less strong according to the remnants of life which it outlives,
being the last to perish. So true is it that this force of the animal
parts can be preserved and strengthened by that of the circulation, but
that it does not depend on the strength of the circulation, since, as
we have seen, it can dispense with even the integrity of each member or
organ. I am aware that this opinion has not been relished by all scholars, and that Stahl especially had much scorn for it. This great chemist had wished to persuade us that the soul is the sole cause of all our movements. But this is to speak as a fanatic and not as a philosopher. To destroy the hypothesis of Stahl, we need not make as great an effort as I find that others have done before me. We need only glance at a violinist. What flexibility, what lightness in his fingers! The movements are so quick, that it seems almost as if there were no succession. But I pray, or rather I challenge, the followers of Stahl who understand so perfectly all that our soul can do, to tell me how it could possibly execute so many motions so quickly, motions, moreover, which take place so far from the soul, and in so many different places. That is to suppose that a flute player could play brilliant cadences on an infinite number of holes that he could not know, and on which he could not even put his finger! But let us say with M. Hecquet that all men may not go to Corinth. Why should not Stahl have been even more favored by nature as a man than as a chemist and a practioner? Happy mortal, he must have received a soul different from the rest of mankind, --- a sovereign soul, which, not content with having some control over the voluntary muscles, easily held the reins of all the movements of the body, and could suspend them, calm them, or excite them at its pleasure! With so despotic a mistress, in whose hands were, in a sense, the beating of the heart, and the laws of circulation, there could certainly be no fever, no pain, no weariness, ni honteuse impuissance, ni facheux priapisme! The soul wills, and the springs play, contract or relax. But how did the springs of Stahl's machine get out of order so soon? He who has in himself so great a doctor, should be immortal. Moreover, Stahl is not the only one who has rejected the principle of the vibration of organic bodies. Greater minds have not used the principle when they wished to explain the actions of the heart, l'érection du penis, etc. One need only read the Institutions of Medicine by Boerhaave to see what laborious and enticing systems this great man was obliged to invent, by the labor of his mighty genius, through failure to admit that there is so wonderful a force in all bodies. Willis and Perrault, minds of a more feeble stamp, but careful observers of nature (whereas nature was known to the famous Leyden professor only through others and second hand, so to speak) seem to have preferred to suppose a soul generally extended over the whole body, instead of the principle which we are describing. But according to this hypothesis (which was the hypothesis of Vergil and of all Epicureans, an hypothesis which the history of the polyp might seem at first sight to favor) the movements which go on after the death of the subject in which they inhere are due to a remnant of soul still maintained by the parts that contract, though, from the moment of death, these are not excited by the blood and spirits. Whence it may be seen that these writers, whose solid works easily eclipse all philosophic fables, are deceived only in the manner of those who have endowed matter with the faculty of thinking. I mean to say, by having expressed themselves badly in obscure and meaningless terms. In truth, what is this remnant of a soul, if it is not the ``moving force'' of the Leibnizians (badly rendered by such an expression), which however Perrault in particular has really foreseen. See his Treatise on the Mechanism of Animals. Now that it is clearly proved against the Cartesians, the followers of Stahl, the Malebranchists, and the theologians who little deserve to be mentioned here, that matter is self-moved, not only when organized, as in a whole heart, for example, but even when this organization has been destroyed, human curiosity would like to discover how a body, by the fact that it is originally endowed with the breath of life, finds itself adorned in consequence with the faculty of feeling, and thus with that of thought. And, heavens, what efforts have not been made by certain philosophers to manage to prove this! and what nonsense of this subject I have had the patience to read! All that experience teaches us is that while movement persists, however slight it may be, in one or more fibres, we need only stimulate them to re-excite and animate this movement almost extinguished. This has been shown in the host of experiments with which I have undertaken to crush the systems. It is therefore certain that motion and feeling excite each other in turn, both in a whole body and in the same body when its structure is destroyed, to say nothing of certain plants which seem to exhibit the same phenomena of the union of feeling and motion. But furthermore, how many excellent philosophers have shown that thought is but a faculty of feeling, and that the reasonable soul is but the feeling soul engaged in contemplating its ideas and in reasoning! This would be proved by the fact alone that when feeling is stifled, thought also is checked, for instance in apoplexy, in lethargy, in catalepsis, etc. For it is ridiculous to suggest that, during these stupors, the soul keeps on thinking, even though it does not remember the ideas that it has had. As to the development of feeling and motion, it is absurd to waste time seeking for its mechanism. The nature of motion is as unknown to us as that of matter. How can we discover how it is produced unless, like the author of The History of the Soul, we resuscitate the old and unintelligible doctrine of substantial forms? I am then quite as content not to know how inert and simple matter becomes active and highly organized, as not to be able to look at the sun without red glasses; and I am as little disquieted concerning the other incomprehensible wonders of nature, the production of feeling and of thought in a being which earlier appeared to our limited eyes as a mere clod of clay. Grant only that organized matter is endowed with a principle of motion, which alone differentiates it from the inorganic (and can one deny this in the face of the most incontestable observation?) and that among animals, as I have sufficiently proved, everything depends upon the diversity of this organization: these admissions suffice for guessing the riddle of substances and of man. It thus appears that there is but one type of organization in the universe, and that man is the most perfect example. He is to the ape, and to the most intelligent animals, as the planetary pendulum of Huyghens is to a watch of Julien Leroy. More instruments, more wheels and more springs were necessary to mark the movements of the planets than to mark or strike the hours; and Vaucanson, who needed more skill for making his flute player than for making his duck, would have needed still more to make a talking man, a mechanism no longer to be regarded as impossible, especially in the hands of another Prometheus. In like fashion, it was necessary that nature should use more elaborate art in making and sustaining a machine which for a whole century could mark all motions of the heart and of the mind; for though one does not tell time by the pulse, it is at least the barometer of the warmth and the vivacity by which one may estimate the nature of the soul. I am right! The human body is a watch, a large watch constructed with such skill and ingenuity, that if the wheel which marks the second happens to stop, the minute wheel turns and keeps on going its round, and in the same way the quarter-hour wheel, and all the others go on running when the first wheels have stopped because rusty or, for any reason, out of order. Is it not for a similar reason that the stoppage of a few blood vessels is not enough to destroy or suspend the strength of the movement which is in the heart as in the mainspring of the machine; since, on the contrary, the fluids whose volume is diminished, having a shorter road to travel, cover the ground more quickly, borne on as by a fresh current which the energy of the heart increases in proportion to the resistance it encounters at the ends of the blood-vessels? And is not this the reason why the loss of sight (caused by the compression of the optic nerve and its ceasing to convey the images of objects) no more hinders hearing, than the loss of hearing (caused by the obstruction of the functions of the auditory nerve) implies the loss of sight? In the same way, finally, does not one man hear (except immediately after his attack) without being able to say what he hears, while another who hears nothing, but whose lingual nerves are uninjured in the brain, mechanically tells of all the dreams which pass through his mind? These phenomena do not surprise enlightened physicians at all. They know what to think about man's nature (and more accurately to express myself in passing) of two physicians, the better one and the one who deserves more confidence is always, in my opinion, the one who is more versed in the physique or mechanism of the human body, and who, leaving aside the soul and all the anxieties which this chimera gives to fools and to ignorant men, is seriously occupied only in pure naturalism. Therefore let the pretended M. Charp deride philosophers who have regarded animals as machines. How different is my view! I believe that Descartes would be a man in every way worthy of respect, if, born in a century that he had not been obliged to enlighten, he had known the value of experiment and observation, and the danger of cutting loose from them. But it is none the less just for me to make an authentic reparation to this great man for all the insignificant philosophers --- poor jesters, and poor imitators of Locke --- who instead of laughing impudently at Descartes, might better realize that without him the field of philosophy, like the field of science without Newton, might perhaps be still uncultivated. This celebrated philosopher, it is true, was much deceived, and no one denies that. But at any rate he understood animal nature, he was the first to prove completely that animals are pure machines. And after a discovery of this importance demanding so much sagacity, how can we without ingratitude fail to pardon all his errors! In my eyes, they are all atoned for by that great confession. For after all, although he extols the distinctness of the two substances, this is plainly but a trick of skill, a ruse of style, to make theologians swallow a poison, hidden in the shade of an analogy which strikes everybody else and which they alone fail to notice. For it is this, this strong analogy, which forces all scholars and wise judges to confess that these proud and vain beings, more distinguished by their pride than by the name of men however much they may wish to exalt themselves, are at bottom only animals and machines which, though upright, go on all fours. They all have this marvelous instinct, which is developed by education into mind, and which always has its seat in the brain (or for want of that when it is lacking or hardened, in the medulla oblongata) and never in the cerebellum; for I have often seen the cerebellum injured, and other observers have found it hardened, when the soul has not ceased to fulfil its functions. To be a machine, to feel, to think, to know how to distinguish good from bad, as well as blue from yellow, in a word, to be born with an intelligence and a sure moral instinct, and to be but an animal, are therefore characters which are no more contradictory, than to be an ape or a parrot and to be able to give oneself pleasure. Car, puisque l'occasion se présente de le dire, qui eut jamais deviné à priori qu'une goutte de la liqeur qui se lance dans l'accouplement fit ressentir des plaisirs divins, et qu'il en naîtrait une petite créature, qui pourrait un jour, posées certaines lois, jouir des même délices? I believe that thought is so little incompatible with organized matter, that it seems to be one of its properties on a par with electricity, the faculty of motion, impenetrability, extension, etc. Do you ask for further observations? Here are some which are incontestable and which all prove that man resembles animals perfectly, in his origin as well as in all the points in which we have thought it essential to make the comparison. J'en appale à la bonne foi de nos observateurs. Qu'ils nous disent s'il ne'st pas vrai que l'homme dans son principe n'est qu'un ver, qui devient homme, comme la chenille paillon. Les plus graves auteurs [Boerhaave, Inst. Med. et tant d'autres] nous ont appris comment il faut s'y prendre pour voir cet animalcule. Tous les curieux l'ont vu, comme Hartsoeker, dans la semence de l'homme, et non dans celle de la femme; il n'y a que le plus adroit, ou le plus vigoreux qui ait la force de s'insinuer et de s'implanter dans l'oeuf que fournit la femme, et qui lui donne sa première nourriture. Cet oeuf, quelquefois surpris dans les trompes de Fallope, est porté par ces canaux à la matrice, où il prend racine, comme un grain de blé dans la terre. Mais quoiqu'il y devienne monstru-eux par sa croissance de 9 mois, il ne diffère point des oeufs des autres femelles, si ce n'est que sa peau (l'amnios) ne se durcit jamais, et se dilate prodigeusement, comme on en peut juger en comparant les foetus trovés en situation et près d'éclore (ce que j'ai eu le plaisir d'observer dans une femme morte un moment avant l'accouchement), avec d'autres petits embryons très proches de leur origine: car alors c'est toujours l'oeuf dans sa coque, et l'animal dans l'oeuf, qui, gêné dans ses mouvements, cherche machinalement à voir le jour; et pour y réussir, il commence par rompre avec la tête cette membrance, d'oû il sort, comme le pulet, l'oiseau, etc., de la leur. J'ajouterai une observation que je ne trouve nulle part; c'est que l'amnios n'en est pas plus mince, pour s'être prodigieusement étendu; semblable en cela à la matrice dont la substance même se gonfle de sucs infiltrés, indépendamment de la réplétion et du déploiement de tous ses coudes vasculeux. |
こうして、前者にも後者にも
必要な、固体と液体の絶え間ない動きを100年間維持する生命の原因や力が生まれるのである。しかし、固体が液体よりもこの運動に寄与しているのか、それ
ともその逆なのか、誰にもわからない。我々が知っているのは、前者の作用は後者の助けなしには、つまり、それ自体の循環が依存する血管の弾力性を奮い立た
せ維持する体液の助けなしには、すぐに停止してしまうということだけである。このことから、死後も各物質の自然な弾力性は、その物質が最後に滅びる生命の
名残に応じて、多かれ少なかれまだ強いということになる。動物の部位のこの力は、循環の力によって維持され強化されうるが、循環の強さに依存するものでは
ない、というのはその通りである。 私は、この意見がすべての学者に受け入れられたわけではなく、特にシュタールがこの意見を酷評していたことを知っている。この偉大な化学者は、魂が私たち のすべての動きの唯一の原因であると私たちを説得したかったのだ。しかし、これは哲学者としてではなく、狂信者としての発言である。 シュタールの仮説を打ち砕くために、私より前に他の人たちがしてきたような大きな努力をする必要はない。あるヴァイオリニストを見ればいい。彼の指のなん と柔軟で、なんと軽やかなことか!動きはとても速く、まるで連続性がないかのようだ。しかし私は、魂にできることをすべて完璧に理解しているシュタールの 信奉者たちに、どうすればこれほど多くの運動をこれほど素早く行うことができるのか、しかもその運動は魂からこれほど遠く離れた場所で、これほど多くの異 なる場所で行われるのか、教えてほしいと祈る、いやむしろ挑戦する。それは、フルート奏者が、自分の知らない、指を置くことさえできない無限の穴の上で、 見事なカデンツを奏でることができると仮定することである! しかし、すべての人がコリントに行くとは限らないということを、M.ヘッケと一緒に考えてみよう。シュタールは、化学者であるよりも、研究者であるより も、一人の人間として、自然からより多くの恩恵を受けるべきだったのではないだろうか?その魂は、随意筋をいくらか支配することに満足することなく、身体 のあらゆる動きの手綱を容易に握り、その気の向くままに、動きを止めたり、静めたり、興奮させたりすることができる!このような専制的な女主人がいれば、 ある意味では心臓の鼓動も循環の法則も、その手に握られているのだから、熱も痛みも倦怠感も、名誉な衝動も、顔面性嗜癖も、確かに存在しえない!魂が意思 を持ち、バネが遊び、収縮し、弛緩する。しかし、シュタールの機械のバネは、どうしてこんなに早く狂ったのだろう?これほど偉大な医師を自らに持つ者は、 不死身であるはずだ。 さらに、有機体の振動の原理を否定したのはシュタールだけではない。もっと偉大な頭脳の持ち主は、心臓の働きや陰茎の勃起などを説明しようとしたとき、こ の原理を使わなかった。ボアハーヴェの『医学の体系』を読むだけで、この偉大な人物が、その強大な才能の労苦によって、すべての身体にこれほど素晴らしい 力が存在することを認めなかったために、どのような手間のかかる魅力的な体系を発明せざるを得なかったかを知ることができる。 ウィリスとペローは、もっと弱々しい頭脳の持ち主だったが、自然を注意深く観察していた(一方、有名なライデン教授にとっては、自然は他者を通じて、いわ ば二次的にしか知られていなかった)ので、われわれが説明しているような原理ではなく、魂が一般に身体全体に及んでいると仮定することを好んだようだ。し かし、この仮説(これはヴェルギルやすべてのエピクロス派の仮説であり、ポリープの歴史が一見有利に見える仮説である)によれば、魂が宿っている対象の死 後も続く運動は、収縮する部分によってまだ維持されている魂の残骸によるものである。このことから、哲学的な寓話を凌駕するような確かな著作を残している これらの作家たちは、物質に思考能力を与えた者たちのやり方でしか欺かれていないことがわかるだろう。つまり、曖昧で無意味な言葉で自分たちを悪く表現し ているのだ。実のところ、この魂の残骸がライプニッツ派の「動く力」(このような表現ではまずい)でないとすれば、それは何なのだろうか。ペローの『動物 のメカニズム論』を参照されたい。 デカルト派、シュタールの信奉者たち、マレブランチ主義者たち、そしてここで言及するにあまり値しない神学者たちに対して、物質が、たとえば心臓全体のよ うに組織化されているときだけでなく、この組織化が破壊されたときでさえも、自己運動していることが明確に証明された今、人間の好奇心は、身体がもともと 生命の息吹を与えられているという事実によって、その結果、どのようにして感情の能力、ひいては思考の能力で飾られるようになるのかを発見したいと思うだ ろう。そして天よ、これを何とか証明しようと、ある種の哲学者たちがどんな努力をしたことか! そして私はこのテーマについて、どんな無意味なことを読むのに忍耐を強いられたことか! 経験が教えてくれるのは、1本またはそれ以上の線維に、たとえわずかであっても運動が持続している間は、その線維を刺激するだけで、ほとんど消滅した運動 を再び励起し、活性化させることができるということだけである。このことは、私がこのシステムを解明するために行った数々の実験で証明されている。した がって、運動と感情が交互に興奮し合うことは、身体全体においても、構造が破壊された同じ身体においても確かなことである。 さらに、思考とは感情の一能力にすぎず、理性的な魂とは、思想を思索し、推論する感情的な魂にすぎないことを、どれほど多くの優れた哲学者が示してきたこ とだろう!このことは、例えば脳溢血や嗜眠、カタレプシスなど、感情が抑えられると思考も抑えられるという事実だけでも証明されるだろう。このような昏睡 状態の間にも、魂は思考を続けているというのは馬鹿げている。 感情や運動の発達に関しても、そのメカニズムを求めて時間を浪費するのは馬鹿げている。運動の性質は、物質の性質と同様、私たちには未知である。魂の歴 史』の著者のように、実質的な形態という古くて理解しがたい教義を復活させない限り、運動がどのように生じるかを発見できるわけがない。私は、不活性で単 純な物質が、どのようにして活動的で高度に組織化されるのかを知らなくても、赤い眼鏡なしで太陽を見ることができないのと同じように満足する。 組織化された物質には運動原理が備わっており、それだけが無機物と区別していること(そして、最も疑いようのない観察結果を前にして、これを否定すること ができるだろうか)、そして動物の間では、私が十分に証明したように、すべてはこの組織化の多様性に依存していること。こうして、宇宙には一つのタイプの 組織しか存在せず、人間がその最も完全な例であることが明らかになった。彼は猿や、最も知的な動物にとって、ホイヘンスの振り子がジュリアン・ルロワの時 計にとってそうであるように。ヴォーカンソンは、フルート奏者を作るのに、アヒルを作るよりも多くの技術を必要としたが、しゃべる人間を作るには、さらに 多くの技術を必要としただろう。同じように、100年もの間、心と精神のすべての動きを記録することができる機械を作り、維持するためには、自然はより精 巧な技術を用いる必要があった。私は正しい!人間の身体は時計であり、巧みな技術と工夫によって作られた大きな時計である。それどころか、体積が減少した 体液は、より短い道程で、心臓のエネルギーが血管の端で受ける抵抗に比例して増大する新鮮な流れに運ばれて、より速く地面を覆うからである。視神経が圧迫 され、物体の像を伝えなくなることによって起こる)視力の喪失が、(聴神経の機能が阻害されることによって起こる)聴力の喪失が視力の喪失を意味するのと 同じように、(視神経が圧迫され、物体の像を伝えなくなることによって起こる)聴力の喪失が聴力の妨げにならないのは、このためではないだろうか。同じよ うに、ある人は(発作の直後を除いて)何を聞いたか言うことができないのに、別の人は何も聞こえないのに、舌神経が脳内で損傷を受けていないにもかかわら ず、頭の中をよぎるすべての夢を機械的に語るのではないだろうか?このような現象は、賢明な医師たちをまったく驚かせない。二人の医師のうち、より優れた 医師、より信頼に値する医師は、常に人体の構造や機構に精通し、魂や、このキメラが愚か者や無知な人間に与えるあらゆる不安はさておき、純粋な自然主義に のみ真剣に取り組んでいる医師である、と私は思う。 だから、動物を機械とみなす哲学者たちを、M.シャルプ気取りが嘲笑する。私の見解はいかに異なるか!もしデカルトが、啓蒙する必要のなかった世紀に生ま れ、実験と観察の価値と、それらから切り離されることの危険性を知っていたならば、デカルトはあらゆる点で尊敬に値する人物であっただろうと私は信じてい る。しかし、デカルトを不謹慎に笑うのではなく、彼がいなければ、ニュートンのいない科学の分野と同じように、哲学の分野も未開のままであったかもしれな いことをもっとよく理解したほうがいい。 この高名な哲学者が多くの欺瞞に満ちていたことは事実であり、それを否定する者はいない。しかし、とにかく彼は動物の性質を理解し、動物が純粋な機械であることを初めて完全に証明した。そして、これほど重要な発見をしたのだから、これほど賢明であるべきだ! 私の目には、その偉大な告白によって、すべての誤りが償われたと映る。というのも、結局のところ、彼は二つの物質が別個のものであることを賞賛している が、これは明らかに、神学者たちに毒を飲ませるための巧みな策略にすぎないからである。というのも、この強力な類比こそ、すべての学者や賢明な判断者たち に、高慢でうぬぼれの強い存在であり、どんなに自分を誇示したくても、人間という名前よりもその誇りによって区別される存在であり、その本質は、直立はし ても四つん這いになる動物や機械にすぎないことを告白させるからである。この本能は、教育によって心へと発達し、常に脳(脳が欠けていたり硬化している場 合は延髄)にその座を置き、決して小脳には存在しない。 機械であること、感じること、考えること、善と悪を区別すること、青と黄色を区別することを知ること、つまり、知性と確かな道徳的本能をもって生まれなが ら、動物にすぎないということは、猿やオウムでありながら自分に喜びを与えることができるということ以上に、矛盾する性格ではない。 私は、思考は組織化された物質とはほとんど相容れないものであり、電気、運動能力、不可侵性、伸展性などと同列の性質のひとつであると考える。 これ以上の観察が必要だろうか?ここに挙げるものは議論の余地のないものであり、人間が動物に完全に似ていることを証明するものである。 私は、我々の観察者たちのある確信を申し上げる。Qu'ils nous disent s'il ne'st pas vrai que l'homme dans son principe n'est qu'un ver, qui devient homme, comme la chenille paillon. この動物を観察するために、私たちは、このような行動をとる必要があることを、最も偉大な研究者たち [Boerhaave, Inst. Med. et tant d'others]は述べている。そのような動物が、そのような動物が、そのような動物が、そのような動物が、そのような動物が、そのような動物であるこ とを、我々は知っている。この卵は、ファロープのトロンボーンに驚かされるやいなや、この水路を通ってマトリーチェに運ばれ、まるで土の中の一粒の泥のよ うに、その上に置かれる。しかし、9ヶ月の成長によって怪物になったとはいえ、他の女性の卵と何ら違いはない、 これは、出産前に死亡した女性から観察することができた幸運なことである: このように、常に、卵は卵の中にあり、動物は卵の中にあり、その動きは、生気に満ち、機械的にその日を迎えようとしている。 , de la leur. J'ajouterai une observation que je ne trouve nulle part; c'est que l'amnios n'en est pas plus mince, pour s'être prodigieusement étendu; semblable en cela à la matrice dont la substance même se gonfle de sucs infiltrés, indépendamment de la réplétion et du déploiement de tous s coudes vasculeux. |
| Let
us observe man both in and out of his shell, let us examine young
embryos of four, six, eight or fifteen days with a microscope; after
that time our eyes are sufficient. What do we see? The head alone; a
little round egg with two black points which mark the eyes. Before
that, everything is formless, and one sees only a medullary pulp, which
is the brain, in which are formed first the roots of the nerves, that
is, the principle of feeling, and the heart, which already within this
substance has the power of beating of itself; it is the punctum saliens
of Malpighi, which perhaps already owes a part of its excitability to
the influence of the nerves. Then little by little, one sees the head
lengthen from the neck, which, in dilating, forms first the thorax
inside which the heart has already sunk, there to become stationary;
below that is the abdomen which is divided by a partition (the
diaphragm). One of these enlargements of the body forms the arms, the
hands, the fingers, the nails, and the hair; the other forms the
thighs, the legs, the feet, etc., which differ only in their observed
situation, and which constitute the support and the balancing pole of
the body. The whole process is a strange sort of growth, like that of
plants. On the tops of our heads is hair in place of which the plants
have leaves and flowers; everywhere is shown the same luxury of nature,
and finally the directing principle of plants is placed where we have
our soul, that other quintessence of man. Such is the uniformity of nature, which we are beginning to realize; and the analogy of the animal with the vegetable kingdom, of man with the plant. Perhaps there even are animal plants, which in vegetating, either fight as polyps do, or perform other functions characteristic of animals. Voilà à peu près tout ce qu'on sait de la génération. Que les parties qui s'attirent, qui sont faites pur s'unir ensemble et pour occuper telle ou telle place, se réunissent toutes suivant leur nature; et qu'ainsi se forment les yeux, le coeur, l'estomac et enfin tout le corps, comme de grans hommes l'ont écrit, cela est possible. Mais, comme l'expérience nous abandonne au milieu des ces subtilités, je ne supposerai rien, regardant tout ce qui ne frappe pas mes sens comme un mystère impénetrable. Il est si rare que les deux emences se rencontrent dans le congrès, que je serais tenté de croire que la semence de la femme est inutile à la génération. Mais comment en expliquer les phénomènes, sans ce commode rapport de parties, qui rend si bien raison des ressemblances des enfants, tantôt au père, et tantôt à la mère? D'un autre côté, l'embarras d'une explication doit-elle contrebalancer un fait? Il me parait que c'est le mâle qui fait tout, dans une femme qui dorrt, comme dans la plus lubrique. L'arrangement des parties serait done fait de toute éternité dans le germe, ou dans le ver même de l'homme. Mais tout ceci est fourt au-dessus de la portée des plus excellents observateurs. Comme ils n'y peuvent rien saisir, ils ne peuvent pas plus juger de la mécanique de la formation et du développment des corps, qu'une taupe du chemin qu'un cerf peut parcourir. We are veritable moles in the field of nature; we achieve little more than the mole's journey and it si our pride which prescribes limits to the limitless. We are in the position of a watch that should say (a writer of fables would make the watch a hero in a silly tale): ``I was never made by that fool of a workman, I who divide time, who mark so exactly the course of the sun, who repeat aloud the hours which I mark! No! that is impossible!'' In the same way, we disdain, ungrateful wretches that we are, this common mother of all kingdoms, as the chemists say. We imagine, or rather we infer, a cause superior to that which we owe all, and which truly has wrought all things in an inconceivable fashion. No; matter contains nothing base, except to the vulgar eyes which do not recognize her in her most splendid works; and nature is no stupid workman. She creates millions of men, with a facility and a pleasure more intense than the effort of a watchmaker in making the most complicated watch. Her power shines forth equally in creating the lowliest insect and in creating the most highly developed man; the animal kingdom costs her no more than the vegetable, and the most splendid genius no more than a blade of wheat. Let us then judge by what we see of that which is hidden from the curiosity of our eyes and of our investigations, and let us not imagine anything beyond. Let us observe the ape, the beaver, the elephant, etc., in their operations. If it is clear that these activities cannot be performed without intelligence, why refuse intelligence to these animals? And if you grant them a soul our are lost, you fanatics! You will in vain say that you assert nothing about the nature of the animal soul and that you deny its immortality. Who does not see that this is a gratuitous assertion; who does not see that the soul of an animal must be either mortal or immortal, whichever ours is, and that it must therefore undergo the same fate as ours, whatever that may be, and that thus in admitting that animals have souls, you fall into Scylla in an effort to avoid Charybdis? Break the chain of your prejudices, arm yourselves with the torch of experience, and you will render nature the honor she deserves, instead of inferring anything to her disadvantage, from the ignorance in which she has left you. Only open wide your eyes, only disregard what you cannot understand, and you will see that the ploughman whose intelligence and ideas extend no further than the bounds of his furrow, does not differ essentially from the greatest genius, --- a truth which the dissection of Descartes's and of Newton's brains would have proved; you will be persuaded that the imbecile and the fool are animals with human faces, as the intelligent ape is a little man in another shape; in short, you will learn that since everything depends absolutely on difference of organization , a well constructed animal which has studied astronomy, can predict an eclipse, as it can predict recovery or death when it has used its genius and its clearness of vision, for a time, in the school of Hippocrates and at the bedside of the sick. By this line of observations and truths, we come to connect the admirable power of thought with matter, without being able to see the links, because the subject of this attribute is essentially unknown to us. Let us not say that every machine or every animal perishes altogether or assumes another form after death, for we know absolutely nothing about the subject. On the other hand, to assert that an immortal machine is a chimera or a logical fiction, is to reason as absurdly as caterpillars would reason if, seeing the cast-off skins of their fellow caterpillars, they should bitterly deplore the fate of their species, which to them would seem to come to nothing. The soul of these insects (for each animal has its own) is too limited to comprehend the metamorphoses of nature. Never one of the most skillful among them could have imagined that it was destined to become a butterfly. It is the same way with us. What more do we know of our destiny than of our origin? Let us then submit to an invincible ignorance on which our happiness depends. He who so thinks will be wise, just, tranquil about his fate, and therefore happy. He will await death without either fear or desire, and will cherish life (hardly understanding how disgust can corrupt a heart in this place of many delights); he will be filled with reverence, gratitude, affection, and tenderness for nature, in proportion to his feeling of the benefits he has received from nature; he will be happy, in short, in feeling nature, and in being present at the enchanting spectacle of the universe, and we will surely never destroy nature either in himself or in others. More than that! Full of humanity, this man will love human character even in his enemies. Judge how he will treat others. He will pity the wicked without hating them; in his eyes, they will be but mis-made men. But in pardoning the faults of the structure of mind and body, he will none the less admire the beauties and the virtues of both. Those whom nature shall have favored will seem to him to deserve more respect than those whom she has treated in step-motherly fashion. Thus, as we have seen, natural gifts, the source of all acquirements, gain from the lips and heart of the materialist, the homage which every other thinker unjustly refuses them. In short, the materialist, convinced, in spite of the protests of his vanity, that is he but a machine or an animal, will not maltreat his kind, for he will know too well the nature of those actions, whose humanity is always in proportion to the degree of analogy proved above [between human beings and animals]; and following the natural law given to all animals, he will not wish to do to others what he would not wish them to do to him. Let us then conclude boldly that man is a machine, and that in the whole universe there is but a single substance differently modified. This is no hypothesis set forth by dint of a number of postulates and assumptions; it is not the work of prejudice, nor even of my reason alone; I should have disdained a guide which I think to be so untrustworthy, had not my senses, bearing a torch, so to speak, induced me to follow reason by lighting the way themselves. Experience has thus spoken to me in behalf of reason; and in this way I have combined the two. But it must have been noticed that I have not allowed myself even the most vigorous and immediately deduced reasoning, except as a result of a multitude of observations which no scholar will contest; and furthermore, I recognize only scholars as judges of the conclusions which I draw from the observations; and I hereby challenge every prejudiced man who is neither anatomist, nor acquainted with the only philosophy which can here be considered, that of the human body. Against so strong and solid an oak, what could the weak reeds of theology, of metaphysics, and of the schools, avail, ---- childish arms, like our parlor foils, that may well afford the pleasure of fencing, but can never wound an adversary. Need I say that I refer to the empty and trivial notions, to the pitiable and trite arguments that will be urged (as long as the shadow of prejudice or of superstition remains on earth for the suppose incompatibility of two substances which meet and move each other unceasingly? Such is my system, or rather the truth, unless I am much deceived. It is short and simple. Dispute it now who will. |
人間を殻の中と外の両方で観
察し、4日、6日、8日、15日の若い胚を顕微鏡で調べてみよう。何が見えるだろうか?小さな丸い卵に、目を示す2つの黒い点がある。その前に、すべては
形がなく、脳である髄質が見えるだけである。脳にはまず神経の根、つまり感覚の原理が形成され、心臓がある。それから少しずつ、頭部が頸部から長くなって
いくのがわかる。頸部は拡張し、まず胸郭を形成し、その中に心臓がすでに沈んでいて、そこで静止している。胴体のこれらの肥大のひとつが腕、手、指、爪、
髪を形成し、もうひとつが大腿部、脚、足などを形成する。この過程はすべて、植物の成長のような奇妙なものである。私たちの頭頂部には髪の毛があり、その
代わりに植物には葉や花がある。いたるところに同じような自然の贅肉が見られ、最後には、私たちの魂、つまり人間のもうひとつの真髄がある場所に、植物の
指示原理が配置される。 動物界と植物界、人間界と植物界の類似性。おそらく動物性植物も存在し、それらは植生する際に、ポリプのように闘ったり、動物に特徴的な他の機能を発揮したりするのだろう。 このように、「生殖」についてはあらゆることが分かっている。そして、その結果、眼球、心臓、消化器官、そして最終的には体全体が形成されるのである。し かし、このような神秘的な状況の中で、私たちが経験することを放棄しているように、私は何も仮定せず、私の感覚を揺さぶらないものをすべて不可解な神秘と みなしている。この2つの感情が会議で交わることは非常にまれであり、私は女性の存在が世代にとって無意味であることを知ることになる。 しかし、そのような関係性を説明するのはどうだろうか?もう一つの点として、説明の難しさは、ある事実を覆すものなのだろうか?私は、"淑やかな女性 "のように、"淑やかな女性 "のように、"淑やかな女性 "のように、"淑やかな女性 "がすべてを決めると思う。当事者の配置は、生殖器、あるいは人間の真の姿の中で、まったく永遠に行われるものである。しかし、このようなことは、優れた 観察者たちの手から離れたところにある。体躯の形成と発育のメカニズムについては、羊の一匹が歩ける道程を歩くのと同じように、何も知ることができず、そ れ以上に判断することもできない。 私たちは自然のフィールドではまさにモグラであり、モグラの旅以上のことはほとんど成し遂げられない。私たちは、寓話作家なら、時計を愚かな物語の主人公 にするような腕時計のような立場にある: 私はあの愚かな職人によって作られたのではない、私は時間を分割し、太陽の進路を正確に刻み、私が刻む時間を声に出して繰り返すのだ!そんなことは不可能 だ!」。同じように、私たちは、化学者が言うように、このすべての王国の共通の母を、恩知らずの哀れな人間だと軽蔑している。われわれは、われわれがすべ てを負い、真に想像を絶する方法で万物を生み出した原因よりも上位の原因を想像し、いや、むしろ推論する。いや、物質には卑俗なものは何も含まれていな い。そして、自然は決して愚かな仕事師ではない。彼女は何百万人もの人間を、時計職人が最も複雑な時計を作るのに要する労力よりも強烈な能力と喜びをもっ て創造する。その力は、最も下等な昆虫を創造する際にも、最も高度に発達した人間を創造する際にも、等しく輝いている。動物界は植物界よりも、最も素晴ら しい天才は一本の麦の葉よりも高くはない。それでは、私たちの目や調査の好奇心から隠されているものについて、目に見えるものだけで判断し、それ以上のも のを想像しないようにしよう。類人猿、ビーバー、ゾウなどの活動を観察してみよう。これらの活動が知性なしには行えないことが明らかであるならば、なぜこ れらの動物に知性を拒むのか。そして、もし彼らに魂を認めるなら、われわれは迷うことになる、狂信者たちよ!動物の魂の性質については何も主張せず、その 不滅性を否定している、と言っても無駄だろう。動物の魂は死すべきものであるか、不滅のものであるかのどちらかに違いなく、したがって、それが何であれ、 われわれと同じ運命をたどるに違いないのだ。 偏見の鎖を断ち切り、経験という松明で武装すれば、自然があなた方に残した無知から不利なことを推測するのではなく、自然にふさわしい名誉を与えることが できる。目を大きく見開き、理解できないことは無視すればよい。そうすれば、耕作者の知性と発想は、その耕作の埒外には及ばないが、最も偉大な天才と本質 的な違いはないことがわかるだろう; 要するに、すべては組織の違いに絶対的に依存しているのだから、天文学を学んだことのあるよくできた動物なら、日食を予知することができるのである。この ような観察と真理の積み重ねによって、われわれは思考という素晴らしい力を物質と結びつけることができる。 なぜなら、この属性の主体は本質的に私たちにはわからないからである。あらゆる機械やあらゆる動物が、死後完全に消滅したり、別の形態になったりするとは 言わないことにしよう。一方、不滅の機械がキメラや論理的虚構であると断言するのは、毛虫が仲間の毛虫の脱ぎ捨てられた皮を見て、無に帰すと思われる自分 たちの種の運命を痛烈に嘆くのと同じように、不合理な理屈である。昆虫の魂(動物にはそれぞれ魂がある)は、自然の変態を理解するにはあまりに限られてい る。最も賢い昆虫の一匹も、自分が蝶になる運命にあるとは想像できなかっただろう。私たちも同じだ。われわれの運命について、われわれの出自以上に何を 知っているというのか。それならば、私たちの幸福がかかっている無敵の無知に従おう。 そう考える者は、賢く、公正で、自分の運命について平穏であり、したがって幸福であろう。恐怖も欲望もなく死を待ち望み、生を大切にし(多くの喜びがある この場所で、嫌悪がいかに心を堕落させるか、ほとんど理解できない)、自然から受けた恩恵を感じるのに比例して、自然に対する畏敬の念、感謝、愛情、優し さに満たされるであろう。それ以上だ!人間性に溢れ、敵であっても人間性を愛する。彼が他人をどのように扱うか見てみよう。彼は悪人を憎むことなく憐れ む。しかし、心と体の構造の欠点を赦すことで、その両方の美と美徳を賞賛する。自然が寵愛した者は、継母のような扱いを受けた者よりも尊敬に値すると考え るだろう。このように、これまで見てきたように、すべての獲得の源である自然の賜物は、他のあらゆる思想家が不当に拒絶する敬意を、唯物論者の口と心から 得るのである。要するに、唯物論者は、虚栄心の抗議にもかかわらず、自分は機械か動物にすぎないと確信し、自分の同類を悪者扱いすることはないのである。 そこで大胆にも、人間は機械であり、全宇宙には異なる変化を遂げた単一の物質しか存在しないと結論づけよう。いわば松明を持った私の感覚が、自ら道を照ら すことによって理性に従うよう私を誘導してくれなければ、私はこれほど信用できないと思う道しるべを軽んじていたことだろう。経験はこのように、理性に代 わって私に語りかけてきた。 しかし、私は、いかなる学者も異論を唱えないような多くの観察の結果を除いては、最も精力的で即座に推論されるような推論さえも自分に認めていないことに 気づかれたに違いない。さらに、私は、観察から導き出した結論の判断者は学者だけであると認識している。このように強く堅固な樫に対して、神学や形而上学 や学問の弱い葦が何の役に立つというのだろう。私は、(偏見や迷信の影が地上に残る限り)絶え間なく出会い、動き続ける2つの物質が相容れないと仮定して 主張される、空虚でつまらない観念や、哀れで陳腐な議論について言及する必要があるだろうか。私がよほど欺かれていない限り、このようなのが私のシステム であり、むしろ真実である。簡潔で単純だ。論争するのは勝手だが。 |
| http://bactra.org/LaMettrie/Machine/ |
|
リンク
文献