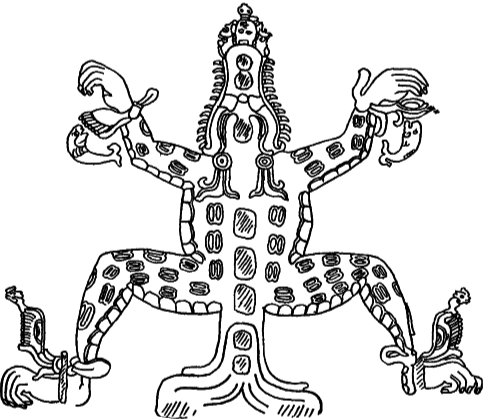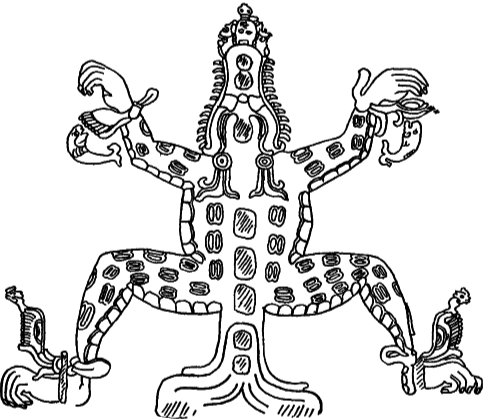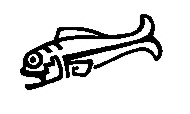【高齢化】社会のデザイン:コミュニティから発信する【このページ】
|
「高齢化社会」の理想と幻想(1990)
|
2025
年問題(日本の高齢化問題)
|
老
人問題・高齢
化社会・
研究叢書
|
□老年人類学入門・加齢現象の文化人類学入門
□エイジングの文化人類学
|
老人が尊敬される/軽蔑される社会的メカニズムについて
|
認知症、痴呆症、ぼけ
|
高齢者への対応——敬うか、遺棄するか、
殺すか?
|
従
属人口:じゅうぞくじんこう, dependent population
|
生きのびるための関わり合いと、そのデザイン
|
社会福祉とネオリベラリズム政策 |
社会文化的「ぼけ」から社会医療的「認知症」へ
|
老人虐待の起源
|
コミュニティに基礎をおく参加型研究
(CBPR)とは何か?
|
プ
ライマ
リ・ヘルス・ケア 2.0について
|
そ
の名は「定常型社会」
「持続的開発目標(SDGs)」
|
アクティブ・エイジング
|
医療介護の現場における身体コミュニケー
ション
|
チャート式医療社会学
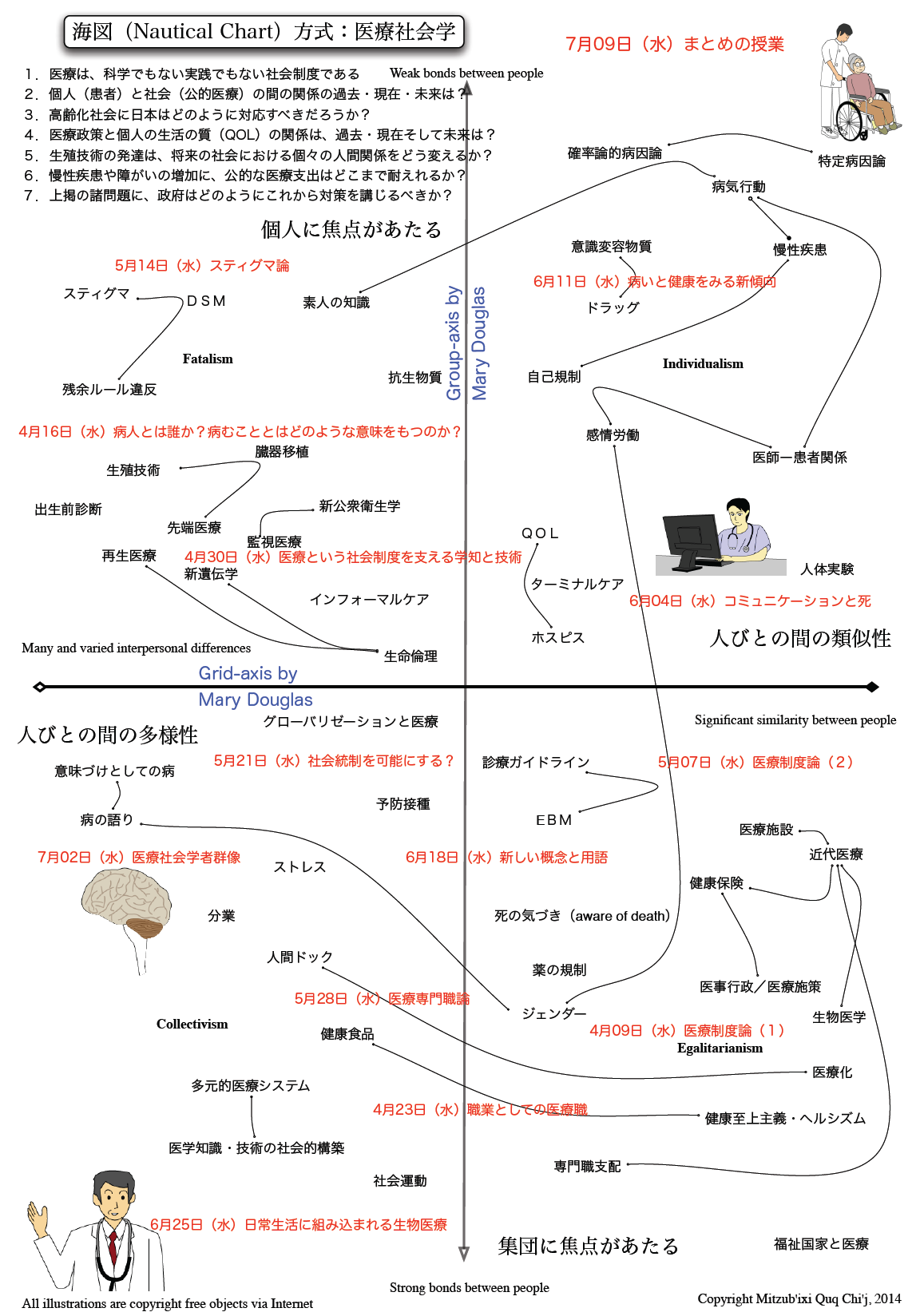
|
高齢者の外傷後成長と認知症に関する学際的研究に参加して
|
お灸
をすえ
る:鹿児島三島のヤイトヤキ
|
医
療労働市場と医療労働者の国際移動 に関する研究
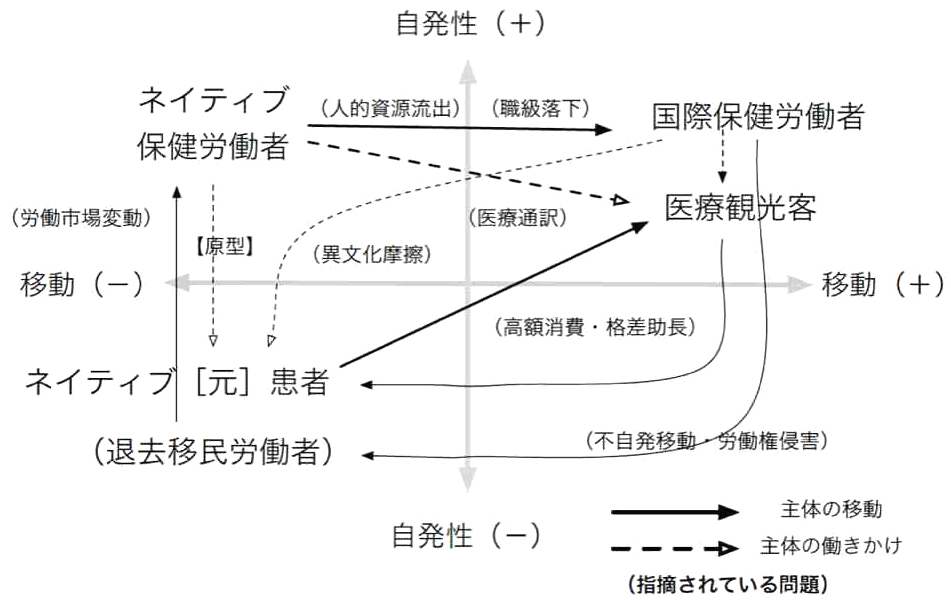
|
マインドマップ:「虚構としての認知症」
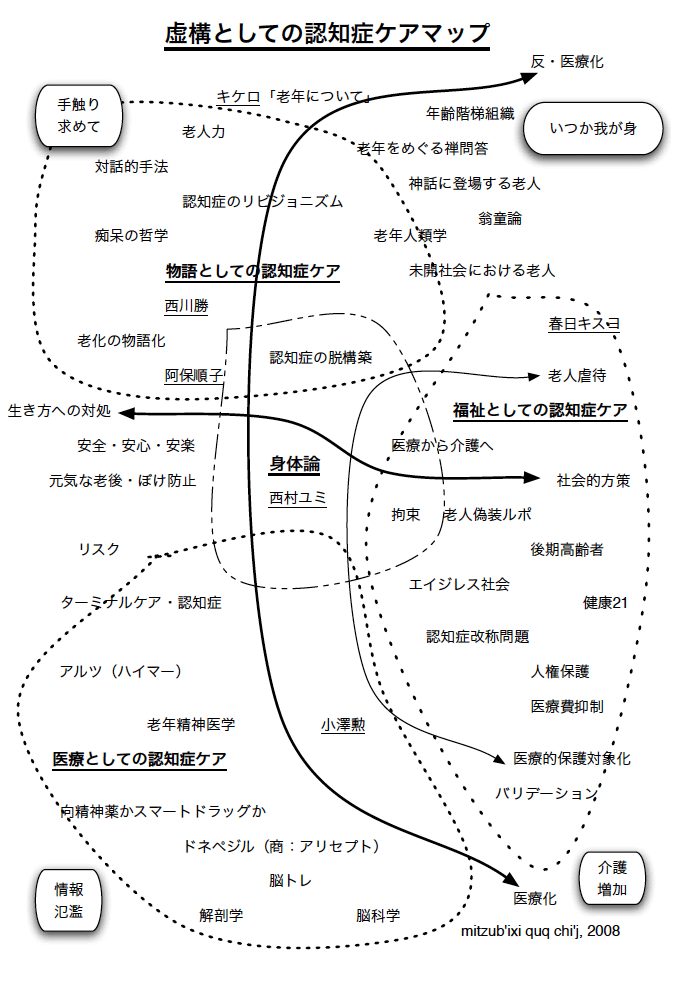
|
語りをのこす行為
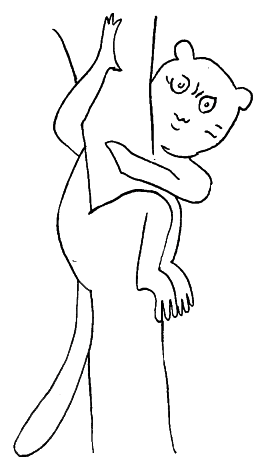
|
現代社会が抱える問題
|
国際労働移民の受け入れの問題:日本のケース
|
戦
争とアルツハイマー
|
John C. Campbell『日本政府と高齢化社会』ノート
|
認知症コミュニケーションへの招待
|
コミュニティ
「コミュニティについて考える」
|
ぼけの復権をめざして!
|
老いのパラドックス
|
私
たちは多文化医療 について何を考えないとならないか?
■テキスト編
■スライド編
|
認知症・経済格差・社会関係資本・トラウマ -レジリアンス
|
国連の持続可能な開発目標とグローバル・
イシューズ
|
進化生物学と医療社会学
|
| 安心して徘徊できる社会は可能か? |
協働術A:ネオ・アクションリ
サーチの探
究
■2017年度版
■2018年度版
|
外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れ
|
へき
地
医療研究 |
EPA にもとづく看護師・介護福祉士候補者の受け入れ制度について考える
|
マーガレット・ロック著『アルツ
ハイマー
の謎』
|
医療やケアのグローバル化に伴うコミュニ
ケーションの問題をあぶり出す
|
グローバル・スタディーズ・批判 |
移民
|
ASEAN経済共同体(AEC)・EPA状況下の医療保健人材の東アジア域内移動に
ついて
|
John C.
Campbell『予算ぶんどり : 日本型予算政治の研究』ノート
|
ジャレド・ダイアモンド『昨日までの 世界』問題集
|
グローバル・イシューズと先住民
|
アジアの域内労働移動のトレンド
|
マ
クロウィキノミクス・研究・ノート
|
スティグリッツ+グリーンウォルド『学習する社会を創造する』
を読む
|
安倍晋三首相による日本政府の国際保健に対する取
組み声明について
|
医療人類学における生命倫理学
|
教育を通した人類学的デモクラシーの実践
|
予算編成の政治学
|
フー
コー
の生権力論
|
大熊
由紀子
「ケアの思想」を読む
|
学生・院生の社会化に必要なのか?
|
Florence Nightingale
|
未開社会における安楽殺の倫理
|
アジアの〈こころ〉と〈からだ〉
|
医療社会学語彙集
|
認知症者の世界へのマッピング
|
認知症研究とロボットとの共存
|
見えない障害
|
ヒューマン・サービスに関わる科学とは?
|
ケアの思想・叢書
|
薬物・人間・社会の実践的比較文化論
|
看取り力から「看取られ力」へ
の構造転換
|
認知症ケアの創造:その人らしさの看護へ

|
医療人類学辞典
|
嬰児殺しと棄老に関する考察ノー
ト
|
コミュニティにもとづく参加型研究
|
ヘーゲルと親殺し
|
生・
権
力(せい・けんりょく)
|
「支配的存在」を名指し、可視化する試みについて
|
マーガレット・ロックの医療人類学
|
医療人類学:高知大学2009
|
【老人】が尊敬される/排除されるメカニズムについて→
|
エグゼ
クティ
ヴ・ホテルの老人
|
老いる
こと〈労
働〉の価値概念の変遷について
|
パーソンズ「老人の 健康と社会の成長」ノート
|
『老人Z』をめぐる議論
|
ベイルイマン『野いちご』(1957)[読解ならぬ]視解
|
映画『別離』を通して認知症の人について考える
|
私たちの高齢者に対する人道的対応について〈異文化〉の者が私たちに激高する時
|
介
護の社会的問題および介護保険法用語集・定義集
|
エイジズム
|
嬰児殺しと棄老の文化的解釈
|
虚構としての認知症
|
高齢者研究への招待
|
「よい死に方」について考え、そして行動してみよう!
|
在
日外国人支援の現場における参与実践
|
医療化
|
現代の棄老としての 安楽死と尊属殺人
|
浦島太郎:認知症コミュニケーションにおける〈時間感覚の相対論〉について
|
エイジレス・セルフ
|
アンセルム・ストラウスの医療社会学
|
リップ・ヴァン・ウィンクルと入植者たちの啓蒙について
|
姨捨伝説・異説
|
ヘーゲル哲学におけ る死の概念
|
現場力と状況学習の関係
|
今村充夫『日本の民間医療』研究ノート
|
マー
ガレッ
ト・ミード『サモアの思春期』読書ノート
|
上野千
鶴子『資
本制と家事労働』再入門!
|
ルー ス・ベネディクト『菊と刀:日本文化の諸パターン』1946
|
老人の地位処遇に関 するドナルド・カウギル(Donaldo O. Cawgil,
1972)の仮説
|
心的外傷後ストレス障害
|
トラウマを想起することに関するエッセー
|
心と社
会 狂気
をどのように捉えればいいか?
|
ス
トレス理
論の使われ方
|
癒しを見る眼
|
プナン民族誌と老人
|
〈こころ〉と社会
|
書評『苦悩することの希望:専門家のサファリングの人類学』浮ケ谷幸代編著
|
専門家の横暴について
|
現代社会を
考える上
でもっとも代表的な病気とは?
|
病いと疾病
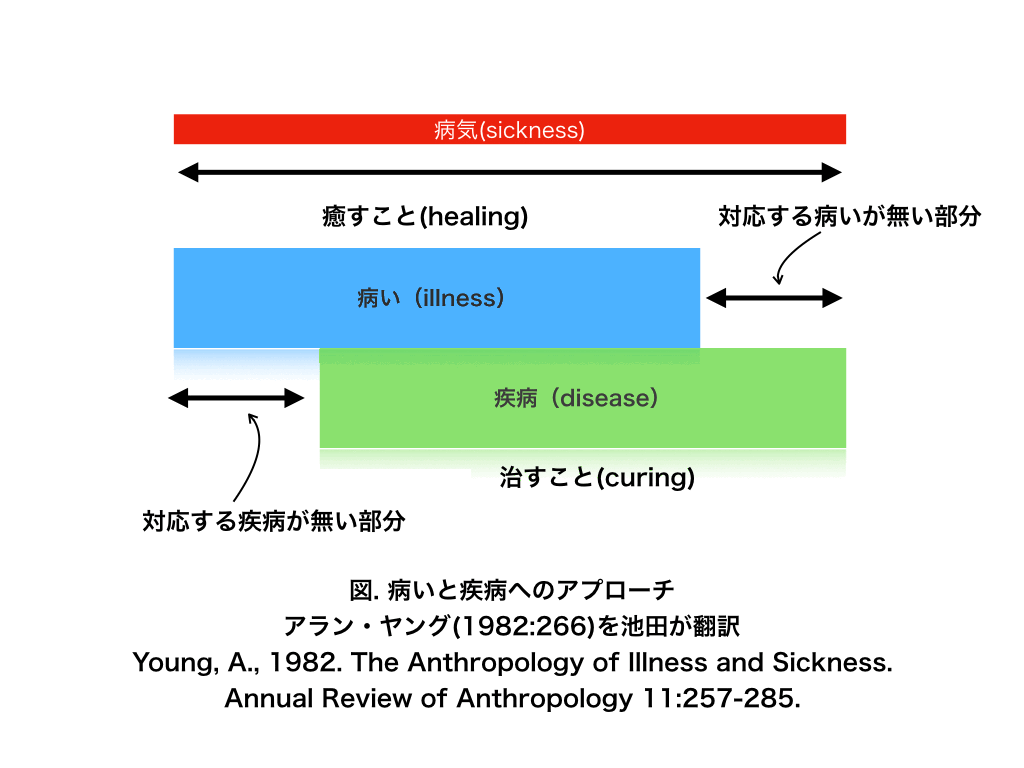
|
サンブルにおける長老制
|
W.H.R.リヴァーズ
|
社会科学への審問としての強制絶滅収容所
|
ゴ
ジラと現
代社会
|
トランスマイグレーションの倫理学
|
多文化共生はじめの一歩
|
シリオノの高齢者の 取り扱い
|
我々は何をなすべきか
|
Challenging to Our
low-birth-rate-hyper-aging-society: Japanese government, health
sectors, and citizen
|
認知症倫理学は可能か?(ハンバーガー倫理学について)
|
薬物利用者の高齢化について(ハームリダクション政策)
|
Harm Reduction
|
エルマン・サーヴィ スの〈狩猟民の長老は尊敬される〉説
|
ヘルスコミュニケーション研究リソース
|
From Sickness to Badness:opular images on
"Boke" (senile dementia and other related symptoms) in Japan.
|
おサキさんの老後は「標準的な老女」のライフの基準から外れてしまうのだろうか?
|
「年寄りはそう信じているんです」——犬と人間の共存に関する覚え書き
|
「年寄りが教科書を書く」——文化人類学に体系はあるのか?
|
棄老の伝説は殉死の 伝統を誤解したものである——中山太郎説
|
健康転換
|
ユマニチュードについて学ぶ
|
Alive Inside(内なるいのち)の衝撃
|
そ
の名は
「定常型社会」
|
国際労働移民の受け入れの問題:日本のケース
|
利他行動の進化論的 解決を「老人殺し」に適応できるか?
|
アイデンティティ
|
医療過誤
|
「多
文化
共生社会とプライマリヘルスケア」
|
「多
文化共生保健コミュニケーター」
|
「医療と文化の多元主義:日本事例の検討」
|
未開社会における安楽殺の倫理
|
生きることの意味
|
国連の持続可能な開発目標とグローバル・イシューズ
|
「生
活知(せいかつち)」
|
「ウィ
ル・キムリッカの「多文化主義」講義」
|
「民族=国家[国民]医療」
|
安楽死会話と終末期ケアを介した社会的死の予防:オランダからのレッスン
|
ヘルシズム
|
ツァイガルニク効果
|
「日常生
活活動
(ADL)」
|
「ノートハウスのヘルスコミュニケーション「異文化間コミュニケーション編」」
|
ソクラテスとアスクレピオスと鶏とニーチェ
|
B・マイヤーホフ論文「ちょうどいい時に死ぬ」論文ノート
|
人は多様に病み単純に治る(テーゼ)
|
高度副プログラム「ソーシャル・デザイン」
|
科学人類学(科学の人類学)
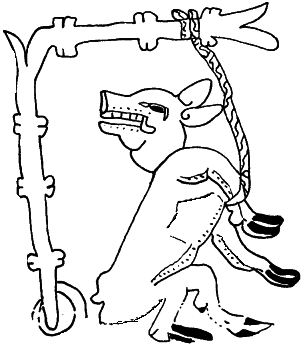
|
「〈言
語
の翻訳〉における現場での混乱」
|
【老人がもつ生産的権力について
考え
よ!】フーコー『知への意志』ノート
|
看取り力から「看取られ力」へ
の構造転換
|
加齢ははたして病気か?
|
「ローカル・グローバル・コネクション」
|
「患者サイボーグ宣言」
「人間機械論・再考」
「サイボーグ」
|
塩、
砂 糖、脂肪、怠惰
|
「生命の質」
|
書誌:日本における自殺研究
|
現代不老不死論——脳死・臓器移植問題を考える(1993)
|
「公的領域と私的領域に関する議論」
|
「道
具と
人間の身体がつくる世界」
|
ワー
ク・ ライフ・バランス批判
|
阿南成一『安楽死』(1976)の研究
|
医療人類学資料集:老女ナタルクの最期
|
アーサー・フランクの「死に行く人とその人の
権利」テーゼ
|
ジャ ン=ジャック・ルソーは囚人のジレンマを感じるのか?
|
看
護の定義
|
語
りは出来事の報告ではなく、出来事そのものである
|
狂気を装う
|
語り部の意味
|
未開社会における安楽殺の倫理
|
人間は〈病む存在〉である
|
散骨は自然葬ではない!
|
苦悩体
験の理解
|
ユカギールの悲劇
|
がんサバイバーとのコミュニケーション
|
人の身体は物質によって定義できぬ
|
歴史は死を前提とする
|
死の問題について
|
天
使の死とスープの味
|
加藤尚武氏書評「安楽死問題の名著」へのコメンタリー
|
オランダにおける安楽死の研究
|
アステカの生と死の女神
|
近代病院のなかの伝統的「死」
|
死
の
勝利について
|
生と
死の儀礼
における分類の次元
|
神は死んだ、をめぐる人間の誕生
|
安楽死の研究
|
魔法医学の起源
|
家族に埋め込まれた死——文化人類学からの諸見解
|
病気と
文化 人
間の医療とは何か?
|
認
知症コミュニケーションへの招待
|
「リプロダクション:「産むこと」は単純ではないのか?」
|
憑依 病める身体は誰のものか?
|
老女ナタルクの最期
|
構築主義について
|
老人問題・研究
叢書
|
認
知症と
呼ばれる老い人が「うちに帰りたい」 というとき、何が起きているのか?
|
老いをたのしむ〜♪
|
9「エイジングと文化 老いはどのように捉えられているか?」
|
高齢化社会のデザインに関する韓日比較研究プロジェクト
|
高齢化社会のデザイン
|
2025年問題(日本の高齢化問題)
|
高齢者研究への招待
|
エイジングの文化人類学
|
|